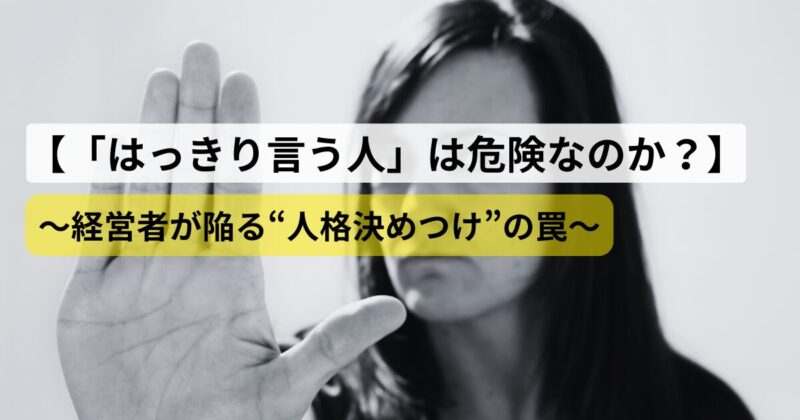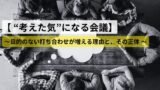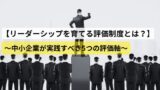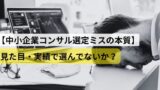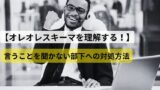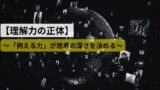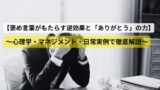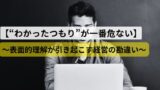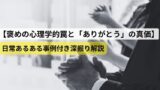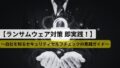経営の現場では、「思ったことをはっきり言う人」はしばしば“扱いにくい存在”とされる。会議で意見をずばり言う社員に対して、「協調性がない」「空気が読めない」といったネガティブな印象が先行し、その人の実力や貢献が見落とされることがある。だが、経営者や管理職がそのような“印象”に基づいて評価してしまえば、組織は重要な戦力を自ら遠ざけることになる。本稿では、「はっきり言う人=危険人物」という誤解がなぜ生まれ、どんなリスクを招くのか、そしてどのような視点転換が組織に成長をもたらすのかを、具体例とともに掘り下げていく。
「言い方が強い人=危険人物」という思い込み
「声が大きい=主張が強い」「率直に言う=配慮がない」。このような“ラベリング”は無意識のうちに行われている。特に年齢層が高い経営者層には、「人柄」や「態度」で人を判断する傾向が根強く残っている。
会議での誤解:実は論点を整理しているだけ
ある会議で、40代の営業マネージャーが「この計画では費用対効果が見合わない」と発言したとする。これを「批判的」と捉えるか、「論点の明確化」と捉えるかで、まったく評価は変わる。だが現実には「雰囲気を壊す」「言い方がキツい」という理由でマイナスに受け止められがちだ。ここには、内容より“話し方”に引っ張られる評価の危うさがある。
「営業には向かない」と決めつけた失敗
過去に、「言い方がストレートすぎるから顧客対応は無理」と判断し、社内業務に配置換えをした社員がいた。だが、後にその社員が異動先で取引先との価格交渉を担当したところ、理路整然とした説明とフェアな態度が評価され、大きな契約を獲得した。これは、「印象」と「適性」を混同した結果、貴重なリソースを見誤った典型例だ。
部下育成でのすれ違い
若手社員がミスをした際、「何が問題だったか、次どうすればいいか」を明確に伝えることは本来、育成の基本である。しかし、“感情をぶつけられた”と誤解されれば、指導そのものが問題視されてしまう。だが本質は、相手を思ってこその「厳しさ」だったりする。
別の見方:「明確に伝える人」は交渉や意思決定の場に向いている
はっきりものを言う人は、時に「空気を読まない」「刺々しい」と受け取られる。しかし、見方を変えれば、彼らは“感情”に流されず、“事実”に即して判断する特性を持っている。これは、交渉や経営判断の現場では、非常に価値のある特性だ。曖昧さを排し、論点をクリアにする力は、組織のスピードと判断の質を大きく左右する。
曖昧さを嫌う姿勢が、判断スピードを上げる
経営会議では、立場や遠慮が交錯し、発言がどうしても曖昧になりがちだ。
「B案もいいと思いますが、A案も否定できないですね…」というような、“どちらとも取れる”発言が並ぶと、結論がなかなか出ない。
そんな時、率直な社員が「A案にはこのリスクがある。B案の方が数字的に確実だ」と論点を整理し始めると、場の空気が一変する。「強い言い方」ではあっても、それが“議論の停滞”を打破し、焦点を絞る起爆剤になる。

経営において時間はコストである。曖昧なまま長引く議論ほど、目に見えない損失を生んでいる。だからこそ、「結論を急ぐ」力は、会社全体の推進力を左右するのだ。こうした人材は、見方を変えれば“厄介な存在”ではなく、“会議の生産性を守る砦”とも言える。
外部交渉では「遠回し」が裏目に出ることも
日本的なビジネスの場では、直接的な表現を避け、「察してほしい」「にごして通す」といった文化が根強い。だが、それが通じない場面も多い。
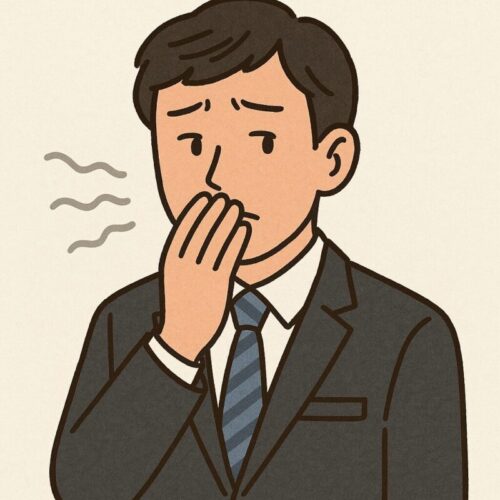
たとえば価格交渉の現場。取引先に対して「このあたりでご検討いただけると助かります」といった言い回しでは、「まだ下がる余地があるのか?」と誤解される可能性が高い。
その一方で、「この価格が当社の上限です。利益率と納期を考慮した結果です」と明確に伝える人は、最初は“冷たい”印象を持たれるかもしれないが、結果的に「誠実な会社」「信頼できる交渉相手」として評価されやすい。
この“伝えきる力”を持つ人が社内にいることは、組織としての信頼性を対外的に高めるという意味でも、大きな資産になる。
会議での発言が「軸」になる
組織内の議論が迷走し始めたとき、誰かが「それって、お客様視点で見るとどうですか?」と発言するだけで、一気に空気が締まる瞬間がある。
これは単なる“意見”ではなく、“軸”を打ち込む行為だ。
経営判断は、往々にして「多数決」ではなく「判断軸の明確化」で決まる。何を優先するのか。何を守るのか。そこを見失うと、どんなに議論を重ねても、方向性が定まらない。
率直な発言者は、その“軸”を言語化してくれる。たとえそれが不器用な言い回しだったとしても、本人なりの信念が宿っているからこそ、組織にとって貴重なのだ。
まとめておきたい視点
- 言葉が強い=乱暴ではない
- 即断する=独断的ではない
- 率直に言う=自己中心的でもない
そう思ってしまうのは、私たちの“受け取り方のクセ”である可能性が高い。
逆に言えば、「受け取り方の視点を少し変える」だけで、これまで敬遠していたタイプの社員が、組織の中核を担うキーパーソンに変わるのだ。経営者や上司が“印象”ではなく“機能”で人を見られるようになった時、会社全体が一段階ステップアップする。その始まりが、こうした視点の転換にある。
なぜ“はっきり言う人”を誤解してしまうのか
はっきりものを言う人が、なぜか「扱いにくい」「危なっかしい」と敬遠される。本人は意図的に敵を作るような言い方をしているわけではないのに、周囲からは「一緒にやりづらい」「感情的」と受け取られる。なぜそんな“ズレ”が生まれてしまうのか?
そこには、評価する側の“過去の経験”や“自分自身の不安”が静かに影響している。
自分の経験を他人に投影してしまう心理
多くの経営者や管理職は、過去に誰かしら「強い言い方をする人」とぶつかった経験を持っている。
会議で言い争いになった、納得できない批判を受けた、あるいはチームの空気を乱された——そんな記憶が、似たような言動をする社員に重なってしまうのだ。
これは「またあのときと同じことが起きるのでは?」という無意識の防衛反応。その社員本人が何を言ったかより、「言い方があの人に似ている」という印象が先に心を占めてしまう。そして、その印象が冷静な評価を曇らせていく。
たとえば、ある社員が「今のやり方だと効率が悪いと思います」と意見を出したとする。過去に同じような言い方で反発を招いたケースを持つ経営者は、「また空気を乱すつもりか」と感じてしまう。だが、言っている内容自体は合理的で、的を射ていることも少なくない。
ここで必要なのは、「これは今の社員の言葉であって、過去の誰かの再来ではない」と、一度自分の感情と距離をとること。判断の精度を上げるには、過去と現在を切り分ける視点が欠かせない。
「自分と違うタイプ=危険」という錯覚
人は、どうしても“自分と似たタイプ”に安心感を抱く。言い方が穏やかで、立場を尊重し、聞き役に回ってくれる人の方が「信頼できる」と感じやすい。逆に、自分と考え方や伝え方が違う人には、警戒心が芽生える。
だが、会社に必要なのは「感じがいい人」ばかりではない。むしろ、「違う角度からものを見る人」「異なる価値観で行動する人」がいることで、組織には“広がり”が生まれる。
似たようなタイプだけで固めたチームは、確かにストレスは少ないかもしれない。しかし同時に、「発想が偏る」「変化に鈍感になる」「問題の芽に気づけない」というリスクも高まる。
違和感や異質さを感じたとき、それを「危険」ではなく「新しい切り口」として捉えることができるかどうか。これが、経営者の成熟度を測る一つの物差しになる。
言い方にばかり注目し、中身を見ない危うさ
人は、感情に強く反応する生き物だ。だからこそ、言い方や声のトーン、表情など“非言語の部分”が記憶に残りやすい。
「口調がキツかった」「言い方が上からだった」──こうした印象が先に残ると、その人が伝えようとした中身や意図が後回しになってしまう。そして最悪の場合、「発言の内容自体がなかったこと」になってしまう。
だが、少し考えてみてほしい。その発言は、言い方こそ尖っていたかもしれないが、
- 実は顧客の視点を代弁していたかもしれない
- 経営上のリスクを先回りして指摘していたかもしれない
- 現場の停滞感を打破しようとしていたのかもしれない
私たちが評価すべきなのは、「伝え方」よりも「何を伝えたかったのか」。その視点を持てるだけで、評価の質は格段に変わる。
誤解は“対立”ではなく“気づき”の入口にできる
「強く言われたから、苦手…」–「自分と違うタイプだから、危ない…」
そういった感覚は、誰しも一度は持つだろう。だが、それをきっかけに「なぜ自分はそう感じたのか」「もしかして見落としていることがあるのではないか」と、立ち止まって考えてみる。
そうすることで、ただの誤解が、「新たな気づき」や「視点の転換」につながることがある。経営者にとって重要なのは、“心地よさ”ではなく、“組織が前に進むこと”であるはずだ。
組織に必要なのは「感じのいい人」ではなく「誤解を恐れず伝える人」
「和やかな人」「波風立てない人」「みんなと仲良くできる人」。そういった社員が組織にいると、確かに安心感がある。場の空気も穏やかで、衝突も少ない。だが、その“心地よさ”がいつの間にか「言うべきことを言わない空気」へと変わっていくことがある。 経営において必要なのは、「感じの良さ」ではなく、「伝えるべきことを、恐れずに伝える力」だ。
「波風を立てない文化」が招いたプロジェクトの崩壊
ある中堅の製造業で、新製品の開発プロジェクトが進められていた。営業部門は「現場の声を反映した売れる商品だ」と自信を持ち、開発部門は「これ以上のスペック変更は難しい」と訴えていたが、調整はなされないままスケジュールだけが進行した。
会議では、誰も「このままだと失敗するかもしれない」とはっきり言わなかった。言えば“場の空気”が悪くなる。営業部長の機嫌を損ねる。社長がその場にいたらやりづらくなる。──だから、誰も言わなかった。
結果、商品は発売されたが、蓋を開けてみればクレームが相次ぎ、初回ロットの8割が返品。営業は疲弊し、開発は落ち込み、経営陣は原因がわからず社内がギクシャクする始末。誰も“間違っている”とは言わなかった。言わなかったことが、最大のミスだった。
「調整型の社員」は、一見組織の潤滑油。でも…
「○○さんはいつも感じがいいよね」「誰とも揉めないし、空気も読めるし」と評価されがちなタイプは、組織内では重宝される存在だ。
だが、こうした“調整型”の社員が、問題の芽を見て見ぬふりしてしまうと、事態は深刻になる。たとえば社内に不正まがいの処理や、納期を過ぎることが常態化している部署があったとしても、「まあ、誰も文句言ってないし…」と流してしまう。
「角が立たないように」「波風を立てないように」と考えるあまり、本来伝えるべき違和感や不整合が放置されるのだ。これは表面上の“秩序”を守る代わりに、中身の腐敗を進行させる行為でもある。
「誤解されるかもしれない」が、黙る理由になっていないか
一方、発言をためらっている社員の側にも葛藤がある。「正しいことを言っても、否定されるんじゃないか」「怒られるんじゃないか」「変な空気にしたくない」。
そうして、「もういいや」「関わらない方が得」となってしまえば、企業にとっては大きな損失だ。なぜなら、本当に気づいているのはその人だからである。
誤解を恐れずに発言する勇気は、簡単なようで難しい。だが、それが組織にとっては“沈みかけた船の穴を最初に見つける行為”にもなる。本人は煙たがられるかもしれないが、長い目で見れば組織を救う存在なのだ。
社内で“火種”になった社員が、実は会社を救った話
別の事例を挙げたい。ある食品加工業の若手社員が、「原料の仕入先に衛生管理の問題がある」と気づき、上司に報告した。が、「そんなの昔からの付き合いだ。口を挟むな」と突っぱねられる。
だがその社員は黙らなかった。品質管理部門と連携し、再調査を申し入れた。その後、その仕入先が過去に他社で異物混入を起こしていたことがわかり、契約見直しが即時決定された。
当初は「面倒なやつ」「新人のくせに」と冷たく見られていた彼が、数か月後には社内表彰を受けていた。言いにくいことを言ったからこそ、会社は信用を守ることができたのである。
空気を読まないのではない。「空気の質」を変えている
「はっきり言う人」は、空気を壊しているのではない。空気の質を変えようとしているのだ。
ぬるま湯の空気、なんとなくの同調、空気読みの文化──その中で「本当にこのままでいいのか?」と問いかける存在は、実はとても貴重だ。その発言が「耳に痛い」と感じるときこそ、組織が見直すべき“盲点”がある。
和やかさと健全さは違う。雰囲気と本質はイコールではない。「言ってくれてありがとう」と後から思えるような発言ができる人は、組織にとって“炎上予防装置”でもあるのだ。
結論として…
感じの良さは、場を円滑にする潤滑油である。だが、潤滑油だけでは、エンジンは動かない。推進力が必要だ。「誤解されるかもしれないけど、言う」。その姿勢こそが、組織を前に動かす力になる。経営者がそうした社員の“本気の声”を受け止める構えを持てば、組織の風通しは確実に変わる。
誤解を恐れず伝える人。それは、時に「嫌われ役」になるが、本質に向き合う覚悟を持った“組織の背骨”でもあるのだ。
「評価の物差し」を変えると、見える人材が変わる
組織内で“評価される人”と“見落とされがちな人”──その差は、必ずしも能力や貢献度ではない。むしろ、“評価する側の物差し”に大きく左右されていることがある。
声が大きい人は“目立つ”、空気を読む人は“感じがいい”、物静かな人は“真面目そう”──そういった「キャラクター」で人を見る評価軸に偏ると、役割や強みが見えにくくなる。経営者こそ、“人を見る目”をアップデートし続ける必要がある。
「タイプ」ではなく「機能」で見る
たとえば、ある社員が「いつも批判的」と敬遠されていたとする。だがその発言は、よくよく聞けば「論理の抜け」「数字の矛盾」「前提の崩れ」を見抜いたものだったりする。つまり、場を整える「調整型」ではなく、判断を鋭くする“分析型”の機能を持った人材かもしれない。
評価とは、「この人はどの場面で力を発揮するか」を見極めること。話し方や人当たりの印象ではなく、発言の中身と効果に注目することが重要になる。
「衝突=悪」ではない。“対立”を戦力化せよ
意見が割れる。議論が熱を帯びる。会議が長引く。こうした場面に対して、「もっとスムーズに進めたい」「喧嘩は避けたい」と思うのは自然な感情だ。だが、衝突そのものを排除するのではなく、意図を持った“機能的対立”として活かすという発想が必要だ。
異なる視点がぶつかることで、議論の幅が広がる。新しい選択肢が生まれる。チームとしての“視野の広がり”が生まれる。これを恐れて意見を丸めてしまえば、短期的にはラクでも、長期的には“鈍い組織”になってしまう。
「感じの良さ」ではなく、「伝えた内容」に注目する
面談や会議の場で、「印象」ではなく「論点」に注目しているだろうか?たとえば評価の際、「あの人は協調性がある」「印象がやわらかい」といった表現が並んでいるとしたら、すでに“主観”に引っ張られているサインかもしれない。
本当に見るべきなのは、「この人は何を伝えたのか」「どういう立場で発言したのか」「組織にどんな影響を与えたか」という“言動の中身”だ。見方の焦点を少し変えるだけで、それまで見えなかった人材の価値が立ち上がってくる。
物差しを変えると、人が変わって見える
評価とは、「人の価値を決める作業」ではない。「人の可能性に気づく作業」だ。これまで見えなかった人の強みが見えてくる。声の小さな社員の熱意に気づける。意見が強い社員の“誠実さ”が分かるようになる。
評価の軸を「印象」から「機能」へ、「感じの良さ」から「貢献度」へと切り替えるだけで、組織の中の景色はまったく違って見えてくる。
それは、経営者にしかできない“視点の再設計”である。
まとめ:はっきり言う人こそ、組織に必要な「軸」をつくる存在
率直な人は、ともすれば組織で浮いて見えることもある。だが、彼らの「曖昧さを許さない姿勢」は、組織の軸となる事実を掘り起こし、判断にブレない基準をもたらす。経営者がその真価に気づき、“印象”ではなく“機能”として人を見始めた時、これまで埋もれていた人材の力が大きく花開く。視点を少し変えるだけで、組織はもっと強く、しなやかに変われるのだ。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。