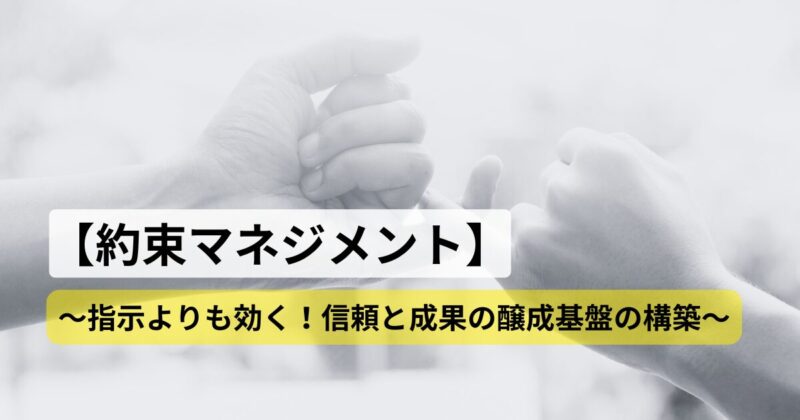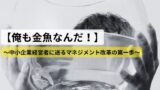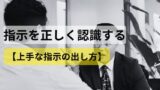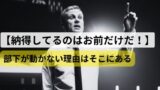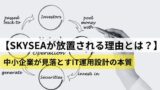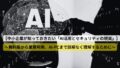中小企業における人材育成やチームマネジメントにおいて、「指示したのに動かない」「伝えたのにやってくれない」といった悩みは根深い。これは単に“伝え方”の問題ではなく、上司と部下との間にある「認識のズレ」「責任の所在」「関係性の質」など、構造的な課題に起因する。本稿では、そうしたマネジメントの行き詰まりを突破する手法として「約束マネジメント」という視点を提示する。ただ指示を出すのではなく、「一緒に決める」「責任を共有する」プロセスこそが、信頼関係と行動力を引き出すカギである。指示から約束へ。組織文化を変える第一歩を掘り下げていく。
なぜ「指示」では伝わらないのか?
中小企業で多く見られる「指示したのに動かない」問題は、単に言葉の伝達ミスでは片付けられない。上司が当然と思っていることが、部下には“曖昧で不安な命令”に見えていることが多いのだ。
上司が思う「指示」と部下が受け取る「指示」のズレ
指示とは、業務遂行のための指導や依頼であるが、ここに大きなズレがある。上司は「簡単に伝えた」「明確に言ったつもり」でも、受け取る部下にとっては、内容が曖昧だったり、背景が不明だったりすることが多い。
なぜこのズレが起きるのか。それは、上司が「指示=伝えること」と誤解しており、部下側が「指示=評価される対象」と過度に捉えるからだ。要するに、上司は完了を前提に話し、部下は失敗したときの責任を恐れる構図になっている。このギャップを埋めるには、「指示の本質」を見直す必要がある。
抽象的な言葉(「朝イチ」「今日中」)が混乱を生む
「朝イチで出して」「今日中にお願い」といった表現は、上司にとってはごく自然な日常会話の一部だ。しかし、受け手である部下にとっては、その言葉の意味する時間帯や優先順位は明確ではない。「朝イチ」とは始業直後なのか?8時か?それとも「出社して最初に」という意味か?「今日中」とは何時までか?18時なのか、日付が変わるまでか、あるいは上司が確認できる時間までか…。

このように、“相対的な表現”は受け取り方に個人差が出やすく、結果として「指示通りにやったのに叱られた」「そんなつもりではなかったのに怒られた」と部下の中に“理不尽感”が残る。これは小さな誤解のように見えるが、積み重なれば信頼関係の崩壊に直結する、極めて深刻なマネジメントの問題である。
では、なぜこうした曖昧な言葉が使われるのか?単なる言葉足らずの問題だろうか?実はそこには、見逃されがちな“心理的な背景”が大きく関与している。
なぜ曖昧な言葉になるのか?その心理を見逃すな
「今日中に」「調整しておきます」「検討します」…こうした抽象的な表現は、ビジネス現場で日常的に飛び交っている。だが、本来コミュニケーションとは具体的な情報を交換する行為である以上、こうした曖昧表現は合理性を欠いている。そもそもこれでは、具体的な行動に繋がらない…いつまでに何をするかが不明なまま何をするということになるのだろうか?…それでも使われ続けるのはなぜか。これは“曖昧にしておくことで、当事者が心理的な負担を回避している”からだ。
たとえば上司が「今日中に」と言うとき、実は自分でも本当の期限を明確に決め切れていない場合が多い。「何時まで」と言い切ることが、部下に対して強く要求しすぎるのではと躊躇したり、自分自身がその時点でまだ優先順位を整理できていなかったりする。つまり、“あえて曖昧にしておくことで、決断の責任を保留している”状態とも言える。

一方、部下が「検討しておきます」「調整します」と言うときも同じだ。実際は「いますぐ動ける確信がない」「決めるには上司の意向も確認したい」など、何らかの“心理的保留”をしている。つまり、明確に返答できない状態を「検討中」という言葉で一時的に正当化しているのである。
このように、曖昧な表現には“衝突を避けたい” “責任を先送りしたい” “現時点で断定できない”という、いわば人間らしい防衛本能が働いている。だからこそ、「なぜ曖昧にした?」と責めるのではなく、「なぜそう言わざるを得なかったのか?」という“背景の感情”に寄り添う姿勢が重要なのだ。
曖昧な表現が出てきたとき、どう会話を発展させるか?
この“心理的防衛”を前提として捉えることができれば、マネジメント側にできるのは、「曖昧な表現を責める」のではなく「それを一緒に具体化する」アプローチ」である。
たとえば、部下が「今日中にやっておきます」と言ったとき、「ありがとう。18時までに確認できるようになってると助かるんだけど、大丈夫そう?」と問いかけてみる。これは詰問ではなく、“合意形成”のための丁寧な会話である。
逆に、上司が曖昧な指示を出してしまった場合でも、部下が「すみません、今日中というのは18時くらいを想定しておけばよろしいですか?」と確認できる関係性をつくっておくことが、マネジメントの土台になる。
このように、「なぜ曖昧になるのか?」という構造と心理を理解しておくことで、表面上の言葉に振り回されずに、“具体性のある会話”へと発展させることが可能になる。
「約束」という発想がマネジメントを変える
「指示」ではなく「約束」という言葉に置き換えることで、マネジメントの構造そのものが変化する。これは単なる言葉遊びではない。関係性と行動の質を根本から変える思考法だ。
「一緒に決める」から始まる主体性
約束は一方的に与えるものではなく、互いに合意するプロセスである。つまり、部下の意思を確認し、納得したうえで行動を促す形になる。
〜この「一緒に決める」姿勢こそが、部下の主体性を引き出す〜 自分で決めたことは守ろうとするのが人間であり、上からの命令よりも“自らの意志”に基づいた行動は圧倒的に強い。マネジメントにおける「約束」は、動機づけの仕組みそのものなのだ。
約束は守るもの → 信頼関係を育む仕組み
「約束を守る」は誰にとっても当たり前の常識である。だからこそ、“指示”を“約束”に変えることで、「ちゃんとやらなければ」という内発的な責任感が生まれる。
また、上司が「自分も約束を守る」姿勢を見せることで、部下との信頼関係が構築される。信頼されていないと感じる職場では、人は動かない。信頼が蓄積された組織だけが、自律的なチームになる。
報告を強制せず「約束を確認」するだけで動き出す
部下からの報告を待っていても、なかなか上がってこない。だが、それは「報告しろ」という命令だからだ。
「どうなった?」「あの件、進捗どう?」という“約束の確認”であれば、部下は自然と応じやすくなる。これは心理的安全性の違いである。命令の追及ではなく、約束の確認という形でコミュニケーションすることで、報告が自然に行われるようになり、マネジメントの手間が激減する。
実践!「指示を約束に変える」具体ステップ
では、どうすれば「指示」が「約束」になるのか。実務で活用できる具体ステップを提示する。
5W2Hを「一緒に確認」して約束に落とし込む
「誰が(Who)」「何を(What)」「いつまでに(When)」「どこで(Where)」「なぜ(Why)」「どうやって(How)」「いくらで(How much)」….これを一緒に確認するだけで、抽象的な指示が“具体的な約束”に変わる。
この確認プロセスを「上司の確認」ではなく、「一緒に決める話し合い」として実施するのが重要だ。「OK、これでやってみるよ」と部下が答える状態まで持っていくことで、行動の質が飛躍的に高まる。
期限や成果物は“絶対表現”で明文化する
「できるだけ早く」「なるはやで」ではなく、「9月10日の18時までに」「A4で2ページの企画書」と明文化することが重要だ。
なぜか?それは、「曖昧な約束」は守られないからである。絶対表現で書かれた約束は、確認ができ、管理がしやすく、責任の所在も明確になる。これは成果物の品質にも直結する。
具体的なカタチや日時を告げられると脳内で、瞬時に可否をイメージすることができる。これで思考が活性化するし認識齟齬の回避にも繋がることになる。
約束を小さく分けて積み重ねる(マイクロ約束法)
大きな仕事を一気に任せても、部下は動けない。「じゃあ、まずはこの資料だけ明日までに出せる?」といった小さな約束からスタートするのが効果的だ。
この“マイクロ約束”を積み重ねることで、部下の行動が加速し、自信がつき、結果的に大きな成果へとつながる。心理的ハードルを下げる意味でも、マイクロ約束は極めて有効である。
経営者・管理職が押さえるべきポイント
「約束マネジメント」を成立させるには、経営者・管理職側の覚悟と姿勢が問われる。
約束の結果責任は上司が持つ
これは極めて重要な視点だ。「やらせたけどできなかった」ではなく、「任せた結果として、自分に責任がある」と上司が認識すること。
これは部下への信頼を示すと同時に、上司としてのリーダーシップの証でもある。任せた責任を背負う姿勢が、部下を動かす最大の要因になる。
部下のミスを責めず「約束の設計」に立ち返る
部下がミスしたときに「なぜやらなかった?」と責めるのではなく、「そもそもの約束の内容に不備はなかったか?」と設計段階に立ち返る視点が必要だ。
ミスは部下の能力不足ではなく、設計ミスであると捉えることで、再発防止が可能になり、部下との関係も悪化しない。これは「人を責めず、仕組みを問い直す」マネジメントの基本である。
約束文化を組織に根付かせるための仕組み(議事録・タスク管理ツールの活用など)
「約束」は記録されてこそ意味を持つ。口約束ではなく、議事録やタスク管理ツールなどで“見える化”することで、約束の確認・進捗管理がスムーズになる。
また、組織として「約束を守ること」を文化にするためには、定期的な振り返りや共有の場を設けることも重要である。これは単なるツール導入ではなく、仕組みとしての定着が肝となる。

まとめ:指示から約束へ ― 自律的に動く組織づくりの第一歩
中小企業における人材育成や組織マネジメントは、単なる業務指示やチェックだけでは機能しない。「指示したのにやらない」の背景には、関係性の希薄さ、責任の押し付け、不明確な表現という構造的課題がある。
これを打開するには、「指示」ではなく「約束」という視点に立ち、「一緒に決める」「記録して確認する」「小さく積み重ねる」アプローチが不可欠だ。
そして最も重要なのは、約束の結果に対して上司が責任を持ち、部下に信頼を示すこと。これが組織全体に信頼と成果をもたらす文化を生み出す。今こそ、指示から約束へ。マネジメントの本質的な転換が求められている。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。