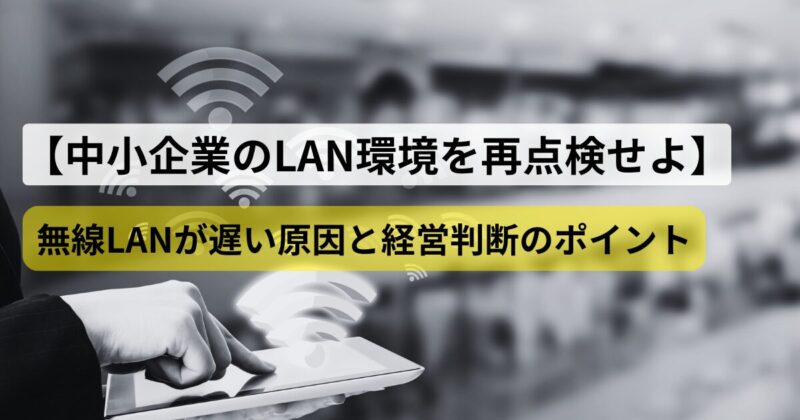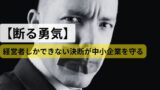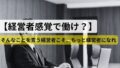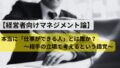中小企業のネットワーク環境は、有線LANと無線LAN(Wi-Fi)が混在するのが一般的だ。スマートフォンやタブレットの業務利用が進み、運用上の利便性から無線LANの比重が増している一方で、「接続が遅い」「TV会議だけ不安定」「特定の端末だけ挙動が悪い」といった“体感的な不満”が蓄積されているケースは多い。
設備更新をしたにも関わらず改善が感じられない背景には、構成や設定への理解不足がある可能性も高い。本稿では「LAN環境の見直し」をテーマに、経営者が判断材料として押さえておくべき視点と、現場で使える改善方法を提示する。
無線LANと有線LANの違いと判断基準:利便性か安定性か
LAN環境を構築する際に最初にぶつかるのが「有線と無線、どちらを選ぶべきか?」という問いである。答えは一つではないが、それぞれの特性を理解したうえで“目的に応じた使い分け”をすることが、現実的な運用には不可欠である。
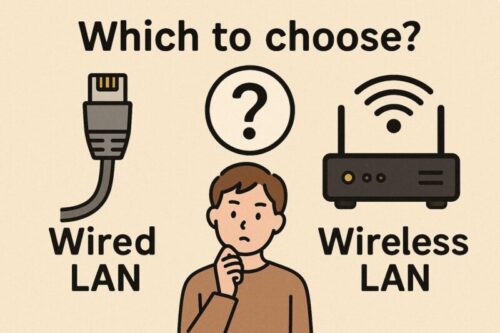
デバイス別に求められる通信特性
スマホやタブレットはモビリティが重視されるため、無線LAN接続が前提となる。一方、デスクトップPCや常設の業務用機器では、有線LANによる安定接続が適している。ノートPCについては運用形態により分かれるが、TV会議や動画配信など通信負荷の高い作業が中心の場合、有線接続とした方が良いこともある。
アプリケーションによる通信量の差異
リモート会議、クラウドアプリ、遠隔アクセス(VPN接続)などは無線LANの弱点が顕著に現れやすい。とくにZoomやTeamsをスマホやタブレットで使用する場合、帯域不足や遅延が音声品質を著しく低下させることがある。
このような場合には、有線接続もしくはWi-Fi 6対応ルーター+中継器などの補強をしないと、リモート会議がストレスと感じてしまうことになる。
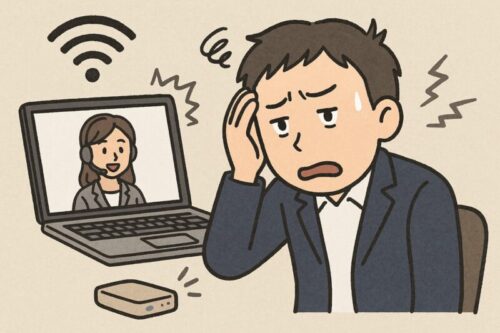
接続数と帯域の関係性
Wi-Fiは“見えない共有資源”であり、接続するデバイスが増えればそれだけ通信速度が低下する。同時接続が10台を超えると、家庭用ルーターでは性能の限界に達することもある。
社員の私物スマホやIoT機器が無意識に接続されている場合もあるため、見直しの際は「何が何台つながっているか」を明確にすることが第一歩となる。
光回線にしたのに遅くなった?原因は“回線”ではなく“接続の仕組み”にある
「光回線を新たに契約して専用のWi-Fiルーターも設置したのに、スマホでの初期接続が遅く感じるようになった」。これは実際に中小企業の現場で起きたリアルな声である。設備としてはアップグレードしているにもかかわらず、体感速度が向上しないどころか、逆に“遅くなった”と感じるケースだ。
特にTV会議に限定せず、Web閲覧やメール受信といった日常利用の初期段階で“ワンテンポ遅い”ような現象が顕著だという。このような状況で考慮すべきポイントは以下の通りである。
❶ スマホのWi-Fi接続時の“スリープ”・“省電力”モード
スマホ(特にiOSやAndroid)は、バッテリー節約のためにWi-Fi接続を自動的に一時切断・スリープ状態にする機能がある。再び通信が必要になったタイミングでWi-Fiを「再接続」するため、“最初の数秒だけ遅い”“ルーターを探しているような挙動になる”という症状が出る。
これは通信環境の問題ではなく、端末側の仕様や設定による挙動である場合が多い。特に以下のような設定に注意が必要だ。
❷ ルーター側の“バンドステアリング”機能が原因となる場合
最近のルーターには「バンドステアリング」と呼ばれる機能が搭載されており、2.4GHzと5GHzのどちらの周波数帯が適切かを自動的に選択する。
この自動判定に“数秒”かかることがあり、これが「初期接続が遅い」という感覚に繋がるケースがある。さらにこの機能が誤動作を起こす場合、特定の端末で2.4GHzに固定されてしまい、混雑しているチャンネルに巻き込まれることもある。対処としては以下の設定が有効だ。
❸ DHCPリースの設定不備または接続台数オーバー
初期接続に時間がかかる場合、DHCPによるIPアドレスの割当てでタイムラグが発生している可能性もある。これはWi-FiルーターのDHCP設定における「リース期間が短すぎる」「IPアドレスの範囲が狭い」「一度に多数の端末が接続しようとしている」などの要因が影響する。特に社員のPC、スマホ、タブレット、ゲスト用端末まで含めると、想定以上の端末が同時接続しているケースは少なくない。
経営者視点での補足
このように「回線は光に変えた、ルーターも新しい、でも遅い」の背景には、ネットワーク機器の自動最適化機能や端末側の省電力制御が影響している場合がある。ここで重要なのは、「設備を最新にすれば速くなる」という誤解を正し、現状の構成と運用設定の見直しこそが改善の鍵であると認識することだ。
必要以上に“ベンダー任せ”にすることなく、ログの取得や定点測定によって原因を切り分け、必要に応じてITアドバイザーや顧問といった専門家にセカンドオピニオンを求めるのが、中小企業経営者にとって最も現実的で無駄のない対処法となる。
通信速度が遅い原因を「感覚」ではなく「数値」で把握する方法
「なんとなく遅い」「このアプリだけ時間がかかる」など、感覚や伝聞ベースでは真因にたどり着けない。中小企業でも実践可能な“見える化”の方法を導入することで、改善施策の優先順位が明確になる。
SpeedtestやFast.comによる定点測定
無料の通信速度測定ツールを使い、場所・時間帯・デバイス別に数値を記録する。日常的なネットワーク状況を数値で把握することで、ルーターの設置場所や混雑時間帯のボトルネックが判明する。
Wi-Fiアナライザーを用いた電波状況の可視化
「WiFi Analyzer(Android)」や「NetSpot(Mac/Windows)」などのアプリを活用することで、電波の強度や干渉状況がグラフ表示できる。会議室・倉庫・壁際などで通信不安定が発生している場合、構造的な問題の検出が可能。
ルーター管理画面での接続状況確認
多くのルーターには、現在接続されている端末の数や通信量をリアルタイムで確認できる管理機能がある。ゲストWi-Fiや業務端末、個人端末の利用状況を把握し、適切に制限・分離することで、通信環境の健全化が図れる。
まとめ:LAN環境は“機器”ではなく“構成と運用”で決まる
通信環境の不安定さに対して「ルーターが古い」「回線が遅い」と決めつけて設備投資に走る前に、本当に必要なことは現状の定量的な把握と適切な構成である。特に中小企業においては、余計な機器を増やすことよりも、既存設備の最適な活用と“感覚を数値に置き換える作業”が最もコストパフォーマンスに優れる対策だ。
最終的に構成設計や運用改善が必要な場合、専門家の助言を得ることが無駄な投資を避ける最短ルートとなる。IT顧問やセカンドオピニオンの活用も視野に入れ、経営者自身が判断軸を持つことがITリテラシーの本質である。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。