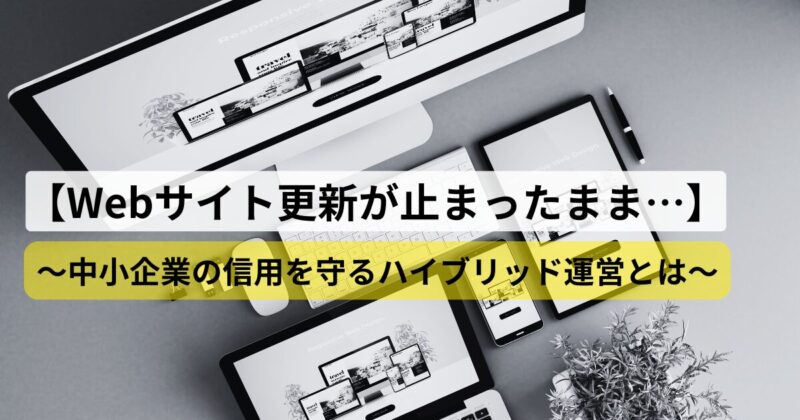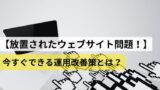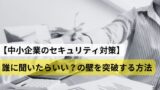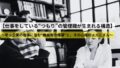更新されないWebサイトは「誰の担当かも曖昧」「見て見ぬふり」で放置されがちだ。だがその状態こそ、信用の低下・取引や採用の機会損失・セキュリティ事故といった、目に見えにくい経営リスクを静かに積み上げている。特に中小企業では、Web運用の責任者不在やベンダー任せのブラックボックス化によって、「必要性は感じているけど、どう対処すればいいのかわからない」状態に陥っていることが多い。本稿では、なぜWebサイトは“放置”されるのか、その構造的な背景を掘り下げた上で、限られたリソースの中でも取り組める現実的な選択肢…「ハイブリッド型運営(外部委託+内製対応+顧問サポート)」という実践的な対応策を提案する。
なぜ中小企業のWebサイトは放置されやすいのか
中小企業のWebサイトが「放置」されてしまう理由として、「IT担当がいない」「更新にかける時間がない」「予算がない」といった声がよく聞かれる。確かにそれも事実ではあるが、それはあくまで“表面的な要因”にすぎない。実際にはもっと根本的な、「Webサイトに関する経営判断がなされていない」「判断するだけの情報・視点が社内に存在しない」という構造的な問題こそが、放置の本質である。
IT担当がいない、任せられる人がいない ― それは“放置の結果”である
中小企業では専任のIT担当者がいないことが多く、Webサイトの管理・更新は営業や総務が「片手間でやるもの」とされがちだ。だがこれは、本来「誰にどこまで任せるべきか」を経営として設計していないことの裏返しでもある。
実際には、“誰が担当するか”の前に、“Webサイトにどんな役割を期待するのか”という経営判断が抜け落ちている。その結果、「気づけば何年も更新されていない」「誰もログインできない」という状態に陥る。つまり“任せられる人がいない”のではなく、“経営者自身が、任せるべきことを定義していない”という方が正確だ。
「更新の必要性」はわかっているつもり ― でも“判断できるレベルでは理解していない”
多くの経営者は「情報が古いと印象が悪い」「見た目が時代遅れだと信頼を失う」といったことは感覚的に理解している。だが、それが経営リスクになるという“質的な問題”として、本質的に思考できているかというと疑問が残る。
たとえば、更新作業にどれだけの時間がかかるのか、どういうスキルが必要なのか、誰に相談すればいいのか…といった“判断の前提となる知識”を持ち合わせていない。結果として、優先度を正しく見積もることができず、「まあ後回しでいいか」となってしまう。
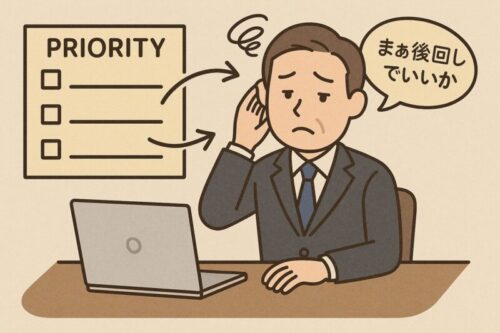
放置されるのは「忙しいから」ではない。忙しい中でも優先されるべき理由が“明確に理解されていない”からである。要は、Webサイトは「手をつけるべきテーマ」だと判断されるステージに乗っていないのだ。
ベンダー任せで“中身がブラックボックス化”している
構築を外部業者に依頼したものの、その後の運用方法や更新体制が共有されておらず、社内に知識もノウハウも蓄積されていないケースは非常に多い。
たとえば『IT顧問のススメ』でも紹介したように、Webサイトを構築した担当者が退職し、ベンダー側の担当者も不在。結果として「ID/パスワードが不明でログインできない」「更新を依頼できる人がいない」といった事態に陥り、販売終了した製品が延々と掲載され続けていた…という事例がある。
これは単に「担当がいなかったから」ではない。「どの情報を、誰が、どうやって管理すべきか」が経営レベルで設計されていなかった」ことが原因である。技術的なことがわからなくてもいい。だが、少なくとも「何がわかっていないのか」を知っておく必要はある。放置されているWebサイトには、この“わからないことすらわかっていない”という構造的な盲点が潜んでいる。
放置されたWebサイトが生む“見えない損失”
「うちは営業中心だから、Webサイトはあまり関係ない」「更新していないけど特に困っていない」という感覚があるかもしれない。だが実際には、Webサイトの放置は“気づかないうちに信用と機会を失っていく”構造的な損失を生み出している。それは広告費や人件費のように明確に見えるコストではないからこそ、余計に厄介である。
古い情報が“信頼”を損なう
ある製造業の会社では、2年前に廃番となった製品がいまだにWeb上で「販売中」として掲載されていた。問い合わせがあるたびに「その製品は終了しています」と説明して断る手間が発生しているという。これは顧客対応の効率低下であると同時に、企業の“信頼損失”でもある。

Webサイトの情報は、企業の“姿勢”そのものである。古い情報がそのままになっていれば、「この会社は社内管理もずさんでは?」という印象を与えることになる。たとえリアルな営業で信頼を積み重ねていても、初見でWebサイトを見た人にはそれが伝わらない。信用の第一印象が損なわれるのだ。
セキュリティリスクが静かに積み上がる
もうひとつ深刻なのが、セキュリティの“見えない劣化”だ。CMS(WordPress等)で構築されたWebサイトの場合、プラグインやテーマの脆弱性を突かれて不正アクセスや改ざん被害を受けるリスクがある。特に更新されていないサイトは、攻撃者にとって“狙いやすい獲物”に見える。
「導入したツールや仕組みを放置することがむしろリスクを拡大させる」といった実例は非常に多い。セキュリティは「何を導入するか」よりも、「どう運用し続けるか」が問われる領域だ。更新されないWebサイトは、常にリスクが高まり続けているといっても過言ではない。
採用・取引の“無自覚な機会損失”
最近の採用活動では、求職者が会社のWebサイトをくまなくチェックするのが当たり前となっている。にもかかわらず、「社員紹介が5年前のまま」「社長の挨拶が初代のまま」「スマホで表示が崩れる」などの状態はよくある。
本人は気づかないが、Webサイトによって“選ばれない理由”が静かに積み重なっている。採用だけでなく、協業や仕入れのパートナー選定でも同様だ。パートナー候補が「Webもちゃんと管理できていない会社」と判断すれば、連携が見送られることもある。“失敗したわけではないが、得られなかった”チャンスは、放置されたWebサイトの裏側に隠れている。
現実的な解決策は“ハイブリッド型”運営
ではどうすればいいのか?外注すべきか、内製すべきか…その二択で悩む必要はない。結論から言えば、「外部委託+内製対応+IT顧問サポート」のハイブリッド運営こそが、もっとも現実的かつ持続可能な選択肢である。特にリソースに限りがある中小企業にとっては、無理なく・手戻りなく運用できる仕組みが重要だ。

構築やリニューアルは外部に任せるのが合理的
サイトの構築やリニューアルは、専門性が高く設計・導線・セキュリティなど幅広い知識が求められる領域だ。これは外部のプロに任せた方がコストパフォーマンスが高い。
ただし、「全部丸投げ」はNG。構築時に「運用のしやすさ」や「社内更新のしやすさ」も設計に含めることが必要だ。具体的には、「誰でも触れるように管理画面を整備する」「マニュアルを共有してもらう」など、納品後に“使いこなせるかどうか”を見越して外注することがポイントである。
日常の情報更新は“社内で完結”できる仕組みに
最新情報の追加や、採用情報の更新、お知らせの投稿などは、社内で手軽に行える体制を整えるべきだ。それが日常の運営コストを抑え、Webサイトの“鮮度”を保つ最もシンプルな方法である。
操作が難しい場合は、最初の段階で「誰が・何を・どうやって更新するのか」を明確にし、それに合わせたCMS構成や操作レクチャーを外注先に求めておくとよい。
外部協力者を“セカンドオピニオン”として活用する
構築は外注、更新は内製…それだけでは対応しきれないのが、ITまわりの現実である。たとえば、「セキュリティ設定が適切か不安」「CMSのアップデートで不具合が出た」「SEO対策として何をすべきか」など、日々出てくる“ちょっとした相談”に答えてくれる存在が必要だ。
そこで効果的なのが、IT顧問や外部アドバイザーの活用である。これは、販売目的で動くベンダーではなく、中立的な視点で助言をしてくれる立場の専門家を指す。IT顧問という選択は、中小企業における強力なリスク回避策となるだろう。
ハイブリッド型運営とは、「人がいないから内製できない」「コストがないから外注できない」というジレンマから抜け出す、持続可能でリスクにも強い運営モデルなのである。
まとめ ― Webサイトは“信用インフラ”である
Webサイトは、営業活動の一部であり、信用を担保するインフラでもある。その価値を認識せずに放置していれば、知らぬ間に信頼とチャンスを失ってしまう。
中小企業が現実的に取り組むには、「外部委託だけ」「内製だけ」では限界がある。むしろ、構築は外部に任せ、日常更新は社内で回し、専門家に定期的にチェックしてもらうという“ハイブリッド型運営”が最もリスクが少なく、持続可能な方法だ。
Webサイトは単なる「会社紹介」ではない。信頼を伝える“営業の現場”であり、採用活動の“面接官”でもある。だからこそ、定期的に見直し、整備し続けることが重要なのだ。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。