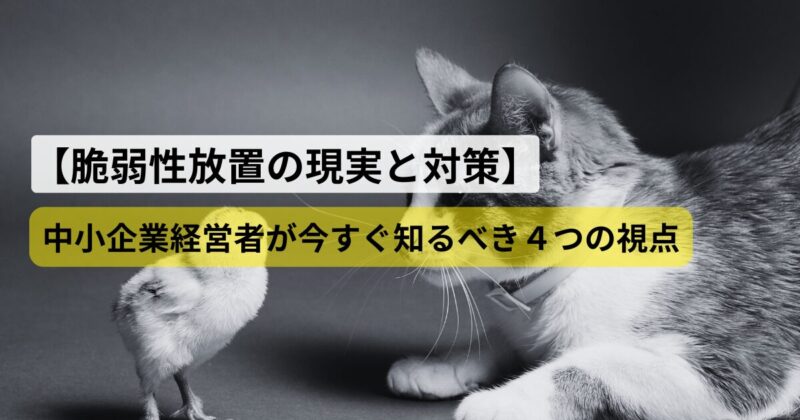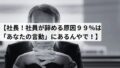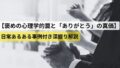中小企業において、日々大量に発信される脆弱性情報は「聞いたことはあるが実感が薄い」「パッチを当てても業績には直結しない」といった理由で後回しにされがちである。しかし放置された脆弱性は、サイバー攻撃の起点となり、情報漏えい、ランサムウェア被害、取引先や顧客への損害賠償請求など、多大なリスクを招く。
そこで本稿では、
①脆弱性放置の実態を示す調査データ
②放置される主因
③パッチ適用の定量的効果証明
中小企業でも実効性のある3つの対策──という流れで整理し、経営者・マネジメント層が一刻も早く取り組むべきポイントを解説する。
実態の調査データ(中小企業にも広がる“未修正脆弱性”問題)
中小企業を含む多くの組織で、未修正の脆弱性が大量に放置されていることが複数の調査で明らかになっている。
Ponemon Institute:脆弱性バックログは平均57,555件
Ponemon Instituteが2020年に実施した調査では、組織あたり平均57,555件もの検出済み脆弱性が未修正のまま放置されており、全体の28%がスキャンで検出されながら対応されていないことが報告された (infosecinstitute.com)。
INFOSEC 「Ponemonのクラウドとオンプレミスにおける脆弱性管理の現状レポートの主な調査結果」で公開されているものです。
引用元:INFOSEC 「Ponemonのクラウドとオンプレミスにおける脆弱性管理の現状レポートの主な調査結果」
Kaseya:42%のみがパッチ管理自動化を導入・計画
2019年のKaseya調査では、中小企業を含む回答者のうち自動化によるパッチ管理を「導入済み・導入予定」と答えたのはわずか42%。残る58%は未だ手作業に頼っており、更新漏れの温床となっている。
Kaseya 「2019年IT運用調査結果:自動パッチ管理は広く導入されていない」で公開されているものです。
引用元:Kaseya 「2019年IT運用調査結果:自動パッチ管理は広く導入されていない」
Sophos:「未修正脆弱性起点」のランサムウェア攻撃が32%
Sophosの「State of Ransomware 2024」報告によれば、32%のランサムウェア攻撃が既知の未修正脆弱性を起点として発生していることが明らかになった 。
SOPHOS 「2024年のランサムウェアの現状」で公開されているものです。
引用元:SOPHOS 「2024年のランサムウェアの現状」
Ivanti:71%が「パッチ作業は複雑で負荷大」、61%が「ダウンタイム懸念」
Ivantiの2021年調査によると、IT/セキュリティ担当者の71%が「パッチ適用作業は複雑・煩雑で時間を要する」と回答し、さらに61%は業務部門から「システム停止への反発」があると報告している 。
ivanti 「ITセキュリティ専門家の71%がパッチ適用が複雑で時間がかかると感じていることが確認された。」で公開されているものです。
引用元:ivanti 「ITセキュリティ専門家の71%がパッチ適用が複雑で時間がかかると感じていることが確認された。」
これらのデータから、中小企業でも未修正脆弱性が常態化しており、サイバー攻撃リスクを高めている実態が浮かび上がる。
脆弱性が放置される主な要因
放置の背景には、リソース不足や業務優先の風土、技術的負荷などが重層的に絡み合っている。
リソース(人員・予算)の不足
中小企業では専任のセキュリティ担当者が不在、あるいは兼務体制で運用業務に追われており、脆弱性対応に割ける人員・時間・予算が限られる (infosecinstitute.com)。
ivanti 「ITセキュリティ専門家の71%がパッチ適用が複雑で時間がかかると感じていることが確認された。」で公開されているものです。
引用元:ivanti 「ITセキュリティ専門家の71%がパッチ適用が複雑で時間がかかると感じていることが確認された。」
作業の複雑性・運用負荷
パッチの検証から展開までのプロセスが煩雑で、失敗リスクを恐れて後回しにされる。手順が属人的になりやすく、具体的な手順書や自動化ツールが整備されていないケースも多い 。
ビジネス部門からのダウンタイム懸念
システム停止やパフォーマンス低下に対する業務部門の反発があり、「止めないこと」が優先され、結果としてパッチ適用が先延ばしとなる 。
互換性やサードパーティ製品依存
複数OS・ミドルウェア・社外製品が混在する環境では、パッチ適用後の互換性検証に膨大な工数がかかり、全社一斉ロールアウトが困難となる。
これらの要因を放置すると、次節で示す効果的な対策が絵に描いた餅となる。
定量的に示す「パッチ適用効果」の証明
理論上、脆弱性対応を徹底すれば攻撃リスクを大幅に軽減できることが、各種調査から定量的に示されている。
1. 未修正脆弱性起点攻撃の削減効果:60~76%
データ漏えい全体の60%、ランサムウェアの76%が既知の未修正脆弱性を起点に発生するとの調査結果があり、迅速かつ完全なパッチ適用が実現すればこれら攻撃ベクトルの理論上60~76%を予防可能である 。
SOPHOS 「未修正の脆弱性:最も凶悪なランサムウェア攻撃ベクトル」で公開されているものです。
引用元:SOPHOS 「未修正の脆弱性:最も凶悪なランサムウェア攻撃ベクトル
2. 初期侵入リスクの低減:20%
VerizonのDBIRでは、脆弱性悪用が全侵害の20%を占めると報告。適時パッチを当てることで、この「脆弱性経由の侵入」をほぼ100%阻止できるため、全体の侵入リスクを20%低減できるとされる (techtarget.com)
Tech Target 「2025年のランサムウェアの傾向、統計、事実」で公開されているものです。
引用元:Tech Target 「2025年のランサムウェアの傾向、統計、事実
3. リスク窓口(Exposure Window)の短縮:180日→約10日
多くの組織が脆弱性発見からパッチ適用までに平均180日を要する一方、自動化ツール導入事例では9~12日まで短縮された。期間短縮により、攻撃者が利用可能な時間帯を95%以上削減可能である (techtarget.com)。(本稿は外部調査データに基づいて作成しており、アップロードファイルは使⽤していない)
4. リスクベース優先対応カバレッジ:上位20%で80%超
脆弱性のうち「30日以内に実際に攻撃で使われる可能性」が高い上位20%に優先適用すれば、全体リスクの80%以上をカバーできるとの知見がある 。
これらを組み合わせると、適切なパッチ管理により全社的なサイバー攻撃リスクを70~80%以上低減できるとの評価が成り立つ。
中小企業の実情に合わせた実効性ある3つの対策
限られたリソース下でも実施可能な、即効性と持続性を兼ね備えた対策を3つ提言する。
1. 自動化と統合プラットフォームの導入
2. リスクベースの優先順位付けと段階的展開
3. 経営層コミットメントとガバナンス強化
まとめ:経営者が「ゼロコスト」で実行できる“次の一手”
脆弱性対応は、単なるIT部門の課題ではなく、企業の存続を左右するリスク管理の最前線である。パッチ適用というゼロコストに近い対策を疎かにすれば、万単位の被害や信用失墜、損害賠償リスクを招く。
一方、本稿で示した「自動化プラットフォーム」「リスクベース運用」「経営コミットメント」を組み合わせることで、中小企業でも限られたリソースで脆弱性管理を圧倒的に強化できる。まずは本日中にIT部門へ「月次パッチ適用KPIの策定」を指示し、一歩を踏み出してほしい。
※本稿は外部調査データに基づいて作成しております。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。