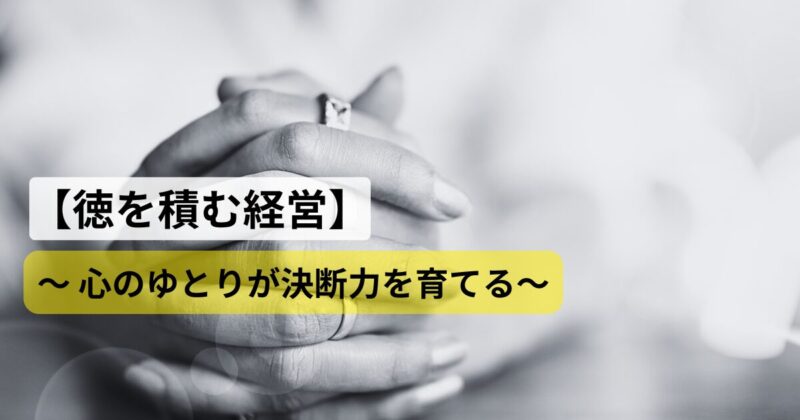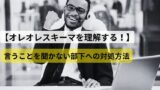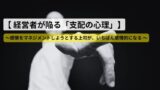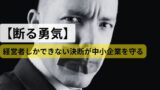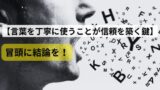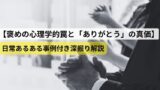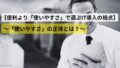「中小企業経営」「リーダーシップ」「人間力」「覚悟と信頼」―この言葉が交差するところに、経営者としての成熟がある。日々、判断と決断の連続の中で、私たちはしばしば他人の未熟さに直面し、時に不満や苛立ちを覚える。しかし、それらはすべて「徳を積む機会」であるとしたらどうだろうか。静かに背筋が伸びるような内省の時間が、経営の本質に気づかせてくれる。本稿では、自身の内面に向き合うことが「決定力」を育てる道であるという視点から、経営と心の在り方を紐解いていく。
人の未熟さも、報われない努力も「心を磨く機会」として見る
経営をしていると、どうしても人の未熟さに出会う機会が多い。部下の配慮に欠けた言動、パートナー企業の浅はかな判断。目をつぶっても目につく場面が、次から次へと現れる。そして、それと同じくらい、こちらが尽くしたことがすぐに報われない場面も多い。
これらは一見、別々の問題に見えるかもしれない。だが本質的にはどちらも、「自分の思い通りにならないこと」とどう向き合うか、という問いに行き着く。私にとってこの問いは、経営という道を歩む中で、何度も立ち止まりながら向き合ってきたテーマだ。
未熟さに苛立つ自分を、責めない
かつて、ある若手社員の不用意な発言に強く心がざわついたことがある。なぜこんなに腹が立つのか、自分でも驚いた。表向きには「そんな言い方はないだろう」という理由だったが、よく観察してみると、そこには「わかってほしかった」「それくらい気づいてほしかった」という、私自身の“期待”があった。
怒りの多くは、裏切られた期待から生まれる。そして期待とは、往々にして自分の中だけで組み立てた“理想”であり、相手には共有されていないものだ。つまり、私は“自分だけの物差し”で相手を裁こうとしていたのだ。
このとき大切なのは、感情を抑え込むことではない。むしろ、湧き上がる感情に「ダメだ」とフタをするのではなく、「なぜこの感情が生まれたのか?」と、静かに見つめ直すことだ。
感情に飲まれず、自分の心の動きを観察する。この習慣が、経営者としての判断を支える土台になる。そして、その視点が持てるようになると、不思議なことに、相手の未熟さも「自分を映す鏡」として見えるようになってくる。
「相手を変えようとしない」と決めた日
もちろん、何度言っても変わらない相手を見ると、疲弊する。だがある時、「人を変えようとするのをやめてみよう」と腹を括ったことがあった。それは敗北ではなく、信頼への第一歩だった。
相手を変えようとするのではなく、自分の接し方を変えてみる。例えば、失敗した部下に「何でこうした?」と詰めるのではなく、「この判断をした背景を聞かせてほしい」と語りかける。口調一つで、空気は変わる。
この変化が、目に見える成果に直結するわけではない。だが、何度も同じトーンで、同じ姿勢で、誠実に関わり続けることで、「この人は本気で向き合ってくれている」と伝わるものがある。それが信頼の芽になる。
見返りを求めない姿勢が、信頼を呼ぶ
人は、自分に都合のいい人を信用するのではない。本当に信頼されるのは、「損得を超えて、誠実であり続ける人」だと私は思っている。
過去に、長い時間をかけて関係構築を試みた取引先があった。毎月足を運び、提案をし、課題解決のヒントを持ち込んだ。だが、契約には結びつかず、「また来たの?」という顔をされることもあった。心が折れそうになったこともある。
それでも続けたのは、「今の私は、この人に必要とされているかどうか」ではなく、「今の私は、必要な姿勢をとっているかどうか」に焦点を移したからだった。結果的に、その会社との関係は時間をかけて信頼に変わり、大きな取引へと発展した。
だが、それ以上に得たものがあった。それは、「私は、見返りがなくても信じて続けられた」という自信だった。
静かに、変わらず、そこに在るということ
「徳を積む」とは、華々しい行いではない。静かに、地道に、自分の姿勢を保ち続けることだ。
怒りや不満に翻弄されず、見返りがないことに焦らず、自分の言動を観察し、選択し続ける。その日々の選択の積み重ねが、やがて“徳”となり、周囲に安心感をもたらす。
そしてその安心感こそが、最終的には「決断力」となる。
このように、一見ストレスとも取れる出来事は、実は「経営者としての成熟度を試されている時間」なのだと思うようになった。人の未熟さや報われない努力に出会ったときほど、自分自身の姿勢が問われている。
そう考えると、経営とは成果を出すだけの営みではなく、「自分を深める稽古の場」なのかもしれない。
報われない時間こそが、覚悟と決断力を育てる
経営を続けていると、「努力が報われない」という時間が必ず訪れる。手を尽くしても成果が見えず、周囲の動きも鈍く、結果ばかりが遅れて届く。そんなとき、心の中では様々な葛藤が渦巻く。「やり方が間違っているのではないか」「自分の価値はここまでか」「もう、やめた方がいいのか」――そうした迷いが、一人の夜にふと頭をよぎることもある。
だが私自身の経験から言えば、こうした“報われない時間”こそが、経営者にとっての最も深い「稽古の場」なのだと思っている。
結果の出ない時間は「信念の根」を下ろす時期
以前、数ヶ月にわたって提案活動を続けたプロジェクトがあった。チームも一丸となり、提案書も準備し、何度も打ち合わせを重ねた。だが、結果は契約不成立。しかも、最終的な決め手は「他社の方が安かった」という一言だった。
そのときは正直、無力感でいっぱいだった。「この数ヶ月は何だったのか」と頭の中で問い続けた。
だが時間が経って冷静になると、「この時間が無駄だったかどうかは、これからの自分の姿勢次第だ」と気づいた。成果に繋がらなかったけれど、提案の進め方、相手の心理、言葉の選び方、社内の連携――学んだことは数え切れない。むしろ、こうした“外れた矢”の中にこそ、次に繋がる確かな技術と信頼が残っていた。
成果は、必ずしも行動の直後には返ってこない。土に埋めた種が芽吹くまで時間がかかるように、経営の多くも「見えないところで根を張っている時間」がある。表面に出ていないからといって、価値がないわけではない。むしろ、静かに自分を深く掘るその時間こそが、後の“決断力”の土台になっていく。
迷いがないのではなく、迷いを抱えたまま決める
経営者は日々、決断の連続にいる。時には、人の人生を大きく左右する決断を迫られる場面もある。解雇、異動、撤退、新規事業の立ち上げ。どれも簡単なものではない。
私もかつて、ある人事判断で「自分がどう見られるか」を優先してしまったことがある。「できるだけ誰からも嫌われずに済む選択をしたい」。そう思った結果、結論が曖昧になり、周囲にも混乱を招いた。結果的に、その人にも、組織にもよくない影響を与えてしまった。
その経験が教えてくれたのは、「誰かに好かれるための決断」は、信頼を損なうということだった。経営者には、誰かのために“嫌われる覚悟”すら必要なときがある。決断とは、すべてをクリアに整えてからするものではない。迷いや葛藤があっても、「これが自分の信じた道だ」と腹をくくれるかどうか。それが、信頼されるリーダーと、そうでない人の分かれ道になるのだと思う。
覚悟とは「背負うこと」であり、「逃げないこと」
「覚悟」と聞くと、大げさな言葉に聞こえるかもしれない。だが、私の実感では、覚悟とは特別な力ではない。「自分が決めたことを、途中で投げ出さない姿勢」のことだと思う。
結果が出なくても、「今は意味がある」と信じて続ける。誰かに非難されても、「自分が選んだことだ」と責任を引き受ける。他人のせいにしない。運のせいにもしない。その姿勢を貫くことで、ようやく「決断できる人」としての土台が整っていく。
不思議なことに、人はそういう「静かに責任を引き受ける人」に安心を覚える。その人の決断に、「納得」が生まれる。だからこそ、決断には徳がいる。そして、徳は報われない時間に育つ。
このように、努力が報われない時間や迷いの中にこそ、経営者としての本質が磨かれていくと感じている。経営とは、自分の未熟さと真っすぐ向き合う時間の連続だ。そして、その時間を恐れずに歩んだ者にこそ、「決める力」が宿るのだと思う。
実践のヒント ― 毎日の経営に「徳の習慣」を持ち込む
徳を積むとは、日々の選択の中に小さく存在する。だからこそ「習慣化」が大切である。
不満を抱いたら「何を学ぶべきか?」と問う
怒りや苛立ちを感じたときは、「なぜこの感情が湧いたのか?」「この出来事は何を教えてくれるのか?」と自問してみる。これだけで、出来事の解像度が上がり、成長の機会に変わる。
言葉を選ぶ習慣をつける
社員に注意をするときでも、まずは「理解したい」という姿勢を示すようにしている。「なぜ、そうしたのか教えてくれ」と問うだけで、相手の防御反応は和らぐ。こうした姿勢が、組織に安心感をもたらす。
感謝の言葉を意識的に増やす
ありがとう、助かったよ、嬉しかったよ。こうした言葉を、意識して多く使うようにしている。感謝は、最も手軽で強力な徳の実践である。日常の中にこそ、徳の種がある。
まとめ ― 経営とは「徳を積む旅」
経営とは、ただ数字を追いかける仕事ではない。「人を育て、自分を磨く」旅であり、その過程で心を鍛える場でもある。不満や理不尽をどう受け止めるかで、その人の器が決まる。信頼を育み、見返りを求めずに続ける姿勢が、経営者としての深みを生む。
そして、何よりも心に留めておきたいのは、「心のゆとりこそ、最大の決断力である」ということだ。静かに、しかし確かな覚悟で歩むその姿が、組織全体に安心と力を与える。今日もまた、私たちは小さな選択の中で徳を積んでいる。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。