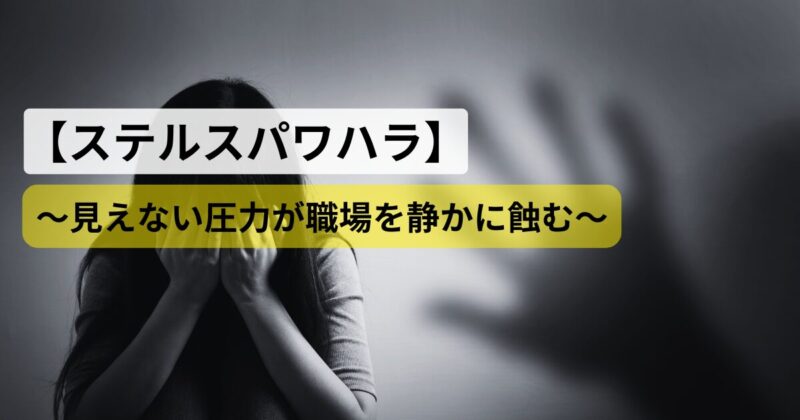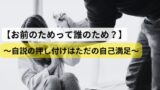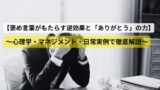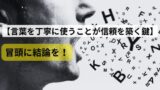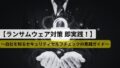職場の人間関係において、上司や先輩が“親しみ”のつもりでかけた言葉が、部下や後輩にとっては“圧力”になることがある。特に中小企業では、組織が小さいゆえに人間関係の距離も近くなりがちだが、それがかえって「ステルスパワハラ」の温床になっている。経営者や管理職が無意識に起こしてしまう言葉の暴力――その正体を解き明かし、心理的安全性を保つ職場づくりのヒントを探っていく。
ステルスパワハラとは何か?
ステルスパワハラとは、表立って怒鳴ったり責めたりするのではなく、“親しみ”や“善意”という名のもとに相手に心理的負担を与える行為である。表現がやわらかい分、加害者側は気づかず、被害者側も訴えづらいため、静かに、確実に職場を蝕んでいく。
「親しさの押しつけ」がストレスになる構造
あるとき、若手社員から「“お前のこと思って言ってるんだよ”って言われるのが一番しんどい」と言われた。ハッとした。こちらは励ましのつもりだったが、相手からすれば逃げ道のない圧力だったのだ。親しさとは本来、双方向の感情であるべきだが、上司が一方的に距離を詰めると、それは「支配」に変わる。
上司は“よかれと思って”やっているケースが多い
「飲み会に誘ったら断られた。最近の若いのは付き合いが悪いな」と感じたことがある人は、もしかしたら自分も無自覚な加害者かもしれない。部下にとっては、上司の誘いは断りづらい“命令”と同義である。上司が無自覚に放つ一言が、部下にとってどれほどのプレッシャーか、想像してみてほしい。
敬語をやめさせる圧力
「そんなにかしこまらなくていいよ」と言った経験はないだろうか?これは一見、部下をリラックスさせる配慮のように聞こえるが、敬語は相手が安心して距離を保てる“防波堤”でもある。無理に崩させるのは、その防波堤を壊し、土足で踏み込むような行為だ。
上司の“善意”が部下を追い詰める瞬間
多くの中小企業の現場では、「社員を思って」「仲間として」接することが美徳とされている。だが、その善意が時に職場のストレス源になることがある。
「飲みに行こう」「家に来い」――善意が地獄になる時
ある中小企業の社長が、「ウチは社員は家族だと思ってるから」と語り、部下を頻繁に自宅に招いていた。しかし、部下側からは「休日も気が抜けない」との声が上がっていた。善意の押しつけは、相手の自由を奪う。家族のような絆を築きたいなら、まずは相手が“離れる自由”を持っているかを確認すべきだ。
断れない構造そのものがパワー関係
「別に強制じゃないから」と言って誘ったつもりでも、立場の差がある以上、それは“拒否できない命令”になってしまう。断ったあとに評価が下がるのでは?と部下が感じた瞬間、その関係はフラットではない。
上司が「気を遣わずに」と言っても、相手は常に“気を遣っている”
「気を遣わなくていいよ」と言えば言うほど、部下は“どうすれば気を遣わずに済むか”を考え始める。つまり、それ自体が気遣いのトリガーになっているというパラドックス。上司が心掛けるべきは、「気を遣わせない言動」ではなく、「気を遣わずにいられる環境」だ。
言葉に現れる“距離感”を理解する力がマネジメントの素養
組織内コミュニケーションで最も見落とされがちなのが、「言葉の文体に宿る温度差」である。特に中小企業では、規模の小ささゆえに距離の近さが生まれやすい分、無意識の“言葉の圧力”が職場を蝕むことも少なくない。経営者や管理職には、「部下がどんな文体で話しているか」を読み解く感受性が求められる。
常体・敬体・ス体 ― 言葉に宿る“関係性の温度差”
まず整理しておきたいのは、文体にはそれぞれ「関係性を示す温度」が存在するという点だ。たとえば、以下の3つを比較してみる。
- 常体(〜だ・〜する):フラットでストレート。上下関係のない対等な関係で使われやすい。
- 敬体(〜です・〜ます):相手に敬意を示しつつ、適度な距離を保つ文体。ビジネス現場の基本。
- ス体(〜っす・〜っすね):敬語の一部を崩し、親しみを加えた柔らかい文体。相手への敬意を保ちつつ、距離を縮めたいという“自発的なサイン”。
ス体は、主に20代〜30代の若手社員や現場職の中で自然発生的に使われてきた言葉遣いだ。例えば、「了解しました」→「了解っす」「お疲れ様です」→「お疲れっすね」といった具合に、敬意と親しみを融合したような表現がされる。
このス体が興味深いのは、単なる砕けた言葉ではなく、相手に対して敬意は残しつつ“距離を近づけたい”という意思表示である点にある。だからこそ、ス体は“礼儀正しさ”と“親しさ”のちょうど中間に位置する、新たなコミュニケーション手段と捉えるべきだ。

「ス体」は“敬意ある親しさ”の表現
「うまいですね」と「うまいっすね」。言葉としての意味は同じだが、受け手が感じる心理的距離はまったく異なる。
「うまいですね」は、丁寧だが少しよそよそしい印象を与えることもある。一方で「うまいっすね」は、言葉としては少し崩れているものの、砕けた親しみと敬意のバランスを感じさせる文体だ。若手社員がこれを使うとき、そこには「自分から近づいていきたい」というサインが込められている。
ここで大事なのは、ス体は“使われる側”の承認ではなく、“使い始める側”の自発性に意味があるという点だ。つまり、部下が「〜っす」と使い始めたら、それは関係性が良好であるという証であり、上司から「ス体でいいよ」「もっとフランクに話せよ」と強要するものではない。
ス体は許可されて使うものではない。信頼があって自然に使われることで、初めて意味を持つ。だからこそ、上司の側はそれを「受け入れる」ことに徹する必要がある。
経営者に求められる“言葉の感受性”
ここで問われるのは、「上司として、言葉の変化をどう読み取るか」という感受性だ。
たとえば、普段ス体で話していた部下が、ある日突然敬体に戻ったとしたら――そのときこそ、何か違和感や距離を感じているサインかもしれない。逆に、ずっと敬体だった部下がス体を交えるようになったとしたら、あなたとの関係性が深まっている証だと捉えられる。
このように、「何を話すか」ではなく、「どう話しているか」に注目することが、現代のマネジメントにおいて極めて重要な視点となる。
言葉の使い方を正す前に、「なぜこの言葉を選んだのか?」を読み解く。その背景にある心理的距離や緊張感、信頼度を察知できる経営者や上司は、職場に“話しやすい空気”をつくることができる。
🔍補足:後輩管理職に伝えたい「ス体」の見方
新任の管理職や現場リーダーにこそ、この「ス体」の概念を教えておくべきだ。なぜなら、彼らがス体を使う若手社員を「礼儀がなっていない」と一刀両断してしまえば、せっかくの信頼構築の芽を自ら潰してしまうからだ。
「〜っす」だから失礼、「〜です」だから丁寧という単純な二元論ではなく、「どういう気持ちでこの文体を選んでいるか」を想像する癖を持つこと。これが部下育成の第一歩になる。
ス体を単なる“若者言葉”として排除するのではなく、言葉を通じて築かれる関係性の「温度」に敏感になること。それは、これからのマネジメントに欠かせない視点であり、人材の能力を引き出すための前提条件である。
ステルスパワハラの原因と、経営者・管理職がとるべき対策
ステルスパワハラが職場で静かに起きる背景には、多くの場合、「良かれと思ってやっている」距離感の誤解がある。とくに中小企業では、社内の風通しの良さや家族的なつながりを良しとする文化があり、それが裏目に出て“親しさの強要”という無意識の圧力を生みやすい。
「距離を縮めることが信頼の証」だと誤解している経営者や上司は多いが、本当の信頼は“相手の距離を尊重すること”から生まれる。強引な飲み会の誘い、休日の予定への干渉、「ウチはアットホームだからさ」という言葉の裏にある“断れない空気”――こうしたものこそが、ステルスパワハラの温床になる。
また、「フラットな関係性」と「無秩序な関係性」はまったく別物であることを認識しておくべきだ。フラットとは、互いが安心して距離を選べること。上下関係がないからといって、配慮まで放棄してしまえば、それはただの無礼であり、支配に近い力関係を生み出してしまう。
では、こうした“善意の暴走”を防ぎ、心理的に安心できる職場を実現するにはどうすればよいのか。経営者や管理職がすぐに実践できる、3つの具体的な対策を紹介する。
1. 距離を保つことを“礼儀”として定義する
「親しさ」ではなく「安心」を優先する文化を、社内の前提として定めてしまうのがよい。たとえば、敬語での会話をあえて推奨する、社長室のドアを常時開けておくのではなく“閉じておく”ことで境界をつくる――こうした行動は、「冷たい態度」ではなく「配慮の可視化」として受け止められる。距離を取ることは、信頼を壊す行為ではなく、むしろ安心感を守る行為であるという価値観を明文化しておくことが重要だ。
2. 部下の“言葉の変化”を観察する
感情や表情よりも、日々の会話の「文体」や「語尾」に注目することで、職場の心理的安全性に関するサインを早期に察知できる。たとえば、これまで「〜っすね」とス体で話していた部下が、急に「〜です」と敬体に変えたとすれば、それは緊張感の現れかもしれない。文体の変化は“気持ちの変化”のバロメーターである。上司が意識的にその“言葉の兆候”に気づくことは、見えないストレスを防ぐ第一歩になる。
3. プライベートへの介入は“ルールで制限”する
「休日に誘わない」「家に呼ばない」「LINEではなく社内ツールで連絡を取る」など、プライベートとの境界を明文化するルールを設けておくことが有効だ。これは、自由な社風を制限するものではなく、「断る自由」を組織として保障するという意味である。曖昧な“空気”に頼るのではなく、線引きをルール化することで、誰もが安心して働けるベースができあがる。
こうした「距離の感覚」「言葉の変化」「プライベートの線引き」を経営者・管理職が理解し、無意識に圧をかけない組織運営を心がけることが、ステルスパワハラのない職場づくりの第一歩である。特別な研修や制度を設ける前に、まずは「関係性の設計」に目を向けることが求められている。
まとめ ― 距離を尊重することが信頼を生む
ステルスパワハラは、悪意からではなく“関係構築の誤解”から生まれる。経営者や管理職が「相手の距離を尊重する姿勢」を示すことが、最も強い信頼の証である。「距離を取る=冷たい」ではなく、「距離を尊重する=安心感」。これこそが、これからのマネジメントに求められる新しいリーダーシップである。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。