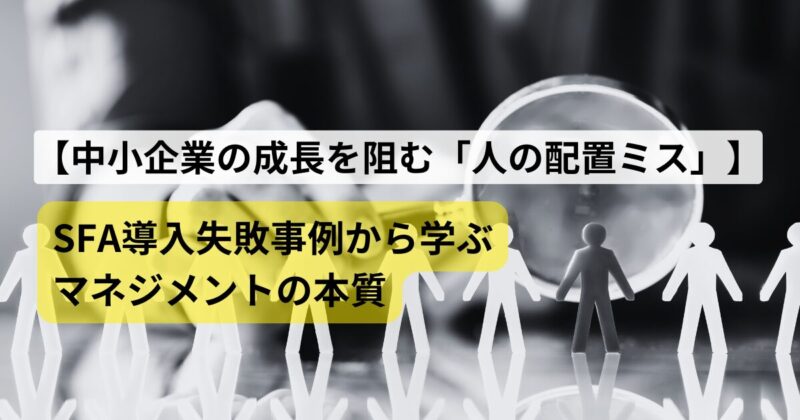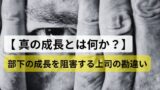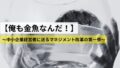「SFAを導入したが、全く活用されていない。どうしたらいいのか?」──筆者がIT顧問として関わるきっかけとなった中小企業の相談である。営業力強化を狙ってSFA(営業支援ツール)を導入したが、運用は停滞し、期待された効果は得られなかった。これは単なるツール選定ミスではない。「何をやるか?」ばかりを重視し、「誰にやらせるか?」という視点が欠落していたことが最大の要因だ。本記事ではこの事例をもとに、IT導入失敗の本質を掘り下げ、中小企業経営者が持つべきマネジメントの視点と、実効性ある対策を提言する。
- IT施策が失敗する中小企業の共通原因
- 「何をやるか?」よりも「誰にやらせるか?」の重要性
- SFA導入失敗の具体的経緯と原因分析
- 経営者にしかできない「人材配置」と「信頼」の実務
- 成功するための具体的マネジメント手法と注意点
経営者のアイデアと限界:「何をやるか?」に囚われた発想の危険性
筆者がIT顧問として相談を受けた中小企業では、営業活動の変革を目指してSFAを導入したが、期待された効果が出ずに困っていた。その背景には、従来の営業スタイルが通用しなくなったという危機感があった。
同業他社のIT活用や業績悪化が影響し、「このままでは競争に負ける」との判断から、営業力を数値で把握し、可視化しようとSFAを導入。しかし、ツールが思ったように活用されず、現場も大きな変革はなく、失敗の道を辿った。この失敗の根本要因を探ると、経営者が「何をやるか」だけに注目し、「誰にやらせるか」…つまり、どのように運用していくか、それを誰に担ってもらうかという人材の視点を欠いていた点に行き着いた。
停滞の連鎖:現場の活用が進まない理由
SFA導入直後は、一部の営業マンが入力を試みたものの、すぐに運用は停滞。理由は明確だった。SFAに関するルールや活用意図が現場に浸透しておらず、個人の解釈でバラバラに活用された結果、収集される情報の質に差が生まれ、全体像が把握できない。ツールは使いづらいとの声も多く、次第に「使う必要があるのか?」「逆に、仕事が増えたんじゃないか?」という疑問が蔓延。最終的には、経営者すら関心を失い、SFAは放置された。
実効性ある人材育成と組織成長の条件:「誰にやらせるか?」がすべてを決める
この失敗を機に、筆者はIT顧問として助言を求められたのだが、まず最初に行ったのは、運用責任者の明確化と、その人材の研修・育成が必要だと指摘した。SFAをただ運用するのではなく、主体的に運用設計し、現場と連携しながら活用する「リーダー」を設け、その人を中心に改革を進める必要があると提言。
導入そのものよりも、「運用の仕組み作り」が成否を分ける。適材に任せて実行させ、信頼して任せる。この基本がなされていない限り、どんなITツールも効果は期待できない。
仕事は「任せる」ことから始まる:信頼が生む自律と成果
多くの中小企業経営者は、「教えること」「管理すること」が人材育成だと誤認しているが、実際には「任せること」から育成はスタートする。実務を任せ、試行錯誤させ、必要な時だけ支援する。そして、結果については指導者(上司)が責任をとる。このスタンスが重要であり、これが人を育て、成果へと導く。
つまり、成長のきっかけとなる環境を与えることが必須なのだ。今回のSFA再活用においても、「信頼して任せる」という経営者の覚悟が現場の変化(自主性)を促し、最終的にはSFAの活用で新たな営業戦略や顧客対応の変化を生み出すことに繋がった。
まとめ:企業の未来は「誰に任せるか」で決まる
中小企業の成長は「やること」ではなく「誰がやるか」で決まる。ツールの導入や施策は手段にすぎない。これをどう活かすかは、任された人次第だ。経営者は施策よりも人材を選び、その人が成果を出す環境を整え、信じて任せる。これが企業を成長させる唯一の道であり、持続的な発展を支える本質である。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。