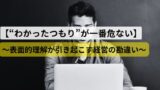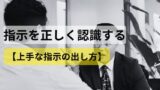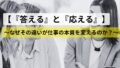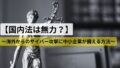戦略的に考えることの重要性は、多くの中小企業経営者も頭では理解している。しかし、いざ実行に移そうとすると、なぜか手が止まる。目の前の業務に追われ、立てた戦略が机上の空論に終わってしまう…そんな「あるある」は数え切れない。本稿では、なぜ中小企業では戦略が「わかっていても実行できない」のか、経営者の心理と組織構造の両面からその要因を深掘りし、現実に即した納得解と実践策を提示する。「FOMO(取りこぼし恐怖)」「合意回避の罠」など、誰もが無意識に陥る落とし穴に気づき、抜け出すための視点を共有したい。戦略とは、やることを増やすことではなく、むしろ「捨てることに納得する技術」であることを、ここで明らかにしていく。
「戦略を考えているつもり」になる心理のワナ
戦略を考えているようで、実際には目の前の業務を整理しているだけ。中小企業経営者が陥りがちな「戦略思考の誤解」には、共通する心理的ワナが存在する。
タスクを並べて“戦略的になった気分”
中小企業の会議でよく見かけるのが、「今月のやることリスト」をホワイトボードに書き出すシーン。これを「戦略会議」と呼んでいたりするが、実態は単なるToDoの整理である。戦略とは、長期視点での方向づけであり、優先順位とリソース配分の決断を含む。だが、タスクを並べることで「考えた気分」になれるため、経営者も社員も安心してしまう。いわば「カロリーゼロの思考」であり、脳がやった気になる幻想だ。

FOMO(取りこぼし恐怖)がターゲットを曖昧にする
「すべてのお客様に対応したい」「あれも売れるかもしれない」──これはFOMO(Fear of Missing Out=取りこぼし恐怖)の典型である。とくに売上に敏感な中小企業では、捨てる決断ができないことが多い。結果、ターゲットが曖昧になり、メッセージは拡散し、施策はぼやける。まるで、結婚式場で全員に向かってプロポーズしているようなものだ。誰にも響かないし、誰にも選ばれない。
合意回避と責任回避の構造
戦略を「皆で決めよう」と言い出した瞬間、それは合意の政治になる。反対者がいない落とし所にしかたどり着かず、結果、誰の心にも刺さらない戦略が出来上がる。これは実は、経営者自身が責任を回避したいがための構造でもある。「みんなで決めたから失敗しても仕方がない」という空気をつくり、自分のリーダーシップの不在を正当化してしまうのだ。
戦略が続かない“現実の壁”
戦略を立てたとしても、それが継続しない。中小企業においては、「考える時間もなくて実行できない」のではなく、「やろうとしたけど続かなかった」という挫折の方が多い。この“現実の壁”は、経営者個人の意思の問題にとどまらず、組織の構造、文化、心理的バイアスなど複雑に絡み合った要因によって形成されている。以下では、それぞれの要素を具体的に分解し、なぜ「続かないのか」の本質を明らかにしていく。
初速はあるが燃料切れする理由
中小企業の経営者ほど、「よし、やろう!」と決断した初期の推進力は強い。実際、多くの戦略や取り組みは最初の1ヶ月〜2ヶ月は動く。メールも飛び交い、ミーティングも設定され、社員にも緊張感が走る。しかし、3ヶ月目を過ぎると空気が変わる。急に静かになり、「あの件ってどうなったんだっけ?」となる。

なぜか?それは、「維持する仕組み」がないからだ。
戦略の継続には、「熱量」ではなく「仕組み」が不可欠である。継続とは、気合や根性ではなく、ルーチンと可視化によって維持される。たとえば、進捗を見える化するダッシュボードがなければ、結果の良し悪し以前に「進んでるのかどうか」すら誰もわからない。KPIが数字で定義されていなければ、評価もできず、自然消滅する。
もう一つの大きな要因は、戦略の「責任者不在」である。多くの中小企業では、戦略を経営者が決め、現場に丸投げされる。しかし、担当が曖昧で、「誰がこのプロジェクトを前に進めるのか」が明確でないままでは、責任の所在が不明瞭になる。結果として、動かない=悪い、と判断されず、やめるタイミングも誰が決めるかわからないままフェードアウトする。
さらに、「そもそも戦略を見直す時間がない」という問題もある。売上や資金繰りなど日々のオペレーションが「緊急」案件として目の前に立ちはだかる中で、「重要だけど緊急ではない戦略」は、後回しにされる宿命を持つ。これは「緊急性バイアス」と呼ばれ、短期的成果を優先する経営判断に影響を与える。
結局のところ、初速が出せるのは「やるぞ!」という気持ちがあるからだが、それを冷静に構造として支える「仕組み」と「時間配分」の設計ができていない限り、長続きはしない。
“お上任せ”という他責発想
多くの中小企業では、「自分たちで考える」よりも「外部が言っていたから」「補助金で言われたから」「ベンダーが提案してきたから」など、外部の声をそのまま戦略に取り込むケースが多い。これは一見、柔軟で適応力があるようにも見えるが、実態は「判断の責任を他人に預ける」思考から抜け出せていない。
この背景には、「失敗したくない」「自分の責任にはしたくない」という潜在的な恐れがある。とくに家業型の経営や、地元での人間関係が濃い企業ほど、「判断を間違えた社長」と見られることへのプレッシャーが大きい。そのため、他人のせいにできる形で物事を進めようとする無意識の行動が生まれる。

ここで問題なのは、外部の論理と自社の現実は一致しないことが多いという点だ。行政のモデル事業、業界団体の推奨、ITベンダーの成功事例…。どれも一見すると「正解」に見えるが、それが自社の文化やリソースにフィットしているとは限らない。
さらに、「お上任せ」の文化が根付くと、社員にもその空気が伝染する。「上から言われたからやる」「どうせまたやめるでしょ」という“やらされ感”が組織に蔓延すると、戦略は実行されないまま形骸化する。
この構造から脱却するには、経営者が「決めることの覚悟」を持つこと、そして外部の提案を受ける前に「自社として何を実現したいか」を明確にする必要がある。言い換えれば、「判断は自分たちがする」姿勢を持たなければ、どんな戦略も風まかせで終わる。
従業員が動けない戦略
立派な戦略を経営者が語っても、現場がまったく動かない──これも中小企業で頻繁に起こる現象だ。その理由はシンプルで、戦略が現場の言葉に落ちていないからである。
経営者は「ブランド価値の再定義」や「カスタマージャーニーの設計」といった言葉を使いがちだが、現場のスタッフにとっては、それが自分の日々の行動とどう関係しているかが全く見えない。
ここには、言語化の壁と抽象化バイアスが存在する。つまり、「難しい言葉で話せば戦略っぽくなる」という思い込みだ。だが実際には、「お客様からの問い合わせに1時間以内に返す」など、誰でも理解できる具体的な行動に落とし込まれなければ、人は動けない。
また、従業員にとって「戦略」という言葉自体がプレッシャーになることもある。「なんかすごいことをやらされそう」「自分にできるのかな」という不安が芽生えると、最初から距離を取ってしまう。
さらに、これは重要な視点だが、「従業員が行動できない」のではなく、「行動するための余白がない」ことが多い。現場はすでに業務で手一杯であり、新しいことを始めるには、まず何かを減らす必要がある。にもかかわらず、戦略は「追加タスク」として降ってくる。これでは誰も動けるはずがない。
この問題に対処するには、戦略を現場目線で翻訳する「中間層のマネージャー」や「言葉の編集者」が必要だ。そして経営者自身も、「この戦略は、誰の、どんな日常行動に変化を起こすのか?」という問いを自らに立ててから発信するべきである。
このように、戦略が「続かない」のは、精神論ややる気の問題ではなく、設計と翻訳、そして責任構造の設計が甘いからである。中小企業こそ、戦略の実行力は「続ける力=構造化の力」であることを認識する必要がある。
腑に落ちる「戦略の納得解」
戦略は“計画”ではなく、“納得”である。ここでいう「納得」とは、経営者の中で理屈が通ることではなく、組織全体が“そうだよな”と腹で理解できることを意味する。この「納得」がないままに掲げられた戦略は、紙に書かれただけのスローガンで終わる。では、納得のある戦略とはどう設計されるのか。以下に、実行可能で本質的な4つの視点を提示する。
先に「やめる基準」を決める
中小企業が戦略を立てる際、多くの場合は「やることリスト」から始まる。もちろん、目指す方向性を明文化するのは重要だ。だが、本当の意味で組織を動かすのは「やらないこと」を明確にすることである。
「やらないこと」を決めるのがなぜ戦略に直結するのか?
それは中小企業が持つ限られた人材・時間・資金というリソースの性質と密接に関係している。何でも手を出せる大企業と違い、中小企業は「何をやらないか」を決めない限り、本当にやるべきことに集中できない構造になっている。
さらに心理的側面から見ると、「やめる」とは、希望を捨てる行為に等しく、実はとても怖い。だからこそ多くの経営者は、期待値の高い事業・長年続けてきた施策・惰性で回しているサービスなどを「もう少し様子見で…」と結論を先送りにする。
しかしここにこそ、“納得できる戦略”への入り口がある。「やらないことを明文化すること」=自ら捨てる覚悟を持つことが、実は組織にとって最も強いメッセージとなる。「これに集中するぞ」と宣言するのではなく、「これ以外はやらない」と言い切れることが、組織の重心を定めるのである。
ターゲットは“状況”で定義する
戦略とは「誰に、何を、どう届けるか」を定義することでもある。だが多くの企業がやってしまうのが、「属性」ベースでのターゲット設定だ。
例:30代の女性、50代経営者、中堅社員…。
しかし現代の消費者や顧客は、同じ年齢や属性でも、状況が違えばニーズはまったく異なる。たとえば「30代女性」といっても、育児中・独身・転職直後では全然違う。つまり、戦略の精度は「状況の切り取り方」で決まるのだ。
状況ベースの定義とは、「どんな課題を抱えているか」「どんな感情を持っているか」「どんな行動をしようとしているか」など、行動・心理・環境のレンズでターゲットを特定することである。

例として、「新しい会計ソフトを探している経営者」ではなく、
「税理士に毎回丸投げしているが、最近経費が不明瞭になってきたと感じている経営者」と定義すれば、響く提案は全く変わる。
このような定義は、組織の共通認識を強化する効果もある。属性だと「なんとなく」になるが、状況定義は「なるほど、あのタイプね」と現場レベルで共有しやすく、施策の一貫性が増す。
“誰か”ではなく、“いつ・どこで・どう困っている人か”に向ける。これが、行動につながる戦略の第一歩だ。
小さく勝つ3か月スプリント
「戦略」という言葉には、どこか“長期的・大掛かり・壮大”というイメージがある。その結果、「まず1年計画を立てよう」となり、資料は分厚くなり、初月から挫折が始まる。
ここで必要なのは発想の転換である。戦略は“持久走”ではなく、短距離ダッシュの連続で設計すべきものだ。
3か月スプリントとは、「3ヶ月後に何を見て、どう判断するか」を明確に決めてから始める小さな区切り戦略である。
この設計にはいくつかの効用がある:
「スプリント」とは言っても、全社プロジェクトである必要はない。一人の社員から始めてもいい。1人でも勝てば、勝ち方を他者が真似できる。そしてこの「勝ちパターンの共有」が、組織の戦略実行力を育てていく。
重要なのは、「この3ヶ月で何かが大きく変わらなくてもいい」と割り切ること。戦略は成果ではなく、実行を通じた納得で強化されていく。筋トレのように「今日は1回増やせた」ことを喜べる設計が、戦略を文化に変えていく唯一の道なのだ。
戦略を従業員が理解できる言葉にする
戦略が動かない最大の理由は、「伝えたつもり」になっている経営者が多いことにある。戦略は「言葉」で共有されなければ組織に浸透しない。しかし、多くの経営者は“経営者語”で話す。
たとえば、「ブランド価値を再定義する」や「リテンション施策を強化する」といった言葉は、現場からすれば「なんかすごいことやるらしい」で終わってしまう。
戦略を機能させるには、“小学生でもわかる言葉”に翻訳する能力が必要だ。たとえば、
このように、行動に変換できる言葉に落とし込んで初めて、組織は動く。
加えて、言葉を使うときのトーンや態度も重要だ。「この言葉を使っても恥ずかしくないか?」という視点を持つと、自然と社員が自分事化できる言葉にたどり着く。
なお、この重要性は『【「文章化できない病」が組織を蝕む】』でも指摘した通り、「組織の停滞は、経営者の言語化能力不足から始まる」という問題にも直結している。
結論として、戦略とは「行動の前にある言葉の設計」である。これができなければ、戦略は1ミリも動かない。
まとめ:戦略とは「納得して捨てる力」
戦略とは、壮大な目標を掲げることでも、カッコいいスローガンを作ることでもない。「これはやらない」と決め、「これだけやる」と全員が納得すること。戦略とは“納得して捨てる力”である。そしてこの納得は、経営者だけの納得ではなく、従業員一人ひとりが「それならやってみよう」と思えるだけの説明と設計が伴ってこそ機能する。中小企業の戦略はシンプルでなければ続かない。小さな成功を積み上げ、その裏側で数多くの“やらないこと”を捨ててきた経営者こそが、戦略を語る資格を持つのだ。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。