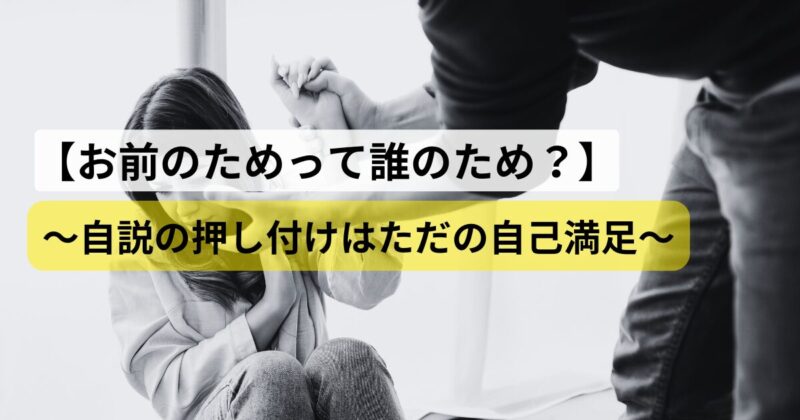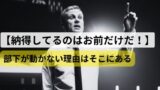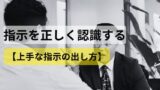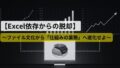「お前のためを思って言っている」…そんな言葉が部下の胸に響かない時代になった。中小企業の経営者・管理職層にとって、人材育成は永遠の課題だが、そこに潜む“自己満足の押し付け指導”に気づいているだろうか。本稿では、現場でよくある「善意の暴走」にメスを入れ、部下との関係性、育成の本質、マネジメントのスタンスについて具体的に掘り下げる。共感と実行可能なヒントを軸に、今求められる「成果を生む伴走型育成」の在り方を提示する。
「お前のため」が通用しないのは、知識の更新を怠った証拠でもある
上司が発する「お前のためを思って」という言葉。その“上から目線”が煙たがられる理由の一つに、言っている内容が的外れであることが多いという現実がある。かつては、現場での経験や失敗談は、直属の上司からでしか学べなかった。つまり「経験者の声=貴重な一次情報」だったのだ。
しかし今は違う。現場の最前線で活躍する人間の知見や、課題に対する具体的な対処法は、ネット上に山ほど転がっている。YouTubeやVoicy、note、LinkedInなどで発信される情報の質は高く、下手をすれば直属の上司よりも明確かつ論理的に説明しているプロがいくらでもいる。
そうした中で、「昔はこうだった」「俺の経験ではこうだ」「こうしないと伸びない」と言われても、
“それ、今の時代に通用します?”
“それってあなたの感想ですよね?”
と心の中で思われてしまうのが現実だ。本人は善意で言っているつもりでも、受け取る側から見ればただの古い知識の押し付けでしかない。

つまり、「お前のため」は本来、情報格差があることを前提としたアドバイスであり、知識や文脈が正確であることが大前提だったはずだ。だが今、部下側の情報取得力は爆発的に高まっており、場合によっては上司よりも深く正しい知識を持っていることすらある。
にもかかわらず、指導者側がアップデートを怠り、「昔はこうだった」「普通はこうする」という価値観をそのまま持ち込むと、相手には押し付け・精神論・感情論にしか聞こえない。
「お前のため」ではなく、正しくは
「自分が安心したいから言ってる」
「知らないことを認めたくないから、経験だけで語っている」
そんな無意識の心情がにじみ出てしまっていることが、部下にはバレてしまっているのだ。
指導する側こそ「学び続けるプロ」であるべき
中小企業では「長くいる人=正しい人」という空気がある。しかしそれは「会社におけるポジション」が上であることを示しているだけで、知識や価値提供のレベルが高いことの証明にはならない。
経営者や管理職が、「俺が上司だ」「俺の経験がすべてだ」と思った瞬間、その人は「学ばなくなった人」になり、部下からは敬意ではなく“距離”を取られる存在になっていく。

現代は、「学び続ける人」こそが信頼される。経験は大事だが、経験に“意味”を与えるのは、そこに現代の文脈をどう接続するかだ。
以下のような上司の姿勢こそが、今求められている。
もはや「俺が言うんだから聞け」では誰も動かない。“自分も学んでいる”というスタンスが、部下を動かす力になるのだ。
部下の成果は上司の責任か?
成果が出ないと「ちゃんと教えたのに」「何度も言ったのに」と嘆く上司は多い。だが、それは果たして上司の責任なのか?まず確認すべきは「それは誰の課題なのか」という視点である。
アドラー心理学「課題の分離」からのヒント
アドラー心理学の中で非常に重要とされるのが「課題の分離」という考え方である。これは、その問題や成果が「誰の責任に属するか」を明確に切り分けようというものだ。
部下が仕事を覚える、ミスを減らす、成果を出す、成長する…これらはすべて部下自身の課題である。上司がどれだけ努力しても、本人がその気にならなければ変わらないし、動かない。
にもかかわらず、多くの上司は、
「自分がちゃんと言えば相手は変わるはず」
「教えたんだから成果が出るべき」
と、相手の課題を自分の手元に引き寄せてしまう。
これは一見“責任感の強い上司”のように見えるが、実態は逆だ。課題を取り上げた結果、こうなる。
課題の分離ができていれば、このような泥沼は避けられる。
つまり、
成果を出すかどうかは部下の課題。
そのための環境やきっかけを作るのは上司の課題。
この境界線を明確に引くことが、健全なマネジメントの第一歩である。
そして、もし部下が成果を出せなかった場合でも、「成果が出なかった」という結果は上司が背負うべきだが、「なぜやらなかったか」というプロセスまで背負う必要はない。この線引きができないと、上司自身が消耗し続ける。
部下に成果を「出させる」ために怒鳴ったり、詰めたり、追い詰めたりするのは、「課題の混同」によって起きる典型例であり、成果にも結びつかない。
「やるかどうか」は部下の自由、「どう受け取らせるか」は上司の工夫
課題の分離とは、「手放すこと」だ。だがそれは「放置すること」ではない。
部下の課題であっても、それに対してどんな問いかけをするか/どんな選択肢を見せるか/どう受け取らせるかは、上司の工夫で変わる領域である。
- 「やる気ないのか?」と詰めるのではなく
- 「どうしたらやれそう?」と聞く
- 「なんでできない?」ではなく
- 「何が壁になってると思う?」と対話する
これはあくまで相手の課題には踏み込まず、関心を寄せるという行為であり、「やれ」と命じることとはまったく異なる。
部下が“自分ごと”として課題を認識しない限り、本質的な成果は出ない。だからこそ、上司は「どうすれば本人が自分の課題として認識できるか」にエネルギーを注ぐべきなのだ。
成果を出す責任は上司にある。ただし、成果を「やらせる権利」はない
ここで誤解してはいけないのは、「成果の責任を放棄する」という話ではないということ。
上司や経営者は、部門や組織の成果について、当然ながら説明責任を持つ。結果責任は免れない。
しかし、そのために「部下を動かす」という発想では限界がある。
なぜなら、部下はロボットではないし、指示や命令で動かされる時代ではないからだ。
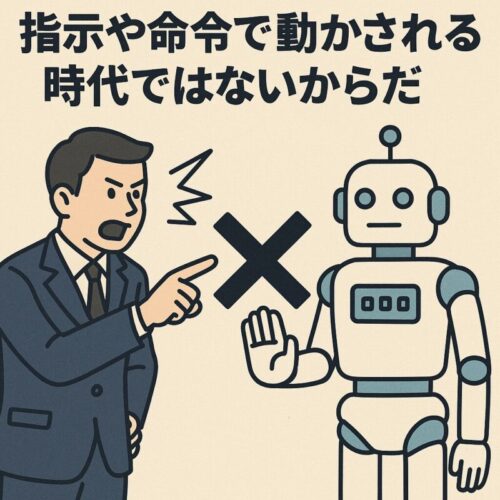
成果は、自発的な行動と挑戦の中からしか生まれない。その自発性を引き出すための環境整備こそが、次の章で述べる管理職の役割となる。
だからこそ、課題の分離によって「やるのは本人」「支えるのが自分」という正しい位置づけに立ち戻る必要がある。
人を育てるとは、仕事を創ることだ——伴走型育成と上司の本質的な役割
育成とは「叱ること」でも「指導すること」でもない。本質は“試合の場”をつくることだ。成長するかどうかは本人次第だが、そのチャンスを与えるかどうかは、完全に上司の責任である。
「育てる」とは、仕事をつくること
多くの上司は、育成という言葉を「できないことを教えること」や「行動させること」と思い込んでいる。だが、本当の育成とはそういうことではない。
育てるとは、仕事を与えること。もっと言えば、仕事を創ることだ。
部下は、組織の一員である以上、自分の裁量で勝手に役割を決めることはできない。どれだけ力をつけても、どれだけ自主的に学んでも、「それを発揮する場」を与えられなければ、自己完結するだけで終わる。
つまり、練習だけしても、試合に出なければプロとして成長しないということだ。
実務の中でしか学べない“本番の経験”を積ませるには、上司が「試合」をデザインしなければならない。これが育成の本質であり、上司の最重要責務である。
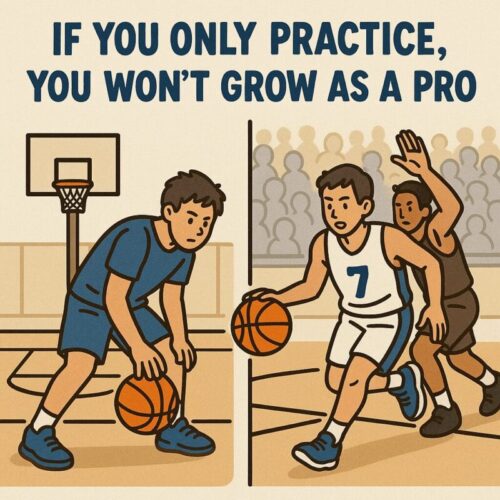
どんなに努力しても、試合に出る機会を与えられなければ結果は出ない。結果がなければ成長も証明されない。にもかかわらず、「成果が出ない」と怒る上司がいるとすれば、それは無能を通り越して責任放棄だ。
指導ではなく、構造を設計せよ
上司がやるべきことは、部下に「こうしろ」と言い続けることではなく、挑戦する構造を設計することである。
こうした環境がなければ、部下は何も仕掛けない。何も起こさない。言われたことだけやって、なるべくミスせずにやり過ごす…それは育成の死である。
管理職とは、部下の成長に責任を持つ立場ではあるが、直接“成長させること”はできない。
できるのは、成長が起きる「場」を整え、「きっかけ」を仕込むことだけだ。
「問いかける上司」は、信頼される上司
問いかけは、育成の武器である。
「なぜそうしたのか?」「次はどうすればもっと良くなると思う?」
…こうした問いは、部下に“自分で考える習慣”を芽生えさせる。説教や指示は、その瞬間は効いているように見えるが、定着しない。学びにはならない。
問いかけは、思考を刺激し、自走を促す。
また、「がんばれ」よりも「○○をこうしてみないか?」と具体的な行動に落とし込む方が、はるかに実行されやすい。人は“厳しさ”より“明確さ”に従うのだ。
長く働いているから、管理職になれるわけではない
そもそも「年数が経ったから」「経験を積んだから」管理職になるという考え方自体が、今の組織づくりには合っていない。
管理職とは、
- 人を活かす場をつくる人
- 組織の未来を設計する人
- 結果ではなく“構造”に責任を持つ人
でなければならない。これができない人は、どれだけ経験があっても、人を育てることは理論的に不可能である。なぜなら、「人が成長する構造」を自分で作り出せないからだ。
仕事を創れない人に、人を育てることはできない。
人を育てられない組織に、成長はない。
だからこそ、管理職には「試合をつくる力」「構造を設計する力」が必要不可欠なのである。
まとめ:育成は伴走であり、強制ではない
「お前のため」という言葉に込めた“善意”が、相手にとっては“圧”でしかないことに気づくべきだ。育成も成果も最終的には本人の責任であり、管理職や経営者ができるのは、信頼と環境を与えることだけだ。
会社の未来を担うのは、社員の“自律的な行動”である。そのためにはまず、経営者・上司自身が「自分の正しさを手放す勇気」を持たなければならない。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。