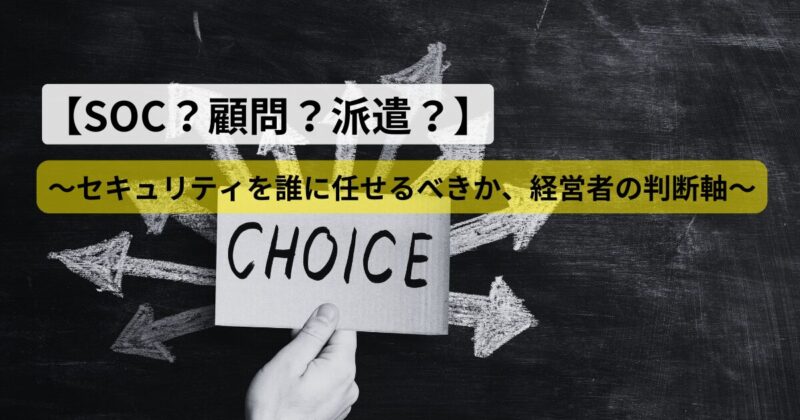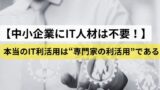「ITに詳しい人がいれば…」
中小企業の多くがそう考える。だが、実際に採用してもうまくいかない。続かない。結果的に何も変わらない…それが多くの現場で起きている現実だ。
セキュリティ対策が急務となった今、社内での人材確保にこだわるのは非現実的である。本稿では、外部の力をどう活用するかを軸に「SOC」「IT顧問」「派遣」の3つを徹底比較。費用感・役割・デメリットを明確に整理し、中小企業にとって最適なセキュリティ運用モデルを提案する。
社内にIT人材を育てるのは、正直ムリだ
採用がそもそも無理ゲー
IT人材の採用は、いま最も難易度が高い領域だ。特にセキュリティ人材は大手企業が高額報酬で奪い合っており、年収800万〜1000万が相場。中小企業が出せる年収では、そもそも候補者リストに載らない。
それでも無理して雇うと、未経験者やスキル不足の人材に頼ることになり、逆にリスクが高まる。業務を任せられず、育成にも時間とコストがかかる。ようやく育った頃には他社に引き抜かれる、というのが現場のリアルである。
しかも、経営者の多くは「ITに強そうな若手を一人置いておけばなんとかなる」と誤解しており、それがさらに問題を深刻にしている。
1人でなんとかしろは酷すぎる
仮に採用できたとしても、その人が社内唯一のIT担当者となる。これが大きな問題だ。
セキュリティも、ネットワークも、システムも、トラブル対応も…すべて1人でこなさなければならない。しかしITというのは非常に専門的かつ多岐にわたる分野で、医療で例えるなら「外科・内科・精神科すべてやって」と言っているようなもの。
加えて、相談相手もおらず、上司もその分野には無関心、判断の支援もなし。しかもトラブルが起きたら「お前が何とかしろ」とプレッシャーだけは大きい。
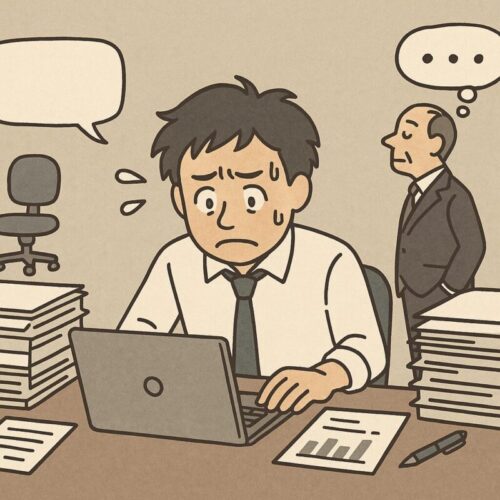
こうした環境では、スキルの成長どころか、精神的に消耗し、短期間で離職するのが関の山だ。孤立したIT担当が定着しないのは、本人の能力ではなく、組織構造の問題である。
評価もキャリアもあったもんじゃない
さらに深刻なのは、人事評価とキャリア設計の不在だ。
営業なら売上、経理ならミスの少なさなど、評価の基準がある。しかしITは成果が見えにくく、「トラブルがない=何もしていない」と誤解されがちだ。実際には、日々のメンテナンスやトラブル予防が仕事の大半なのに、問題が起きないことが逆に評価されない構造になっている。
また、IT人材が成長したとしても、その先のキャリアパスが社内に用意されていない。昇格もなければ、役員登用もない。「この会社にいても成長できない」と思われれば、転職されるのは当然だ。
つまり、中小企業でのIT人材確保は、「採用できない」「定着しない」「育成できない」の三重苦に陥る構造になっている。これを根性論で解決しようとするのは、あまりにも非現実的だ。
🔍補足:この構造的課題の原因は?
- IT=裏方業務という認識のまま、経営課題として扱っていない
- 評価制度にIT領域の基準がない(「何をすれば評価されるか」が不明確)
- 経営者が「自分が理解できない分野は他人任せ」にしている
- 担当者1名=体制ではなく「属人化」であり、常に退職リスクが付きまとう
任せるなら誰がベスト? ― 外部の力、3つの選択肢
外部に任せる方法として、大きく3つのパターンがある。それぞれの「得意分野」と「限界」を整理してみよう。
① SOCサービス:監視はプロに任せる
- 料金目安:月額5〜20万円
- 特徴:24時間体制の不正アクセス監視
メリット:
・人を雇うより安い
・クラウド型で導入が手軽
・専門家によるモニタリングが常時稼働
デメリット:
・「見てるだけ」で、対応はしてくれない
・アラートが来ても、社内に対応できる人がいないと詰む
② IT顧問:経営判断をサポート
- 料金目安:月額10〜30万円
- 特徴:社長の右腕になるITアドバイザー
メリット:
・社長に「何を選ぶべきか」を教えてくれる
・セカンドオピニオンとして冷静に助言
・営業トークに乗せられない仕組みが作れる
デメリット:
・設定や監視は別途業者が必要
・あくまで“相談役”、実務は他で補完すべき
③ 派遣人材:現場で動いてくれる
- 料金目安:時給3,000〜6,000円(月50〜100万円)
- 特徴:手を動かせる即戦力の外部スタッフ
メリット:
・設定変更、障害対応など実務に強い
・「今すぐ誰か来てくれ!」に対応できる
デメリット:
・高い
・スキルにバラつきあり
・担当者が変わると知識が途切れる
最適解は「組み合わせ」しかない
中小企業にとって最も現実的で、かつ持続可能なセキュリティ体制は、「どれか1つに頼る」のではなく、複数の手段を組み合わせて役割分担することである。なぜなら、各サービスには得意・不得意があり、それぞれの穴を埋め合うことでコストを抑えつつリスクを分散できるからだ。
SOCで「見張り役」をアウトソースする
24時間365日、自社で監視体制を敷くのは不可能だ。そもそも人も予算も足りない。しかし、セキュリティインシデントは夜間や休日こそ発生リスクが高い。この「空白の時間」を守る手段として、SOC(Security Operation Center)の活用は非常に合理的である。
SOCは常時ログを監視し、異常があれば即時通知してくれる。これは「火災報知器」のような役割であり、初動対応のタイミングを逃さない仕組みだ。
月額5〜20万円程度でこの安心が手に入るなら、間違いなくコスト以上の効果がある。
ただし、SOCは「警告を出すだけ」で、実際に対応する手は社内や別の外部リソースに委ねる必要がある。監視と対応は分けて考えるべきというのが重要なポイントだ。
顧問で「判断」と「舵取り」をサポートする
システムやツールを導入する際に、経営者が最も困るのが「何が正しい選択なのかがわからない」ことだ。ITベンダーの提案は製品にバイアスがかかっており、営業トークを鵜呑みにすると不要な投資や機能過剰のシステムに手を出してしまう。
ここで必要なのが、経営とITの両方に精通した中立的な立場の「IT顧問」だ。
顧問は、社長の「わからない」を整理し、選定の助言を行い、ベンダーとの交渉にも立ち会ってくれる。さらに、将来的なIT投資の方向性や優先順位づけも含めて戦略的に伴走する。
月額10〜30万円と聞くと高く感じるかもしれないが、誤ったIT投資による損失を1回防ぐだけでも元が取れる。経営判断の支援として顧問を活用するのは、もはや「保険」に近い存在だ。
社内は「IT窓口」役だけでいい
外部を活用すると言っても、完全に丸投げでは運用が回らない。そのため、社内に1人、外部と連携する「窓口担当」を置くことがカギとなる。
この窓口担当は、専門的な知識までは不要だが、以下の役割を担う必要がある。
- SOCや顧問、派遣人材との連絡・調整
- インシデント発生時の社内情報の提供
- 社内での注意喚起や手順の周知
重要なのは、この担当者がセキュリティを理解する必要はないということだ。むしろ「報連相ができる人」「社内外の調整が得意な人」が適任であり、経理・総務との兼任でも問題ない。
つまり、「社内にIT人材を抱える」のではなく、必要なときだけ外部に頼れる“窓”を開いておくことが体制整備の本質となる。
💡総括ポイント
- 「人を雇う」よりも「体制を設計する」ことが本質的なセキュリティ対策
- それぞれの役割をプロに任せて、自社は最低限の橋渡しだけに集中すること
- 予算やリソースが限られる中小企業だからこそ、賢く“分担”する体制が必要
まとめ:外部をうまく使えば、セキュリティは経営課題から外せる
セキュリティ対策は、もはや「余裕があったらやる」ものではない。取引先から求められる。補助金の条件になる。保険も効かない。そういう時代になっている。
だからといって、自社ですべて抱え込む必要はない。
見るのはSOC、決めるのは顧問、動くのは派遣や外部業者。
この構成なら、中小企業でも持続可能な体制が作れる。
必要なのは「人を雇うこと」ではなく、「仕組みを整えること」だ。
経営者は、戦うための装備を選ぶ視点でセキュリティ対策を捉えてほしい。
その判断の先にこそ、安心できる経営がある。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。