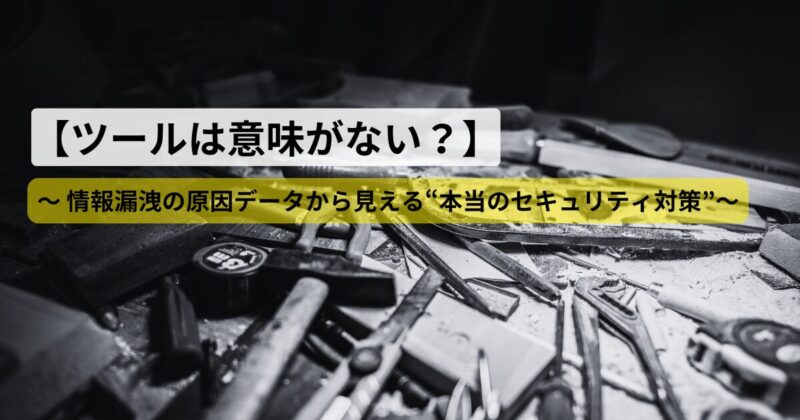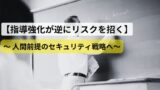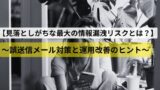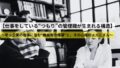セキュリティ対策というと、多くの中小企業では「ツールの導入」が第一選択になりがちだ。ファイアウォール、アンチウイルス、EDR、UTM…。しかし、情報漏洩事故の大半が「人」によって引き起こされているという事実をご存知だろうか?本稿では、「ツールでは防げない情報漏洩」の現実を明らかにし、中小企業が限られたリソースで実行すべき“本質的なセキュリティ対策”としての業務設計の在り方を解説する。中小企業の経営者向けに、IT初心者でも理解でき、かつ実行可能な視点を提示する。
セキュリティツールで防げることをまず整理する
セキュリティツールが無意味だという話ではない。一定のリスクに対しては、確かに効果を発揮する。しかし万能ではないという認識が必要だ。
ウイルス・マルウェア(アンチウイルス/EDR)
外部から侵入するウイルスやマルウェア、ランサムウェアといった脅威には、アンチウイルスソフトやEDR(Endpoint Detection and Response)が有効だ。ファイルの挙動を監視し、不審な活動を検出してブロックできる。しかし、最新の脅威に対応するためには、ツールの運用や更新も含めた「継続的な管理」が不可欠であり、導入だけでは不十分であることに注意すべきだ。
不正アクセス(ファイアウォール/UTM)
ファイアウォールやUTMは、外部からの不正なアクセスをブロックする「門番」のような存在だ。ポートの開閉、通信プロトコルの制御など、技術的には高度な機能が多い。だが、設定ミスや更新漏れ、運用人材の不足によって、その性能は簡単に無効化されてしまう。
盗難・紛失対策(暗号化/リモートワイプ)
ノートPCやUSBの持ち出しによる紛失リスクに対しては、デバイスの暗号化や、万が一の際に遠隔からデータを消去するリモートワイプ機能が効果的だ。しかし、実際には設定されていなかったり、操作ミスで情報が残ったまま廃棄されたりするケースも珍しくない。
操作ログの記録・監視(SIEM/SOC)
ユーザーの操作を記録・監視するSIEMやSOCサービスを導入することで、内部不正や誤操作の兆候を検知できる。だが、検知した後の対応体制や判断基準が曖昧なままでは、有事の対応は間に合わない。
しかし…情報漏洩の大半は「人」が原因だった
最新の調査データが示す通り、情報漏洩事故の主因は技術的な攻撃ではなく、人間によるミスや不注意である。
- プライバシーマーク協会(2023年):事故の6割以上が「作業・操作ミス」
- TSR(2024年):上場企業の漏洩事故の21%が「誤送信・誤表示」
- JNSA調査:情報漏洩の60%以上が「内部要因(誤操作・置き忘れ・管理ミス)」
- Verizon DBIR(2024年版):74%の漏洩に人的要因が関与
- Mimecast(2025年6月):95%が「人的ミスを含む」インシデントと回答
つまり、ツールでカバーできる範囲は限定的であり、最大のリスクは“人間の行動”にあるというのが現実なのだ。
人的ミスはなくせるのか?
「人的ミスをゼロにする」ことは幻想だ。むしろ、そう考えること自体がリスクである。
ヒューマンエラーをゼロにするのは不可能
人間は疲れるし、忘れるし、勘違いもする。集中力は時間とともに落ち、メンタルや体調にも影響を受ける。ミスが起きるのは「気が緩んでいたから」ではなく、「人間だから」起きる。経営者がまず持つべき視点は、「ヒューマンエラーは避けられない」という事実を受け入れる勇気だ。完璧な社員を求めるのではなく、不完全な人間が動く前提で業務を設計する。これが、現実的かつ成熟した経営判断である。

「気をつけろ」「教育徹底」では限界がある
研修、ポスター、朝礼での注意喚起…。これらをいくら繰り返しても、根本的なミスの発生確率は下がらない。注意喚起は対策ではなく「儀式」に過ぎない。確かに教育は重要だが、それは仕組みを補完するための最後の砦であって、ミスを防ぐ手段の第一選択肢ではない。「教育したから大丈夫」は、最も危険な勘違いだ。人は必ず忘れる。だから、「ミスしにくい構造」を業務そのものに埋め込むことが求められる。
むしろ“必ず起きるもの”と前提にすべき
多くのセキュリティ事故は、「まさか、こんな初歩的なミスが…」というケースが多い。しかし、そこに驚いているようでは遅い。ヒューマンエラーは「起きるかもしれない」ではなく「必ず起きるもの」として扱わなければならない。「うちの社員に限って」は通用しない。逆に言えば、「どんな優秀な人材でもミスをする」ことを想定した業務設計ができているか?が、経営リスクを左右する。

たとえば、重要書類をメールで送る際の誤送信を防ぐには、「送信前にダブルチェックを義務化する」「社外メールアドレスには自動で警告が表示される」といった“起きても事故にならない仕掛け”が必要である。ミスを責めるのではなく、ミスが起きたときにどうなるか?を冷静に設計しておくことが、経営者の腕の見せ所である。
じゃあどうする? ― 「ミスをしない業務設計」へ
「人は必ずミスをする」… この前提に立った業務設計こそが、唯一現実的なセキュリティ対策である。
多くの現場で採られている「ダブルチェック」や「承認フロー」は、あくまで“人的な注意の重ねがけ”に過ぎない。だが、いくら目を増やしても、見る人が同じ人間である限り、ヒューマンエラーのリスクはゼロにはならない。本当に目指すべきは、「人がやるとミスが起きる領域」を正しく見極め、そこを仕組みやツールに置き換える設計である。

人がミスをしやすい部分を見極め、ツールに任せる
業務設計とは「人間の感覚に頼らない設計」であるべきだ。たとえば、メールの誤送信。手入力されたアドレスを“見て確認”するのではなく、システムが自動的に社外アドレスを検知して警告を出す。あるいは、添付ファイルをAIがスキャンし、顧客情報が含まれていれば自動で警告を表示する。これが本来あるべき設計であり、「送信前に誰かがもう一度確認する」という手法は、ミスを前提とした対処ではなく、ミスを起こさない構造の不在を放置しているだけである。
「チェック体制」より「事故が起きない仕組み」を優先せよ
たとえば、書類の提出を二人で確認してからアップロードするフローがあるとする。それでも“間違ったファイル名を見落とす”、“見た気になって通してしまう”のが人間だ。であれば、「請求書フォーマット以外のファイルはアップロードできない」「ファイル名に顧客コードが含まれていないと弾く」など、“そもそも間違いが物理的に起きないようにする”設計が最も効果的だ。チェックは不要。ミスが起きない環境を作ること、それこそが“業務設計”の本質である。
ツールは“万能”ではないが、“適材適所”なら人を超える
パスワードの使い回し、記憶ミス、管理ミス…。これらを人に任せる限り、事故は避けられない。しかし、SSO(シングルサインオン)やパスワードマネージャーを導入すれば、ユーザーは1つの認証で複数のサービスに安全にアクセスでき、「管理する」行為そのものが不要になる。
つまり、人がやると事故になる工程を「人から取り上げる」ことが、本質的なセキュリティ強化である。「使いこなせるか?」ではなく、「使わせないこと」が設計思想でなければならない。
業務設計の基本は“判断”をさせないこと
設定作業、アップデート、アカウント削除など、何をどうするかを人に判断させる時点で、ミスは起きる。たとえば、ユーザーの退職時にはアカウントを自動的に無効化するワークフローを設定する。これにより、「削除し忘れた」「設定ミスだった」などの人為ミスは、設計段階で排除できる。
このように、業務プロセスの中で人が“判断する”場面をなくし、クリック一つ、もしくは自動で進むように組み立てることが“ミスをしない業務設計”の原理原則である。
🧠 要約すると:
- 二重チェック=人的処理の倍化であって、本質的な改善ではない
- 人がやると間違う工程を見極め、そこだけツールに任せる
- ツールは“守る手段”ではなく、“人の代わりに実行する存在”
- 業務設計とは「判断を排除し、自動で完了する流れをつくる」こと
まとめ:ツールは補助。守るのは“業務の仕組み”
ツール導入は意味がないのか?いや、「ツールだけでは守れない」という認識を持つべきなのだ。
- ツールは必要だが「人的ミス」は防げない
- 漏洩の大半はヒューマンエラー
- 経営者が投資すべきは「人の注意」ではなく「ミスを前提にした業務設計」
中小企業にとって、ITセキュリティは「知識」ではなく「設計」の問題である。属人性の高い業務から脱却し、再現性ある業務プロセスに変えていくことこそが、最大のセキュリティ対策である。
最後に。中小企業がこのような業務設計を進めるには、自社だけでは限界がある。「IT顧問」や「外部アドバイザー」の活用は、非常に有効な一手である。実際に『IT顧問のススメ』でも、ツール導入より「運用設計」が重要であることが強く提言している。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。