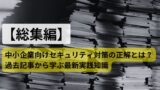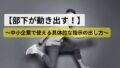社外とのコミュニケーションがデジタル化する中で、Teams、Zoom、Google Chat、Slackなどのオンラインツールを活用する中小企業が増えている。Wi-Fiの顧客提供、オンライン打ち合わせ、ファイルの共同編集などは、業務効率の向上に寄与している一方で、情報漏洩や不正アクセスなどのITセキュリティリスクも潜んでいるのが現実だ。特にIT人材不足の中小企業にとって、「使える環境」はあっても「守れる体制」が欠けていることが多く、それが取引先からの信頼にも関わってくる。本稿では、中小企業が「安心と効率」の両立を図るための実践的アプローチを、現場目線で解説していく。
なぜ「社外とのやりとり」が増えているのか?
社外コミュニケーションの増加は偶然ではない。ビジネスの前提が変化している。
顧客向けWi-Fi提供の一般化と背景
飲食店やサービス業だけでなく、オフィス環境でも「お客様用Wi-Fi」が標準装備となってきている。これは利便性の提供だけでなく、競合との差別化や顧客満足度向上の手段として導入が進んでいる。しかしその裏で「内部ネットワークと分離されていない」「暗号化がされていない」など、基本的なセキュリティ対策がされていないまま利用されているケースが目立つ。
TeamsやZoomの導入で「つながる」が日常に
Microsoft TeamsやZoomは、もはや「非常時の代替手段」ではなく、通常の会議や営業活動に組み込まれている。これにより、社内外を問わず、ITを活用したコミュニケーションの重要度は格段に上がった。一方、アカウントの共用やパスワードの使い回し、ファイル共有の管理が甘くなりがちな点はリスクとなる。
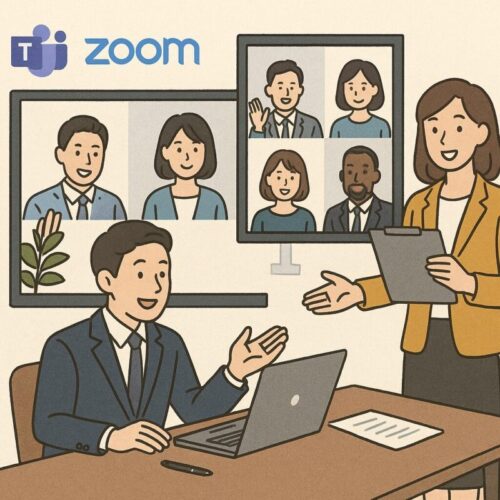
無償チャットツールの普及とグレーゾーンの増加
LINEやMessenger、Chatworkなど、個人利用が前提だったチャットツールが業務に持ち込まれやすくなっている。無料で使える反面、アカウントの権限管理や記録保持、ログ管理が行われておらず、取引先とのやり取りにおける責任の所在が曖昧になる危険性がある。
メリットの裏にある「セキュリティの現実」
利便性が高まるほど、攻撃対象としての「入り口」が増える。だがそのリスクは、往々にして見えにくく、気づいたときには手遅れになっている。
「外とつながる」ことは「攻撃対象になる」ということ
一見当たり前のようで、多くの企業が見落としている視点がある。それは、「インターネットに接続すること=世界中の誰とでも通信できる状態になる」という現実だ。これは良くも悪くも、全方位に扉が開いている状態を意味する。
なぜ、それが問題なのか?
「社外とのスムーズなやり取りのためにVPNを導入した」「Teamsで取引先ともやり取りできるようにした」「お客様用のWi-Fiを設置した」…どれも業務効率化としては正解に見える。だがこの“外部との接続”を一歩間違えば、攻撃者にとっての通用口になる。
▼事例:VPN装置の脆弱性から侵入された現実
たとえば、2022年に発生した小島プレス工業のサイバー攻撃(トヨタ自動車のサプライチェーン被害)では、VPN装置の脆弱性が狙われ、業務が一時停止に追い込まれた。この原因は、機器のファームウェア(内部ソフトウェア)が更新されておらず脆弱な状態のままだったこと。実はこれ、中小企業にありがちな「導入しただけで安心してしまう構造」の典型例である。
VPNそのものは悪くない。問題は、「導入した=安全になった」と錯覚し、その後の運用や更新、ログ監視を怠ったことにある。
この事例が示すように、「外とつながること自体」が悪なのではなく、「つながったあとの対策」が不十分だと、その利便性がそのまま脆弱性になるという点が致命的なのだ。
なぜ、中小企業ほど“対策の穴”が放置されやすいのか?
ここには明確な理由がある。
- 専任のIT担当がいない
- ツール導入=対策完了と誤解している
- 誰が責任者か曖昧なまま運用している
特に中小企業では、総務や経理の担当者が「ついで」でIT関連を見ていたり、外部ベンダー任せにしているケースが多い。UTM(統合脅威管理)やファイアウォールといったセキュリティ機器が導入されていても、「設定の意味がわからない」「ログは確認したことがない」「再起動すらしていない」といった実態が多い。
まさに、『IT顧問のススメ』でも言及したように、“金を払って箱を置いた”ことが対策だと誤認してしまう構造がここにある。
▼実際にあった“放置例”
ある製造業の中小企業では、顧問税理士とのファイル共有のために「無料のクラウドストレージ」を導入していた。便利に使えていたが、ある日、取引先から「御社の資料が他社と共有されていた」との連絡が入った。調査の結果、社員が共有設定を“誰でもリンクを知っていればアクセス可能”にしていたことが原因だった。
これは、セキュリティツールや知識の問題ではなく、「誰がどう使っているかを管理できていない」ことが問題だった。つまり、ツールではなく“人と運用”が最大の盲点だったのだ。
セキュリティは今や「信頼の証明書」である
「そんなに大げさな話じゃない」「うちは狙われるほどの会社じゃない」…そう思いたい気持ちはわかる。しかし今や、取引先がサプライチェーンリスクを強く意識するようになっており、セキュリティ対策の有無が取引判断の基準になる時代である。
- 「貴社はウイルス対策ソフトを導入していますか?」
- 「クラウドの共有フォルダにアクセス権の制限は設けていますか?」
- 「退職者のアカウントはどう管理していますか?」
このような問いに曖昧な答えしか返せない企業は、“取引上のリスク”とみなされる可能性がある。つまり、セキュリティは単なる「防御策」ではなく、「取引を継続する資格」そのものになっている。
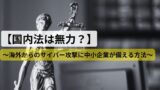
■ポイントまとめ:なぜ、ここを押さえるべきなのか?
- つながる=攻撃の可能性が生まれる
→「つなぐこと」そのものがセキュリティ管理対象になる - 導入ではなく運用こそが本質
→VPNやUTMも「使い続けて初めて意味がある」 - セキュリティ体制=信頼の土台
→取引先から見た「安心して付き合える会社」かを判断される時代
社外コミュニケーションで注意すべき3つのポイント
IT初心者でも意識すべき実務的な注意点を整理する。
ポイント①:アカウントは「個人」に紐づける
アカウントの共用は「誰が何をしたか」がわからなくなる最大の原因だ。特にTeamsやGoogle Workspaceなど、業務用のクラウドサービスでは必ず「個人ID」でログインさせる運用が必要になる。「みんなで使っているから」「退職者のアカウントをそのまま使っている」といった運用は、情報漏洩の温床である。
ポイント②:ツールの「信頼性」と「管理性」を見極める
「無料だから」「手軽だから」と導入したツールに、管理機能が不足していることが多い。たとえばファイルのダウンロード制限ができない、ログが取れない、など。中小企業だからこそ、「コントロールできる範囲で使えるツール」を選ぶことが、長く安全に使うコツだ。
ポイント③:やりとりの「記録管理」はビジネスの信頼基盤
チャットツールやオンライン会議では、記録が残らなければトラブルの元になる。発注・契約などのやり取りをチャットで行った場合、「言った・言わない」の水掛け論を防ぐには記録の保存が必須である。最低限、議事録・チャットログの保存は定期的に行うべきだ。
中小企業が選ぶべきツールと導入の考え方
セキュリティを守りながらも、現実的に「運用できる」体制をどう築くか。
運用できるか?を最優先にする
どんなに機能が優れていても、運用できなければ意味がない。『【総集編】中小企業向けセキュリティ対策の正解とは?』でも言及したように、導入=目的ではなく、運用=成果である。週に一度でもログを確認する、定期的にアップデートをする、それができる体制を前提にツールを選ぶ必要がある。
ベンダー任せにせず「セカンドオピニオン」を持つ
営業トークだけでツールを決めるのは危険である。ツールの導入を検討する際は、独立系のITアドバイザーや信頼できる外部専門家の意見を聞くべきだ。セカンドオピニオンは、ツール選定における「地図とコンパス」である。
IT顧問という「経営の右腕」を持つ
中小企業にとって「IT担当者を雇う」という選択肢は現実的ではない。そこで重要なのが、「IT顧問」を活用するという発想だ。IT顧問は、ツール導入の判断から運用支援、社員教育まで、企業に合った形で継続的なIT支援を行う伴走者である。ツールにお金をかけるのではなく、人に相談する体制を構築することで、初めてIT活用が経営力に変わる。
まとめ:セキュリティは「コスト」ではなく「信頼資産」
セキュリティ対策は、単なるコストではない。顧客や取引先からの信頼を維持する「見えない資産」である。特に社外とつながることが当たり前になった今、情報を守る力は「売上の土台」とも言える。中小企業がIT活用を進める中で最も重要なのは、「導入すること」ではなく、「運用し続けること」であり、そのためには専門家とともに歩む体制づくりが欠かせない。
「安心」と「効率」を両立するには、正しい知識とパートナーが必要だ。
今こそ、中小企業は「守れるITコミュニケーション」を経営戦略の中核に据えるべきである。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。