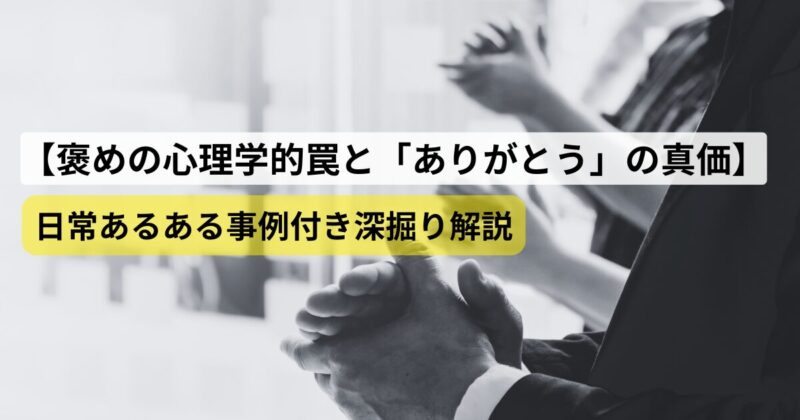「褒めるマネジメント」は瞬間的に場を和ませ、部下のやる気を引き出す手段として広く認知されている。しかし心理学的には、褒め言葉が外的報酬として機能し、長期的には内発的動機を失わせたり、社内の競争を歪ませるリスクが高い。
本稿では、オーバージャスティフィケーション効果や自己決定理論の知見をもとに、経営者が陥りがちな「褒める罠」を具体的な日常あるある事例とともに解説し、対策として「ありがとう」の本質的効果を明らかにする。
褒めるマネジメントに潜む心理学的落とし穴
褒めるという行為は短期的な満足感をもたらす一方で、外的報酬への依存や社内競争の歪みを生む「オーバージャスティフィケーション効果」を引き起こし、長期的には組織パフォーマンスを低下させる可能性がある。
オーバージャスティフィケーション効果で内発的動機が消失する
オーバージャスティフィケーション効果とは、報酬(褒め言葉やボーナスなど)が与えられることで、もともと自発的に行っていた活動への内発的動機が低下する現象である。
1970年代の実験では、パズル遊びに熱中していた子どもたちに報酬を与えると、報酬を取り除いた後は再びパズルに対する興味を示さなくなったことが示された。これは、褒め言葉が「外的インセンティブ」として認知されることで、「自分が本当に楽しんでいた」感覚を損ねるためである。
verywell mind「過剰正当化効果がモチベーションを低下させる仕組み」で公開されているものです。
引用元:verywell mid 「過剰正当化効果がモチベーションを低下させる仕組み」
- 月次ミーティングで「今月もよくやった!」と繰り返し誉めるうち、部下は翌日から成果報告メールで数字だけを盛るようになる。
- 「●●くん、ナイスプレゼン!」という社長の一言を期待して、会議資料を見栄え重視で作り込み、内容の検証がおろそかになる。
承認欲求の加速が社内競争を歪ませる
褒め言葉が承認欲求を刺激し、「誰よりも褒められたい」という動機づけを生むと、同僚との比較や足の引っ張り合いが発生しやすくなる。認知評価理論によれば、評価者からの肯定的フィードバックが「コントロール的」と受け止められると、内発的動機をさらに低下させる傾向がある。
THE DECISION LAB「ある活動に対して報酬を得た後、なぜ私たちはその活動への興味を失ってしまうのでしょうか?」で公開されているものです。
引用元:THE DECISION LAB「ある活動に対して報酬を得た後、なぜ私たちはその活動への興味を失ってしまうのでしょうか?
- 「お前は今月一の売上記録だ!」とトップセールスを褒めると、ほかの営業は数字を隠そうと情報共有を拒否し始める。
- プレゼンで誉められた部下を妬んだ同僚が、裏で悪い噂を流し始め、気づくとチーム内の連携が崩壊寸前に。
自律性の喪失が長期的パフォーマンスを阻害
褒め言葉が承認欲求を刺激し、「誰よりも褒められたい」という動機づけを生むと、同僚との比較や足の引っ張り合いが発生しやすくなる。認知評価理論によれば、評価者からの肯定的フィードバックが「コントロール的」と受け止められると、内発的動機をさらに低下させる傾向がある。
- 予算編成時、部下が「社長が喜ぶ数値を出す」ために安全策ばかり選び、挑戦的な施策を避ける。
- 新規プロジェクト提案の場で「褒められそうな簡単な改善案」だけが提出され、画期的なアイデアが影を潜める。
「ありがとう」が生む深い心理的恩恵
「ありがとう」は外的報酬ではなく感謝という共感を伝え、社員の自律性と有能感を支え、心理的安全性と組織貢献意欲を同時に高める魔法の言葉である。
感謝が生む自己決定感と有能感の強化
自己決定理論は「自律性(autonomy)」「有能感(competence)」「関係性(relatedness)」の三大基本欲求を満たすことが内発的動機を支えるとする。感謝の言葉は、社員が「自分の意思で選択し貢献した」と実感させ、有能感を高める。評価ではなく行動の意義にフォーカスすることで、自律的な動機づけを促進する。
- 売上目標未達でも「今回の試みで得た学びに感謝するよ。次に活かせる貴重なデータだ」と言われると、部下は前向きに改善策を模索し始める。
- 普段は業務に追われがちな若手が、顧客からの感謝メールを社長が転送し「君の動きが取引先に信頼感を与えた。ありがとう」と伝えると、自分の仕事が組織の成果に直結している実感を持つ。
感謝が醸成する心理的安全性と協力文化
感謝の文化は、他者の貢献を当たり前とせず認め合う風土を育み、発言の自由や失敗からの学習を許容する心理的安全性を高める。心理的安全性の高いチームは業績向上や創造性向上との関連が多くの研究で示されている (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)。
National Library of Medicine「「お疲れ様でした」:感謝の言葉が従業員の就業意欲に与える影響」で公開されているものです。
引用元:National Library of Medicine「「お疲れ様でした」:感謝の言葉が従業員の就業意欲に与える影響
- 会議の冒頭で「先週のデータ整理、○○さんのおかげでスムーズに進められた。ありがとう」と共有すると、メンバー間で細かなサポートが当たり前の光景に。
- 失敗事例を共有するときにも「おかげで学びがあった。ありがとう」と言われると、誰もが安心して問題点をオープンにし、建設的な議論が生まれる。
日常的な「ありがとう」が持続的モチベーションを生む
感謝は外的報酬と異なりコストがほとんどかからず、大小問わずどのような行為にも適用可能な普遍性を持つ。定期的に感謝を伝えることで、報酬制度や表彰制度に頼らずとも持続的なモチベーションが維持される。結果として組織運営の柔軟性や迅速性も向上する。
- 朝礼やチャットの定型文に「ありがとうタイム」を導入し、小さな貢献にも感謝を伝え合う習慣が生まれる。
- 月次評価面談で業績数字ではなく「チームのために尽力してくれたことにありがとう」と言われることで、目標の数字達成だけではない価値観が根付く。
まとめ
褒めるマネジメントは表面的にポジティブな手段に見えるが、オーバージャスティフィケーション効果や承認欲求の肥大化、自律性の喪失など、組織に深刻な歪みをもたらすリスクを内包する。経営者は「褒める」ではなく、本質的な「感謝」を意図的に言葉と行動で示すことで、社員の内発的動機を支え、心理的安全性と協力文化を育むべきである。
日常の「ありがとう」が繰り返される職場は、社員が安心して挑戦し学び合う場となり、持続的な成長と健全な組織運営を可能にする。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。