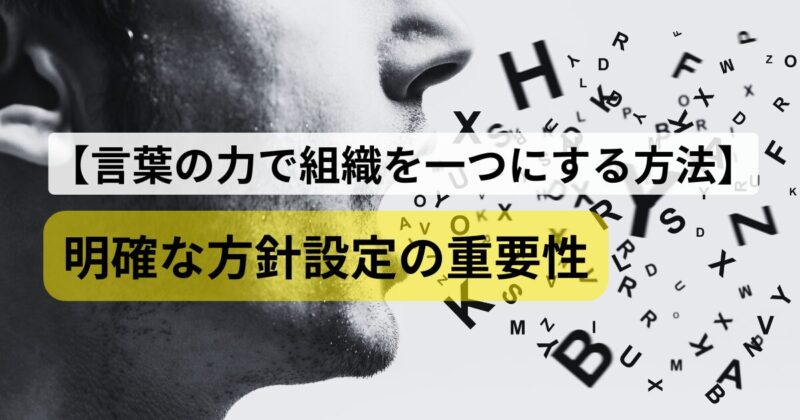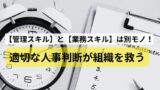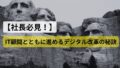企業が新年度や新期のスタート時に掲げる方針は、組織の方向性を明確に示し、全社一丸となって目標達成に向かうための重要な戦略ツールである。しかし、その方針が抽象的で曖昧な表現に留まる場合、従業員一人ひとりの解釈が異なり、結果として統一した行動を生むことができない。
例えば「売上拡大」や「成長促進」といった表現では、何をどこまで達成すれば目標に到達したといえるのか不明確であり、組織の各部門や個々の従業員が別々の方向に進む原因となる。本稿では、明確で具体的な方針設定が組織運営にどれほど重要かを掘り下げ、その実践方法について具体例を挙げながら解説する。
抽象的な方針が生む問題とは?
企業が掲げる方針が曖昧な場合、組織全体の動きが分散し、目標達成が困難になる。ここでは抽象的な方針がどのような問題を引き起こすのか、その具体例と共に詳しく解説する。
解釈のばらつきがもたらす組織の混乱
「拡大」「成長」「促進」など、抽象的な表現は受け手によって解釈が異なる。例えば、「売上拡大」という目標が掲げられた際、一部の従業員は新規顧客の開拓を重視し、別の従業員は既存顧客との取引額を増やすことに注力するかもしれない。
また、製品やサービスの販売量を増やすことを目指す部門もあれば、単価を上げることを拡大と捉える部門も出てくるだろう。こうした解釈のばらつきが、組織全体の一貫性を崩し、目標達成を妨げる大きな要因となる。
具体例:売上拡大の解釈の違い
仮に「売上拡大」という目標が掲げられた場合、営業部門は新規顧客の獲得を優先する一方で、マーケティング部門はキャンペーンを通じた認知度向上に取り組むかもしれない。また、製品開発部門は新製品の開発に集中し、販売部門は既存製品の在庫処分に注力するといった具合に、部門ごとの取り組みがバラバラになる。このような状況では、組織全体で売上を最大化するという目標は達成できない。
管理職の独自解釈によるリスク
抽象的な方針が与えられると、管理職はそれを自ら解釈して部下に指示を出すことになる。例えば、「製品の拡大」を掲げた方針を、ある管理職は販売数量を増やすことと捉え、別の管理職は市場シェアを拡大することと捉える可能性がある。その結果、部門間で矛盾が生じ、組織全体の統一感が失われる事になるだろう。
リアルなケース:曖昧な指示が現場を混乱させる
とある中小企業では、「顧客基盤を拡大せよ」という経営方針が示されたが、具体的な定義が欠けていたため、営業部門では既存顧客の取引額を増やすことに重点が置かれ、マーケティング部門では新規顧客の獲得キャンペーンを計画していた。両者の戦略が合致せず、かえって営業効率が低下したということがあった。
モチベーション低下と離職リスク
曖昧な方針は従業員の混乱を招き、「何をすればよいのか分からない」という状態を生む。特に、管理職が都合よく方針を解釈し、その場その場で異なる指示を出す場合、現場の士気が著しく低下する。「一貫性のない会社」と見なされることで、従業員の会社への信頼が失われ、最悪の場合、優秀な人材の離職を招く可能性がある。

筆者は「管理職研修」などもやっているので、その講義の中で管理職の方に部門・個人・部下…それぞれがどういう目標設定で活動しているのかを問うことがあるのだが、曖昧になっていることがよくあるのだ。
方針や方向性を、その場に応じた解釈(その場しのぎ)で説明したり、自認することでなんとなく方針に添った活動をしていると納得しているのだ。(納得させている?)あまり具体的に設定しても状況に応じた活動ができなくなるため、範囲を絞ることにデメリットがあるのでは…という意見もあるのだが、方針や戦略を固定化することはなく軸を決めたら市場や顧客、従業員の状況によって戦術も含めてアップデートするのが当然であり、それがマネジメントの役割と認識することが適切だと考える。
明確な方針設定がもたらす効果
一方で、明確な方針を掲げることにより、組織全体が目標に向かって一丸となって動くことが可能になる。その効果を具体的に見ていく。
明確な目標が生む組織の一体感
明確で具体的な目標は、従業員一人ひとりが自身の役割を理解し、組織全体として統一感のある行動を取るための基盤となる。「何を」「いつまでに」「どのように」達成すべきかが明示されれば、個々の行動が自然と組織の目標に結びつく。自分が何をするべきかということは、その組織における自分の存在価値(居場所を生み出す)を認識できることになり「頼られている」と感じることにもなる。
仕事において「頼られる喜び」は原動力にもなるため、それを醸成するにも明確な目標設定をすることは重要である。
事例:目標設定で改善された業績
「新規顧客の獲得数を四半期で20%増加させる」という具体的な目標を掲げた結果、営業部門全体で効率的なターゲティングとアプローチが行われ、短期間で目標を達成。マーケティング部門との連携も強化され、広告費用の削減にも成功したという事例があった。
目標が明確であれば、業務遂行中に確認できる結果(スコアボード)も明確になり、あとどのくらい?時間的な猶予は?何が足りない?どこを強化する?…等々…どのような改善行動が必要となるかも、個々に自認することができる。これが「一体感」「一丸となって」ということだ。
経営方針の正確な共有
方針が明確であれば、経営者から管理職、現場スタッフまで一貫したメッセージを共有できる。これにより、部門間の連携が強化され、無駄なリソースの浪費を防ぐことができる。俗に言う「縦割り」になることがない。中小企業の場合は、大きな組織が並列に配置されることが少ないので、縦割りを実感するというよりも、部門長同士の意思疎通が悪い(単純に仲が悪い…信頼関係が構築されていない…など)ために、部下がそれに振り回され同じ会社でも別の方向を見て走っているというような事態も回避できるだろう。
別の方向を向いてしまうと、相互依存関係も崩れるため自部門だけのことしか考えなくなってしまう…これは、従業員にとっても不幸なことであるし、顧客サービスの低下にも繋がってしまう。経営者の発する方針(言葉)の影響範囲は多岐に渡ると認識する必要があるのだ。
ツールの活用
経営方針を共有する際には、ビジュアルツールやマネジメントプラットフォームを活用することが効果的である。プロジェクト管理ツールや業務進捗の可視化が、組織内の情報共有を促進することに繋がる。週次の定例会議で進捗報告など現代では時間の無駄使いと考える方が適切だろう。まとめて報告ではなくリアルタイムでレポートできる環境を整備することもマネジメントの役割となる。
ただ、画面上でしかコミュニケーションがとられないということのデメリットもあるので、対面でのコミュニケーションや適切なフィードバックをすることがマネージャーには求められる。報告を受け自分が納得するに留まらず、部下を納得・安心させるために報告を受けていると自認するべきであろう。
明確な方針を設定する実践方法
ここでは、組織全体が共有できる具体的な方針を設定する方法について、段階的に解説する。
SMART目標の導入
具体的かつ測定可能な目標を設定するために、SMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)のフレームワークを活用してみるのもいいだろう。この方法を使うことで、目標の曖昧さを解消し、達成可能性を高める。独自の管理手法が確立しているのであれば、何らかのフレームワークを導入する必要はないが、次世代マネージャの育成を考慮し、一般的なフレームワークを使うマネジメント手法を実践的に経験する(させる)ということの意義は大きい。
経験も知識もなく、単に仕事ができるようになってきて後輩に仕事の指導もできる…その立場の延長線で管理職になるとマネジメント未経験の影響によりチームの動きが停滞化することにもなりかねない。
定量的な指標の活用
売上額、顧客数、製品数量といった具体的な数値を用いて目標を設定することで、全社的な理解を得やすくする。これにより、進捗の確認も容易になる。
方針の発表とともに数値で評価できる指標については、スコアボードをあらかじめ用意しておき、ここで全社員が進捗を確認できるということも明示する。そうすることで日々の自分の業務報告がどこに反映されるのかも認識することができる。自己都合の報告がもたらす影響が見えることで、責任感の醸成にも繋がる。
継続的なフォローアップと修正
経営方針の進捗状況を定期的にチェックし、必要に応じて修正を行うことが重要である。これにより、現場の混乱を最小限に抑えることができる。定量化された指標はスコアボードでリアルタイムチェックができるだろうが、定量化されない要素…つまり、定性的な状況については経営者を含め管理職は常にウォッチをして共有することが成功の鍵となる。
売上がどうこう…という定例会議は不要と考えるが、従業員のモチベーションや働く環境については個々の状況など細かく認識し、従業員をしっかりと支えサポートする体制を構築することが求められる。
まとめ
方針が具体的で明確であるほど、組織全体が一丸となって動き、目標達成に向けた効率的な取り組みが可能となる。「言葉の力」を有効に活用し、何を達成すべきかを正確に伝えることが、組織の成功を左右する重要な要素である。言葉の乱立で一見、整理されているような方針でもその言葉が「ビッグワード」でどこの会社でも通じるようなことじゃないか…と、感じるものであれば、自分が何をするべきかを見出すことは、ほとんど不可能だろう。自社の社長や経営者の言ってることが「我事」として聞こえてこないようだと、それは何も言ってないと同じことになる。

筆者は方針を発表する立場にいることが多かったのだが「言われていることは、その通りだし適切だと思いますが、私に何をしろってことを言ってるのでしょうか?」と、問われた経験がある。
綺麗な言葉を並べた方針はただの自己満足に過ぎなかったということに気付かされた。それから、いろいろ工夫しながら方針を発表するということはやっていたが、最も効果的で単純な手法としては、方針発表資料に具体的に社員(部下)の氏名を記述して、これをやって欲しいと伝えるようにした。
具体的な数値目標は本人に設定してもらうようにしていたが、それがイメージできるレベルの指示は方針発表の段階からするようにした。これについては方針について評価コメントはなかったが「わかりやすくて、やる気になりました!」とのコメントをもらった記憶がある。
明確な方針とは内容の是非を工夫して構築するというより、部下の反応がそれを証明してくれるものである。経営者や管理職が方針の重要性を再認識し、明確な目標を設定することで、全社的な成功へとつながる道を切り開かれることになるだろう。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、おあいしましょ。