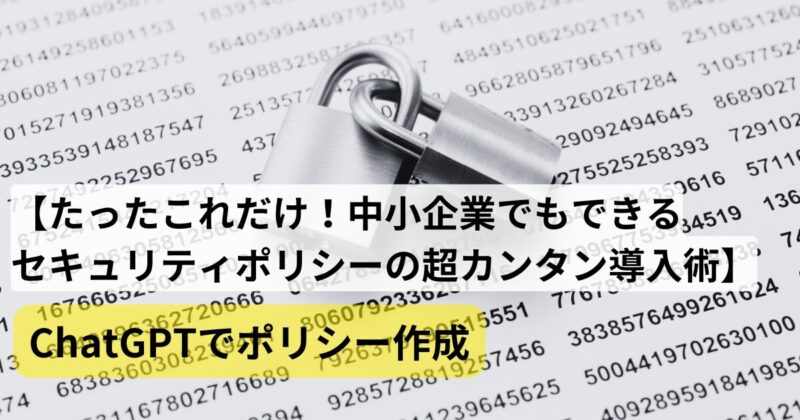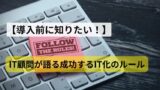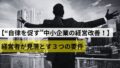セキュリティ対策を進める上で最初に取り組むべきは、華やかなツール導入ではなく、基盤となる「セキュリティポリシー」の策定である。多くの中小企業経営者がその必要性を理解しつつも、専門部署もIT知識もない現実から後回しにしがちだ。
だが、ポリシーこそが従業員の行動を規定し、会社全体でITを安全かつ効率的に活用するための共通認識となる。本稿では、コストを抑えつつ現実的かつ実行可能なセキュリティポリシーの策定手法と、ChatGPTを活用した事例を紹介する。
セキュリティ対策の第一歩は「ポリシー策定」から
中小企業におけるセキュリティ対策の根幹はセキュリティポリシーにある。しかし、IT人材不足やコストの問題から策定に至らない企業が多いのが実情である。
セキュリティポリシーの本質とその役割
セキュリティポリシーとは、企業として情報をどのように取り扱うか、ITの利用をどう規律するかの基本方針を定めたものである。これは単なる書類ではなく、社員の行動を統制する「ルールブック」だ。
ツールではなく「人の行動」がセキュリティを脅かす主因であるという現実を踏まえると、ポリシーがなければ有効な対策など存在しないと言い切ってよい。従業員に対して「どこまで自由にITを使っていいのか」「何が禁止されているのか」を明示するためにも、セキュリティポリシーは不可欠だ。
なぜ中小企業で策定が進まないのか
専門知識がない、コストがかかる、策定しても使い物にならないという懸念が大きい。特に、作成したポリシーが現実と乖離していれば、現場で無視されることも少なくない。厳格すぎるルールは職場の雰囲気を悪化させるだけであり、現実的な内容から始める必要がある。また、従業員に「IT利用は会社員としての義務の範囲である」と認識させる教育的効果も、ポリシーの存在意義として見逃せない。
完璧を求めず「実行できる最小ルール」から
初期段階でのセキュリティポリシーは、完璧さではなく実効性に重点を置くべきだ。抜けがあっても良い。とにかく「存在すること」「従業員が内容を知っていること」「ルールが明文化されていること」それ自体が意味を持つのだ。そして必要に応じてアップデートすることで、状況に応じた柔軟な対策を講じることができる。
ChatGPTでセキュリティポリシーを作成する方法
専門家がいなくてもAIを使えば「最初の一歩」は踏み出せる。実際のプロンプトと出力されたポリシーの内容を紹介する。
実際に作成されたセキュリティポリシーの中身
中小企業でセキュリティ対策を実行していく上で、その基盤となる「セキュリティポリシー」を、セキュリティコンサルタントになって、以下の要件に合致するように作成してください。
# 企業の概要
- 大阪本社で、拠点は東京と名古屋、博多にあり従業員は50名
- 各拠点は光通信で接続している
- 営業マンにはPC持ち出しは禁止しているが、タブレッドを配布している
- PCは一人1台支給しており、ノートPCを利用している
- IT専門部署はなく、詳しい人材もいない。管理部門の人材がIT関連業務は兼務しており必要に応じて対応することにしている
- 各拠点にはIT担当者は不在で、その時に応じて現場の要員が本社の指示で対応している
# 現在のセキュリティ対策
- インターネットの出入り口にはUTMとウイルスチェックのアプライアンス製品を本社含め、各拠点に設置している
- 社内LANについては、ウイルス対策機能が実装されたSW-HUBを設置しウイルスの拡散を防止するようにしている
- OS、アプリケーションのアップデートは基本、各自でやってもらうようにしている
- 原則として無料のクラウドサービスを自由に使うことは禁止しているが、一部で必要に応じて利用していることは認識している
- PCの持ち出しは原則として禁止
- 個々人でアプリケーションをインストールすることは禁止している
- セキュリティ教育などはとくに実施していない。ISMSなど認証取得もしていない
- クライアント管理ソフトは導入しているが、あまり使っていない
# ITの利用状況
- 社内で活用しているシステムは、A社が提供する基幹業務用のパッケージソフトで一部、カスタマイズしている。
- 事務系の処理はMS-365を使っている。リモート会議などはTeamsを使っている。オフィス製品以外はあまり活用できていない
- スケジュール共有や情報共有はクラウドサービスで提供されるグループウェアを利用している
- 自己評価として、機能が重複しているサービス・ソフトがあり、あまり効率的かつ有効活用はできてはいない
# セキュリティポリシー策定について
- あまりガチガチな内容ではなく、認知されて実行しやすく現実に根付いた内容から始めたい
- 漏れがあってもいいので、必要最低限から始めたい
- 運用面については、専門部隊がないので管理部門などの業務範囲で可能な運用体制などの助言が欲しい
- あまりコストかけず運用できるようにしたい
# その他
- この状況で、気がついてなない部分や、重要なポイントがあればそれを含めたポリシー作成をしてください。
以上
以下が実際に、ChatGPTから提示された「セキュリティポリシー」だ。
以下に、貴社の実情に即した**セキュリティポリシー(基本方針と最低限の対策)**を提案します。読みやすく、現場で実行しやすいことを第一にしています。また、最後に運用面の体制づくりや、見落としがちな重要ポイントも補足しています。
セキュリティポリシー(初版)
1. 基本方針
当社は、お客様・取引先・従業員の情報資産を適切に管理し、業務の継続性を確保するために、以下の基本方針に基づき情報セキュリティ対策を実施します。
- 無理なく、業務に支障をきたさない範囲で対策を実施する
- 社内のITリテラシーを踏まえ、理解・実行しやすい運用を目指す
- 外部攻撃・内部ミスの両面に備える
- 少人数体制でも継続可能な運用を重視する
2. 情報資産の取り扱いルール
2.1 PC・端末の利用
- PCは一人1台。貸与されたノートPCおよびタブレット以外の端末で業務を行わない
- PCの持ち出しは禁止。やむを得ない場合は管理部門の許可を得る
- アプリのインストールは禁止。必要な場合は管理部門へ申請
2.2 ソフトウェアとサービスの利用
- 業務利用するクラウドサービス(無料/有料問わず)は管理部門で承認を受ける
- 利用中のOffice365(MS-365)およびグループウェアを業務の中心とする
- 同じ機能を持つサービスの整理は随時行い、効率的な運用を目指す
3. セキュリティ対策
3.1 ネットワークおよびインフラ
- 全拠点でUTMとウイルスチェック機能を有効化
- LAN内ではウイルス対策機能付きスイッチ(SW-HUB)により拡散防止
- 各拠点からのネットワークトラブル・不審通信があれば本社へ報告
3.2 アップデート・パッチ管理
- OS・アプリの更新は各自で月1回以上実施(週次リマインドをTeamsで通知)
- 管理部門はリマインダー作成および状況確認(クライアント管理ソフト活用)
3.3 ウイルス対策
- PCにウイルス対策ソフトを必ずインストール・有効化
- 不審なファイル・メールがあれば、開封せず管理部門に報告
4. ユーザー教育・意識向上
- 年2回(4月・10月)を目安に、10分で終わる簡易なオンライン教育を実施(動画・資料等)
- 管理部門から「やってはいけないことリスト」を配布し、常に目に触れるようにする
- 「よくあるトラブル事例集」を全社で共有し、注意喚起に活用
5. インシデント対応
- 機器の故障、ウイルス感染、不審なメール・挙動があった場合はすぐ管理部門に報告
- 拠点では現場担当が一時対応し、必要に応じて本社の指示に従う
6. 管理・運用体制
- 管理部門をセキュリティ管理の中心とし、以下を担当
・方針の見直し(年1回)
・ソフト・サービスの利用許可管理
・アップデート実施状況の把握
・簡易教育の実施および記録 - 現場からの報告・相談はすべて管理部門へ一本化
- 拠点には専任担当を置かず、各拠点の対応可能者を年度初に1名指定し、リスト化
7. 禁止事項(抜粋)
- 業務PCでの私的利用(SNS、ゲーム、個人メール等)
- フリーWi-Fiの利用(出張時のタブレット利用含む)
- 無断でのアプリ・外部サービス利用
- パスワードの共有、メモ書きでの管理
8. 今後の検討課題(重要)
- クライアント管理ソフトの活用強化
→ アップデートやソフト構成の状況把握に役立てる(教育後に段階的運用) - アカウント管理の整備(特に退職時)
→ 利用中のMS365やグループウェアからのアカウント削除手順を定義 - ファイル共有ルールの明文化
→ グループウェア・Teamsの使い分けを定め、誤送信や情報散乱を防止 - 定期バックアップ体制の整備
→ 最低でも月1回、基幹業務パッケージのデータバックアップ実施を推奨
運用上の助言
- 管理部門には「セキュリティ係」を明確に1名決めて役割を与える
- 業務マニュアルやTeams内に「情報セキュリティ」チャンネルを設け、情報集約
- 教育・通知・報告はTeamsかグループウェアで統一することで、業務との分断を防ぐ
- 施策を全員に強制するのではなく、「実現可能な最小ルール」から始めて改訂していく運用を継続
このポリシーは、**「セキュリティは業務の妨げではなく、支える基盤である」**という理解を社内に浸透させるための第一歩です。今後の社内事情に応じて、段階的に見直し・改善を行ってください。
必要であれば、この内容をWordやPDFのフォーマットでお渡しできます。ご希望があればお知らせください。
今回はこの内容が適切であるかなどの是非は解説しないが、このようにAIを活用することで、必要最低限のセキュリティポリシーの策定ができることを知っておいていただきたいという意図だ。
それなりの内容が盛り込まれているとは、個人的な主観だが評価できる。
ポリシーの運用と管理体制の整備
策定したポリシーを形骸化させないためには、運用面での体制整備が重要だ。管理部門には「セキュリティ係」を明確に指定し、Teams内に「情報セキュリティ」チャンネルを設けることで、情報の一元管理と社内への周知が図れる。また、ポリシーの見直しを年1回実施し、運用状況に応じた改善を続ける体制が必要だ。
コストをかけずに始める現実的な方法
すべてを自社で賄うのが困難な場合は、IT顧問契約やセカンドオピニオンの活用が有効だ。ITに精通した専門家のアドバイスを受けることで、無駄なIT投資やツール選定の失敗を回避できる。
まとめ:セキュリティポリシーは“攻め”のリスク管理である
セキュリティポリシーの策定は、守りの姿勢に見えて実は“攻め”のIT戦略である。ルールを明文化することで従業員の自律性を促し、組織の統一的なIT活用を推進できる。そして、ツールやサービスの導入はこのポリシーの上に積み上げていくべきものなのだ。
セキュリティ対策において最初にやるべきことは、セキュリティポリシーの策定である。これは形だけの書類ではなく、企業のIT活用における行動規範であり、最低限のセキュリティラインを明文化するものである。
専門部署がなくても、AIの力を借りれば現実に即したポリシーのドラフトを作ることは可能だ。そしてその運用には、社内の管理体制の整備と、必要に応じた専門家の助言が必要である。中小企業がセキュリティリスクに立ち向かうためには、まず自社で実行できる現実的なセキュリティポリシーからスタートすることを強く推奨する。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。