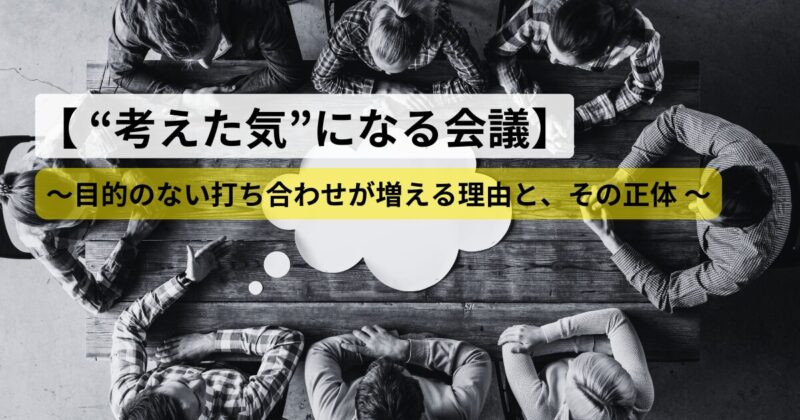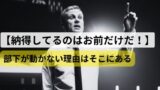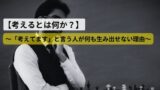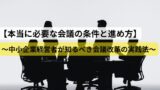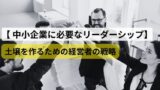「とりあえず集まろう」「一度話しておこう」…そんな打ち合わせが、実は会社の時間と生産性を静かに蝕んでいる。中小企業において、IT人材不足や現場の多忙さが“考えた気になる”会議の温床となっており、意思決定を曖昧にし、行動を遅らせる最大要因となっているのではないか…本稿では、目的のない会議がなぜ増えるのか、誰がその会議を主導しているのか、そしてその構造的な背景を明らかにする。加えて、意味ある会議へと再設計するための3つの条件と、最終的に経営者が変わらなければ現場は変わらないという本質について、実例と共に提示する。経営資源としての「時間」と「意思決定力」を取り戻すための具体的視点を提案する。
なぜ人は“とりあえず打ち合わせ”をしたがるのか
会議とは、本来「決めるための場」であるべきなのに、いつの間にか“安心するための場”にすり替わってしまう。特に中小企業では、この“とりあえず打ち合わせ”が常態化している。

話し合えば前に進んでいる気になる心理
「とりあえず話してから決めよう」「一度集まって情報を整理しよう」――こうしたフレーズに覚えはないだろうか?これは“会議を開く”という行動を通じて、自分たちは前進しているという錯覚を得ている状態だ。実際には何も決まっていないし、動き出してもいないのに、会議をしたことが“成果”のように扱われてしまう。
特に、明確なKPIや成果基準が曖昧な職場では、「今日は3件も打ち合わせしたから頑張った」といった、“がんばった感”が成果の代替品になる。だが、こうして話し合いを繰り返すほど、実は判断が先送りされ、行動が遠のいている。
そして会議を重ねることで、「まだ検討中だから」という名の“待機状態”が正当化されていくのだ。
“考えない人”ほど会議を開きたがる理由
「一人で考えても答えが出ないから、とりあえず会議しよう」――この言葉もよく耳にするだろう。しかし、これは考えることから逃げる言い訳にすぎない。一人で深く考え、自分の意見や仮説を持つことなく、他人のアイデアを拝借することで「自分も参加した感」を得ようとする人は意外に多い。
会議という“集団”の中に入ってしまえば、責任の矢印が曖昧になる。「決まらなかったのは全員の責任」「反対した人がいたから」など、判断の不在を他者の存在に転嫁できる構造がそこにはある。実際には“発言した風”の人たちばかりが集まり、結論は誰も持ち帰らない。こうして、打ち合わせは「時間を使って何も決めなかった」のに「何かした感」だけが残る空間になる。
自分の責任を薄める“安全地帯”としての会議文化
もっと根深いのが、“会議という場”に逃げ込む文化そのものだ。とくに中間管理職がその傾向を強く持っている。
たとえば、上から何かの指示が降りてきた時、「部内で共有して意見をまとめます」と言って会議を設定する。だが、実際には何もまとめず、「みんなで検討しましたが、結論は出ませんでした」という結果にすることで、「俺の責任じゃない」という立場を確保している。あるいは「皆で決めたから」と言えば、意思決定の失敗も集団責任に変えられる。
こうして会議は、失敗しても責任を問われにくい“安全地帯”として機能しはじめる。
しかも、この“安全地帯”に依存する人ほど、会議を頻繁に開きたがる傾向にある。「週次ミーティングをなくすわけにはいかない」「関係者が多いから、一度集まって話す必要がある」…それ、本当に“話す必要”があるのか?それとも“話した方が気がラク”だからやっているのか?――この問いに、自信を持って「前者だ」と答えられる打ち合わせは案外少ない。
こうした“とりあえず会議”が、会社の動きを止めているにも関わらず、「なんとなく安心」「なんとなく参加感」があるために、長年放置されてきた。それが今、経営者が正面から見直すべき“構造的ムダ”になっている。
主導しているようで何も決めない人の正体
表面上は「会議を回している風」、実際は責任も判断も他人任せ――そんな“擬似リーダー”が蔓延すると、会議はただの「自己演出の場」と化し、組織の思考はどんどん浅くなる。
「それ、僕もそう思ってました」と言う人たち
会議でよく見かける光景がある。誰かが明確な提案や意見を出した瞬間、少し間をおいて「それ、僕もそう思ってました」と被せてくる人間が現れる。これ、実は最もズルくて、最もラクなポジション取りだ。
一見すると同調によって場をまとめているようにも見えるが、実態は他人の意見を自分の意見にすり替えて、あたかも“共犯者”のように振る舞っているだけ。何もリスクを取っていないし、自ら意思表示もしていない。

そして、会議後には「俺もあれ、提案してたよね」と周囲にアピール。主導した“フリ”だけして、実質的な責任は何一つ負っていない。このような“責任ゼロの同調リーダー”が増えれば増えるほど、組織には「自分の頭で考える人」がいなくなる。
会議は「意見の場」ではなく「評価を取りにいく場」になり、出世競争の“舞台装置”に成り下がるのだ。
目的がないのに開く会議がもたらす弊害
「とりあえず集まろう」「何か見えてくるかもしれない」――そんな目的不明の会議が繰り返されると、どうなるか?
まず、人の集中力は急速に失われていく。話している内容に明確なゴールがないから、「何を話しているのか分からない」という空気が広がる。メンバーの視線は資料ではなく時計に向かい、誰かの発言を待つ“沈黙の時間”だけが積み重なっていく。
そして何より恐ろしいのは、「何も決めないことが当たり前」になっていくことだ。つまり、“会議疲れ”ではなく“議論に期待しない癖”が組織全体に蔓延する。
社員が口にするようになる。「また会議?どうせ決まらないでしょ」「どうせ◯◯さんが仕切って終わるだけ」――これは末期症状である。会議が「行動を決める場」ではなく、「話した気になる場」に変質してしまった証拠だ。
“主導している風”のリーダーが増える構造的背景
なぜこの“見せかけのリーダー”が量産されるのか?
理由は明快だ。「会議で目立つ=仕事をしている」と誤解されているからである。
経営者が「発言量の多い人=頼れる」と勘違いし、「まとめ役になってくれるから助かる」と評価してしまう。だが、それは「まとめてる風」に見えるだけであって、実際には誰の意見を代弁しているだけであり、本人の思考や判断は空っぽなのだ。
しかも、こうした“擬似リーダー”は自分の意見を持っていないから、誰とでも合わせられる。「上の方針には従います」「現場の声も取り入れましょう」「全体最適を考えて…」と、それっぽいワードを並べて、誰も傷つけず、自分もリスクを取らず、波風を立てない。
だがその実、誰よりも組織の決断力を鈍らせている存在だ。
このような人物が上に立つと、会議は“沈黙”と“忖度”で構成される場になり、会議の「目的」は消え、「発言者の顔色」がすべてを決める場になる。
では、この「主導している風」の人たちに気づくにはどうすればいいか?
簡単な質問がある。
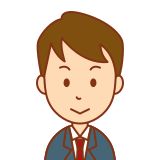
「あなたの提案は何ですか?」
これに対して、即答できない人間は、“会議のための会議”を回すだけの人だ。そんな人にリーダーシップを期待してはいけないし、評価してもいけない。
必要なのは、「声の大きさ」ではなく「決断する覚悟」を持った人間である。
会議は、“演技の場”ではない。“意思決定の場”である。
その原点に立ち戻らない限り、組織の時間も、知性も、そして経営のスピードもすべて蝕まれることになる。
会議が仕事になっている人の危うさ
打ち合わせへの参加が「業務」になり、参加すること自体が目的化してしまっている人材が、組織のコスト構造を悪化させている。
スケジュールが埋まる=働いているという錯覚
「今日も打ち合わせがびっしり入ってるから忙しい」という発言が、なぜか仕事をしている証明になる。だが実際には、1時間の会議に5人が参加すれば5時間の人件費が発生していることを誰も意識していない。中小企業においては、この無意識の“時間搾取”が経営資源を食いつぶしている。
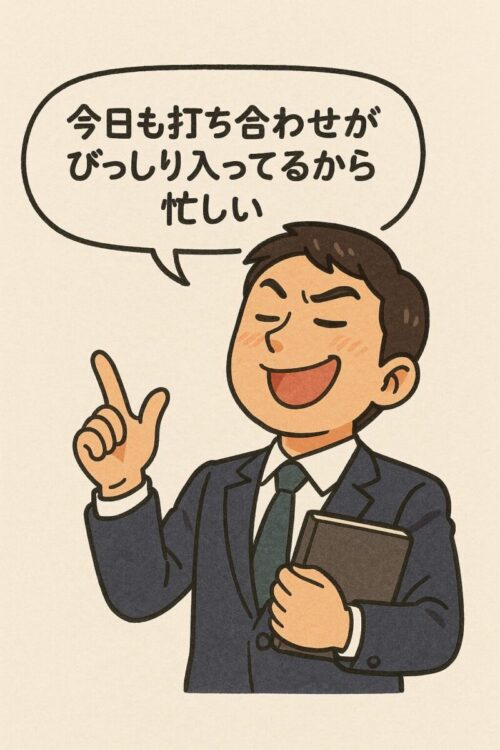
「会議で決める」という免罪符
「これは会議で決まったことだから…」というセリフは、責任回避の合言葉である。誰が最終的に判断したのかを曖昧にすることで、「自分は関与していない」「多数決だったから仕方ない」という防衛構造を築いているのだ。こうした文化が広がると、最終決定者がいないまま進むプロジェクトが量産される。
合意形成ではなく“責任回避の仕組み”としての会議
本来、合意形成とは「誰が何をどう判断するか」を明確にするためのプロセスである。だが会議が責任回避の場になってしまった瞬間、それは経営にとって害でしかない。判断せず、同調し続ける組織は、必ず沈む。
意味のある打ち合わせに変える3つの条件
形式としての会議を、“意思決定を支える手段”へと進化させるための条件は明確に存在する。
① 会議の目的を一文で言えるか?
「今日の会議は何を決めるのか?」を冒頭で共有できない会議は即中止すべきである。目的のない集まりは、単なる“しゃべり場”にしかならない。打ち合わせ前に議題を一文で定義し、それが参加者に伝わっているかをチェックするだけでも、会議の生産性は劇的に改善する。
② 結論を持ち寄る会議に変える
「とりあえず話そう」ではなく、「自分の結論を持って集まる」ことが前提の会議運営が必要だ。意見交換は手段であり目的ではない。あくまでも各自が持ってきた結論を“すり合わせる”ために会議があるのだ。これが本来の意思決定プロセスであり、考えない人の“思いつき参加”を排除する鍵でもある。
③ 決める人を明確にする
「みんなで決めよう」ほど無責任な言葉はない。誰が最終的に判断を下すのかを会議冒頭で明確にしておくだけで、議論は格段に引き締まる。責任の所在がはっきりしていれば、意見も出やすくなり、最終決定もスムーズになる。“決める人”の不在が、最も生産性を下げる原因である。
まとめ|会議を減らす勇気が、会社を動かす力になる
会議という「安心装置」に依存し続ける限り、会社は動かない。特に中小企業においては、一人ひとりの判断と行動が会社の方向性を決める。だからこそ、会議は「決める」ために使われなければならない。
結論を出す会議、責任を明確にする会議、考えた上で参加する会議――これが中小企業の意思決定スピードを変える唯一の道だ。最終的には、経営者がその文化を作る。会議を変えるという決断が、組織の未来を変える第一歩となる。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
また、お会いしましょ。