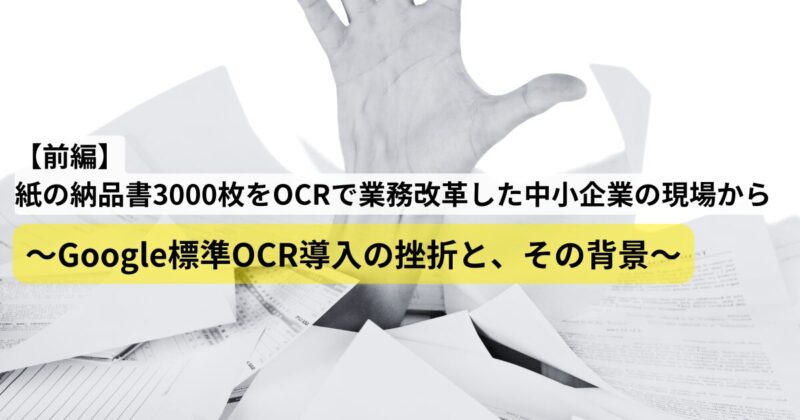中小企業の経理現場では、今なお紙の納品書・請求書の処理に追われる日常が続いている。毎月2000〜3000枚という膨大な紙伝票を目視で確認し、入力・管理する作業は、スタッフの時間と労力、そして精神的負担に直結する。本稿は、実際にそうした課題を抱えていたある中小企業において、OCR(文字認識技術)を活用しようと試みた実例である。導入を支援した立場から、現場のリアルな声と失敗、そして試行錯誤のプロセスを明かす。これは単なるツール紹介ではない。現実と理想のギャップをどう乗り越えるか、実務に根ざしたIT活用の記録だ。
なぜOCR導入の仕組みを作る必要があったのか
中小企業の紙業務には、量・複雑さ・人手依存という3つのボトルネックがある。この企業では、それが限界点に達しつつあった。単なる効率化のためではなく、「このままでは業務がもたない」という危機感が背景にあった。
毎月3000枚以上の紙納品書という現実
この中小企業では、毎月処理しなければならない納品書の枚数が3000枚以上にのぼっていた。しかもすべてが紙で届く。電子化は一切されておらず、原本はすべて手元に残す必要があった。取引先の数は200社を超え、それぞれが独自の納品書フォーマットを使用していたため、統一性がなく、パターンも非常に多い。記載項目の位置も会社によって異なり、慣れていない人では読み間違いも起こりやすい。
実務では、経理スタッフが納品書を一枚一枚確認し、品目・数量・金額・伝票番号などを目視でチェックし、手入力で管理表に記録するという運用を行っていた。スタッフは長年の経験を持つとはいえ、この「量」と「非効率性」は明らかに限界を超えていた。手作業のためミスも避けられず、チェックにも二重三重の確認が必要だった。この時点での業務は、正直“破綻寸前”だったと言える。
目視・人手チェックの限界とストレス
この作業を担っていたのは、パートタイムや時短勤務の女性スタッフが中心だった。彼女たちは全員、子育て中の母親であり、家庭との両立のために「定時で帰ることが大前提」となっていた。会社としてもその働き方を尊重しており、無理な残業を求めることはできない。
しかし、納品書の山は待ってくれない。毎日届く書類を積み上げながら、「今日中に終わらない…」「また月末に残業かも…」という精神的プレッシャーが日増しに強くなっていた。あるスタッフは、「この作業、もう限界かも…」とこぼすようになっていたという。しかも、こうした労働環境の中で新しい人を雇っても、単純作業が嫌になってすぐに辞めてしまうのではないかという不安もあった。
結果的に、既存スタッフに業務が集中し、ストレスと疲労だけが蓄積されていく状態に。“人手で回す業務”の限界が、いよいよ目の前に迫っていた。

伝票番号や金額を“すぐ確認できない”非効率さ
業務上さらに大きな問題となっていたのが、必要な情報を「すぐに」確認できないという点だった。納品書の束の中から、「この伝票番号、どの取引先だった?」「金額が違っていないか?」といった照会が発生すると、紙をめくって探すしかない。保管は月別・会社別に仕分けていたものの、現実には瞬時に答えるのは難しく、探すのに時間を要するケースが多発していた。
とくに月末や請求処理のタイミングでは、営業部や管理部門からの確認依頼が集中する。「あの伝票の内容を確認して」「過去の納品データが欲しい」といった依頼に、即答できないことで二次的な業務遅延やミスも誘発していた。経理部門だけでなく、社内全体の業務効率に悪影響が及んでいたのである。
要件に合うパッケージが見つからなかった理由
そこで最初に検討されたのが、市販の納品書・請求書処理パッケージの導入だった。複数のベンダーに相談し、要件を伝えた上で、デモや見積もりを依頼した。
しかし、返ってきた見積額は最低でも300万円以上。しかも、料金の内訳を見ると、初期構築費用に加えて、「パターン対応の個別設定費」「マニュアル整備費用」「運用サポート費用」などが含まれていた。担当営業からは「100%読み取れる保証はできません」「フォーマットごとにチューニングが必要です」との説明があり、多様なフォーマットに対応するためには追加費用がかかる構造になっていた。
さらに、OCR処理後のデータ整形や一覧出力については「別途開発が必要」とされ、コストと時間の両面でのハードルが極めて高かった。こうした条件では、本当に現場で使えるかどうかの見通しすら立たず、現場の期待は次第に冷めていった。
中小企業にとって、“300万円かけても成功するか不透明”な仕組みは導入しづらい。業務改善のための投資とはいえ、その判断はあまりにもシビアだった。
なるべくコストをかけずに考えた全体構成
高額なパッケージ導入が現実的でない中小企業にとって、「今あるもので、どこまで実現できるか」が判断の軸となる。現実と向き合った結果、選択したのは“無理のない一歩ずつのIT化”だった。
中小企業でも使える現実的な前提
このプロジェクトは、当初から“コストを最小限に抑えること”が前提だった。依頼を受けた時点で、筆者も「どこかに適したツールがあれば紹介する」というスタンスだった。だが、すぐに現実を突きつけられる。
スキャナーすらない環境。IT担当者もいない。社内にシステムを構築するノウハウもない。
つまり、専門的なIT人材がいない中で、コストをかけず、現場が無理なく扱える仕組みをどうやって作るか──そこが出発点となった。
また、現場の作業を観察するうちに、「いきなり大規模なシステムを導入するよりも、段階的にIT化していくほうが現実的」だと判断。既存の業務フローに無理なく組み込める仕組みでなければ、運用自体が定着しないと考えた。
“ツールを入れても使えなければ意味がない”という当たり前だが見落とされがちな視点が、今回の構成方針の根幹になった。
スキャン→OCR→テキスト化→一覧化という流れ
最初に描いた構成は、非常にシンプルなものだった。
1)紙の納品書をスキャナーで読み込みPDF化
2)OCRでテキストに変換
3)必要な項目を抽出
4)スプレッドシートで一覧管理する
という一連の流れである。
当初、手元にあるのはGoogleアカウントだけ。つまり、Google Workspaceの標準機能と、Apps Script(GAS)を使ったノーコード・ローコード構成でやりきる必要があった。
特別な開発環境は用意せず、あくまでクラウドベースで完結し、運用に負荷がかからない設計が求められた。
各ステップで使う技術も「現場で理解しやすいこと」を基準に選定。たとえば、OCR処理結果がそのままGoogleスプレッドシートに連携され、スタッフが日々のExcel作業と同じような感覚でデータを扱えるように設計した。
“専門的知識がなくても、普段使っているツールの延長線上で処理できる”──これが導入を成功させる最大の鍵だった。
検索できることをゴールに据えた理由
データが一覧化されても、それを「使えなければ意味がない」。最大の目的は、目視や人手による照合の手間をなくすことである。
そのため、今回のシステムでは、伝票番号、金額、発行日などの主要項目を抽出し、一覧上で検索・フィルタできる状態にすることをゴールに設定した。これにより、
「伝票番号○○○○に該当する納品書を確認したい」
「○月分で10万円以上の納品書だけ抽出したい」
といった実務で頻出する問い合わせに、即座に対応可能となる。
Googleスプレッドシートには元々検索機能やフィルタ機能が備わっているため、スタッフ側も特別な学習や研修を行うことなく、“今まで通りの感覚で、圧倒的に早く探せるようになる”という実用性が担保された。
IT化の本質は、自動化ではなく「すぐに調べられるようにすること」なのだ。
スマホから確認できることの意味
さらに注目すべきは、スマホから納品書データを確認できる設計にしたことだ。これにより、現場や外出先にいるスタッフ、営業担当者、役員なども、会社に戻らずにその場で必要な情報を検索・閲覧できるようになった。
たとえば、取引先との商談中に「支払い状況どうなってましたっけ?」と聞かれたとき、従来であれば「会社に戻って確認します」だったものが、スマホで該当伝票を検索して、その場で即答できるようになった。
この“即答できる”ということが、業務における信頼性とスピード感に直結する。
Googleドライブとスプレッドシートの連携によって、特別なアプリを導入せずに、スマホブラウザでそのまま確認できるという手軽さも、現場に受け入れられた要因のひとつだった。
IT活用の成果は「現場のストレスが消えること」で実感される。スマホ閲覧対応はまさにそれを体現した。
スキャナーのデモで見えた“理想と現実のギャップ”
OCR導入の第一歩としてスキャナーから着手したが、ここで「IT導入あるある」とも言える落とし穴にはまることになる。
この段階で見えたのは、デモ環境と実務環境はまったく別物だという現実だった。
スキャナーベンダーの協力で試験運用開始
OCR処理以前に、そもそも紙をどうデジタル化するかが最初の関門だった。社内には業務用スキャナーがなく、複合機の簡易スキャンでは精度も速度も不安があった。そこで、筆者は信頼できるスキャナーベンダーに相談し、実機デモを依頼することにした。
デモ当日は、実際に使われている納品書を持ち込み、
・連続スキャンの速度
・紙詰まりの起きにくさ
・傾き補正や解像度
といった点を確認しながら、PDF化 → OCR処理までの一連の流れを実演してもらった。
結果は上々だった。
納品書はきれいにPDF化され、OCR処理後のテキストも一見すると問題なく読める。
現場のスタッフからも
「これなら楽になりそう」
「一気に進みそうですね」
といった声が上がり、その場の空気は明らかに前向きだった。
さらに、ベンダー側からは無償貸与による試験運用の提案もあり、「まずはやってみよう」という流れになった。
この時点では、誰もが「いよいよ解決策が見つかった」と感じていたと思う。

デモでは成功、でも実務では通用しなかった
しかし、実際の業務に組み込んでみると状況は一変する。
日々届く納品書をまとめてスキャンし、OCRにかけてみると、読み取り結果に明確なバラつきが出始めた。
原因はいくつもあった。
・紙質の違い
・印字の濃淡
・FAX由来で文字が潰れている納品書
・少し斜めに傾いた状態でのスキャン
・ホチキス跡や折り目
こうした「現場では当たり前の揺らぎ」によって、
同じフォーマットの納品書であっても
・数字が欠ける
・桁がずれる
・項目の位置が変わる
といった問題が頻発した。
スキャン設定を微調整しても、完璧にはならない。
OCR後のデータを確認すると、
「これは合っているが、こっちはダメ」
「昨日は読めたのに、今日は読めない」
といった状態が続いた。
ベンダーも誠実に対応してくれた。設定変更や運用上の工夫も提案してくれたが、根本的な問題は解決しなかった。
最終的に浮き彫りになったのは、「OCRはスキャナーだけで解決する問題ではない」という事実だった。

現場の期待が一気に萎んだ瞬間
試験運用が進むにつれ、現場の反応は徐々に変わっていった。
最初は期待していたスタッフからも、
「これ、結局チェック必要ですよね」
「だったら最初から目で見たほうが早いかも…」
という声が出始める。
これは非常に重要なサインだった。
現場が「楽になる」と感じられないITは、確実に使われなくなる。
OCR結果を信頼できない以上、結局すべてを目視確認する必要があり、二度手間になってしまったのだ。
筆者自身も、この時点で強い葛藤を感じていた。
「やはり高額なパッケージでないと無理なのか」
「そもそもOCRという選択自体が間違いだったのか」
という疑念が頭をよぎる。
同時に、
「このまま引き下がってしまえば、現場は何も変わらない」
という思いもあった。
ここでやめるのは簡単だが、それでは“できない理由を確認しただけ”で終わってしまう。
このスキャナー試験運用の失敗は、
「デモは成功しても、実務では成立しないことがある」
という、非常に重い教訓を残した。
そしてこの経験が、次の一手──OCRそのものの精度を見直す決断へとつながっていく。
まとめ:中小企業のIT活用は“現場のリアル”から始まる
今回紹介した内容は、単なるデジタル化成功例ではなく、中小企業の現場で実際に直面した課題と、その打開を目指した試行錯誤の記録である。特別な技術力があったわけではない。予算が潤沢だったわけでもない。ただ、「このままでは持たない」「どうにかしたい」という現場の切実な声が、取り組みの出発点だった。
スキャナーの試験導入で見えたのは、“できるはず”と“実際に使える”の間にある深いギャップだった。OCRツールを導入すれば自動化される──そんなシンプルな話ではない。読み取り精度のばらつき、帳票レイアウトの揺れ、現場の運用負荷、そしてITに対する信頼感。それらがすべて揃ってはじめて、業務として成立する。
この経験を通じて再認識したのは、中小企業のIT活用は、現場のリアルに即していなければ意味がないということだ。「できることから」「無理のない範囲で」「目の前の困りごとに対応する形で」始める。それがITを業務に根づかせる第一歩となる。
そして、“とにかくやってみる”という行動が、次の選択肢を連れてくる。
今回の前編では、OCR導入の壁と向き合った過程をリアルに振り返ったが、まだこれはプロジェクトの途中にすぎない。
次回の【後編】では、この行き詰まりを突破した鍵──Vision OCRとの出会いと、それによって「業務で本当に使えるIT」へと昇華させたプロセスを詳しく紹介する。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。