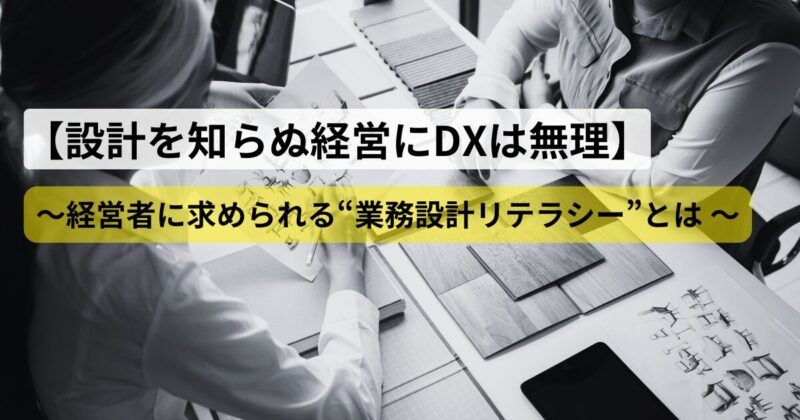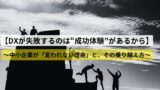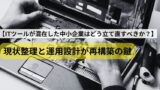中小企業がIT導入やDXを進める際、見落とされがちなのが「設計」の重要性だ。IT化はツールの導入ではない。業務をどのように構造化し、どのような思想で再設計するかが成否を分ける。しかし多くの中小企業では、この設計をベンダーや外部委託に丸投げしてしまい、結果として自社にフィットしないシステムが生まれてしまう。ITスキルではなく、「設計力」こそが経営者に求められるリテラシーである。本稿では、構造的思考としての「設計」とは何か、経営者が設計に関与することで得られる経営上のインサイトとは何かを明らかにする。
経営者が“設計”を理解すべき理由
「設計」と聞くと、建築やエンジニアの専門領域のように思えるかもしれない。だが中小企業におけるIT化・DXの成否は、この“設計力”にかかっていると言っても過言ではない。経営者自身が業務設計を「見える化のための思考」として理解しなければ、IT導入は高確率で失敗する。設計とはツールの話ではない。業務の関係性を整理し、判断と責任の流れを構造化する“経営の眼差し”そのものである。
経営の本質は「意思決定と構造化」である
経営者の仕事は、ひと言で言えば「決めること」である。しかし、「決めたこと」がどう伝わり、どこで実行され、誰が責任を持ち、どのように検証されるのか――これを設計していなければ、決定はただの「掛け声」に過ぎない。
現場ではこんな声がある。
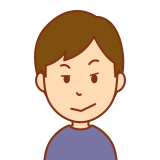
「それ、誰がやるんですか?」
「あの作業、営業もやってるし、総務もやってる気がしますけど…」
「言いましたよね? いえ、そんなこと聞いてません」
これは、設計がされていない組織の“あるある”だ。業務の責任範囲が曖昧で、情報の流れにルールがなく、個人の記憶や慣習に頼った属人的な運用になっている。こうした組織にITツールを入れても、混乱を助長するだけだ。ツールが悪いのではない。「設計がされていない状態で導入された」ことが問題なのである。
経営とは、社員が自律的に動ける「構造」を作ることだ。その構造を見える形にし、言語化・図式化するのが“設計”であり、これは経営者自身が担うべき仕事だ。
設計を理解せずに進めるIT導入は、ほぼ失敗する
『IT顧問のススメ』でも繰り返し語っているように、「システムを導入したけど、思ったように使えていない」という中小企業は非常に多い。これはベンダーやツールの問題ではない。「設計」を外注任せにしているから、経営者の思考と現場の実態が反映されないのである。
例えば、ある中小製造業で「工程管理システム」を導入したが、1年後には誰も使っていなかった。理由は明白だ。現場のフローがバラバラで、「工程」という言葉の定義すら人によって違った。ベンダーが提示した画面設計も、実態と噛み合わず、結局“Excelでの手作業”に戻ってしまった。設計なき導入の典型である。
IT導入の失敗は、往々にして「設計フェーズの不在」によって起きる。現場を知らない外部業者が作る仕様書には、経営者の思想も、現場の機微も反映されない。業務設計という骨格がなければ、システムはただの“箱”であり、魂は宿らない。
設計は“人任せ”にできない経営活動だ
「システムのことはよくわからないから、任せてある」と言う経営者は多い。しかし、わからないのはITの仕組みであって、“設計”を理解しないまま任せるのは経営放棄に近い。
設計とは、「誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どうやって」という問いに答えること。これは経営そのものだ。特に中小企業では、現場と経営の距離が近いため、設計段階での経営者の関与が、組織の方向性を決定づける。現場の感覚、経営の意図、事業の本質――これらを接着剤のように束ねるのが設計であり、それを誰かに丸投げしてはいけない。
「設計を他人に任せた時点で、そのシステムは他人のものになる」
これを肝に銘じるべきだ。
設計とは技術ではなく“思考の構造化”
「設計」という言葉には、どこか専門的で技術者の領域という印象がつきまとう。しかし、経営における設計とはプログラミングやコードの話ではない。それは「業務の関係性を整理し、構造を見える形にする」という思考の作法であり、むしろ経営者や管理者にこそ求められるリテラシーである。
設計とは、物事の関係を整理し“地図”にする力
業務とは単なる作業の積み重ねではなく、情報・判断・責任が連鎖的につながった構造体である。そして、その構造を「見える形」に落とし込むのが設計である。ここで重要なのは、「見える」だけでは足りないということ。“意味のある関係性”として見えるようにすることが設計の本質だ。

例えば、業務改善のヒアリングで「見積書って誰が作ってますか?」と尋ねたとき、「営業がやってると思います」という曖昧な答えが返ってくる組織は危険だ。
「誰が」「何を」「どの順序で」「なぜ」やっているのかが言語化できない状態で、ITを導入しても、そのITは“迷子”になる。システム化とは、業務構造に沿って情報を流すパイプを設けること。構造が見えていなければ、どこにパイプを引けばいいかもわからないのだ。
設計とは、いわば「業務の地図づくり」である。地図のない旅は迷うのが当たり前だ。設計図のないIT導入もまた、迷走するしかない。
DB設計やフラグ管理は「棚の作り方」にすぎない
ITに苦手意識を持つ経営者ほど、「DB(データベース)設計」や「フラグ管理」といった言葉に尻込みしがちだ。だが、これは難しい話ではない。たとえば書類棚を想像してほしい。
請求書は左の棚に、発注書は右の棚に、古い書類は一番下の引き出しに…。これは物理的な棚の構造だが、DB設計とはこれを“デジタルでやる”というだけの話である。 棚にルールがなければ、書類が迷子になるように、システムも情報を正しく扱えなくなる。棚があるから探せる。棚の構造が“整理の知恵”であり、それが設計である。
つまり、設計とは技術者がやることではなく、情報をどう整理したら使いやすくなるか?を考える“思考の整頓”作業なのだ。
フラグ管理(たとえば「支払い済み:1、未払い:0」といった判定ルール)も同様で、「この情報をどう分けたら、後で判断しやすいか?」というだけの話。難しい理論でも数式でもない。片付けのセンスに近い。
業務を俯瞰して“構造化”する力が経営者の設計力
よく「業務を理解していればシステムも作れる」と思われがちだが、それは不十分だ。業務を“やっている”のと、“構造として見ている”のとでは意味が違う。経営者に必要なのは、業務の詳細ではなく“関係性の再設計”を見る力である。
たとえば、注文が入ってから出荷されるまでの流れを追った時、
この一連のプロセスが図式化され、関係者が認識を共有できていなければ、ITツールがどこに入るべきかを判断できない。
設計力とは、「構造として業務を見る力」だ。
現場を点で見るのではなく、線として、さらに面として俯瞰する力。業務の流れを川のように眺め、「どこで水が詰まっているか」「どこで漏れているか」を見極める。この感覚がなければ、ITを導入しても課題の根本は解決しない。
そして、この俯瞰は現場担当者にはできない。なぜなら、現場は“川の中”にいるが、経営者だけが“上空から”川の流れ全体を見渡せる位置にいるからだ。IT導入に必要なのは技術ではなく、構造を観察し、構造に意味を与える視点=経営的設計思考である。
業務を設計せずにITを導入するリスク
設計を省略してIT導入すると、表面だけの“業務風”なツールができあがる。その結果、「現場が使いづらい」「管理が逆に煩雑になった」といった声が上がるのは必然だ。
外注業者は仕様通りにしか動かない
外注業者は経営者の代弁者ではない。契約書の範囲外のことは動かないし、例外処理を想定していなければ対応できない。つまり「仕様外=対応不可」である。これはシステム構築の常識であり、良し悪しの話ではない。経営者が関与しない仕様書には、経営思想は反映されない。
業務理解のない設計は“断片”しか再現できない
「請求書の発行」だけを切り取ってIT化しても、それがどのような業務の文脈で行われているかが見えなければ、単なる“帳票印刷機”に終わる。業務は相互に関係し合っている。その関係性を再現しなければ、断片的な機能の集まりにしかならず、現場はむしろ混乱する。
設計段階で経営者が関与することで思想が伝わる
業務の細部に経営の思想が宿る。たとえば「クレーム対応を何分以内に行うか」といった設計上の閾値に、企業の価値観が反映される。経営者が設計に関与すれば、こうした思想がシステムに組み込まれる。それが「仕組み化された価値観」として組織に定着していく。
設計に関与することで見える“現場の真実”
設計の過程には、現場の実態と向き合う“副次的効果”がある。これは経営者にとって最大のメリットだ。
現場のムダや属人性が顕在化する
設計を進めていくと、現場の二度手間・意味不明な業務・個人任せのルールなどが次々と可視化されていく。「この作業、なんのためにやってるの?」という問いが頻発するのだ。これは業務改善の第一歩である。

設計の議論は“現場の棚卸し”である
設計段階での対話は、業務の再発見の場である。業務フローを図解し、役割と目的を明確化する作業は、暗黙知を形式知に変えるプロセスだ。現場が普段無意識にやっていたことが、初めて言語化される瞬間でもある。
経営者が関与することで“現場の真実”に触れられる
現場からの報告やデータだけでは見えない「本当の問題」は、設計の場でこそ明らかになる。言い換えれば、設計に参加しなければ、経営者は「自社の実像」を一生知ることができない。
まとめ:ITではなく“設計”を理解せよ
IT導入で最も重要なのは、ツール選定でもベンダー選びでもなく、経営者自身の「設計への関与」である。設計とは、業務の意味を問い直し、構造化し、図解する営みだ。それはすなわち、組織の価値観を仕組みに埋め込む行為である。
経営者が設計を理解し、対話に加わることで、現場の真実が見え、組織の透明性と信頼が育まれる。技術ではなく「思考」で勝負する時代に、設計リテラシーを持った経営者こそが、変化に強い企業をつくるのだ。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。