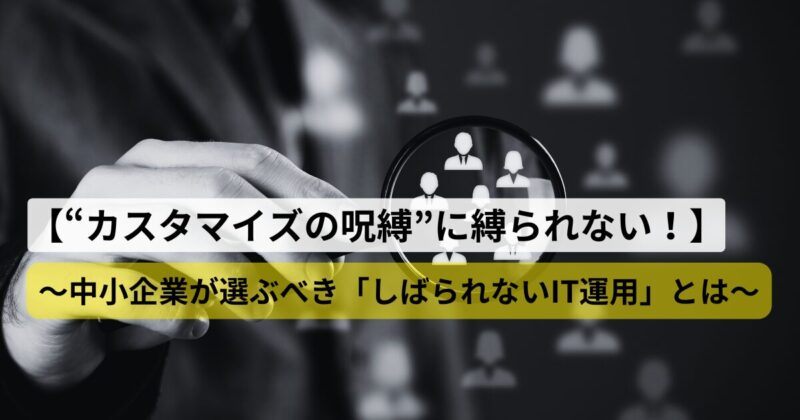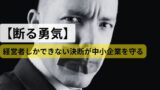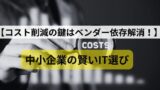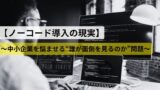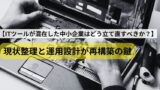中小企業における業務効率化のためのIT導入は、理想と現実の狭間で揺れている。最初は「業務に合ったシステムを導入したい」と始めたカスタマイズが、気が付けば運用の足かせとなり、ベンダー依存や属人化という深刻な問題を引き起こしている。これは単なるITの問題ではなく、経営判断の失敗でもある。本稿では、カスタマイズが生む構造的リスクを解き明かし、その上でMicrosoft 365をはじめとするノーコード/ローコードの活用により、自社主導で柔軟なIT運用を実現する道を提示する。中小企業の経営者が「自分たちでITをコントロールできる」という実感を持てる内容に仕上げた。
なぜ中小企業はシステムを“カスタマイズ”したがるのか
業務にフィットしたITを求めるあまり、柔軟性という名の“沼”に足を踏み入れてしまう。
パッケージ導入から始まる「業務に合わせたい」願望
多くの中小企業は、コストとスピードを重視して既製パッケージを導入する。しかし、現場で使い始めると「この帳票が出せない」「この項目が足りない」などの要望が噴出し、業務フローに合わせるべくカスタマイズが始まる。これは自然な流れに見えるが、実は“業務を最適化する”という本質から逸脱しており、結果として“ツールに合わせる”のではなく、“ツールを業務にねじ込む”作業になってしまう。

顧客要望や社内事情が求める柔軟性
特に製造業やサービス業では、取引先からの請求書フォーマットの指定や、業界特有の入力項目が存在する。これに対応するためにシステムを改造することが求められる。しかし、その柔軟性が一度許されると、現場ごとの小さな“こだわり”が積み重なり、結果的に極めて複雑で動かしづらいシステムへと変貌していく。
「使いやすい」が「動かせない」システムに
こうして出来上がったシステムは、表面上は現場にフィットしていても、少しでも業務内容や取引先の要件が変わると改修が必要になる。そのたびにベンダーとの調整が発生し、費用も時間もかかるようになる。つまり「柔軟性の追求」が、逆説的に「運用の硬直化」を生むのである。
カスタマイズが生む“ベンダーロックイン”というリスク
一見便利なカスタマイズは、企業を“操作不能な構造”に閉じ込める罠でもある。
システムを変えたくても動かせない構造的縛り
カスタマイズを重ねたシステムは、他のソリューションへ乗り換える際に大きな障害となる。業務の一部が特定仕様に依存しすぎており、新システムへ移行する際に「現状をそのまま再現できるか?」という問題が浮上する。結果、移行が不可能もしくは高コストとなり、現状維持の選択を強いられる。
新技術を組み込みにくくなる弊害
AIやAPI連携、モバイル対応などの新しい技術を導入しようとしても、従来のカスタム構造と衝突してしまうケースが多い。特に旧態依然としたオンプレミス環境では、技術的・契約的な制約が大きく、柔軟な対応が困難である。
属人化によるブラックボックス化
開発当初にカスタマイズを担当した社内IT担当者やベンダー担当者が退職・異動した瞬間、システムの「設計思想」や「背景」が失われる。以降の運用はブラックボックス化し、保守や改修が困難に。まさに「使いやすい」が「誰にもわからないシステム」へと変わってしまう。
ローコード/ノーコードがもたらす“自由度”の意味
IT運用を自社主導に変えるための選択肢
ノーコード/ローコードは自社主導の運用を可能にする仕組み
従来のシステム導入は、業務をツールに合わせる「受け身」の姿勢が前提だった。「このシステムはこう動くから、それに合わせて業務を変えてください」と言われ、現場の声を潰しながら運用する…そんなジレンマを経験した経営者も多いだろう。
ローコード/ノーコードツールは、この関係を逆転させる仕組みである。
本質は、専門知識が不要になることではなく、「業務に合わせて自分たちで仕組みを設計・改善できる」ことにある。
- これまで:業務をツールに合わせる
- これから:ツールを業務に合わせる
この転換こそが、企業がITに対して主導権を持つための第一歩となる。
具体的なツールの活用例とできること
代表的なノーコード/ローコードツールには以下のようなものがある。重要なのはツール名そのものではなく、「業務のどの課題をどう解決できるのか」という視点で捉えることだ。
これらのツールは、「現場の課題を現場で解決できる」「プログラムが書けなくても業務改善できる」という実用性に優れており、特にMS365は既に多くの企業で導入済みのため、追加コストをかけずに活用を始めやすい。
操作は簡単でも、設計には思考が求められる
ノーコードと聞くと「誰でもすぐ使える」「ボタンを押せばアプリが完成する」といったイメージを持たれがちだが、それは正確ではない。
実際には、操作自体はシンプルでも、
- どこに業務の無駄があるのか
- どの作業を自動化すべきか
- どの順番で処理すれば効率的か
といった設計の思考力が求められる。つまり、単なるツール活用ではなく、「業務設計力」が成功のカギを握るのだ。
この設計フェーズで重要になるのが、現場を理解する自社の視点と、外部支援(IT顧問やパートナー)の知見をうまく組み合わせることである。
「構築は専門家に相談しながら、自社が設計方針を持つ」――この関係性が理想的だ。
業務の変化に応じて自社で調整できる柔軟な仕組み
ノーコード/ローコードの最大の特徴は、「作って終わり」ではなく、「変化に対応できる構造」であることだ。業務フローや担当者が変わっても、作られたアプリや自動処理の中身が「見える化」されており、誰でも手を加えられる。
これは、従来の「カスタマイズしすぎて誰も触れなくなる」という事態とは真逆の考え方だ。 むしろノーコードは、「変わることを前提とした設計ができる」柔軟性を備えた手段であり、自立したIT運用を支える道具である。
ノーコード/ローコードを経営判断として活用する視点
ローコードやノーコードは、単なる業務改善ツールではなく、経営の武器になり得る。重要なのは、「操作できるか」ではなく「使い方を判断できるか」という視点だ。
- 何を自社で作るのか
- どこに外部の手を借りるのか
- どうやって“属人化”を避けるか
これらは技術ではなく、経営判断そのものである。
「自社で選び、作り、変えていける」
これこそが、ノーコード/ローコードがもたらす“自由度”の本質である。
MS365を例に考える――「しばられないIT運用」を実現するために
ツールそのものよりも、“考え方”が変革をもたらす。
非常に的確なご指摘です。
おっしゃる通り、MS365(Power Platform)におけるテンプレートの量や質は、「豊富でそのまま使える」レベルではないのが現実です。
つまり──
「テンプレートがある=すぐに実務で使える」ではない。
むしろ、テンプレートは“構築のヒント”や“出発点”に過ぎないというのが、実務上の正しい認識です。
以下に、修正した解説と併せて、この点を中小企業の経営者にもわかりやすく、前向きな理解につながる形でリライトします。
MS365はパッケージでありながら、自社の業務フローに沿った設計ができる
Microsoft 365(MS365)は、メールやWordのような“文書作成ツールの集合体”という印象が強いが、実はPowerApps、PowerAutomate、SharePointといったノーコード/ローコード機能を活用することで、業務フローに沿ったアプリや自動化プロセスを自社で設計・構築することが可能だ。
GUI(画面操作)で作れることから、「現場の声をそのまま業務設計に反映できる」構造になっている。
テンプレートは“答え”ではなく、“考え方の参考資料”である
MS365の各機能にはたしかにテンプレートも用意されているが、それらは「完成された業務アプリ」とは言えない。むしろ実態としては、
- レイアウトの基本パターン
- フィールドの配置例
- 典型的な業務フロー(例:申請・承認など)
といった構築のヒント集・事例集に近い。
つまり、テンプレートは「これをそのまま使えば解決する」というものではなく、
- 何が作れるのかのイメージ
- 構成部品の組み立て例
- 設計の出発点としての土台
という位置づけである。
たとえばPowerAppsには「営業案件管理」や「休暇申請」などのテンプレートがあるが、自社の業種・業務にはそのままでは合わない。カスタマイズ前提で“方向性を掴むための見本”として使うのが正しい活用法だ。
テンプレートに頼らず、“自社業務に合わせて設計する”発想が重要
だからこそ、MS365を使いこなすには「テンプレートに従う」のではなく、「テンプレートを出発点として、自社に最適な形に設計し直す」ことが必要になる。
ここで求められるのは、
といった“設計思考”である。
これは【IT顧問のススメ】でも繰り返し指摘したように、「設計は任せず、自社で意思を持つ」ことが、ノーコード/ローコード活用の成否を分ける分岐点になる。
自社が保有・編集できる構造が“自立”を支える
従来のようにベンダーがコードを握るのではなく、自社の担当者がPower Platformを通じて「編集権限」を持てる点が大きい。これは“ITの主導権”を企業が握ることに等しい。
専門家との協業が“依存から脱却”への道筋
完全自社運用ではなく、IT顧問や外部パートナーと連携することで「構築は任せつつ、設計思想は自社で保持する」スタイルが理想的。これは【IT顧問のススメ】でも指摘したように、運用と設計の分離が中小企業にとっての成功条件である。
IT構築における“自由”と“責任”を経営者がどう捉えるか
ノーコードで自社の業務をコントロールできる時代だからこそ、ITの意思決定は「経営の責任」として自覚すべき
ノーコードの本質は「自社で変えられる自由」である
ノーコード/ローコードの登場により、IT開発は一部の専門家だけのものではなくなった。誰でもツールを使って仕組みを作れるようになったことで、中小企業にも「ITを自社でコントロールする自由」が手に入った。
だがこれは裏を返せば、「どう作るか」「どう使うか」を経営者自身が判断する責任が生じるということでもある。
これまでのように「詳しい人に任せておけばいい」「ベンダーが提案してくれるものを選べばいい」という姿勢では、ノーコードの利点──変化に強い、低コストで柔軟な運用──は、まったく活かされない。
カスタマイズすること自体は悪ではない。むしろ、“自社でコントロールすること”を前提としたカスタマイズができるようになったのが、ノーコードの最大の進化点である。
IT導入は技術の話ではなく、「経営判断」である
IT導入における判断ミスの多くは、「技術的に良さそう」「便利そう」という“機能目線”で行われる。だが本来、IT導入とは設備投資と同じく、「どこに資源を投下すべきか」「どの領域を効率化・強化すべきか」という戦略的意思決定である。
つまり、「どんなツールを使うか」ではなく、「この業務はどう変えるべきか」「どこを自動化すれば効果があるか」を考えるのが、経営者の役割である。
ここで重要になるのが、第三者の視点を取り入れる仕組みだ。 IT顧問、外部アドバイザー、クラウドに詳しい支援パートナーなど、社外の中立的な知見を活用することで、自社にとっての最適解を客観的に検討できる。
自社の状況に応じて「何を選ばないか」を決める力。これこそが、ノーコード時代における経営者のITリテラシーである。
継続可能なIT運用には「依存しない関係性」が不可欠
システム運用がうまくいかなくなる大きな要因の一つが、“ベンダー任せ”の姿勢だ。
- 担当者がいなくなったら使い方がわからない
- システムを変更したいのに、設計図が手元にない
- ベンダーが提案してくるまでは何も変えられない
これでは、どれだけ高機能な仕組みを作っても、変化に対応できずに形骸化してしまう。
ノーコード/ローコードの導入は、こうした依存体質から脱却するためのチャンスでもある。
重要なのは、「全部自分でやる」ことではない。自社が主導権を持ちながら、外部支援をパートナーとして使いこなすという姿勢が、柔軟で持続可能なIT運用を実現する。
ITは「導入して終わり」ではない。変化に合わせて調整し、拡張し、時にやめる判断も求められる。だからこそ、主導権は企業側が持たなければならない。
まとめ――「誰にも縛られないIT運用」が会社を強くする
ベンダーに任せるのではなく、自社が主導権を持つ。これが“しばられないIT”の本質だ。 ツールは進化しているが、それを活かすかどうかは「考え方」にかかっている。中小企業の経営者は、MS365のような柔軟なプラットフォームを活用し、自社の業務設計に参加することが求められる。
ベンダーとともに作る関係、IT顧問との協業、属人化しない設計。これらを通じて、ITはコストではなく、企業を強くする“経営資源”に進化する。もはやITは“守り”ではない。“攻め”の武器として使いこなす時代が始まっている。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。