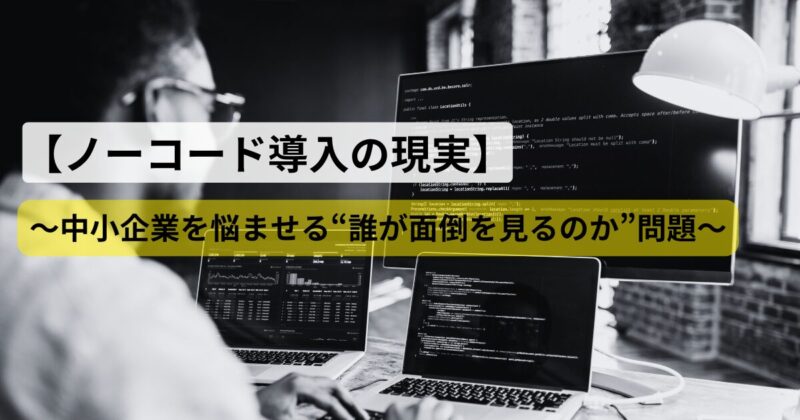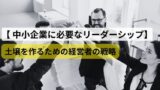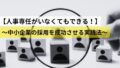ノーコード/ローコードツールは「中小企業でも手軽に業務改善が可能」として注目を集めている。確かに導入ハードルは低く、業務に特化したシステムをスピーディに構築できる魅力がある。だが、その利便性の裏に隠された最大の課題が「運用体制の欠如」である。誰がそのシステムを保守し、進化させていくのか?この“面倒を見る人がいない”問題こそが、導入効果を半減させ、時には“負の遺産”を残す。中小企業におけるIT人材不足や運用定着の難しさを背景に、ノーコード導入の真の現実に迫る。
ノーコードに寄せられる期待とその背景
ノーコード導入は「手軽で速いIT化」として中小企業経営者に希望をもたらす。現場に合わせた柔軟な業務アプリが自社で構築できることは確かに魅力的だ。

プログラミング不要の開発環境が魅力
ノーコードの最大の特徴は「専門的な知識が不要」という点にある。従来のシステム開発では、開発会社への依頼、長期スケジュール、数十万〜数百万円単位の投資が必要だった。これがノーコードでは、ドラッグ&ドロップでフォームやデータベースを構築でき、テンプレートも豊富だ。中小企業の現場でも「社内の誰かが作れるかも」という期待が生まれる。
自社業務にピッタリのシステムが作れる
Excelでは限界がある業務の可視化や、現場に最適化されたワークフローの自動化が可能になる。特にクラウド型ノーコードサービスであれば、リモートワークや多拠点業務にも対応できるなど、DX推進にも寄与するとされている。業務にフィットするツールを、外注せずとも自社で生み出せるという「内製化」の発想が加速する。

IT部門がなくても始められる手軽さ
多くの中小企業ではIT部門が存在しない、または実質的に1人が兼任している。ノーコードは「誰でも使える」ことを謳っており、IT専門家がいなくても運用が可能という前提がある。ベンダーも「すぐに始められる」「操作は簡単」と強調しており、経営者の関心も高まっている。
導入後に直面する「担当者不在」の現実
導入まではスムーズだが、問題はその後にやってくる。最大の課題は「誰がこのシステムを育てていくのか?」である。
初期構築後、放置されるノーコードシステム
最初は熱意ある社員が中心となってシステムを作る。だが、その熱意が長続きしないのが現実だ。作っただけで満足してしまい、メンテナンスや改修が行われず、やがて使われなくなる。業務変更にも追従できず、現場では「結局またExcelに戻った」という声も少なくない。これは『IT顧問のススメ』でも言及した「導入効果と実運用の乖離」に他ならない。
担当者の退職・異動でブラックボックス化
担当者が異動、退職した時点で「何がどうなっているのか分からない」状態に陥る。ノーコードであってもシステムはシステムであり、ある程度の構造理解が必要だ。ドキュメントも残されていなければ、手の出しようがない。こうして「業務を効率化するはずのシステム」が、むしろ非効率を生む存在へと転化する。
IT人材が孤立する中小企業の組織構造
中小企業ではITを任された担当者が社内に1人だけというケースが多い。しかも、上司がITに疎く、同僚に相談できる相手もいない。評価制度も曖昧で、成果が見えにくいため定着しづらい。結果、担当者が疲弊し、やがて離職…という悪循環に陥る。

担当者をどう確保するか?中小企業の選択肢と現実的課題
担当者不在問題を解決するにはどうすればいいのか?中小企業が取り得る現実的な選択肢を比較検討する。
専任担当者を置く
責任の所在が明確になり、ノウハウの蓄積も可能。しかしIT人材の採用はそもそも難易度が高く、採れたとしても定着させるのが難しい。待遇やキャリアパスが示せなければ、すぐに流出する。『中小企業に必要なリーダーシップの土壌を作るための経営者の戦略』でも述べたように、裁量と信頼がなければ、社員は力を発揮できない。
兼任で対応させる
コストは抑えられるが、本業優先となり、改善は後回しになる。特に営業や経理など他の役割を持つ社員にノーコード運用まで担わせるのは、現場の負荷が高すぎる。中小企業の多くで失敗しているパターンである。
派遣社員に任せる
即戦力としての導入は可能だが、ノウハウが社内に蓄積されない。また、派遣期間が終わればまた振り出しに戻る。継続性の欠如はリスク要因である。
スポット外注を利用する
必要な時にだけ頼めるためコスト効率は良い。ただし、トラブルが発生した際の即応性に課題が残る。属人的なシステムに対して、都度違う外注先が対応するのも限界がある。
IT顧問・外部パートナーとの契約
最も理想的な解決策の一つ。継続的な支援が可能で、システムの成長を一緒に伴走してくれる。『IT顧問のススメ』ではこの形を強く推奨している。導入時の判断ミスや投資の失敗を回避するためにも、外部視点の導入が不可欠だと考える。
継続運用を成功させるためのポイント
ノーコード導入を成功に導くためには、導入そのものよりも「継続運用」にフォーカスすべきである。
導入時点で「誰が面倒を見るか」を明確にする
最初に「システムの管理者は誰か」を明確に決め、役割と責任範囲を文書化しておくことが不可欠である。属人化やブラックボックス化を防ぐためには、このプロセスが最初の一歩となる。経営者自身がこの点を見過ごすと、数ヶ月後に手のつけられない状況になる。
属人化を避けるナレッジ共有
システム設計・運用に関する手順書やマニュアルを整備することで、誰が見ても理解できる状態にしておく。『「文章化できない病」が組織を蝕む』でも強調したように、言語化と記録がなければ業務は再現性を失い、属人化が進む。
社内だけで完結させようとしない
中小企業では「できる人に任せる」傾向が強いが、それは長期的にはリスクになる。外部パートナーの活用を前提に、複数の支援先を持つことが継続性と安定性につながる。IT顧問、システム会社、フリーランスなど、状況に応じて組み合わせることで対応力が増す。

システムは“完成品”ではなく“進化するもの”
導入時点の要件で完成したシステムは、数ヶ月後には現場の業務フローに合わなくなる可能性が高い。だからこそ「改修・改善ありき」の文化を根付かせる必要がある。「一度作って終わり」ではなく「運用しながら育てる」ことが求められる。
まとめ:導入よりも“続ける仕組み”が価値を生む
ノーコード/ローコードは確かに中小企業におけるIT活用を後押しする。しかし、その真価は導入後の「継続的な運用体制」にこそある。誰が面倒を見るのか、どう育てていくのか。その仕組みを設計せずに始めてしまえば、やがて使われなくなるか、逆に業務の足を引っ張る存在になってしまう。
経営者がすべきは、「ツールを導入する決断」ではなく、「それをどう活用し続けるかという仕組みづくり」だ。そして、その仕組みづくりには、信頼できる外部パートナーの存在が欠かせない。属人化を避け、継続的に改善できる体制こそが、中小企業のIT活用における最適解なのである。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。