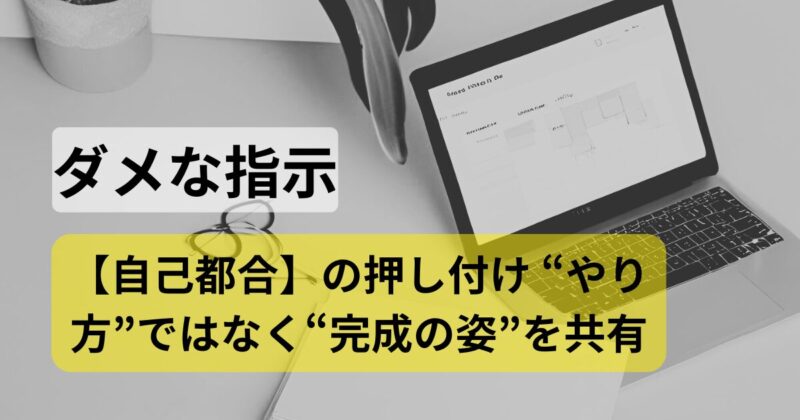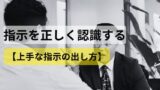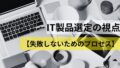指示することの本質的な意味や意義を理解せず、上司だからやっている。立場が上だから指示をしいてるというマネージャが、ダメな指示をしている。「ダメな指示」一般的に言われていることはあるが、どうもわかりにくいので、本稿では何がダメで、どうしたら良い指示となるのかをシンプルに解説します。
✔️ ダメな指示の定義が曖昧だからダメ指示が継続する
✔️ 指示がダメだからリモートワークに不都合が生じる
ダメな指示の定義が曖昧だからダメ指示が継続する
ダメな指示の出し方などで、ググって見るとダメな指示の例としては主に以下のようなことがでてくる。
具体性に欠け、曖昧で、同時にいくつも言われて、最終的には感情論にうったえられても受ける側は迷惑であろうし、自分なりに考えながらやるしかないということになる。ダメな指示には違いないのだが、この例そのものも曖昧ではなかろうか。
もっと、具体的にダメな指示ってどういうものなのか?客観的に評価できるような定義はないのか。私自身の経験や上司の言動を見聞きしながら「そういうの指示って言うのかなぁ…」と常々、感じていたことがある。
「やり方」って適切な指示と言えるか?
少し極端な例ではあるが、以下のようなやりとりを考えていただきたい。
営業職で明日、お客様(B社)に最終プレゼンをする予定になっているので、その資料を作らなければならない時のダメな指示は

明日のプレゼンは以前のA社と同じ感じだから参考にするといいよ。
・A社の資料は、サーバーの**というフォルダにある
・それを参考にだいたい同じ構成にしておいてよ
・できたら言ってよ。
・なんかわからないことあったら、今日は外出しないのでいつでも聞きにきて。
これは指示なのだろうか?この上司が自分自身で資料を作る時の、自分のやり方を部下に押し付けているだけではないのか。これを部下の立場で受けると…こんな風に思わないだろうか?

A社と同じような構成で、それを参考に…?
だったらA社をB社に変えたらいいんじゅないっすか!
って、ならないだろうか?(私ならそう思う)
適切な指示は完成の姿を共有すること
✅ プレゼンの目的:なんのために?どうなったら成功なのか?
✅成功のために必要な要件はなにか?
✅受注のキモとなるものは?:価格?競合排除?…等々…
これを確認し、共有してから

・30分なので、10〜15ページ以内で収めよう。
・ストーリー(流れ)は自分なりに考えてみてくれ。
・とっかかりが難しかったらA社向けの資料を参考にしてみるといい。
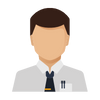
わかりました。

・まずは、下書きで流れと構成要素を入れ込んだものを作って。
・それを互いの意見と感覚に照らして確認しみようか。
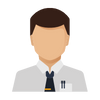
わかりました。

どのくらいの時間でできそう?
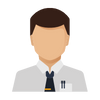
3時間くらいです。

じゃー…16時に、ちょっとすり合わせしようか。
無理に時間内に仕上げようとしなくていいし、なんかわからん。ってなったらいつでも聞きにきてくれ。
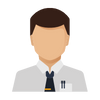
はい。ありがとうございます。
このような、やりとりが自然ではないのか?指示をするとか、受けるとかそういうことではなく目的のためにお互いの力を合わせて成果物を作り上げる。結果として、指示を出していることになるだろう。上司だから部下に指示を出してやらせるという発想や概念は要らない。
上司と部下の関係性や指示の意味と意義については、こちらの記事も参考にしてください。
ここでダメな指示の一つの結論が導かれたことになる。それは、やり方を言うな!ということである。完成の姿を互いに共有し、そこに行き着くまでにどのような問題があるかも合わせて共有する。これが、本来あるべき指示というものの本質的なカタチではないのか。
指示がダメだからリモートワークに不都合が生じる
やり方を押し付けて(指示して)部下が思ったような成果物を出してこなかった時の上司は…

・なんでこうやったんだよ!
・言っただろ!これを見てやれ!って。
・そんなやり方、言ってないよな!
・なんで、言った通りにやらないんだよ!
・お前は、俺の言ったこと聞いてたか?
成果物には一切言及せずに、部下の態度や行動…つまり、やり方を叱責する。上司の感情がエスカレートすると、その部下の人格に触れそうなところにまで言及しかねない。そうなると、やっぱり俺がそばで見てないと、こいつはちゃんとやらんなぁ(できない)…ということになる。これが、リモートワークだと仕事がしにくくなるという指示が下手な上司の典型的なパターンである。
やり方は部下の好きに、自由にやってもらえばいい。規定やなんらかの枠内でやってもらう必要はあるが、共有した成果物を完成させるために、何から初めて、途中経過としてどうなってなければいけないのかまで、管理・監督され、言われた通りにしかやってはダメということなら、自分でやってくださいよ!ってなるのではないか。
これでは、部下育成なんてことはできない。やらされているだけで、自分で仮説を立てて、やってみて、検証して、改善してという経験値が積み重なることにはならない。自分で考えてやってみるから、自分なりのスタイルや技能として定着するのではないのか。
上司ができることは、部下に体験・経験させるという環境(仕事)を与えることであり、自分の培ったやり方…たとえそれが成功したものであっても、その通りに部下ができるという確証も保証もないのではないか。言った通りにやる部下が良い社員で、自分のやり方を通す社員は聞き分けが悪いと評価されることになれば、成果物の質ではなく上司に忖度して、言った通りにやるという行動をする社員が増えてしまうことにならないだろうか?
そして、うちの部下は自分で考えて動くやつがあまりいないんだよ…なんて、言ったりすることになる。自分(上司)でやっていることを、まるで部下が無能であると言ってるかのようだが、とんでもない勘違いである。
まとめ(ダメな指示とは?)
❶ やり方を言う
やり方を言うから、成果物の質よりも、自分(上司)の言う通りにやっているかどうかがチェックポイントになり、管理(監視に近い)しないと、ちゃんとできないだよなぁ…という誤解を生み出す。
❷ 完成の姿(成果物)の共有がない指示は意味がない
どうなったら成功か?どういう状態をもって完成なのか?これが共有されてないければ、部下は何をしているのかわからなくなるだろう。ここを明確に言わない上司は決して少なくない。もしかすると、上司自身が何をやったらいいのかわかってないのではないか…(私は過去の上司に対して、よくそう感じていた…)だとしたら、もっと勉強して上司としての機能(職責)を果たせるよう、部下の監視に注力するのではなく自己研鑽するべきだろう。
多少、極論的な解説とはなってしまいましたが「指示する」とか「指示」という言葉や表現にとらわれず、部下という仲間と一緒に成し遂げるという感覚を持てば、人は動いてくれるようになるのではないか…
最後までお読みくださってありがとうございます。
また、お会いしましょ。