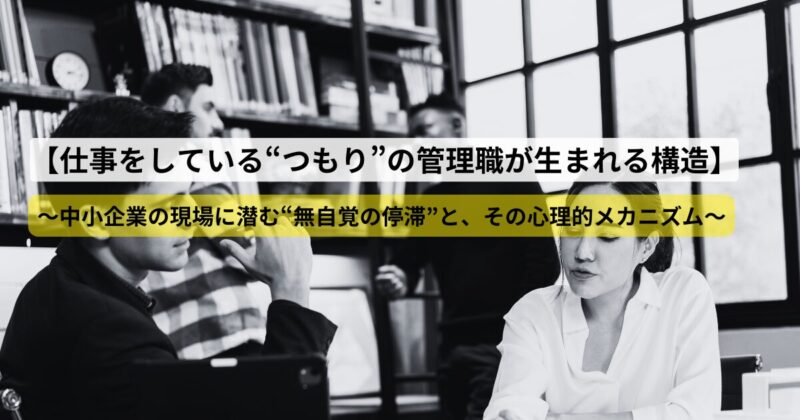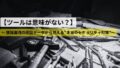報告もするし、指示も出している。会議にも出て発言しているし、部下からの信頼もある…。
だが、その管理職のチームは一向に成果が出ない。提出される資料は薄く、意図が曖昧で、次の一手も見えない。
それでも当人は「自分はちゃんとやっている」という自信に満ちている。指摘すれば、「価値観の違いですね」と煙に巻かれる。
これは決して“怠慢”でも“能力不足”でもない。本人が“本気でやっているつもり”になっているからこそ厄介なのだ。
この記事では、「評論家化する管理職」の心理構造を深掘りし、経営者が“誤解せず、甘やかさず、責めすぎず”に向き合うための視点を提供する。
「できていないこと」が認識できない構造
指摘されても“通じない”理由は、心の設計にある
「わかったつもり」が生み出す無敵の自己評価
人は、自分が“理解できていない”という現実を、なかなか受け入れられない。
たとえば、「クラウドって何?」と聞かれた時、言葉は知っていても、自分で説明できる人は少ない。
これと同じで、管理職も以下のような“誤解”をしていることがある:
- 会議で発言した → 考えた証拠
- 指示を出した → 動かした証拠
- 提出物がある → 成果を出した証拠
“行動の有無”が“仕事の質”を保証しているかのような錯覚に陥るのだ。
そしてこの錯覚が、“自分はやっている”という揺るぎない自負を生み、
経営者からの指摘が「事実の指摘」ではなく「文句」や「理解不足」として受け取られる。
「意見の違い」として逃げる心理防衛
指摘された時に、「なるほど」と受け入れる人は少ない。特に管理職となると、
「自分のやり方が否定された」と感じやすくなる。
その防衛としてよく使われるのがこのセリフ:
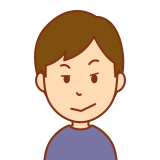
「それって、意見の違いじゃないですか?」
これは論理的な反論ではない。“否定されること”から逃れるための防衛反応だ。
「あなたの基準では足りないかもしれないが、私の価値観では十分だ」
という枠組みに話を持ち込むことで、“間違っている”という評価を避けようとする。
結果、「どちらも正しい」という無風地帯に話が着地し、責任も検証もあいまいになる。
成果がなくても「努力した」という免罪符
- 報告した
- 企画を考えた
- 部下とも対話した
…これらの行動の“履歴”が、「頑張った」の証拠になると思っている。
指摘されればされるほど、「なぜ理解してくれないのか」という被害者意識が膨らみ、
自分の中で「自分=正しい/経営者=わかっていない人」という構図が強化される。

管理職は経営者をどう見ているのか?
“指摘されている”のではなく、“絡まれている”と思っている可能性
経営者を「評価できていない人」と見下している場合もある
本人の中では「現場は自分の方がわかっている」「部下も自分を信頼している」という確信がある。
そこへ経営者から、「ここが浅い」「こうすべきでは?」という指摘が入ると…
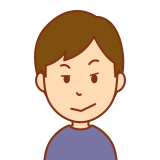
「現場も知らないくせに」
「だから社長はズレてるんだよ」
「部下の信頼もないのに、何をわかるというのか」
…と、上から目線で“下から批評”してくる状態になる。
本人は“意見されている”と思っていない。“誤解されている”と思っている。
指摘が「注意」ではなく「攻撃」に変換される
「ちょっと中身が浅いかな」→「俺を潰したいのか?」
「もう少し踏み込んで」→「仕事増やしたいだけだろ」
「現場の声をもう少し整理して」→「部下の信頼を奪う気か?」
このように、経営者の言葉が“攻撃”に変換される“脳内フィルター”が存在する。
これはパーソナリティの問題というより、“防衛反応”だ。責められたと感じたくないのだ。
「正しくない上司に絡まれるのは損だ」とすら思っている
本人の思考:
- 「自分は一生懸命やってる」
- 「現場も信頼してくれている」
- 「それなのに認められない」
→ 結論:「社長がわかってないだけ」
つまり、“上司から評価されない”のではなく、“評価する側が間違っている”という逆転構図が成立している。
なぜこうなるのか? その深層にある「構造」
これは“人間性の問題”ではなく、“構造的な誤作動”だ
誰にも「ちゃんと教えられていない」まま管理職になった
多くの中小企業では、プレイヤーとして優秀だった人材が、そのまま“なんとなく”管理職になる。
するとこうなる:
- 成果が出ない → 誰のせいかわからない → 自分は頑張っている
- 会議は回している → チームも壊れていない → 自分はうまくやっている
仕事の評価基準が“成果”ではなく“混乱が起きていないこと”になる。
「やることが明確でない=やっているつもり」現象
プレイヤーは、「いつまでに/何を/どのレベルで」が明確だった。
管理職になると、“ふんわりと全体を見る”という業務に変わる。
この“あいまいさ”の中で、「会議で発言した」「報告した」「資料出した」が、
本人にとっての“成果の指標”にすり替わっていく。

誰も「それは成果ではない」と言わない組織
そして最大の原因は、
経営者側も「言っても響かない」と諦めてしまうこと。
- 「また指摘するのも面倒だな」
- 「言っても反論されるだけだし…」
- 「まぁ波風立てるよりは…」
この“甘さ”こそが、評論家管理職を生み、温存し、増殖させていく土壌になっている。
まとめ:仕組みより、まず「理解」が先にある
人は、わかっていない自分を直視するのが怖い。だから、やっている“つもり”で自分を守る
評論家化した管理職に対して、
テンプレを配り、ガントチャートを作り、定例会議を入れても、
本人が“なぜそうなるのか”を自覚していなければ、形だけの対応しか返ってこない。
だからこそ、対策より先に必要なのは、“構造を理解すること”である。
その上で、経営者は問いを変える必要がある。
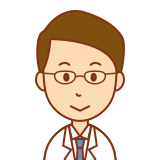
- なぜ彼は“やっているつもり”になるのか?
- なぜこちらの言葉が“攻撃”に変換されるのか?
- なぜ「現場を回している」という言葉が自信に繋がるのか?
それが見えた時、はじめて建設的な関係性の再構築が始まる。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。