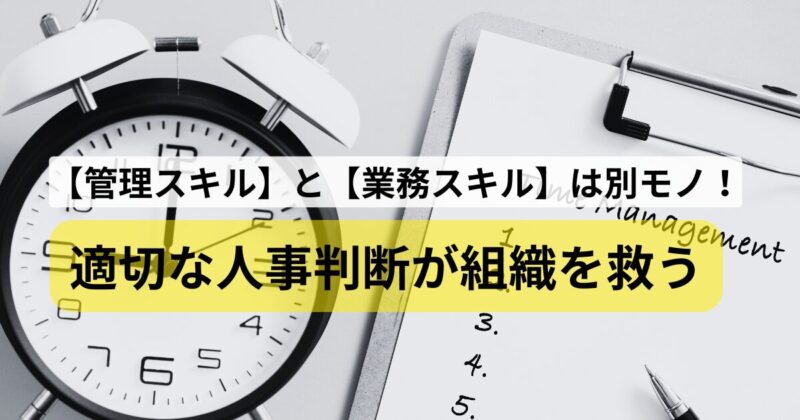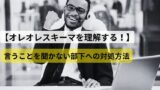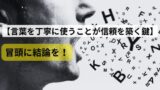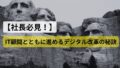日本の中小企業では、優れた業務スキルを持つ個人が、その能力を評価されて管理職に昇進するケースが多い。しかし、管理職に求められるのは、個人としての業務能力だけではない。チーム全体をまとめ、部下を育成し、公平な評価を与えるスキルも不可欠である。しかし、この認識が浸透していない現状が、多くの課題を引き起こしている。部下の成長が停滞し、職場の士気が低下、さらには高い離職率を招く状況が散見される。本稿では、管理職に求められるスキルを再定義し、実際の育成プロセスについて詳細に解説する。
管理職に必要なスキルの再定義
日本の中小企業における「管理職」は、従来の役割を超えて多面的なスキルを求められるポジションである。ここでは、管理職として最低限求められるスキルを以下に分解し、それぞれの重要性を解説する。
人材育成スキル:部下の成長を支援するために
人材育成は、管理職の最も重要な責任の一つだ。優れた管理職は、部下一人ひとりの能力や性格を理解し、その強みを最大限に引き出す方法を知っている。例えば、部下が抱える課題を明確にし、具体的な解決策を提示できる能力が求められる。また、部下の心理的要因に配慮したアプローチも重要であり、認知心理学や行動経済学の知見を活用することで、部下のモチベーションを高めることができる。
さらに、フィードバックの方法論も注目すべき点である。効果的なフィードバックは具体性を伴い、ポジティブな視点を重視することで、部下の成長意欲を刺激する。たとえば、「もっと頑張れ」という抽象的な表現ではなく、「前回のプロジェクトで見せた分析能力を、次回の課題でも活かしてみよう」といった、具体的で行動指向のアドバイスが必要だ。
管理職は語彙力が求められる
「ダメなところを率直に指摘して欲しい。」と求める部下もいるが、完璧な人間は存在しないのだからダメなところに注力させるようなフィードバックではなく、結果としてダメなところを補うような行動を促すポジティブな指導をする方が効果的だ。自分が見て、知っていることを伝えるだけで、後は受け取る部下の問題としてしまうのであれば管理職としての責任を果たしているとは言えない。部下の前では否定後は完全に排除する注意深さと語彙スキルも求められる。
公正な評価スキル:公平な環境を構築する
管理職は、部下を評価する際に公平性を保つことが重要である。曖昧な基準や主観的な視点に頼った評価は、チーム内の不和を生むだけでなく、個々のモチベーションを低下させる要因となる。なにより、管理職としての信頼性を失うことになり、人間関係の崩壊へと繋がっていくかもしれない。評価をするというスキルはそれほど重要なものだと認識するべきだ。大事な視点は、客観的なデータを基にした評価制度の導入である。
公正な評価には、明確な基準と透明性が必要だ。たとえば、部下の業績を数値化した指標で測定し、結果を定量的に分析する方法が効果的だ。さらに、評価基準を事前に共有し、全員が理解できる形で公開することで、不満を未然に防ぐことができる。また、評価プロセスにおいて部下との対話を取り入れ、評価の妥当性を説明する機会を設けることも、公正性を高めるための一助となる。
目標管理制度との連動
「何をやったら評価されるのか?」「どんなスキルを求めているのか?」「頑張ったら…ではなく、成果・貢献度が高いと評価されるために必要な要件、数量は?」….具体化・定量化し、運用していく中で現実との乖離が無いか分析し、必要に応じてアップデートする。目標管理制度と連動させる運用が望ましい。

目標管理制度についてはまた別の記事で詳細を説明することにします。
コーチングスキル:自発性を引き出す
従来の指示命令型のマネジメントスタイルは、部下の自主性を損なう可能性が高い。そこで、コーチングスキルの活用が注目される。コーチングは、部下自身に問題解決の方法を考えさせ、そのプロセスをサポートする手法である。この方法により、部下は自分の能力を高め、成長の実感を得ることができる。
筆者は個人的な感覚であるが、このコーチングスキルが一番必要なスキルだと考えている。マネージメントの現場で”コーチング”という言葉を耳にすることはほとんどない。一般的な認識となっていないのだろうか?…前述の通り、仕事ができて一定の成功を収めた人が多いので自分のやり方を教える(時には押し付ける)ような指導になりがちだ。違う言い方をすると、ちょっと偉くなってしまい「悪い癖」が出てしまうのだ。これはコーチングの観点から言えば、直すべきことである。
☑️ 極度の負けず嫌い
☑️ 善し悪しの判断をくだす
☑️ 「いや」「しかし」「でも」で、文章を始める
☑️ 自分がいかに賢いかを話す
☑️ 否定、もしくは「うまくいくわけがない、その理由は…」と言う
などだ。。このような癖がある管理職は今すぐにでも改善する必要があるだろう。
管理職育成のための具体的なアプローチ
管理職に求められるスキルを育成するためには、体系的かつ計画的なプログラムが必要である。このセクションでは、効果的な育成プロセスについて解説する。
現状分析:課題を明確化する
育成プログラムを設計する際、まず現状の課題を明確にすることが不可欠である。これには、管理職自身による自己評価、上司や同僚からの360度評価、さらには部下からのフィードバックが役立つ。たとえば、「部下の満足度調査」を実施し、現在の管理職のスキルセットのどこに改善の余地があるのかを特定する。
さらに、現状分析の結果を基に、管理職ごとに個別の育成プランを作成することで、効果的なスキル向上が期待できる。例えば、部下とのコミュニケーション不足が課題であれば、ロールプレイング形式の訓練が有効となる。
経験豊富なプロ(専門家)の支援を受ける
中小企業において、育成プログラムや計画立案と運用をすることは無理であろう。そのような人材もいないだろう。その場合は、外部の専門家の支援を受けた方がいい。コストは発生するが、採用に多くのお金をかけても3年以内に人が辞めてしまうのであれば、それは全てが無駄な投資となる。人材に関するコストは、採用コストだけではなく今いる人材にもそれなりのコスト…コストではなく、投資をするべきである。研修などを提供する事業者は多々あるが、筆者もそれに該当するのだが…実際に中小企業の経営に携わって、数十名の部下をマネジメントした経験がある人の支援を受けることをお勧めする。
机上の知識や一般論だけでは通用しないことも多々あるのだ。多くの練習をして技術を磨いても、一度も試合に出たことがない人…部下を持ってマネジメントをしたことがない人に、コーチングをして欲しいだろうか…説得力と信頼性に疑問を感じる。これはあくまでも筆者の個人的な考えである。また、研修を受けた経験からもそう思う。「べき論」を言うだけで、焦点がズレている…と、感じたし、そんなもん実際の現場で通じるかいな!…いやいや、そんな風にはなりませんし、なってませんから!と、言いたくなるような研修ばかりだったような記憶しかない…それで、結果として自分が現実的かつ実践的な内容の研修をする立場になったのだが…

プロフィールに少しだけ、どんな研修をやっているのか触れているので興味がある方は一読ください。
育成プログラムの導入
管理職育成プログラムは、理論的な知識と実践的なスキルを統合した内容で構成されるべきである。認知心理学や行動経済学を活用したセミナーやワークショップは、管理職が部下の心理を深く理解するための助けとなるだろう。
また、実践的なスキルを養うためのOJT(On-the-Job Training)も有効だ。たとえば、管理職候補者が先輩のサポート役としてチームを率いることで、実務を通じてスキルを磨くことができる。このような現場での経験は、座学では得られない洞察を提供する。定期昇給のタイミングに合わせて、管理職になるということではなく、管理職候補という位置付けも明確にして日常業務の中でマネジメントスキルを磨けるような制度・仕組みを構築することは大事な視点だ。
明日から管理職で、部下が3人!となって、ぶっつけ本番でマネジメント業務をすることになれば、本人も当惑するかもしれないが…部下にとっては当惑どころか、結果として迷惑になるかもしれないのだ。誤った人事判断は優秀な人材を放り出す手助けをしてしまうことにもなりかねないのだ。これをよく理解した上で、管理職の任命をしなければならない。
定期的なフォローアップ
育成プログラムの効果を最大化するためには、継続的なフォローアップが必要である。これは、定期的な評価会議やフィードバックセッションの形で行われるべきだ。たとえば、育成プログラム終了後も、管理職としての行動が改善されているかを確認するためのチェックリストを活用するとよい。
現実的には、外部の専門家に依頼・委託することで運用するのが望ましい。追加トレーニングや、最新の管理手法に関するセミナーへの参加を奨励することで、学び続ける文化を育むことができる。全て自社で完結する体制を作っていくことが文化ではなく、人材育成に力を入れて投資を惜しまない…しっかりとした育成プログラムがあり、定期的に見直しもされ、学ぶ機会も用意されており、専門家の支援を受けて運用が停滞・陳腐化・形骸化しないようにしている。従業員がこのように感じることができたら、それはもう文化として確立したものと言えるのではなかろうか。
まとめ
中小企業における管理職のスキル不足は、組織全体の成長を妨げる大きな要因となる。業務スキルだけでなく、人材育成や公平な評価、公正なマネジメントを実現するためのスキルが必要不可欠だ。そのためには、現状分析から始まり、体系的な育成プログラムの設計、実施、フォローアップまで一貫した取り組みが求められる。これにより、管理職の能力が向上し、組織の生産性や士気が大きく向上することが期待できる。
中小企業には、多少ハードルが高い内容になっているとは思うが、仕事ができる人が良い管理職になるとは限らず、無知識のままさせることはリスクを伴うとの認識は持っていただきたい。人材育成をするためには、人材を育成ができる人材を育成しなければ、その企業では人財を作ることはできない。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
また、お会いしましょ。