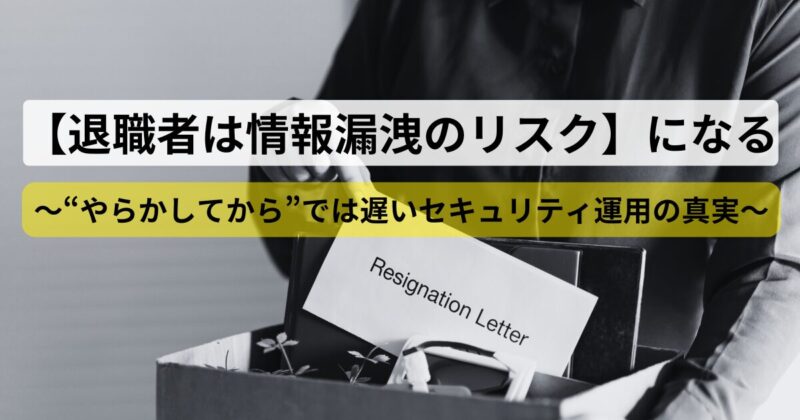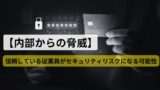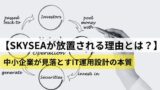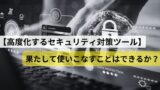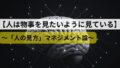中小企業における「人手不足」と「情報セキュリティ対策」。この二つは一見すると無関係に見えるが、実は密接に関係している。特に、社員の退職というイベントは、セキュリティ上の重大なリスクを内包しており、これを軽視したまま運営を続けることは経営的にも致命的な判断ミスになりかねない。
本稿では、情報漏洩・外部アクセス・悪意ある操作など、退職者が引き起こすリスクについて経営者の視点から解説し、事前に講じるべき現実的なセキュリティ対策を提案する。
退職者が引き起こす情報セキュリティリスクとは
退職という事象がセキュリティリスクになる理由を、以下に説明する。
退職者による「情報持ち出し」リスク
業務に必要な情報へのアクセス権を付与している以上、退職者がその情報を持ち出してしまう可能性は常にある。特に、会社への不満を抱えたまま退職した場合や、転職先で競合となる企業に移るケースでは、重要情報を「お土産」として持ち出す動機が生まれやすい。顧客情報、販売データ、見積書などの営業情報は、すぐにでも次の職場で活用されてしまう恐れがある。

アカウントやアクセス権限の「残存」リスク
退職後もVPNやクラウドアカウント、社内システムなどにアクセス可能な状態が続いているケースは少なくないだろう。IT専任者が不在の中小企業では、総務や事務が物理的な退職手続きに追われる一方で、IT関連のアカウント削除は「後回し」や「忘れられている」状態になってしまうのだ。これにより、悪意あるアクセスやデータの操作が可能になってしまう。

「嫌がらせ」や「消去」などの内部不正
持ち出し以外にも、退職前の社員が故意にデータを削除したり、名前を伏せたまま不正な操作をしたりするリスクも見逃せない。特に中途社員や短期間で辞めた人材がアクセス可能だった範囲に、共有サーバやバックアップフォルダが含まれている場合、何らかの形で被害を及ぼすことは現実に起こりうる。
アクセス制限は「信頼構築」まで段階的に行う
入社直後からすべての情報にアクセスできる仕組みは、リスクでしかない。この認識は情報セキュリティ対策の観点では重要な視点だ。
試用期間中はアクセスを限定する
採用した人材に即戦力を期待するのは自然なことだが、入社直後の社員に全情報へのアクセスを与える必要はないだろう。基幹システム、顧客情報、財務データへのアクセスは厳格に制限すべきだ。試用期間中は最低限の業務情報のみに制限し、会社理解のための情報は限定的に与えれば十分である。
フォルダ設計は「段階的開放型」に
共有フォルダや業務システムにおいては、「新入社員専用フォルダ」や「教育用資料専用エリア」を設け、試用期間や業務スキルの習熟度に応じてアクセス範囲を拡大していく「段階的アクセス管理」が有効である。これにより、必要な情報だけが共有され、万が一の退職時にも損害を最小限に抑えることができる。
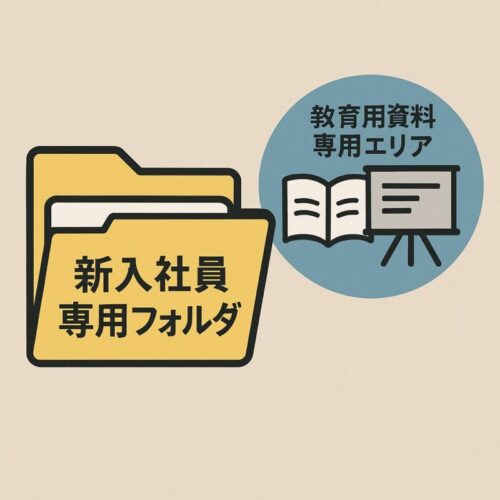
アクセス権限は「業務範囲」ベースで管理する
すべての社員に一律のアクセス権を与えることは、企業にとって非常に危険である。特に情報資産においては、役職・部署・担当業務に応じた権限設定を厳密に行うべきだ。「社員を信用していないのか?」という声があるかもしれないが、それは信用の問題ではなく、業務上のリスク管理の問題である。
ツール導入だけでは機能しない「運用体制」の構築
セキュリティツールの導入は手段であり、目的ではない。
ログ監視ツールの「形骸化」に注意
クライアント管理ツールやログ記録ソフトは導入していても、運用されていないことが多い。ツールの存在そのものが「導入した安心感」を生むが、記録されたログを「誰が」「いつ」「どうやって」確認するのか、運用体制がなければ機能しない。形だけのセキュリティでは、退職者による不正操作も見逃される。
管理体制がなければリスクは増大する
IT専任者が不在の中小企業では、総務担当が兼務するケースが多いが、専門知識が求められるセキュリティ対策を素人判断に任せることは危険である。最低限でも、「誰が何を管理するか」の役割分担とマニュアル化は必須だ。アクセス権限の管理・退職時のアカウント削除・ツールのログ確認は、定期的にチェックする仕組みが求められる。
IT顧問や外部パートナーとの連携が不可欠
中小企業が自力で高度なセキュリティ体制を維持するのは現実的ではない。退職者対応、アクセス管理、ログ監視といった実務レベルの運用には、外部の専門家と連携し、「顧問契約」や「セカンドオピニオン」を導入することが効果的だ。これにより、現場に即した助言と、適切な判断が可能になる。
まとめ:退職リスクに備えるのは経営判断である
退職者による情報漏洩や不正アクセスといったリスクは、中小企業にとって極めて深刻な経営リスクである。だが、このリスクは「事前に想定しておく」ことにより、大部分は回避できる。採用時点からアクセス範囲を限定し、段階的に開放していくセキュリティ運用。
導入したツールを実際に運用する体制。そして、外部の専門家の知見を活用する戦略的な判断。これらの対応こそが、情報資産を守るだけでなく、組織としての信頼性を高める経営の基本である。セキュリティ対策はコストではなく、経営のインフラ投資であると捉えるべきだ。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。