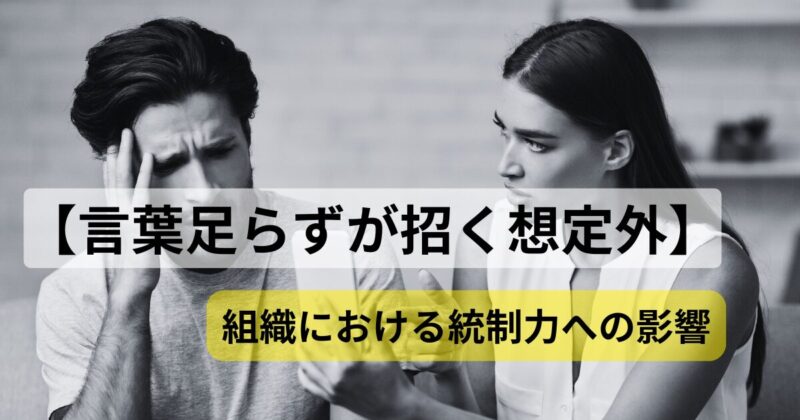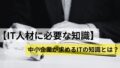人間は人にモノを伝える時には言語を用いる。メールやチャットなどの文章の形態もあるが、身近な存在…特に組織内においては、口頭で会話をしながら伝えることがほとんどであろう。だが、この時にどのような言葉の選択をするかによって、人の解釈は様々なものになる。管理職として組織を統制する上で不適切な言葉の選択・使い方とはどのようなものなのかを、日常的に起こり得ることを想定しながら解説させていただく。
✔️ 立派な言葉だから人を動かせるとは限らない
✔️ 主語が大きすぎる、主体が存在しないのは説得力に欠ける
✔️ 本質を見失ってしまう言葉の使われ方
立派な言葉だから人を動かせるとは限らない
単純で俗っぽい言葉よりは、四字熟語や故事で使われるような表現を用いると、自分が博識であるかのように見えて、敬われることにもなり、伝えることにも重みが増すので、言葉選びは慎重にしている。もし、そう思っているとするならば、果たしてそうなのだろうか?ただの自己満足に過ぎないのでは…
動詞よりも副詞が強調される
「目標達成のために、お客様には誠心誠意、心を込めて接して受注に繋げて欲しい。」と、言われても、「何を?」「どうやって?」と、具体的な行動に繋げようがないのではないか。“誠心誠意”“心を込めて”などの副詞に力が入り過ぎて、行動を促す動詞が曖昧すぎて、単なる掛け声にしかなっていない。
結局、何をしろとの指示なのか不明確なのだ。
「営業活動に注力できるよう、事務作業の軽減を目的としたIT化を検討しているので、今まで以上に頑張って欲しい。」これは一体、何を言ってるのだろうか?検討をしているということなら、導入しないということもあり得るということなのだろうか?どの事務作業なのか?まったく具体性に欠けて何を伝えたいのか意味がわからない。
「**月より、交通系ICカードの導入で、交通費精算作業が無くなります。」
など、具体的にいつ、何を、導入するのか説明がなければ、どの程度、営業活動に注力できるようになるかすらわからない。交通費精算作業に、1時間程度かかっていたなら、その時間をアポイント獲得のために費やすことで週間の訪問数が1.5倍は見込めるようになる。など、行動改善のイメージができるような伝達をして欲しいものである。
「こんなことやる予定だ」「こう考えている」「***という方針で進めている。」など、良いことを伝えているつもりなのかもしれないが、聞く側にとっては実現するかどうかも曖昧な薄っすらとした期待感しかなく、実利はない。
横文字の乱用で、ごちゃごちゃになる
「当社の事業戦略は、顧客ニーズの多様化に対応すべく、プロアクティブなマーケティング施策の実行を基軸としています。」このような説明を受けても、抽象的な上に、何を言っているのか意味がわかりにくい。言いかえるならば、「お客様の様々なご要望に応えるために、私たちはお客様のニーズを先読みして、積極的に新しい取り組みを進めています。」ということになるだろうか。
何れにせよ、抽象的な表現ではある。この後に、例えば…ということで、取り組みの事例など解説があると聞き手は理解が深まると思われる。
ちょっと思い出したことがあるので、言っておこう。丁寧な言葉を使って説明や会話をすることは決して否定しない。が、行き過ぎた丁寧は、アホを露呈することになるかもしれない。これは、私の経験談なのだが、人材教育を請け負った会社で、営業マンの育成のために同行営業をした時のことである。
課長クラスの中堅営業マンで、経験豊富で実績もそれなりであるとは聞いていた。その営業マンがお客様のとの会話の中で、「どのような“ごニーズ”がございますか?」と、言ったのだ。「えっ?はぁ?ご・ご・ごニーズぅーーー?!」なんじゃそりゃ!って、思って、その後、笑いをこらえるのに必死だった。
ニーズは英語だ。英語に「ご」を付けて丁寧語という敬語に仕立て上げたのだ。本人なりの造語なのかもしれないが、正直なところ…アホ丸出しやな…って思ってしまった。「ご」や「お」を付けると丁寧な言葉にはなるが、使い方を間違えると恥ずかしいことになる。ふと考えてみると…なぜ、「お」じゃなく「ご」を選んだのだろうか?…いずれにしても笑える話であろう。珍しい人だなと思っていたのだが、実はその後、再び「ごニーズ」を聞く機会があった。それは別の会社の営業マンなのだが、営業成績は残念ながらあまり芳しくないとのことだった。
主語が大きすぎる、主体が存在しないのは説得力に欠ける
自分の言ってることに自信がないのか、正当化したいのか、やたらと大きな主語を使ったり、主体のないものを主語にして相手を説得しようとする上司がいる。これでは、人を動かすことはできない。なにより、自分が指示を出す主体者にも関わらず、主語を自分以外のモノで説明をするのは、逃げているのか、無責任なのか…上司の言動としては不適切である。
主語が大きすぎてピンとこない
「どうしてこれをやらないといけないのか?」と、指示に対して、それを実行しなければならない理由や目的を尋ねられた時に、「いや…それは、みんなやっていることだろ!」と、理由を説明せずに、“みんな”という主語を持ち出し、お前だけが異端児で、その疑問を呈していること自体が間違いである。という方向に話を持って行こうとする。これでは、なんの説明にもなっていない。これは不適切な表現である。
この「みんな」というのは、私は部下に対してもあまり使わないように指導していた。よくあることとして、「どうして、そう思うんだ?何か問題とかあるのか?」と、部下に問うと、「だって、みんな言ってますよ。」と、回答することがあるのだ。そういう時は決まって「そうか、そのみんなってのは誰のことだ?」って聞くと、名前が出てくるのは、せいぜい2〜3名くらいなのだ。3名しかいないじゃないか。だったら、みんな言ってるってのは正しくないよな?と、言うとだいたいの人(部下)は黙ってしまう。
理屈ではあるが、ちょっと屁理屈にも近い言い方なので、あまりおススメはできないのだが、自分の意見や考えを言わず、正当化するために「みんな」という主語を持ち出して、相手を説得するという手法をとることをやめさせたいとの思いでそういう対応をしていた。営業の現場でお客様に、一般的には…とか、導入いただいたお客様のほとんどは…など、主語を大きくして回答を誤魔化すようなことをして欲しくないと思ったからだ。この説明は、まったくと言っていいほど説得力を持たないと私は思っている。
存在しないものを主体(主語)にして指示をする
「なんで、これをやるんですか?意味ありますか?」
「また、やるんですか?前にやった時もあまり効果ありませんでしたよね?」
と、指示に対して部下が、不満というか疑問を呈してきた時に
「これは会社が決めたことだから」
「上からやれって言われてるんだよ」
と、「会社」とか「上」など、人物として存在しないモノが、言っている。として、指示を正当化するのはまったく不適切である。直属の上司にそう言われると、そうならないように対応するのが上司の役目じゃないんですか!と、部下は言いたくなるだろう。
上司は上司で「いや…俺も、これはどうかなって思うけど、まぁ…上の方で決まった強い意向なんで、何も言えないんだよ..」と、まるで自分は言いたくもない、やりたくもないのに、君らに伝えないきゃならないという貧乏くじを引いた被害者かのように振舞われると、部下としてはもう何も言うことはなくなる。
この「会社が」「上が」という表現を使う会社の共通点は(私の見聞きした範囲だが)管理職に適切な権限が与えられておらず、ほとんどが名ばかり管理職で、何かを決められるのはたった一人。社長だけ。という組織体の会社である。「会社=社長」「上=社長」という構図である。このような会社の社長がよく口にする共通点もある。それは、「ウチはなかなか人が育ってこないんだよ。とくに管理職がもっとしっかりしないとなぁ..」ということである。
こうなる原因はいくつかあり、決定的なのはこれ!というのがあるが、それを本稿の主旨ではないため、別の記事で解説させていただく。
本質を見失ってしまう言葉の使われ方
最後の項として、本質が違ってしまう言葉の使い方を申し述べたい。直接的にマネジメントとに関わることではないが、言葉によって指し示すものが違うけど、それが当たり前になって、本質的なものからはズレてしまっているということを言いたいのだが…
今(執筆時:2024年8月19日)は、自民党の総裁選候補が乱立しているというメディアの報道が日々、加熱している世相なのだが、こうなった原因に「裏金問題」の影響があると言われている。この裏金の話は置いておくとして、このようなことが話題になると、いつも決まって「政治と金の問題」との表現で報道なり、解説が行われるのであるが…
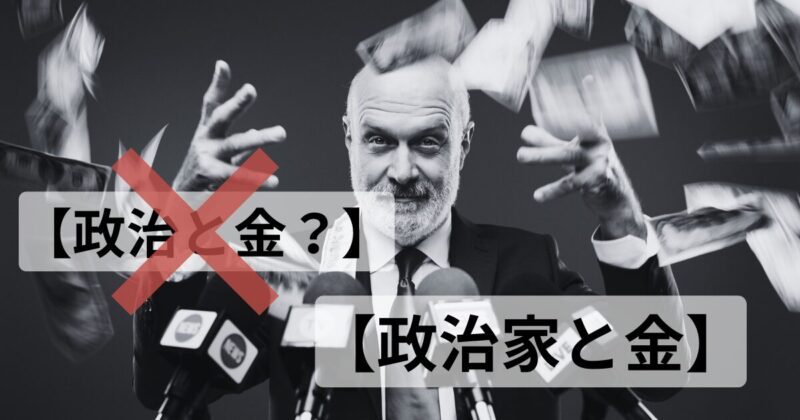
これにはどうにも違和感を禁じ得ない。正しく論じるなら「政治家と金の問題」とするべきではないのか?金を扱うのは政治家であり、「政治」という人は存在しないし、「政治」は金を動かすことはできない。それを、政治と金としてしまうことで、政治には金がかかる…という、論調が出てきて、政治に金が必要なのだから、政治を担っている政治家は金が必要で、それを確保しなければならない。だから、裏金で….ということに聞こえるのだ。
決して、裏金を肯定しているように見えるということではなく、政治という主体のないものを問題視することで、責任の所在が曖昧になっているのではないか。社長ではなく、会社が、上が…と、言ってる中間管理職の自己保身のようなカタチに見えるのである。
これによって、本質的な問題(ここではあえて言及はしないが)は改善されず、置き去りにされ、うやむやなままになってしまう。企業組織においても、その言葉が何を指し示すのか?責任の所在が明確になる主体・主語を指していなければ、組織員はその解釈が本質と大きな乖離を生み出し、統制がとれない脆弱な組織となってしまうだろう。
それだけ言葉というものが持つ力は偉大であり、重要なことだと改めて思う。
最後まで、お付き合いくださってありがとうございます。
また、お会いしましょ。