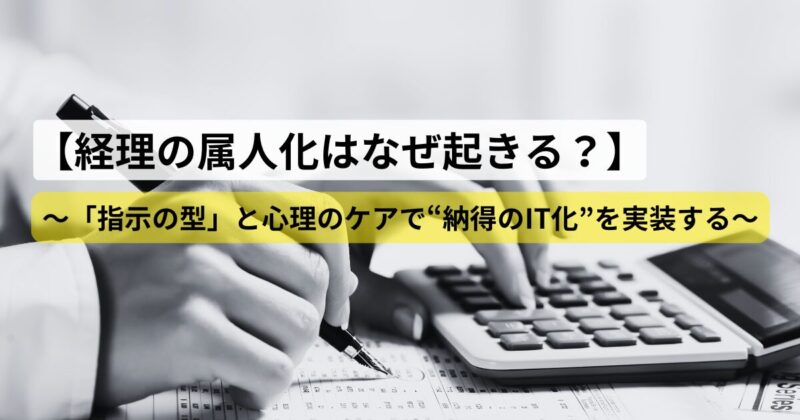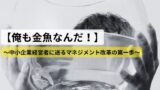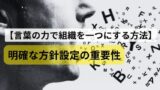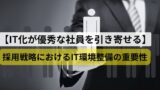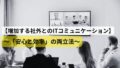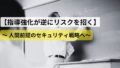中小企業の経理業務がなかなかIT化されない──その背景には、単なるツール導入の問題ではなく、「属人化」と呼ばれる構造的な課題がある。引き継ぎができない、休めない、他の人が触れない。業務が“個人の頭の中”に閉じ込められている状態だ。なぜこうした属人化が生まれるのか?そして、それを解消しようとする時に、なぜ“反発”や“混乱”が起きるのか?本稿では、指示の出し方を起点としながら、組織の内側にある心理的な壁を紐解いていく。単なる効率化ではなく、「人が安心して働き続けられる環境づくり」としてのIT化を、現場に定着させるための実践的な視点を提示する。
属人化業務をIT化するとき、なぜ「指示の出し方」で成果が変わるのか?
「なぜ今までのやり方ではダメなのか?」を伝えることが第一歩
業務のIT化というと、どうしても「効率化」「ミス削減」「作業時間の短縮」といった言葉が先に出てくる。しかし、それを現場にそのまま伝えると、「今までのやり方は非効率だった」と言われているように感じてしまう人は少なくない。特に経理のように、ミスが許されず、細かい積み上げが求められる業務では、「自分なりのやり方」を確立し、それが誇りになっているケースが多い。
「私のやり方に問題があるの?」と感じる心理への理解
経理担当者が長年担ってきた業務には、目に見えない工夫やリスク回避の知見が詰まっている。外から見れば非効率に見えても、本人にとっては「安心して業務を回せる型」なのだ。そこに新しい仕組みを持ち込めば、「それって、今までの私は間違っていたということですか?」という疑念が生まれるのも当然である。つまり、変化に対する抵抗の背景には、「自分が否定される」という感情がある。

変革は「否定」ではなく「進化」であることを丁寧に言葉にする
この誤解を避けるには、「過去のやり方を変える」ことが否定ではなく、“より良い未来への進化”だと伝える必要がある。「ここまで会社を支えてくれたやり方があったから今がある。その上で、これからの10年を見据えて、新しい形にしていこう」といった言葉には、過去を肯定したうえで変化を受け入れる余地がある。ポイントは、「何かを変える」という表現ではなく、「これまでの積み上げを“誰でも使える形”にする」という姿勢で向き合うことだ。

目的は「効率化」ではなく「会社の安心・未来の安定」
仮に作業時間が短縮されたとしても、現場が不安定になったり、誰かが「置いていかれた」と感じるなら、それは“安心”を犠牲にした効率化でしかない。経理の属人化を解消する目的は、単に早く終わらせることではなく、誰がやっても止まらない仕組みをつくること。それによって、担当者が休めるようになり、組織全体が持続可能になる。そこに目を向けてこそ、IT化は「人の安心のための投資」になる。
誰でも実践できる!IT化を進める時の「指示の型」
指示の曖昧さが混乱を生み、属人化を助長する
ITツールの導入がうまくいかない理由の多くは、「使い方がわからない」ではなく、「何をどう進めればいいのかが共有されていない」ことにある。つまり、原因は“ITそのもの”ではなく、“それをどう伝えるか”にあるのだ。
指示は「約束」に近い形に落とし込む
たとえば、「今日中に処理しておいて」と言われた場合、受け手によって“今日中”の定義が違う可能性がある。「18時までに、処理したものをメールで送って」と具体化すれば、そこで初めて指示は“共有された認識”になる。抽象的な言葉は避け、「何を」「いつまでに」「どうやって」やればよいのかを明確に伝えることが不可欠だ。
【経費精算の指示例】
→「7月分の経費申請は、9月18日(月)18時までに申請フォームへ入力。金額ミスは訂正せず、コメント欄に理由を記入すること。確認は私が19日9時に行う。」
5W2H+指示7点セットが指示の“完成形”
属人化を防ぐためには、個人の勘や習慣に頼らない設計が必要だ。そこで有効なのが、5W2H(What/When/Who/Where/Why/How/How much)に加え、以下の指示7点セットである。
【目的/期待成果/期限/優先度/判断基準/相談ポイント/報告方法】

この7点を明示することで、「言われた通りにやったつもりだけど…」というすれ違いを未然に防げる。
【請求処理の具体例】
→「今月の請求書は、目的:月末締めの売上確定。成果物:A社・B社分のPDF請求書。期限:9月20日(水)18時まで。優先度:A社先。判断基準:先月と同じ品目。相談:不明点はSlackで。報告:完了後に#経理チャットへ送信。」
指示者の責任を前提とする
属人化の構造は、「任せてるのにうまくいかない」という文句からも見えてくる。だが、そもそも指示が不十分であれば、成果責任を現場に押しつけるのは筋違いだ。部下の仕事は“上司の代わりにやること”であり、結果の責任は指示者にあるという視点を持たなければ、信頼も納得も生まれない。
【クラウド会計初期設定の指示例】
→「初期設定は、私と一緒に進める形でOK。期限は今週金曜。わからないところはZoomで共有しながら一緒に確認。完成度は70%でもいいので、金曜16時時点での画面を見せてほしい。」
なぜ心理的配慮が欠けると反発が起きるのか?
変化への反発の根っこには「自己否定された」と感じる心理がある
経理の仕事は「見えない苦労」が多い。だからこそ、長年担ってきた人にとっては、そのやり方が「自分のアイデンティティ」に近いものになっていることがある。
「自分しかできない」という感覚が支えになっている
属人化は問題だが、逆に言えばそれだけ「責任感を持って守ってきた」人がいるということでもある。その仕事が仕組み化され、誰でもできるようになった時、「じゃあ、私は必要ないのでは?」という不安が頭をよぎる。ここに寄り添わずに変化だけを押しつければ、形式的には進んでも、心は置いてけぼりになる。
変化は「仕組みを強くすること」であり「人を弱くすること」ではない
IT化によって、「人がいなくても回る」体制ができる。それは、人が不要になるのではなく、「人が安心して続けられる」体制でもある。「万が一休んでも大丈夫」「誰でも助け合えるようにしておく」…この考え方に立てば、変化は脅威ではなく、安心への布石となる。
小さな“任せる”から始めると心理的ハードルは下がる
いきなり丸投げせず、一部の設定や操作を任せて「自分でもできた」という感覚を得てもらうと、抵抗感は大きく和らぐ。ポイントは「完全にやらせる」のではなく、「一緒にやるけど主導してもらう」設計にすることだ。
絶対に避けるべきNG指示とは?
曖昧な言葉は、指示ではなく“混乱の種”である
「とにかくやってみて」「前と同じように」「できなかったら困る」…これらの言葉は、表面的には“指示”のように見える。しかし実際には、そのどれもが曖昧であり、責任の所在も期待される行動も不明確だ。結果として、現場は動けなくなり、属人化が温存される。ここで必要なのは、技術的な言い換えではなく、“言葉が人に与える影響”を理解することである。
「とにかくやってみて」が投げかけるのは、“責任はそっち”という無意識のサイン
この一言の裏には、「まずは自分で考えて」「結果はあなたの責任で」という無言のプレッシャーが含まれている。受け手が経験豊富であれば、「お任せされた」と前向きに捉えることもあるかもしれないが、IT化のように新しいことに挑む場面では、判断基準がなくて動けないのが普通だ。
「とにかく」という言葉の不安定さは、指示ではなく“丸投げ”として受け取られやすい。これは単に業務を進めないだけでなく、「相談しづらさ」や「失敗したら責められるのでは」という恐れを生み、組織の“無言化”を招いてしまう。
「前と同じようにやって」が伝えるのは、“変化を受け入れたくない”という管理者の本音
この言葉は、言っている側にとっては安心かもしれない。いつも通り、いつものやり方、ミスも少ないだろう。しかし、これがIT化を進めようとしているプロジェクトの場で出てきたとしたら、それは「変える理由を理解していない」か「変化に不安を感じている」側のサインである。
また、受け取る側にとっては、「今までのやり方が正解だったんだから、新しい提案は要らない」という圧にもなる。つまりこの言葉には、改善の芽を摘む“無意識のブレーキ”としての側面がある。たとえ相手が「新しいやり方を試してみたい」と思っていても、これではそのモチベーションごと封じてしまう。
「できなかったら困る」が伝えるのは、“失敗は許されない”という心理的な壁
プレッシャーをかけるつもりがなくても、「これ、失敗したらまずいよね」という雰囲気が出ると、人は慎重になりすぎて動けなくなる。人は「完璧にできる自信がないこと」には手を出せないのだ。
この言葉の背後には、「重要だから失敗したくない」という気持ちがある。しかし、それをそのまま伝えると、「やるなら完璧に」というプレッシャーになってしまう。
結果として、「できる範囲でやってみよう」という発想は消え、「失敗するくらいなら手を出さない方がいい」という消極性が生まれる。
指示は「言葉」であり、「関係性」である
こうした曖昧な言葉がなぜ属人化を助長するのか? それは、指示というのは単なる業務伝達ではなく、“上司と部下の関係性の中で交わされるメッセージ”だからだ。
上司が自信なさげに曖昧な言葉を使えば、部下は「判断は自分でしろ。でもミスは許されない」と受け取り、結果としてリスクを避ける動きになる。これは、属人化を“温存”する心理的なメカニズムである。
一方で、明確な言葉で、背景や判断基準を共有しながら伝えることができれば、「それならやってみよう」となる。大切なのは、“指示の中に込められた意図や信頼”が、相手にどう伝わるかを考えることだ。
「言葉」は、意図ではなく“解釈”で意味を持つ
どれだけ良い意図があっても、それが相手に“どう受け取られるか”によって、意味が変わってしまう。だからこそ、「伝えたつもり」ではなく、「伝わったかどうか」を確認し続ける姿勢が求められる。
この視点を持つことで、指示は“業務命令”から、“信頼を育てる行為”へと変わっていく。属人化を解消したいなら、まずは言葉の解像度を高めることから始めるべきである。
なぜIT化は“定着しない”ことが多いのか?
解消したはずの属人化が、別の形で再発する
新しいツールを導入し、手順も文書化したはずなのに…いつの間にか「使えるのはあの人だけ」「設定は〇〇さんが詳しい」となっている。これが、“新しい属人化”だ。ツールを導入するだけでは仕組みにはならない。継続的な運用が必要になる。
文章化・マニュアル化を「仕組み」にしないと、またブラックボックス化する
例えば、クラウド会計の初期設定を行ったとして、その設定方法や操作手順が記録に残っていなければ、担当者が離れた瞬間に“わからない”が再発する。最低でも以下の3文書は必要だ。
- 初期設定マニュアル
- 入力ルール一覧
- 問題が発生したときの問い合わせ先まとめ
この“3文書セット”があって、ようやく属人化の連鎖を止めることができる。
定着には「日常の繰り返し」が必要
いくら立派な仕組みを作っても、現場の会話に出てこないなら、それは“使われていない”ことと同じである。会議や朝礼の中で、システムの利用状況や改善点を1分でも共有するだけで、「活用している」という空気が生まれる。
定着させるための工夫 ― なぜ「組織文化」に落とし込むことが重要か?
一時的な“プロジェクト”ではなく、“日常の文化”にする
IT化はプロジェクトではない。人が入れ替わっても回る状態を目指すには、それが“習慣”として根づく必要がある。そのためには、最初から“属人化しない工夫”を設計に入れることが不可欠だ。
「誰でもできる」を合言葉にする
再現性のない仕組みは、ただの個人技術に過ぎない。クラウド経費精算の導入時も、「この設定は〇〇さんにしかできない」では意味がない。手順やルールを全員が把握し、「自分でもできそうだ」と思える水準にしておくことが肝となる。
失敗しても責めない文化がIT定着を支える
属人化が起きる背景には、「ミスしたら責められる」という恐れがある。失敗を“学びの一部”と捉えることで、チャレンジしやすい空気が生まれる。IT化の本質は、“人を守るための仕組み”だという共通認識が必要である。
外部のIT顧問や第三者の併走で“中立の視点”を入れる
IT化の定着には、現場と経営の間に立つ「中立の調整役」が重要な存在になる。外部のIT顧問であれば、専門的なサポートだけでなく、「第三者だからこそ言えること」で組織全体の納得を引き出せる。
まとめ ― IT化は「人を大事にする仕組みづくり」である
経理業務の属人化は、単なる“やり方の問題”ではない。そこには、「守ってきた自負」や「見えない努力」「変化への不安」が詰まっている。その構造を無視してツールだけ導入しても、うまくはいかない。
IT化は、作業を奪うためのものではない。人が安心して働き続けられる状態を作るための“仕組み化”である。
指示の出し方を工夫することで、現場の迷いや反発を減らせる。心理的な壁を理解することで、協力は得られる。定着の工夫を重ねることで、組織は確実に変わっていく。
「仕組みで人を支える」…これが、経営としての“IT化の本質”である。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。