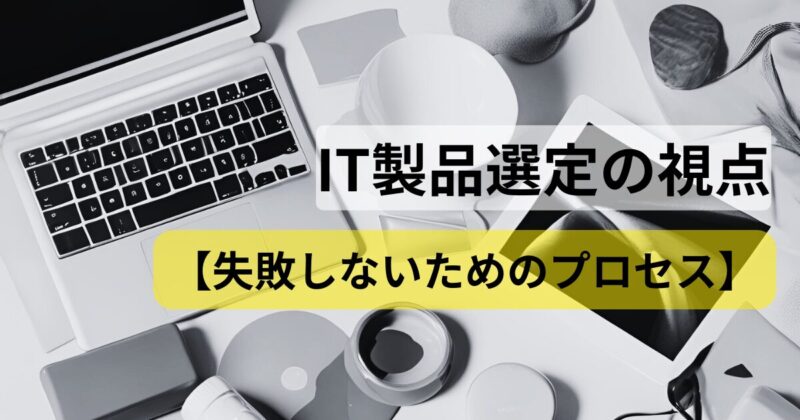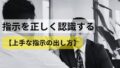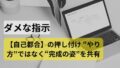どれがいいかなぁ…?似たり寄ったりだし…中小企業でIT製品の導入を決定するのは悩ましい問題であろう。ITに精通する人材がいない、あまり多くのコストをかけられないなど、選択肢が限定される。その中で自社の環境と運用に合致するものを選定しなければならない。失敗しないためには、どのような視点・プロセスが必要となるのか、以下の3項目でわかりやすく解説します。
・ IT製品選定に必要な3ステップ
・ ITベンダーが言わないこと3つ
・ 失敗しないための極意
IT製品選定に必要な3ステップ
製品の導入を決めるのに、多くの時間と人を割くことはできない。これは中業企業ならどこでもそうであろう。だが、失敗しないために直接的な持ち出しとはならないので、多少の時間をかけて効率よく製品選定を進めていただきたい。
Step1:現状の整理と把握
あまり多くの時間をかけられないのであれば、いきなり導入しようとしている製品の機能などでググってみるのも悪くはないがあまりオススメはできない。やはり、時間がなくても少なくても整理しておくべきことはある。
少なくともこの2つは現状把握として整理しておきたい。
なんのために導入するのか…「何かの代わり(代替品)」「業務効率向上(手作業からの脱却・二度手間排除)」、人員の有効活用、コスト削減…等々…ここを明確にしておく。
そして、導入することで具体的にどういう効果を狙っているのかも明確にする。人、個、回、時間、%..等々の単位で減らす、増やすなど。俗に言う投資対効果を算定する。
現状把握については、詳しく論じた自著:「IT顧問のススメ」に記載があるので是非、それを一読いただきたい。
Step2:必須機能を抽出する
現状の把握と整理ができたら、こういう機能が必要だよね…というのは、ある程度は出てくるであろう。この段階で導入製品のカテゴリーでググって、実装されている機能がどのようなもので、それが自社に必要かどうかは判断できるはずである。この段階で、検討対象となる製品が絞られることになり、最終的には価格を見て導入できそうな製品を3つに絞ってみると良いだろう。
あまり多いと時間というコストがかかってしまう。2つだと、どっちがいいかなぁ…と、視野が狭くなる可能性があるので3つが適切である。取り引きのあるITベンダーにも声かけをして、製品を提案してもらうと良い。絞った3つの製品と重複するなら、その提案を受ければ良いし、別の製品であったとしても4つ目として検討しても良いだろう。
Step3:デモを見るか、使って見る
Webサイトや紙面だけでは使用しているイメージができないので、実機で画面など操作感を確認することは必須だ。動画の説明とデモでは知ることの量も質も違う。動画には質問ができない。デモの場合は、良いところを中心に説明されることが多く、導入後に勘違いや誤解に気付くということもあるので、試用版などで実際に使ってみることを強くオススメする。必須といいたいところでもある。理由については後述する。
ITベンダーがあまり教えてくれないこと“3つ”
ITベンダーの営業マンやエンジニアは丁寧な説明をしてくれるのだが、言いたいことを中心としているため、聞きたいことを言ってくれないことが多い。マイナスに受け取られそうなことをあえて言わない(言わないことは嘘をついたわけでも、隠し立てしているということでもない…)のだと思われるが、説明がなければ以下については確認しておくべきだ。
❶ 必要となる作業(運用・メンテナンス)
どんな機能があって、どういう操作をするかということに説明時間の多くが費やされるので理解できるが、その前後もしっかりと確認しておきたい。前後とは、インストール(設置・設定)と、メンテナンスである。使えるようになるまでに、どのような工程があり、それは自社内で完結できるレベルなのか?
導入後も、そのままただ使い続けているだけで良いのか?バージョンアップ(パッチの適用含む)は手動か自動か(クラウドサービスの場合)、どのくらいの時間がかかるのか…等々…不具合があった場合の具体的な対応プロセスは?販売管理システムなど、請求書の発行が2〜3日できないとなれば業務への影響は甚大である。トラブルがあった場合は一刻でも早い復旧が望まれるが、実際にどのような対応でサポートしてくれるのかは確認しておきたい。
❷ 使用するために必要なITスキル
機能説明によって、できることはわかったとしても、それを使いこなせるかどうかの判断が難しい場合がある。デモを見ても説明している人は簡単に操作しているが、それは果たして誰でもできるものなのだろうか?販売管理システムのようなものだと、ITに関する知識は不要だろうが、セキュリティ対策ツールの場合は、設定と表示の因果関係を理解して画面表示を理解する必要があるし、必要な設定が施されているかも認識していなければ適切な運用ができない。
このくらいのITスキルを持っていないと使いこなせませんよ。と、明確に教えてもらうべきだ。簡単・誰でも使える。などの表記はよく見るが、誰を想定しているのかまでは説明がない。そこは確認しておく必要がある。
中小企業に必要なITスキルについては以下の参考時期を参照ください。
❸ 失敗事例
導入事例は成功事例としてWebサイトに掲載されたり、資料で紹介されているのでアピールとして説明されることになるが、こういう理由で結果として失敗したお客様がいました。との説明をされることはほとんどない。失敗を説明することで不安を与えるというマイナス面があるので、積極的に言う必要はないが、リスク回避のために、こういう状況や事情があると失敗するかもしれないというのは事前に確認しておきたい。成功事例を真似るよりも失敗事例から学んでそうならないようにする方が、取り組みとしては易しい場合が多いからだ。
失敗しないための極意
3つ目の視点として、失敗しないためにやっておくべきことを解説する。
比較表って必要ですか?
だいたいの企業が2つから3つの製品を検討する時、比較表を作っている。上長への説明資料としても、選定の根拠を示すにも便利なものだ。だが、作成にはそれなりの時間がかかるだろう。本当に必須なのか?私見ではあるが、必須と言わないまでも、あった方がいいのは確かだ。複数人が査閲し決裁するなら必須と言えるかもしれない。
ただ、ここで大事なのは何を比較するかだ。機能や価格などは当然、比較項目として列挙されることになるだろうが、バージョンアップの回数(リリースしてから)、サポート体制、導入後に必要なメンテナンス…等々…製品の将来性や導入後についても、しっかりと比較検討をしないと、導入コストは抑えられたが、運用コストが高くついて…という話は決して少なくないのだ。
実際に使ってみるのがBEST!
時間をかけて慎重に検討を重ねることは良いことだが、最終的には使ってみないとわからないことは意外に多い。ですから、是非とも実際に試用をするということをやってください。
ソフトウェアのよくある機能で、CSVで抽出できる。CSVをアップロードとして取り込める。というものがあった場合、デモでその操作を見てできることを確認した。ところが、実際に導入してみるとCSVデータは1日単位でしか操作できないことが発覚して、一ヶ月分のデータを扱う時にはCSV抽出操作を30回やらないとダメ…など、管理・運用面で手間がかかるということはあります。
インプットや設定はまとめてできるけど、削除する時は1つ1つやらないとダメとか…印刷してみると、思ってたのとは違ったなど…(デモで印刷をすることは滅多にない)。機能の確認はデモでもできるが、実運用上の検証は使ってみることが確実で早くて安心できる手法です。
導入までに多少、時間をとられることになりますが確実と安心を買ったと思えばコストメリットは大きい。試用版とか無料期間等が無い場合は、期間限定で有料として利用できるならお願いしてもいいだろうし、そういうサポートが一切ない場合は、納得いくまでQ&Aに対応してもらうということですね。
第三者の意見(アドバイス)を聞く
IT業界およびITスキルを持った第三者にアドバイスを求めることも重要です。第三者とは、ITベンダーのように製品やサービスを販売しない立場の人です。IT業界に精通している方であれば、導入を検討している製品のベンダーの表には出てこない裏事情なども把握しているかもしれません。セカンドオピニオン的な考えでアドバイスを取り入れることで安心を得ることもできます。
まとめ
最後に視点とプロセスをシンプルに整理すると以下の通りです。
✔️ 導入目的と動機を明確にする
✔️ 期待する効果を定量化
✔️ 必要機能のピックアップ
✔️ デモを見る/実際に使って見る
✔️ 3つの確認事項
✔️ 第三者の意見(アドバイス)を聞く
この手順が面倒…って思われるなら、これだけはやっていただきたいと思うのは文中でも申し上げたとおりですが、実際に使ってみてから判断してください。ってことに尽きます。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。