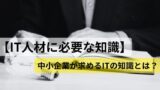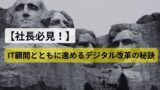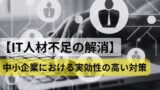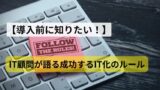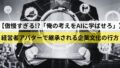「IT人材不足」が叫ばれて久しいが、中小企業において“IT人材”は本当に必要なのか? 答えはNOだ。ITに詳しい社員を雇うことにこだわる必要はない。むしろ、社内に専門人材を抱え込むことこそが非効率であり、無駄なコストを生む原因になりかねない。
現代のIT環境は複雑化・専門化しており、社内で対応できる範囲を超えている。中小企業が取るべきIT戦略とは、自社の業務を理解した“外部の専門家”を利活用し、最小限のコストで最大の効果を得ることである。IT顧問やアドバイザーのような“社長の右腕”を持つことが、実は最も現実的かつ効果的なIT利活用のカタチなのだ。今こそ「IT人材を持たないこと」が中小企業の戦略的選択になり得るという視点で見直してみる。
IT人材は不要である──それは“現実解”である
「中小企業はIT人材がいないから不利」という声は、IT業界の中(今風の言葉だと…IT界隈か…)で半ば常識のように語られている。だが、この前提は果たして正しいのか? 経営資源が限られる中小企業においては、すべてを内製化しようとすること自体が無理筋であり、戦略として非合理と考えることが現実的である。
IT人材=万能な存在という幻想
IT人材という言葉は耳馴染みが良いが、その実態はあまりに漠然としている。ネットワーク、サーバ、アプリ開発、セキュリティ、クラウド……このどれかに特化した人材はいても、すべてを担える存在などほとんどいない。
中小企業が自社で“なんでも屋”のようなIT人材を育てようとするのは現実離れしているし、そもそもそんな人材が市場に出回ることはほとんどない。
大手企業の情報部門も“外注依存”が基本
IT部署のある大手企業であっても、実作業の多くはITベンダーに外注している。社内にいるのは、ベンダーとの連携・調整を担う“橋渡し”の役割が主であり、技術的に手を動かすわけではない。

。自治体も同様で、業務の大部分は常駐ベンダーが担っている。つまり、“IT人材が社内にいる”というよりも“専門家を活用している”というのが実態である。
中小企業にとっての“人材不在”はむしろ強みになる
専任のIT人材を抱えていないからこそ、外部の専門家の知見を柔軟に取り入れる体制が整う。固定コストがかからず、必要なときに必要なだけのリソースを調達できる。
これは今の変化の激しいIT環境において、極めて合理的な戦略である。社内に人材を抱えることがリスクになることも、十分に考慮すべきである。
システム導入“後”の落とし穴──人がいないと回らない
IT導入はゴールではない。むしろ本質的な課題は導入“後”に始まる。アップデート、メンテナンス、活用、情報整理──すべては継続的な運用があってこそ初めて成果につながる。
メールからチャットへ──情報共有の変化に追いつけない
かつて業務連絡はメールが中心だったが、現在はチャットツールによる即時性と情報の整理性が重視されている。にもかかわらず、多くの中小企業はメールに固執し、情報の見落としや重複ファイルの管理に苦慮している。これは単なるツールの問題ではなく、情報設計そのものを見直す必要がある証拠だ。

導入ベンダーに依存しすぎると“売りたい製品”を押し付けられる
ITベンダーは自社製品を売る(自社にとって有利な製品)ことが目的である。顧客の業務適性を第一に考えて提案してくれるとは限らない。だからこそ、中小企業には“自社の業務を理解し、提案を評価・選別できる存在”が必要だ。経営者が直接判断するのではなく、ITアドバイザーのような存在に委ねることで、選定の精度が格段に上がる。
メンテナンス、バージョン管理、トラブル対応……人がいないと止まる
システムは生き物のように、常に変化し続けるものだ。アップデートや設定変更に追随できなければ、せっかくのIT投資も宝の持ち腐れになる。中小企業がこれを内製化で回そうとすれば、IT人材の確保だけでなく継続的な育成・維持が求められる。それが不可能である以上、外部の専門家の“継続関与”が鍵になる。

IT人材ではなく、IT顧問を持つという選択肢
「自社にはIT人材がいないから…」と嘆くより、「外部に頼れる人がいるから安心だ」と言える環境を整える方が建設的だ。これは“代替”ではなく、むしろ“最適解”なのである。
採用での人材確保は、現実的ではない
ITを専門とする人材は、成長機会の多いITベンダーを選ぶ。新技術に触れる機会もなく、裁量も与えられない中小企業に転職してくることはほぼない。仮に来たとしても、高い給与と環境整備を求められ、コスト的に見合わない場合が多い。
IT顧問は“社長の右腕”であり、外部ブレーンである
IT顧問は単なる技術者ではない。自社の業務と経営を理解した上で、最適な技術導入・ベンダーとの交渉・見積の妥当性検証など、経営的視点から助言をしてくれる存在である。つまり“社長の右腕”として機能する、戦略的なパートナーだ。
外部とつながることで、知見・判断力が拡張される
現代のIT運用は、“人を囲う”のではなく“専門性にアクセスする”時代だ。SOCサービスやITアドバイザー、クラウド専門業者など、必要な領域をピンポイントで委託するのがコスト効率の面でも最も優れている。中小企業にとって、これが効率的かつ最適化されたIT利活用である。
まとめ:中小企業こそ、“人を雇わず知恵を借りる”時代
中小企業の経営にとって、ITは重要だ。しかし、重要だからといって“自前で人材を育てる”必要はない。むしろそれは現代のIT構造においては非合理であり、高コストで成果が見込めない危険な選択である。
自社に最適な助言者──すなわちIT顧問を戦略的に配置することが、これからの中小企業における最も現実的なIT利活用のかたちとなる。「IT人材不足」に悩む必要はない。「知見ある専門家を味方につける」こと。それが、経営における最も賢明な判断となる。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。