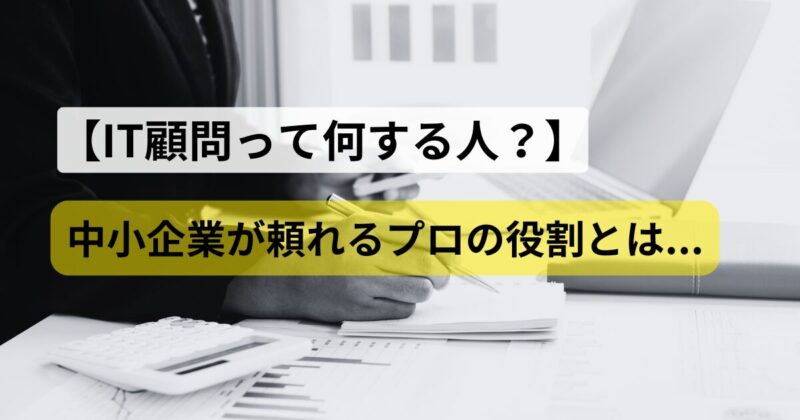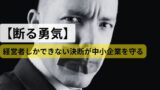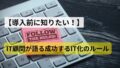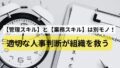中小企業が成長を目指す上で、ITの活用は避けて通れない時代になっている。業務効率化、顧客管理、売上拡大といった課題を解決するためにITを導入する企業は増加しているが、その一方で適切な活用法が分からず、失敗に終わるケースも多い。IT製品やサービスを導入しても、運用が停滞し、結果として無駄な投資になってしまうことも珍しくない。
そんなときに頼りになるのが「IT顧問」の存在である。IT顧問は中小企業の現状を深く理解し、的確なアドバイスや実務支援を行う専門家だ。本稿では、IT顧問が果たす具体的な役割と、その活用が中小企業にどのような利益をもたらすのか…実体験より詳しく解説する。
IT顧問の役割と重要性
IT顧問は、経営者の視点からITの導入や運用を最適化し、企業が直面する問題を解決する専門家である。その役割は広範囲に及び、IT戦略の立案からサポート体制の構築までを手掛ける。単なる「ITのアドバイザー」ではなく、経営と技術の橋渡し役を担う存在となる。情報部門要員の業務を一部、引き受けることも状況によってはあるが、実際に手を動かすことがIT顧問の役割ではなく、専門家の見地から経営者(社長)のために適切な判断ができるよう、IT用語や専門用語を理解しやすく翻訳することが主な役割となる。
IT戦略の立案と実行支援
IT顧問の最も基本的な役割は、企業が求める成果を達成するためのIT戦略を立案することである。ただITを導入すれば業務が効率化されるわけではない。知人が導入した…最近はAIが注目されている…CMでよく見るな…など、噂や感覚で必要性や導入を検討するのではなく、なぜ必要なのかを吟味し、具体的な目標を設定し、その達成に向けた戦略が必要となる。たとえば、新たな顧客管理システムの導入によって売上を10%向上させることを目標とする場合、IT顧問は以下のようなプロセスを提供する。
特に中小企業では、ITの専門知識を持つスタッフが少ないため、こうしたプロセスを自社で行うのは難しい。IT顧問のサポートがあれば、無駄な投資を避けつつ、目標達成に向けた確実な一歩を踏み出せる。中でも重要なのが【現状分析】のフェーズだ。ほとんどの企業はツールの選定に多くの時間を割いているのだが「どうして必要なのか?」「それを導入してどのような問題・課題を解決したいのか?」「導入後は誰が、どのように運用するのか?」を、確かめると曖昧な答えが返ってくることが多い。(明確な答えを聞くことはほとんど無い。)
IT顧問はIT製品導入を勧めない
導入が前提で検討する…スタート地点を誤っているのだ。現状分析をして、どの部分をIT化することが目的に適っているのかを論理的に検証すると、実はIT製品を導入しないという選択肢もあり得る。筆者の経験から、ツール選定時の相談事の約半数は「導入は一旦、保留にして***について再構築をしてからの方が良いです。その方がより適切なIT化になり、自然と答えが導かれますよ。」と、助言になることが多いのだ。IT顧問は適切なIT製品の選定よりも、IT製品導入を再考させるという役割も担う。それが、無駄な投資を回避することに直結する。
ベンダーとの交渉や製品選定のサポート
IT製品やサービスを導入する際、多くの中小企業はベンダーの提案に依存しがちである。しかし、ベンダーの目線は自社製品の販売に重きを置いており、必ずしも中小企業の利益を最優先に考えているとは限らない。ここでIT顧問の中立的な立場が重要になる。
たとえば、ベンダーから「最新のセキュリティ対策ツール」を提案された際、IT顧問はその必要性を検討し、他の選択肢と比較することで、最適なソリューションを見極める役割を果たす。これにより、不必要な機能が多い高価な製品を購入するリスクを回避できる。提案を受けるベンダーが違うと、機能が重複しているものを導入してしまうこともある。筆者はこのケースをよく目にする。機能(仕組み)は違えど、目的(どういう効果を狙ったものか)は同じというセキュリティ製品を2つ、3つ導入しているということは決して少なくない。無意味とは言わないが、セキュリティ対策が強化されているかどうかについては疑問を禁じえない。
さらに、IT顧問はベンダーとの価格交渉やサービス内容の調整も代行することもある。中小企業が自ら交渉を行う場合、ITの専門用語に戸惑い、理解しているつもりが、結果的に不利な契約条件を受け入れてしまうケースがあるが、IT顧問が関与すれば、こうしたリスクも大幅に軽減される。
サイバーセキュリティ対策の強化
中小企業もサプライチェーンの中では、サイバー攻撃の標的にされるケースが一般化しており、セキュリティ対策は重要な課題となっている。しかし、限られた予算やリソースの中で、どこまでの対策を講じるべきかを判断するのは難しい。IT顧問は、企業の現状に応じた適切なセキュリティ対策を提案する。
中小企業もサプライチェーンの中では、サイバー攻撃の標的にされるケースが一般化しており、セキュリティ対策は重要な課題となっている。しかし、限られた予算やリソースの中で、どこまでの対策を講じるべきかを判断するのは難しい。IT顧問は、企業の現状に応じた適切なセキュリティ対策を提案する。
また、セキュリティインシデント発生時にどのような対応(対処と根本対策)をとるべきか迅速に判断し、被害を最小限に抑えるための助言をする。これにより、企業はセキュリティ対策に過剰なリソースを割くことなく、不安や戸惑いを回避できるので安心して事業を運営できる。
IT顧問を活用するメリット
IT顧問を活用することで、中小企業は多くのメリットを享受できる。その中でも特に重要なのが以下の3点であると筆者は考える。
コストの最適化とROIの向上
IT顧問は、中小企業が不要(無駄)な投資を行うリスクを排除し、導入したIT製品やサービスのROI(投資利益率)を最大化するための具体的な提案を行う。たとえば、クラウドサービスの選定では、従来のオンプレミス環境と比較して、どれだけのコスト削減が可能かを試算し、最適な選択を導く。また、既存のIT資産を有効活用するための運用改善も支援する。
IT製品の導入コストや維持コストという目に見えるコスト以外にも、「運用コスト」という観点からもコスト効率を試算することもある。「入れっぱなし」で放置されてしまうような製品は導入・維持コストが自体が無駄となってしまう。本来の目的のために稼働させることが絶対に必要となる場合、自社のリソースで運用することが不可であれば、外部リソースに運用を委託することで導入効果を発揮するという視点も必要となる。この場合、運用コストを考慮した導入コスト試算(製品選定)が重要となる。コストが抑えられれば最適化されているとは言えないのだ。
継続的なサポートによる信頼関係の構築
IT顧問のもう一つの強みは、単発的な支援にとどまらず、長期的なパートナーとして経営者を支える点にある。ITは常に進化しており、導入時に適切だったシステムが数年後には時代遅れになる可能性もある。IT顧問はこうした変化に対応し、継続的な運用改善やアップデートをサポートすることで、企業のIT環境を最適な状態に保つためのアドバイザーであり、良き情報源となる。
中小企業にはIT部門が設置されていないことが多いが、IT顧問の支援があれば総務、管理部門の中にITの運用チームを構築することも現実的なものとなる。IT業務を分析・評価し自社内で完結させるべきことなど整理することで、必要最低限のIT知識とIT顧問のサポートでITの運用を賄う体制を構築することが可能となる。今いる人材でなんとか賄って行きたい…との経営者の心理も理解はできるのだが、IT業務を兼務しておりそれを単独でこなしている状況であれば、それはIT運用におけるリスクとなるとの認識を持っていただきたい。長期休暇や退職によって、その会社のIT運用は停滞することになるだろう…
トラブル対応力の向上
IT環境でのトラブルは、業務の停止や顧客信頼の喪失につながる重大なリスクとなる。IT顧問はトラブル発生時に迅速な対応を行い、問題を解決するだけでなく、再発防止策を講じることで、企業の安定した運営を支える。また、トラブル発生前にリスクを予見し、未然に防ぐアドバイスも提供する。IT製品を複数のベンダーから導入している場合、トラブルの原因が不明確だと「それはウチの責任ではなく、**社側の問題だと思います。」など、ベンダー間をたらい回しにされることもある。障害の切り分け方法についても、IT顧問のサポートがあるとどのベンダーの責任範囲なのかテクニカルな視点で根拠を説明し対応を促すことができる。
1社のベンダーに全てを任せると「たらい回し」という状態は回避できるのだが、その一方で「ベンダーロックイン」という別のリスクを抱えることになるので一長一短ではある。筆者は経験上、1社にお任せするということは、楽で安心できるという心情は理解するものの、選択肢が狭まってしまうのは大きなリスクになるという観点で推奨はしない。
まとめ
IT顧問は、中小企業が抱えるITに関する課題を解消し、事業の効率化と成長を支える重要な存在である。適切なIT戦略の立案、無駄のない投資計画、的確なサポート体制の構築を通じて、経営者は本業に専念できる環境を手に入れることができる。変化の激しいIT業界で成功するために、IT顧問という「頼れるパートナー」を活用することは、非常に賢明な選択である。
筆者は中小企業の経営者(社長)向けに【PIT-Sec.】というサービスを提供している。セキュリティ対策を支援するものだが、本稿記載のIT顧問的な要素も包含したサービスという側面もあるので、是非見ていただきたい。
最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。
また、お会いしましょ。