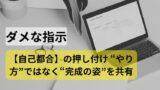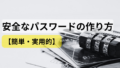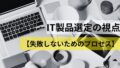指示が曖昧なせいか、部下が思った通り動いてくれない。どうやって伝えたらいいのだろうか?的確な指示を出すために必要な知識や勉強方法ってあるなら教えて欲しい。という悩みを抱えている管理職の皆さんに、中小企業で28歳でマネージャ職になり30歳で役員。(興味のある方はプロフィールをご覧ください)そして、多くの部下を抱えながら退職者続出の大失敗の連続…そこから培った指示することについての成功談の一部を記します。
本記事では、正しく指示を理解する3つの視点でまとめました。
・指示上手な人は部下とのスタンスに特徴あり
・未経験・若手社員でも的確な指示が出せる理由
・指示する時に大事な“言葉選び”のコツ
指示上手な人は部下とのスタンスに特徴あり
先に結論から言ってしまいますが、そもそも俺の方が立場が上で指示してんだから…とか、部下なら言うこと聞いてちゃんとやれよ…とか、そういう“上と下”という概念を捨てるところから始めてください。これは部下がやること。俺はやらせる人。って前提を壊せばいいんです。
人の関係性に上下などない
組織はピラミッド構造なのでどうしても上下という概念になって、上司・部下というように人間関係が上と下になってしまう。言い方を変えると上の人は“偉い人”ってことになる。自分より年長の方を敬うことは普通にあったとしても上から目線的な感じで、一方的に何か言われたり、理不尽なことを押し付けられるのは許容できないのが普通であろう。指示をする立場になったら、自分が上の立場とは思わない方がいい。その概念は捨てるべきだ。組織…チームと考えたらわかりやすくなるだろう。野球でもサッカーでもいい。4番バッターは偉くて8番は下の存在ってことになるのだろうか。
これは求められる機能や期待される成果が違うだけだ。サッカーもFWが偉くてGKは偉くないのか?上下という概念があるのか?そんなものはない。上司というのは組織(チーム)の中の一機能でしかない。ソフトウェアのファイルメニューにある「保存」とか「印刷」と同様、単なる機能にすぎないと認識するべきである。機能に上下も偉いもない。それぞれが求められている機能を果たすことで、ソフトウェアに価値をもたらす。組織もチームも同様の認識にすべきで、これを自然に振る舞える人が上司としての機能を発揮するのだ。部下とのスタンスにおいてこれが大事なポイントなのだ。
指示するとはどういうことか?
指示をしたら、受けた人が責任をもってその業務を全うする。これはこれで正論ではあるが、指示者としての適切な認識は責任は自分が引き受ける。とならなければいけない。本来は自分でやらなければならないことを、自分の代わりにやってくれるのが部下で、何をやって欲しいかを伝えることが指示であり、その結果は自分(上司)の責任である。これが正論なのだが、指示をしたら受けた側にその責任があるかのように振る舞う上司と呼ばれる人がいるが、これは全くの間違いだ。こういう人に適切な指示が出せるはずはない。
「報告しろ!」という指示はない
上司が指示を出したら部下には報告の義務がある。それはその通りだが、上司が望むタイミングと質で報告できる部下はそう多くはない。上手くいってなかったり、失敗してしまった、まだ報告できる段階じゃないなぁ…という状況では報告を躊躇してしまうのは人間の心理だ。「結果はいいから、とにかく報告はしてくれよ!」と、言ってもなかなかその通りに動いてはくれない。そうなると、「報告をしろ!」という指示?を出したくなるし、出している上司も存在する。
報告をしろ!と、言わざるを得ない状況になったとしたら、それは部下よりも指示の仕方が悪いと思った方がいい。改善できるのは自分自身の言動しかないのだから。どういう指示がいいのか?どうやって…等々…考えると難しくなり答えは出ない。だったら、報告を求めなければいい。自分から部下に「どうだ?」「どんな感じ?」「順調か?」「なんか問題とかないか?」など、声かけをしたらいいのである。なんで、上司の俺が…なんて思ったら、部下は動いてくれない。状況を認識できたらいいのだから、部下からの発信なのか、自分からなのかなんてどうでもいいと考える。これをやっていれば、そのうち部下の方から自然に報告をするようになってくる。私が経験した自分自身でも驚く「目から鱗」のマネジメント手法の一つである。“報告”というテーマではもっと発信したいことがあるのだが、それはまた別の記事でお伝えしようと思う。
未経験・若手社員でも的確な指示が出せる理由
管理職(マネージャ)として従事するには、それなりの経験が必要となるだろうとか、まだ2〜3年くらいじゃ部下を持つには早いんじゃないの。と、考える方は少なくない。だが、そんなことはない。それなりの経験とは何か?早いというなら適切な時期(年数)はいつなのか?定義として答えられる人も多くはないだろう。発想の転換をすれば経験があろうがなかろうが無理なことはないのだ。
指示をしようとか、立場とか考える必要はない
自分が上の立場になった…部下を持った…部下の育成をしないと…ちゃんと指示を出して…等々…この考え方をすると全てが未知であり、わからないことだらけなので大事なことが後回しになったり、判断を誤ったりする可能性が大きい。
例えば、営業マンで考えてみる。今までは100万/月が目標でこれを達成すれば自分の役割を果たしていると言えた。だが、自分を含め5人の営業部隊の管理職となれば500万/月が目標になる。自分だけで500万/月は不可能だ。5倍の努力なんて無理だし…だから、それを自分の代わりに4名がやってくれると考えたらいい。4名全てが100万/月である必要もなく、150万/月と50万/月という実績の営業マンが2名でも結果として達成したことにはなる。
それぞれの営業マンがどう動いたらいいか、どうして欲しいか(自分の代わりなので)を考えて、指示を出す。とするのではなく、こうしてみよう。これをやろう。このアクションが必要だ。と、思案したらそれを部下と以下のような会話をしてみるといい。

「これを*日までにやってみるってのはどうだろうか?」
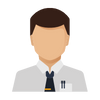
「そうですね。いいと思います。」

「じゃー、*日に確認させてもらっていいかな。何時ころがいい?」
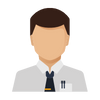
「その日は外出予定とかないので何時でもいいですよ。」

「じゃー、*時に確認するということで。」
これは指示としたというより、単に約束をしただけである。
そう!特に指示とか考える必要はない。約束をすればいいだけだ。約束の積み重ねが結果として指示になる。約束は子供のころから普通に経験しているだろうし、「約束ってなに?」「約束って守る必要があるか?」など、聞いてくる人はいないだろう。約束事が未経験なんて人はいないだろう。そうなんです!約束をするという観点で部下と接してみてください。指示という概念に縛られる必要はありません。
指示する時に大事な“言葉選び”のコツ
指示をする時はだいたい口頭ですることが多いだろうし、メールなど文書の場合もあるだろう。共通しているのは言語を使うということ。だが、この言語…言葉を使って人にモノやコトを伝えるのは、なかなか難しいものである。
人は思ったより人の話を理解しない
人は、経験したこと、育った環境などによって同じ言葉でも、その意味合いや、程度、解釈、ニュアンス、印象など人それぞれに理解をする。
例えば…「Aさんってマメな人ですよね。」という表現があった場合、この“マメ”というのはどういう人なのだろうか?複数の捉え方があるのではないか…
✔️ 几帳面で机上が綺麗に整頓されている人
✔️ 待ち合わせには遅れずに来る人
✔️ 必ず事前に確認をしてくる人
✔️ 些細なことでもメモをとる人
✔️ 約束したことを反故にせず守る人
…等々…どちらかと言うとプラスの評価になることが多いと思われるが、一方で
✔️ いろんな女性と遊んでいそう
と、捉える人もいるかもしれません。「あいつってモテるよな。」「だって、あいつはマメだから…」という会話を聞いたことがないだろうか。この場合のマメは、几帳面という捉え方もある一方で、貪欲とか自己満足の追求などマイナス面もあり、マメな男=女ったらし(女性にだらしがない)という、その人を揶揄する言葉と捉える人もいるかもしれないのだ。
これは、少し偏った例だったかもしれないが、会話の中でよくある表現で
「朝一で提出します」
「今日中にはやります」
これは、一体いつを指しているのか?朝一とは、起床時?9時?…始業時間を指していても会社によって違う場合もある。今日中…18時?約束の相手が退社するまで?日付が変わる12時まで?結果として翌日に確認すると想定して9時?自分の立場や環境によって、その言葉の認識・理解は異なる。伝えたつもりでも、結果として何も伝えてなかったことにもなりかねない。
相対的に捉えられる言葉ではなく、絶対的な表現を心がけるべきだ。
・朝一で → 「9時まで」
・今日中に → 「18時までに」
互いに共有(同じ認識)してなければ、指示も約束も意味がなくなってしまう。
抽象語は排除する
前述の内容の補足にはなるが、指示をする時は抽象的な表現は排除する。一般的な研修などでは「指示は具体的に」ということで指導をしているようだが、この具体的というのも人によって程度が違ったりする。何をもって具体的といえるのか?耳に新しいことではないが「5W2H」で、互いの認識を確認しあうのが良いだろう。
ただ、確認することの順番も注意した方がいい。
「明日までに、B社向けの提案書作ってくれよ。」
これは、曖昧な指示であろうことは認識できるであろう。明日まで…これは何時なのか?乱暴な指示の典型的なものである。
・いつまで(WHEN) :明日の18時
・作ってくれ(HOW・WHERE) :提出の方法→メールで送ってくれ
・成果物の確認(WHAT) :提案書のページ数
もう少し細分化できるかもしれないが、5W2Hに当てはめるとこのような感じになるだろう。
ここで、大事になるのは何から確認するかである。
指示内容を確認する順序が重要なポイントとなる
この場合
❶ → 成果物の確認(WHAT):提案書のページ数
❷ → 作ってくれ(HOW・WHERE):提出の方法→メールで送ってくれ
❸ → いつまで(WHEN):明日の18時
この順序が適切かと考える。期日が決まっている場合においては、3番のいつまで?が0番目に来ることになるのだろうが、まずは成果物がどういうものか、その質と量を確認することが大事だ。そこで部下がどの程度までできそうかを反応を見ながら確認をする
難しそうであれば、完成品として提出する前に確認という段階を作り、それがあることで日数が必要となれば3日後に期日を設定するなど、成果物の質と量によって、提出方法や確認の回数、必要な時間が変わってくるからだ。とにかくこの日までにやれよ!という指示をしてしまうと、内容によっては残業や休日に自宅でやらなければならない…など、”パワハラ”と、捉えられかねない乱暴な指示になってしまう。
こうならないために、指示する時には順序は成果を出すためには大事なことである。
5W2Hは複数の要素があるが、指示をするということを鑑みると以下の3つについてはとくに重要であり、丁寧に説明し認識を共有しておかなければならない。
✔️ What:何を?どのような成果物が求められているの説明し共有する
✔️Why:なぜこれをやるのか?なぜ必要なのか?それをやることの狙いは何か?説明し共有
✔️When:いつまでに完了させる必要があるのか。完成日、時間の確認
まとめ
指示者の立場から、難しく考えずに自らができる改善行動を経験値から解説してきました。
指示が的確かどうか?という視点は多岐に渡り、現実的に考えると考え方だけでは通用せず実践的な手法を理解しておかなければならないこともある。
【指示】については以下の記事も参考にしてください。
最後までお読みくださりありがとうございました。
また、お会いしましょ。