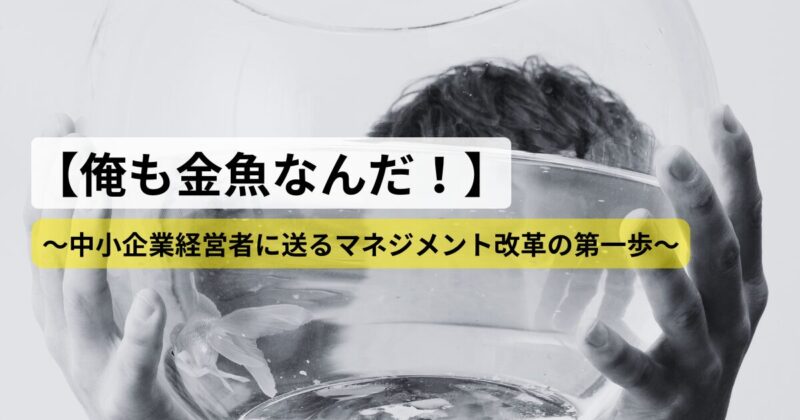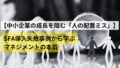中小企業の経営者や管理職にとって、「営業マンが定着しない」「人が育たない」という悩みはつきものだ。しかし、どれだけ優れた営業手法を伝授しても、部下が同じように成果を出せない現実に直面する。そこには、実は見落とされがちな“マネジメントの根本的な誤解”が存在している。
自らが現場に降り立ち、共に行動する覚悟がなければ、どんなノウハウも空回りする。この記事では、「俺が売れたんだから、真似すればいい」という思考から脱却し、「俺も金魚なんだ」という気づきによってチームを一変させた実体験をもとに、中小企業におけるマネジメントの本質とその改革の道筋を提示する。
マネジメント失敗の本質を知れ〜「俺が売れた」では人は動かない〜
自身の成功体験に固執した指導は、組織を疲弊させ、チームの成長を阻害する。なぜ成果が出ないのか? その答えは“自分ではなく、他者”がやることへの理解が欠けているからだ。
営業の成功体験がマネジメントに通用しない理由
営業マンとしての優れた成果は誇るべきことだが、そのスキルを他人に再現させるのは別の話である。営業は個人技の側面が強く、自らの感覚や直感で対応してきたことが多い。だが、それをそのまま部下に求めても、本人の背景、性格、価値観が違う以上、同じように動くことはない。
むしろ、上司の「できて当然」という圧力により、部下の自信は削られ、挑戦する意欲を失う。成功者ほど、自分の手法を標準的であり最適解だと誤認しがちだが、マネジメントは「相手に合わせる技術…相手をその気にさせて動かすこと」それが肝である。
「言えばやるだろう」は幻想でしかない
「勉強して営業に活かせ」「努力しないのは怠けている」…..こうした考えは一見正論だが、それだけでは人は動かない。言われてやる人間は、すでにある程度自立した人材であり、問題の多くは“言っても動かない人”への対処である。もっと言えば、何を言われているのか理解できていない、自分はやっていると思っている人にどうやって現状認識を変えてもらうかなのだ。
人が行動を起こすには「納得」と「共感」が必要であり、それには信頼関係が不可欠だ。つまり、言うだけではなく、なぜそれが必要なのか、どう取り組めばいいのかを丁寧に共有する姿勢がなければならない。部下が怠惰なのではなく、納得していないだけという可能性に、上司自身が気づくべきである。
信頼関係を具体的に表現するなら、「この人の言うことを聞こう」「この人の言うことだから信じてやってみよう」そのように思ってもらえる関係になるということだ。
結局、現場に“降りていない”マネジメント
部下に対しては厳しく、成果には敏感。しかし、現場で起きている苦労や実情には無関心(現実を正確)….そんなマネージャーは珍しくない。実際には現場感覚が乏しいまま指示を出しているケースが多く、結果的に部下は「わかってくれない」「信用されていない」と感じて距離を取るようになる。
真のマネジメントとは、言葉ではなく“同じ目線で共に汗をかく”ことから始まる。現場に降り、自らが模範を示すことで、初めて人はついてくるのだ。
昭和的な表現…って思われるかもしれないが、背中を見せて着いてきてもらえるように動く…それが現場マネジメントの基本だ。
金魚鉢の外から指示しても、誰も動かない
マネジメントの第一歩は「自分も同じ金魚鉢にいる」と気づくことだ。共に泳ぐ姿勢がなければ、どんな言葉も届かない。
「お前も金魚なんだ」と言われた衝撃
ある日、「お前も金魚なんだぞ」と言われた一言が、筆者のマネジメント観を根底から揺さぶった。自分は特別な存在ではなく、同じ水槽の中で生きる一匹の金魚にすぎない….この認識の変化は、指示を出す側と受ける側の関係性を根本から変える。
金魚鉢の外からあれこれ言うのではなく、同じ水の中に入り、共に泳ぐ姿勢を見せることで、部下の態度は確実に変化する。距離のある指示ではなく、寄り添う実践が必要なのだ。
金魚鉢の外から餌を与えてるんだから、ちゃんとやれよ!的な言動では人は動かない。部下は「お前も金魚ちゃうんかい!」と、筆者よりも先に私も金魚であることに気がついてる。外から言うだけなら、俺でもできるわ。と…多分、そう思われていたんだろうと回想する…人としても不適切な言動が多々あったのだろうと思う。(詳細まで記憶にはないのだが…)今の時代なら完全にパワハラとか、エラハラ(エラそうにするハラスメント)、〜ハラ…ありとあらゆるハラスメントの対象になっていただろうと思う。
模範となる行動が信頼を生む
マネジメントにおいて、言葉だけで人を動かすことは不可能に近い。近いというより不可能と思った方が正しいだろう。特に中小企業のような少人数組織では、上司の行動が組織全体の空気を作る。営業方針に従わせたいなら、まず自分がその方針を体現する。部下に勉強を求めるなら、自らも学び続ける姿を見せる。模範がないところに信頼は生まれず、信頼がなければ指示も空虚な命令に過ぎない。自らの行動がすべての土台となる。
勉強が必要であるとの正論や理屈ではなく、勉強をするとどのように結果が変わるのか体感させるようにすることで人の認識と行動は変わっていく。
チームの空気は「言葉」でなく「雰囲気」で伝染する
職場の雰囲気は、理屈ではなく空気で伝染する。上司がピリピリしていれば、部下は萎縮し、挑戦を避ける。逆に、上司が積極的に現場に関わり、楽しそうに仕事をしていれば、自然とそのムードが組織に広がる。感情は共鳴するのだ。チームの活性化には、上司の感情マネジメントが不可欠であり、自らポジティブなムードを作り出すことが、最強のマネジメントスキルとも言える。
心理学的にもポジティブな気持ちや、笑顔がない組織では良い考えも生まれないことは、様々な実験データからも明らかだ。暗い雰囲気と空気感となり、どんよりと停滞してしまうことになる。

心理学と営業マネジメントについては、また別の記事で詳細をお伝えする
共に泳ぐマネジメントが業績を変える
マネジメント改革は、チームの雰囲気だけでなく、明確に業績にも影響を与える。「俺が」ではなく「俺たちが」の精神が結果として売上向上と営業マンの自立と自律を促すこととなるのだ。
営業マンが定着する組織の条件
離職が止まらない職場は、待遇ではなく「環境」に問題があることが多い。人が辞める理由は、実は業務内容ではなく、“居場所がない”という感覚に起因している。上司が仲間として接してくれる。困った時に助けてくれる。成長を共に喜んでくれる…このような環境がある職場では、人は長く働き、パフォーマンスも高まる。マネジメントの本質とは、こうした「心理的安全性」の確保にある。
別の言い方をすれば、離職の理由の99%は人間関係にあるのだと筆者は考えている。経験からすると、私が原因で辞めていったのだろう…ただ、中小企業の場合は社長に起因して離職する者が多い。(筆者が見聞きする範囲ではあるが)
直接的に「社長が嫌です」「この社長の下では働きたくありません」と、言う社員は少ないだろうが….人間関係が良く無い根源を作り出しているのは、間違いなく社長であるからだ。社員間での情報交換や体験談から上司が知らない社長像を知ってる…そのような職場は決して少なくないだろう。
“俺が売った”から“みんなで売る”へ
「自分が売る」から「チームで売る」への移行は、経営者にとって最大の転換点となる。トップ営業マンとしての誇りを捨てきれず、つい自分で動いてしまう人も多いが、それではいつまで経っても組織は拡大しない。人に任せ、人を育て、チーム全体の底上げを図ること。それこそが“経営者としての営業”であり、マネジメント力の証明でもあるのだ。
金魚鉢で泳ぐことの“しんどさ”と“成果”
自分も金魚鉢に入るということは、楽ではない。プライドを捨てる必要があるし、恥をかく場面も増える。しかし、その“しんどさ”を乗り越えた先には、組織の一体感と、飛躍的な成果が待っている。自分の背中を見て人が動くというのは、何物にも代えがたい快感であり、組織経営の醍醐味でもある。金魚として共に泳ぐ。その姿勢が、真に強いチームをつくる。
何よりも自分で売る。自分が売った。ということよりも、今月は達成しました!と、部下の報告を聞く時の、部下の顔を見ている時の方がよっぽど嬉しいし、充実感も自分自身の達成感も味わえる。それを体験したら、金魚鉢の中が最高の快適ゾーンであったことに気が付くことになる。
まとめ:マネジメントに必要なのは「泳ぐ覚悟」
中小企業の経営者にとって、人を育てることは会社を育てることに他ならない。「俺が売った」ではなく「みんなで売れるようにする」。この意識改革こそが、マネジメント再構築の核心である。部下が動かない理由を外に求めるのではなく、自らが“金魚”になり共に泳ぐことで、初めて本当の信頼関係と成長が生まれるのだ。「俺も金魚なんだ」。この気づきが、あなたの組織の未来を変える起点になるだろう。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。