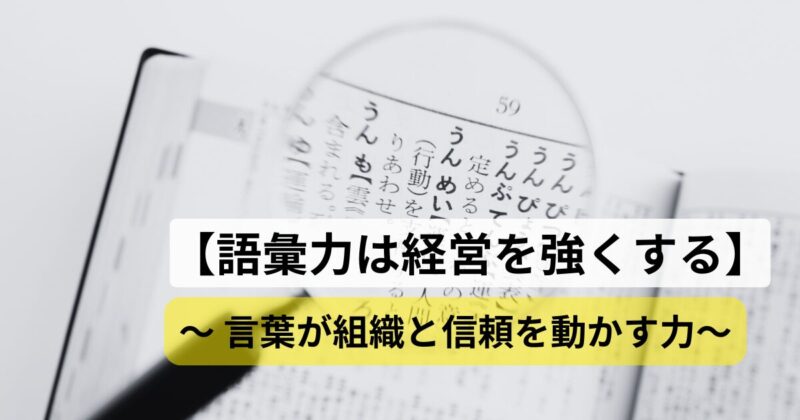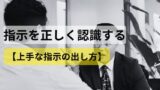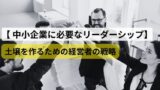チャットやスタンプでのコミュニケーションが当たり前になった今、言葉は「短く速く」伝えるものへと変わってきている。だが、それは本当に“伝わって”いるのだろうか?とくに中小企業の経営において、語彙力は組織の思考、信頼、そして成果に直結する。語彙が乏しければ、伝えたいことも受け取るべきことも正しく理解できず、コミュニケーションは「通じたつもり」の錯覚で終わる。本稿では、語彙力を発信と受信の両面から「経営力」として捉え直し、なぜ今それが求められるのかを具体的に紐解く。
なぜ今、語彙力が問われるのか ― 簡略化社会の落とし穴
「通じる」ではなく「伝わる」が必要な理由
LINEやSlackのやり取りで「了解です」「あとでやっておきます」…こうした表現は一見スムーズに感じる。しかし、実際には「了解=どこまで理解したのか」「あとで=いつ?」という点が曖昧だ。とくに中小企業では口頭でのやり取りも多く、曖昧な言葉がそのまま指示や報告に使われてしまう。
語彙が乏しければ、相手の意図を“深く”汲み取ることはできない。これは「文章化できない病」が組織を蝕むと警鐘を鳴らした【出典:『【「文章化できない病」が組織を蝕む】〜中小企業経営者が見落とす最大のリスク〜』】でも触れている重要な問題である。

スタンプや略語では思考を共有できない
スタンプや絵文字は感情は伝えられても、「判断の背景」や「優先順位」など、思考の構造は共有できない。これが組織にとって致命的なノイズになる。
本質を表現できる言葉がなければ、どれだけ情報を共有しても、誤解は避けられない。経営者はそのことを強く自覚するべきだ。
発信する側の語彙が浅ければ、組織は誤解と混乱に満ちる
抽象語は社員を迷子にさせる
「主体性を持って」「スピード感を持って」…こうした表現は、聞こえは良くても社員にとっての“具体的行動”が何も伝わらない。これは、【出典:『上手な指示 指示の正しい認識』】で解説している「抽象語での指示は部下の思考を曇らせる」という主張と同義だ。
曖昧な言葉は判断を誤らせ、結果的に「やったつもり」「伝えたつもり」のトラブルを引き起こす。語彙力の高いリーダーは、“伝える技術”を持っている。

経営者の語彙が文化をつくる
言葉は上から下に染み込んでいく。経営者が明瞭な語彙で語れば、社員もそれを真似し、組織全体の言語力が向上する。これは、【出典:『中小企業に必要なリーダーシップの土壌を作るための経営者の戦略』】で強調している「組織文化の醸成には日常的な対話が必要」という視点にも通じる。
語彙の豊かさは、組織の知的な厚みを生む。
受信する側に語彙がなければ、すれ違いが起こる
相手の意図を読み取れないという“知的エラー”
語彙が乏しい社員は、「検討してみて」と言われた時に「やらなくてもいい」と解釈することがある。これは発信者の問題ではなく、受信者の語彙的な処理能力の問題である。
言葉を正しく受け取れないというのは、「聞いているのに理解していない」ということ。それは【出典:『【「文章化できない病」が組織を蝕む】』】でも指摘した「自己認識の甘さと理解力の不足」によって生じるエラーだ。
専門用語や業界語が理解できないリスク
経営の現場では、「API」「業務フロー」「PDCA」などの言葉が頻繁に使われる。語彙力が不足していれば、これらを曖昧に理解し、議論に参加できない。
これは、【出典:『IT顧問のススメ』】の中で語った「IT投資がなぜ失敗するか」の要因にも通じる。理解できない言葉を放置した結果、誤った判断を下してしまうという事例がいくつも紹介している。
明日から取り組める「語彙力経営」の実践習慣
「曖昧語チェック」で会議と報告を変える
「なるはや」「適当に」「まぁまぁ」などの表現を排除し、必ず具体化して再確認するルールを作る。これにより、認識ズレによる業務の手戻りを防げる。
共通語彙リストの整備で“意味のずれ”を防ぐ
「対応」「報告」「相談」などの社内用語を共通定義化する。これは【出典:『上手な指示 指示の正しい認識』】における「共有前提の誤解」への対処にもつながる。
“言葉の定義”こそが、組織の行動の精度を決める。
経営者自身が語彙の“翻訳者”になる
社員が使った曖昧な表現を「つまりこういうことだね?」と具体的に言い換えて確認する。この小さな繰り返しが、組織に“わかる文化”を根付かせる最初の一歩になる。

まとめ ― 語彙は経営のインフラである
語彙力は、発信力だけでなく、理解力、思考力、信頼構築力にまで直結する“経営のOS”である。特に中小企業では、指示の曖昧さや認識のズレが大きな損失に繋がりやすい。語彙を磨くことで、組織の生産性、判断力、チームワークまでもが向上する。
「語彙力は無形資産である。」リーダーが語彙を意識し、部下に伝え、受け取ることの意味を教える。それこそが、持続的成長への最短ルートである。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
また、お会いしましょ。