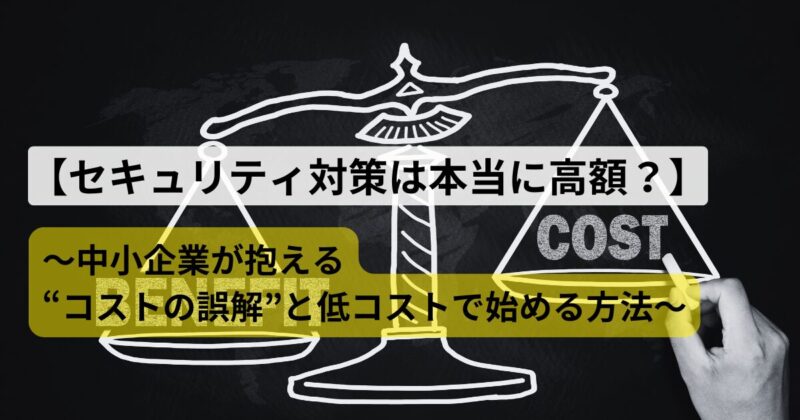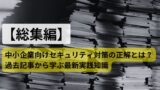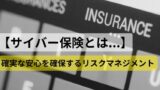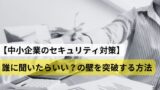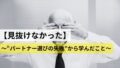「セキュリティ対策は高すぎる」「うちは関係ない」「予算がないから後回し」。中小企業の現場でこうした声を耳にするのは珍しくない。だが、果たしてそれは本当なのか?実際には、誤解や一部の極端な事例が独り歩きしていることが多く、“高額”というイメージが先行しているに過ぎない。本稿では、中小企業がセキュリティ対策を「高い」と感じてしまう構造を紐解き、低コストで始められる現実的な対策や考え方を提示する。ITセキュリティ、クラウドセキュリティ、リスク管理など、経営者向け・IT初心者向けの視点で解説する。
なぜ中小企業はセキュリティ対策を「高い」と感じてしまうのか
「セキュリティは大企業のもの」〜そう思い込んでいませんか?〜
「ウイルス対策ソフトを入れているから十分」「うちはターゲットにならない」…こうした言葉はよく耳にするが、実態は違う。近年では、サプライチェーンを狙った攻撃で中小企業が“踏み台”にされる被害が急増している。2022年に発生した「小島プレス」「徳島県・半田病院」などの事例(参考:『【徹底解説】セキュリティ対策ガイドライン 5か条!【事例から検証】』)では、VPN装置の脆弱性を突かれた中小企業が攻撃の入り口とされていた。これは大企業だけの問題ではない。
製品購入=対策?その思い込みがコストを膨らませる
「セキュリティは高価なソフトや機器を買わなければ意味がない」と考える企業も多い。しかし、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が提唱する「情報セキュリティ5か条」(参考:『【徹底解説】セキュリティ対策ガイドライン 5か条!【事例から検証】』)を見ると、重要なのは運用やルールであり、ツールはあくまでも補完でしかないとわかる。OSやソフトを最新に保つ、パスワードを強化する、共有設定を見直すといった基本の積み重ねが、最も効果的かつ低コストな対策だ。

メディアやベンダーの報道が生む「高額」イメージ
新聞やネットニュースで報じられるサイバー攻撃の多くは、大企業が被害に遭い、億単位の損害を出すケースばかりだ。さらに、セキュリティ製品ベンダーも自社製品を売るために「危機感」を煽りがちである。その結果、「セキュリティ対策=高い」という印象だけが残り、中小企業にとっては心理的なハードルが高くなってしまう。
「高額に見える」原因はどこにあるのか?
成果が“見えない”からこその錯覚
セキュリティ対策は、事故が起きなければ「無駄な投資」に見える。たとえば、バックアップの自動化や多要素認証の導入をしても、それによって何か売上が上がるわけではない。だが、これは「火災保険が不要だ」と言うのと同じで、何も起きていないことが効果の証拠でもある。セキュリティは“成果が見えにくい”からこそ、経営判断として軽視されがちなのだ。

人件費や運用コストを見落としていませんか?
実際のコストは、ツールや機器だけではない。ルール作りや社員教育、そしてそれを継続する体制にこそ時間と人手が必要だ。だが中小企業では「導入さえすればOK」という発想が多く、運用コストを織り込んでいないケースが非常に多い。結果的に、「うまく活用できなかった」「放置されたまま」となり、“高かったのに意味がなかった”という印象が強化されてしまう。
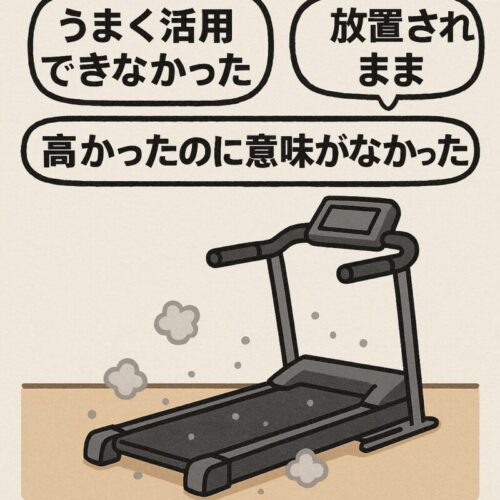
誤った投資が「本当の高額」を招く
『IT顧問のススメ』でも指摘したように、適切な判断をしないままベンダーの言いなりで投資をすると、無駄遣いになる。これは「安物買いの銭失い」どころか、「高額投資して何も得られない」という最悪のパターンを招きうる。中小企業にとって最も避けるべき事態だ。
中小企業でも実現可能な「低コスト対策」とは
ステップ1:情報資産とリスクの棚卸
まず自社の“守るべきもの”を明確にする必要がある。顧客データ、業務ノウハウ、業務停止リスク…。それを洗い出し、優先順位をつけるだけで、必要な対策は見えてくる。ツール選定はその後でいい。これは「自社の状況を把握する」ことに他ならない。
ステップ2:基本の5か条を徹底する
IPAが提唱する「情報セキュリティ5か条」は、実は非常に強力だ。特にOSやソフトのアップデート、パスワードの強化は、ほぼコストゼロで導入でき、被害を劇的に減らす効果があることが実証されている(参考:『【徹底解説】セキュリティ対策ガイドライン 5か条!【事例から検証】』)。こうした“できること”から始めることが重要だ。
ステップ3:外部専門家を「味方」にする
「ITは専門じゃないからわからない」と思う経営者こそ、第三者のアドバイスを受けるべきである。独立系のIT顧問やSOCサービスなど、月数万円で導入できる支援体制が整ってきている。内製化できないのであれば、外部の力を活用するのが最も合理的だ。
「高額に見える」構造を理解すれば、無理なく始められる
小さな投資が大きなリスク回避につながる
セキュリティ事故が発生した場合の被害額は、中小企業であっても数百万円規模になる。であれば、月数千円〜数万円の投資で回避できるのであれば、それは“コスト”ではなく“保険”である。実際、サイバー保険やIT顧問サービスなど、今は手が届く選択肢が豊富にある。
専門家との連携が成功のカギ
「誰に相談すればいいかわからない」「信頼できる人がいない」という声も多いが、今や情報セキュリティの分野ではセカンドオピニオンの仕組みも一般化してきている。営業目的ではない、純粋なアドバイスを提供してくれる存在を“右腕”にすることで、対策は現実的なものになる。
IT人材不足でも対策は可能
人がいないからできない…ではなく、人がいないからこそ“しくみ”で守るべきだ。自動化されたアップデート、強制ログアウト、アクセス制御。すべて、低コストで導入可能であり、属人化せずに実行できる仕組みを整えることは、むしろ人手不足対策にもなる。
まとめ:セキュリティ対策は“高額投資”ではなく“安価な経営戦略”だ
セキュリティ対策が高額に感じられるのは、情報の偏り、誤解、そして「対策の目的」を見失っていることにある。だが、実際には中小企業でも小さく始められる現実的な選択肢は多く存在する。そして最も重要なのは、「何を導入するか」ではなく「なぜ導入するか」。目的を明確にし、外部の力をうまく借りながら、自社のリスクを正しく管理することが、セキュリティ投資のあるべき姿である。
👉 今日から始められる具体策はシンプルだ。
これだけでも“高額対策”の第一歩になる。
経営者は孤独な判断を強いられるが、情報セキュリティに関しては、信頼できる“右腕”を見つけることが成功の第一歩である。IT顧問やSOCサービス、サイバー保険…すべては「安心してビジネスに集中するための投資」なのだ。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。