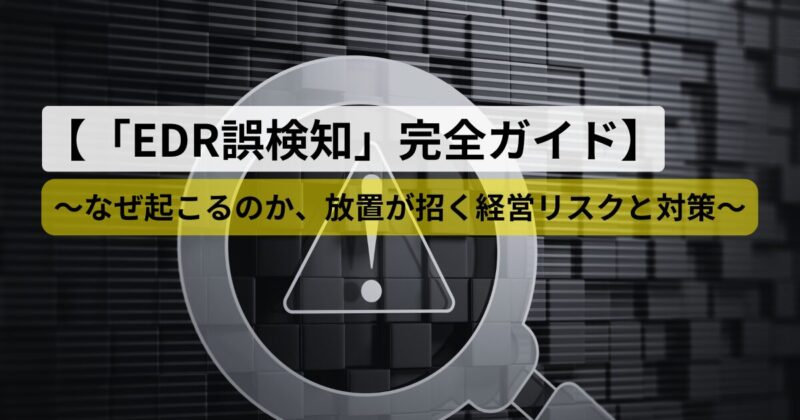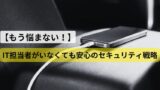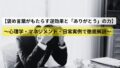EDR(Endpoint Detection and Response)は、高度化するサイバー攻撃に対応するための有力な防御手段だ。標的型攻撃やランサムウェアなど、アンチウイルスでは防ぎきれない脅威に対して、検知・封じ込め・復旧を迅速化できる。
しかし導入後の現場からは「アラートが多すぎて本当に危険なのかわからない」「担当者が疲弊する」といった声も少なくない。その原因の多くは「誤検知」にある。誤検知とは、安全な動きや処理を“危険かもしれない”と判定してしまうこと。本稿では、IT知識がない方でも理解できるよう、誤検知のメカニズム、放置による経営リスク、そして中小企業が取るべき対策を詳しく解説する。
なぜEDRは誤検知をするのか?
空港の金属探知機の例え
空港の金属探知機は、銃やナイフだけでなくベルトや鍵でも反応する。理由は「金属」という特徴を検知したら即座に反応する仕組みだからだ。EDRも同様に、攻撃によく似た動きを見つけた時点でアラートを出す。実際に危険かどうかは人間が確認しなければわからない。
日常業務も攻撃と似て見える
Windowsアップデートや会計ソフトのインストールでは、大量のファイルが一気に書き換えられる。これはランサムウェアの暗号化動作と類似しており、EDRが「怪しい」と判断することがある。
あえて過剰反応する設計
EDRは「安全寄りの過剰反応」で設計されている。多少の誤報があっても本物を見逃さないためであり、その結果、危険度の低い動作も積極的にアラート対象となる。
誤検知が発生する典型的な4つの原因
1. 初期設定のまま運用
導入直後は企業の“普通の業務パターン”を知らないため、通常業務も「見慣れない動き」として警告する。ポリシー設定やホワイトリスト化を怠ると誤検知は増える。
2. OS・ソフト更新時の挙動変化
更新で動作や通信先が変わると、EDRの過去データと食い違い、異常判定されやすくなる。
3. 社内ネットワーク構成の変更
サーバー追加やネットワーク改修など、構成変更をEDRに反映しないとアラートが増加する。
4. 他セキュリティ製品との干渉
ファイアウォールやウイルス対策ソフトの動きがEDRから“怪しい”と見えることがある。連携・除外設定が重要だ。
誤検知を放置するリスク
「また誤報か…」と軽く流す習慣がつくと、実は組織全体のセキュリティ耐性を大きく下げてしまう。誤検知は単なる“ノイズ”ではなく、運用体制や意思決定スピードに悪影響を及ぼす要因である。
1. アラート疲れによる本物の脅威の見逃し
イメージとしては、住宅街で毎日何回も誤作動する防犯ベルが鳴っているようなものだ。最初のうちは住民も気にするが、だんだん「またか」と思い、誰も見に行かなくなる。その時、本当に泥棒が入っても気づくのが遅れてしまう。

EDRでも同じことが起きる。誤検知が多すぎると、担当者の脳は「どうせまた安全なやつだろう」と判断しやすくなり、チェックが雑になる。その隙を突かれれば、重要サーバーが侵入されていても気づくのが遅れ、復旧コストや信用失墜のリスクが一気に跳ね上がる。
2. 運用コストの増大
誤検知とわかっていても、アラートが出た以上は記録や調査を行わなければならない。これを怠ると「本当に安全だったのか」が証明できず、監査や取引先からの説明要求に応えられなくなる。
例えば1件の調査に30分かかるとして、1日に10件の誤検知があれば、それだけで5時間の工数が消える。担当者の本来業務が圧迫され、外部委託すれば月数十万円規模の費用増加もあり得る。結果として「セキュリティ強化のための投資」が「調査と記録のための費用」に変質してしまう。
3. 経営判断の遅延
重大アラートと誤検知が入り混じった状態では、どれが本当に緊急なのか判断がつかない。経営層に情報が上がるまでに時間がかかり、対応の初動が遅れる。
例えば取引先の顧客情報漏洩の可能性が出た場合、初動が1日遅れただけで被害拡大やメディア報道のリスクは倍増する。早期の公表や取引先への連絡ができず、「隠していた」と見られることで信用を大きく失う事例もある。
つまり、誤検知を放置すると「どれが本当に危険かを見極める速度」が落ち、結果的に経営リスクが増幅する。
補足:誤検知は“削る”のではなく“選別する”
誤検知をゼロにすることは現実的ではない。重要なのは、「どれが無視してよい誤検知かを即座に判定できる体制」を作ることだ。これには、導入初期のルール調整、担当者の判断力育成、そしてSOCなど外部専門家による選別支援が欠かせない。
中小企業が取るべき誤検知対策
導入初期のポリシー調整
業務アプリや通信先をホワイトリスト化し、正常な動作を誤検知しないようにする。
運用担当者の教育
OSやネットワークの基礎知識を持った人がアラートを確認することで、不要な調査を減らせる。
SOCサービスの活用
SOC(セキュリティオペレーションセンター)を利用し、誤検知の分析や本物の脅威判定を外部専門家に委託する。中小企業では特に有効。
定期的な設定見直し
IT環境や業務内容の変化に合わせて検知ポリシーを更新する。
まとめ
EDRの誤検知は避けられないが、運用体制次第で被害リスクを大きく減らせる。重要なのは、誤検知を単なる「邪魔なノイズ」と捉えるのではなく、本物の脅威を見逃さないための“選別作業”と位置づけることだ。そのためには、初期設定調整、担当者教育、外部SOCの活用が欠かせない。これらを経営判断として前提に置くことで、EDRは初めて投資価値を最大化できる。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。