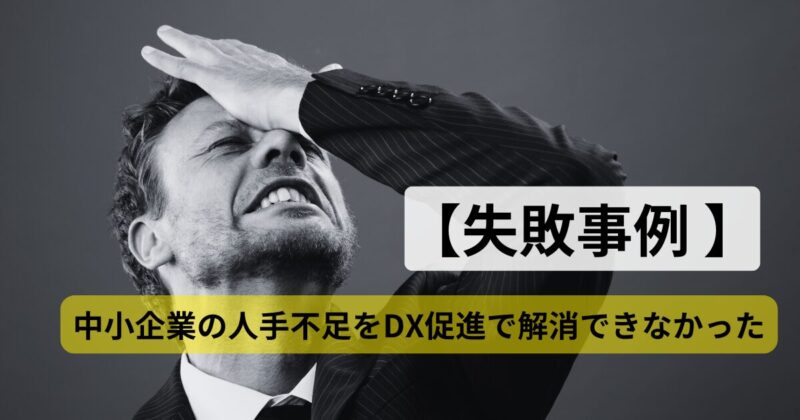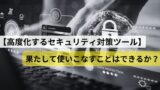セキュリティ対策もDXも、中小企業にとっては必要な経営課題であるし取り組むべきことだとの認識は持っている。だが、その第一歩をどう踏み出すかが、なかなか難しいようである。正しいDXの進め方、どのようにDXを推進するか。という解説を見ることは少なくない。その逆の視点で、これをやってしまうと失敗してしまう…という事例を解説することで、適切なDX推進の認識を持っていただきたい。というのが本稿の主旨である。セキュリティ対策の支援をメイン(詳細はプロフィールをご参照ください)としており、DXの相談はレアケースではあるのだが、その中の体験談を解説させていただく。
✔️ 現状の問題・課題を事象や現象として捉えている
✔️ とりあえずやってみてはいけない
✔️ AIへの過度な期待と幻想
✔️ まとめ:失敗を回避するために
現状の問題・課題を事象や現象として捉えている
なぜDX化するのか?それは現状の問題への改善を期待してのことだろう。現状とはどういう状態なのか?そうなっている根本的かつ本質的な要因はなんなのか?ITでできることは多々あるのだが、万能ではないし意思を持って稼働するものでもない。具体的にどの問題を解消・解決するために、どの機能を活用し成果を出すのか。事前に論理的な検証をしておかなければ成功へと導くことはできない。
人がいないならITで補えばいい…は、可能か?
「人がいないんだよ…」「なかなか人が来ないんだよ…」など、中小企業ではありがちな経営者の悩みである。
「少ない要員でもカバーできるようにIT化することでなんとかならないか?何か提案して欲しい。」
これは実際に受けたことがある依頼なのだが、言わんとすることは理解できるものの、この要件では具体的な提案を構成することはできない。
そもそも、人がいないとはどういうことなのか?何人必要なのか?見方によっては人は充足しているが、無駄な作業や非効率が、結果として多くの要員を必要とする事態となっているため欠員が出ている現状を「人がいない…」と表現しているのか…問題の本質を捉えないとIT化が正しい選択肢となるか判断はできない。
なぜ、今の状態・状況になっているのか、その要因を徹底的に分析しなければ改善策を見出すことはできないのだ。「ITでなんとかできるでしょ。」というほど簡単な話ではない。
「人がいない」とはどういうことか?
「人がいない。」とはどういうことなのか?その詳細を聞いてみると…
「人がいない」という現状は変わらないが、なぜこのようなことになっているのか問題の本質によって改善のポイントはまったく違うものになる。
退職・離職はIT化で解消できない
DXを促進し、IT化が実現できたとしても退職者を減らすことはできない。WebサイトやSNSを使った効果的なプロモーションで応募を増やすということは可能かもしれないが、問題の根本を解決しなければ、退職を防止することはできず採用コストが増えただけになるであろう。
なかなか人が採用できない、採用しても辞めてしまう…だったらそこはITでなんとかやりくりしよう…この発想はDXではない、人がやっていたことをIT(デジタル)に置き換えるということだ。何ら変革を起こすことはない。そもそも、人がいないからITで…ということは実現できるか?それほど単純に解決できることではない。
IT化の成果はアナログ的(多くの書類を目視で確認するなど)な業務の改善など、現実的に見ると適用範囲は限定される。人材不足を直接的に補えるものではない。
とりあえずやってみてはいけない
問題の本質を捉える(現状を分析する)ということは、どうも脇に置かれる傾向にある。考えていても何も変わらない…その進捗の無さに我慢ならないのだろうか?ITツールの導入においても、機能や価格の比較から選定するのではなく、運用計画や期待する効果を決めてから選定をしてください。と、助言しても聞き入れらないことが多い。(私の経験値である)
何かをしなければ始まらない… だったらとりあえずやってみよう!という方向で進むことも珍しくない。
導入することが目的と化す
この事業者は、お客様からの問い合わせ対応をAI ChatBotを導入することで人手不足を補うべく、導入してしまった。(後で確認すると試験導入とのことだったが)我々の提案の中にも、AI ChatBotは一つの選択肢や同業他社でも導入が進んでいることから提示はしていたのだが、価格が安いということで別事業者からの導入を決めたのだ。
どこまで人的負担が軽減されるかの検討も検証もなく…導入が目的化した典型的な事例となった。
AIへの過度な期待と幻想
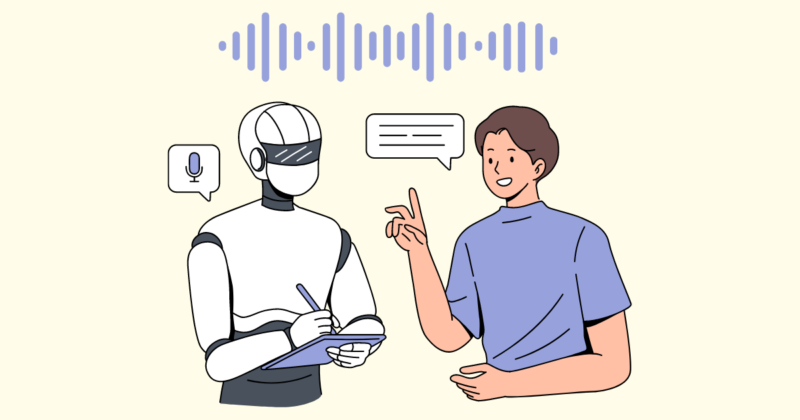
問い合わせへの対応(応対を期待して)なら、過去のデータもあるしAIが学習することで品質も高まるだろう…との期待感はあったものの、現実はそうではなかった。回答内容が適切かどうか以前に、今日、質問したことが翌日や二日後になってしまうなど、ほとんど機能しなかったのだ。(ベンダーに問い合わせるも納得できる合理的な説明はなかったとのこと)
AIなので、時間をかけて学習することで回答精度が高まっていきますとのベンダーの説明があったものの、今知りたいことを、翌日以降に無機質に回答されてしまうのであればサービスレベルが一気に低下することになる。AIへの期待感も一気に薄れてしまうことになったのだ。
AIにできることと現実とのギャップ
私見ではあるが、AI(LLMに関して)はまだ発展途上ではないかと思える。質問の形式も回答もある程度、定型化されており、その情報量が膨大であることから人手でやっていると時間がかかるし無駄(生産性がない)であるというようなものであれば威力を発揮するであろう。サービス業の中でも、コールセンターのように製品の仕様や納期などを回答するケースでなど。
ただ、不特定多数が各人の感覚で質問をしたり、何か限定的な範囲で深い知識が必要となる回答を要求するケースでは多くの情報から学習させる必要があり、まだ実用化レベルではないものもある。少なくともこのレベルまでAIが補ってくれるのなら、導入効果はあると事前に検証をしておかないと期待と現実とのギャップに入り込んでしまい、どうやってAIを機能させるか…と、また目的が変わってしまうことになりかねない。
他社の導入事例は良いとこどりの羅列
同業他社での実績が豊富であるというベンダーの説明を受けて導入を決めたとのことだが、導入事例(資料)には良いことしか書かれていない。今まで5人で対応していたが、1人で対応できるようになったなど…。もともと、どの程度の人が介入していたのかなど詳細を知ることはできないのだ。また、成功しているのだとしたらそれまでにどのくらいの時間がかかったのか?当初からスムーズに機能させることができたのかなど、なるべく詳細を確認するべきだ。
だが、中小企業の経営者はITに詳しくないということもあり、事前に何を確認すべきなのかという情報を持ち合わせていないのだ。結果として、ベンダーが言う成功事例が自社でも同様の結果となるであろうと思い込んでしまう傾向にあるのだ。
ただ、一つだけ重宝したことがあった。それは、多言語対応していることだった。英語で応対できる要員はいるが、その他の言語は苦慮していた。言葉が通じないことを受け入れてた海外の旅行者にとっては、日本の観光地を母語で閲覧できないこともあったため、AIに聞くことでその問題は多少なりとも解消できたということである。がしかし、あまりコスパが良い投資とは言えず、結果として失敗したとの評価が適切であろう。
まとめ:失敗を回避するために
大枠ではあるが、上記の手順を踏むべきだ。DXの進め方など多くの解説記事が各サイトでも閲覧できるが、現状の業務を整理する、問題点を明確にする、導入目的を曖昧にしない…等々…時代の波に乗り遅れないよう、DX化することが目的となってしまうことを回避するよう提言している。どんなツールがあるか選定する方が楽しいし、ワクワクするかもしれないが、そこをちょっと我慢して面倒ではあるが現状分析により多くの時間を割くことで、後に得る果実の実は大きいものとなるだろう。
私が経験値から強調したいのは、3項の導入後の運用について事前に計画しておくということである。ツールは勝手に稼働はしてくれるが、ただ動いているだけでは意味がない。しっかり使いこなさなければ期待した導入効果を発揮することはない。そこは、まだ人が手を出さないといけない部分である。
ツール選定と使いこなしについては、セキュリティ対策ツールを例として以下の記事もあるので参考にしていただけたらと思います。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。