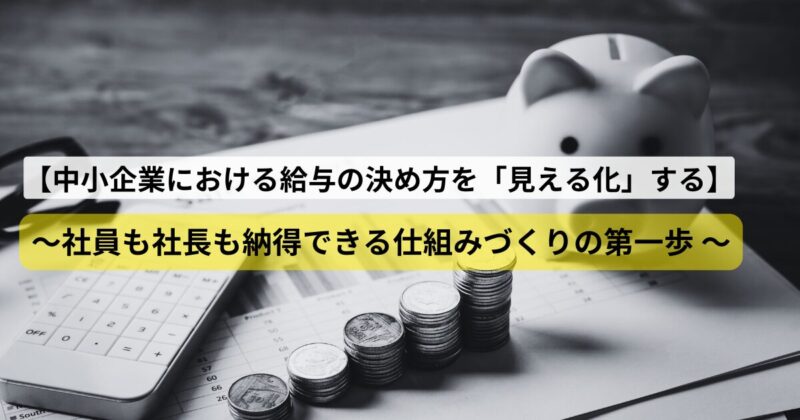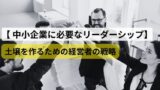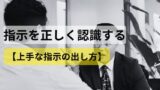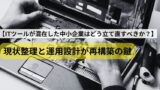中小企業において、給与体系が「社長の感覚」や「過去の前例」で決まっているケースは少なくない。しかしその不透明さは、社員のモチベーション低下や離職リスクを招くばかりか、経営の健全性そのものにも影を落とす。経営数字に苦手意識を持つ経営者も多い中、まず取り組むべきは「給与がどこから生まれるのか」を可視化することだ。売上・粗利・人件費の関係を明確にし、社員と共有することで、納得感と一体感のある経営が可能になる。本稿では、給与設計の「見える化」を軸に、中小企業の経営改善に直結する現実的な一歩を提言する。
なぜ給与の仕組みが不透明になりやすいのか
給与制度が不透明になる背景には、属人的な判断や会計知識の不足がある。
前例踏襲で決まってしまう給与
中小企業では、かつての「初任給は○万円」「毎年○円昇給」といった慣例が、今もそのまま引き継がれていることが多い。その理由は、仕組み化されておらず、都度判断が難しいからだ。人事制度の専門知識がなくても前任者のやり方を踏襲すれば間違いがないという心理が働き、結果として給与の決定プロセスがブラックボックス化する。経営の現状と乖離した給与体系は、持続性を失い、経営者と社員の両方を苦しめる原因になる。

経営者自身も利益構造を理解していない現実
売上が伸びていても、手元にお金が残らない。そんな悩みを持つ経営者は少なくない。問題の本質は「利益構造」を理解していないことにある。売上から経費を引いて何が残るのか、その構造が曖昧なままでは、適切な給与設定もできない。「なんとなくの勘」で給与を決めることが、後になって資金繰りを圧迫するという悪循環を招いている。
数字を非公開にすることが不信感につながる
社員に対して「数字は見せられない」「給与は経営者が決めるもの」といった姿勢で接すれば、社員側には「どうせ評価されても上がらない」「理由がわからない」という不満が溜まる。情報の非対称性は、組織の分断を生む。経営が厳しい中小企業だからこそ、信頼を軸に据えた開示の姿勢が必要である。
売上から給与までの関係を整理する
給与の見える化は、売上と利益の構造を整理するところから始まる。
売上と粗利の違い
売上はあくまで「収入の入口」に過ぎない。そこから原価を引いた「粗利(売上総利益)」こそが、経営の真の原資となる。飲食業を例にとれば、1,000万円の売上があっても、食材・仕入・外注などの原価で600万円が消えていれば、残る粗利は400万円に過ぎない。給与や家賃、広告費、利益はこの400万円の中から賄われる。給与設計を考える際、売上だけを見て判断するのは極めて危険だ。
利益の種類(営業利益・経常利益・最終利益)
粗利から人件費や経費を引いたのが営業利益であり、そこからさらに金融費用などを引いたのが経常利益、そして税金などを引いて残るのが最終利益である。経営者は、どの利益を基準に意思決定をしているかを明確にしておく必要がある。特に、昇給や賞与の判断材料にするならば、「営業利益」や「経常利益」が適しているケースが多い。

労働分配率という考え方
労働分配率とは、粗利のうち何%を人件費に充てるか、という比率である。例えば、粗利が年間5,000万円の会社で、人件費が2,000万円なら労働分配率は40%となる。この指標をもとに給与予算を設計することで、経営の持続可能性と給与の納得感を両立できる。
昇給・賞与をどう位置づけるか
人件費は固定費の中でも大きなウェイトを占める。だからこそ、その設計には戦略的な視点が求められる。
昇給は持続可能な給与から逆算
昇給はモチベーションの源泉となるが、会社の体力を超えた昇給は破綻のリスクを高める。昇給を判断するには、まず「粗利」「労働分配率」「将来予測」をベースに、人件費総額の上限を把握する必要がある。個人単位の評価だけでなく、会社全体として昇給可能な範囲を明確にすることで、無理のない昇給が可能になる。
賞与は業績連動で調整する仕組み
賞与は、固定ではなく変動させる仕組みが望ましい。業績連動型の賞与にすることで、会社の利益状況と連動した形で社員に還元が可能になる。これは経営の健全性を守ると同時に、社員にとっても「成果が報われる」実感につながる。
中期的な利益計画と結びつける
1年単位の感覚で昇給や賞与を設計すると、突発的な業績変動に対応できない。最低でも3年のスパンで利益計画を立て、その中で人件費の成長率を見込むことが重要だ。こうすることで、長期視点での人材育成・配置と、給与体系の整合性が保たれる。
社員にどう伝えるか ― 決算書公開のすすめ
どれだけ戦略的な給与設計をしても、それを社員が理解していなければ意味がない。
わかりやすくかみ砕いて共有する方法
決算書をそのまま見せても、社員の理解は進まない。大切なのは、「売上がこうなれば、給与はこうなる」「利益が出れば、賞与も出せる」というロジックを、図解やストーリーベースで伝えることだ。たとえば、「100万円の売上から◯万円の原価が引かれ、残った△万円の中から給与が出る」と説明するだけでも、社員の理解度は格段に上がる。
数字をオープンにすることで納得感と主体性が生まれる
情報を閉ざすと、不信感が生まれる。逆に、数字を開示することで社員は「どうすれば利益が出るのか」「自分たちの給与がどう決まっているのか」を理解し、自律的な行動をとるようになる。これは単なるモチベーションアップではなく、経営参加意識の醸成にもつながる。
会社の成長と給与を結びつけるストーリー
「給与は会社の成長と連動して上がっていく」というストーリーを社員に浸透させることが、納得感を醸成するカギになる。「利益が上がれば、昇給・賞与に反映される」「赤字ならば調整が必要」というルールを明文化することで、経営と社員の間に健全な信頼関係が生まれる。
実践に向けたステップ
理論だけではなく、現場で実践できる形に落とし込むことが重要である。
経営者自身が数字のつながりを理解する
まず経営者自身が、売上・粗利・利益・人件費の関係性をしっかり理解しなければならない。顧問税理士や信頼できるIT・会計顧問に相談しながら、自社の財務構造を把握するところからスタートしよう。経営者が理解しなければ、社員に説明できるはずがない。
社員向け勉強会や社内資料の工夫
社員全員に決算書を読めるようにする必要はないが、「給与はどこから出てくるのか」「会社の利益構造はどうなっているのか」についての社内勉強会は非常に有効である。図解資料や動画など、ITを活用したコンテンツ作りも有効だ。

給与ルールをシンプルに文書化する
昇給の条件、賞与の算出方法などを明文化することで、属人性を排除できる。これは経営の説明責任を果たすと同時に、社員にとっても安心材料となる。シンプルな1枚資料から始め、徐々に内容を充実させていけば良い。
継続的に見直し、透明性を高める
給与制度は一度作って終わりではない。毎年見直しを行い、実態に合っているか、経営状況と齟齬がないかをチェックすることが重要だ。定期的な社内共有と意見収集を通じて、透明性と納得性を高めていくことが望まれる。
まとめ
給与の決め方を見える化することで、経営と社員の間に信頼と一体感が生まれる。数字に基づいた給与設計は、経営の健全性を守るだけでなく、社員のモチベーションを引き出す武器にもなる。まずは、売上と利益、そして人件費のつながりを正しく理解すること。そこから小さく始め、情報を共有し、制度を整えていくことで、組織は着実に強くなる。すべては「仕組み」と「対話」から始まるのである。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。