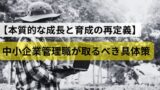中小企業の経営者が口にしがちな「俺の会社」。これは単なる口癖ではなく、経営の意思決定や組織文化、社員の士気に深く影響を及ぼす“経営上のリスク”である。創業者であること、資金を投じたこと、すべての責任を背負ってきたこと…その積み重ねが「会社=自分」という意識を育てる。しかし法律的にも、経営的にも、会社は社長個人の所有物ではない。この記事では、法人格の本質や「所有と経営の混同」が生む弊害をやさしく解説しながら、より健全で持続可能な組織運営のヒントを提案する。中小企業の経営者や管理職の皆さんに向けて、“自分視点”から“法人視点”へと認識をアップデートするきっかけを届けたい。
なぜ社長は「俺の会社」と言いたくなるのか?
中小企業の経営者が「俺の会社」と言う背景には、深い理由と積み重ねがある。それは自然な感情でもあるが、無意識に混同が起こることで、組織にひずみを生むことも少なくない。
資金投入・創業・苦労の積み重ねが“心理的所有感”を生む
創業時に自己資金を投じ、借金の保証人になり、売上ゼロの中で社員に給料を払い続けた。こうした苦労を知る人は社長以外にいない。だからこそ、会社に対して強い“心理的な所有感”を抱くのは当然である。この所有感は、経営への責任感や覚悟を生む原動力になる一方、行きすぎれば「会社=自分」という思考に至る。その結果、経営判断が独善的になりやすく、組織の多様性が失われてしまう。
「会社=自分の延長」と錯覚しやすい中小企業特有の事情
社員数十名の企業では、社長の存在感が絶対的だ。社長が行けば案件が取れ、社長が去れば取引が止まる。こうした環境下では、「会社は俺そのもの」という感覚になりやすい。しかしこれは中小企業特有の“錯覚”にすぎない。実際には法人としてのルールと枠組みの中でしか会社は存在せず、いかに社長であっても個人と法人は明確に分けられるべき存在である。
所有感そのものは悪くないが、混同が起こると組織を壊す
「俺がここまで育てた会社だ」という感情は否定するものではない。それ自体は経営者の誇りであり、モチベーションでもある。ただし、それが「俺の好きなようにやって当然」「社員は黙ってついてくればいい」という思考につながった瞬間、組織は崩れ始める。つまり、心理的所有感は“使い方”次第で、毒にも薬にもなるということだ。
法人は“人”である——法律上の大原則
会社はただの箱ではない。日本の法律では、法人には「人格」が与えられており、社長個人とは別の存在として扱われる。この大原則を理解することが、成熟した経営への第一歩となる。
法人格は社長とは別の独立した“人格”である
株式会社を設立すると、登記を経て法人格が与えられる。この瞬間、会社は法律上の「一人の人」として扱われるようになる。つまり、社長は会社の“代表”ではあっても“本人”ではない。これは中小企業においても例外ではなく、「会社のために」と考えるならば、まずその独立性を認識する必要がある。
「作った=所有」にはならないのは、子どもと同じ構造
自分で会社を作ったからといって、それを「所有する」とは言えない。これは親と子の関係に似ている。親は子を産み育てるが、子どもは親の所有物ではない。会社も同じで、創業者の貢献や影響力がどれだけ大きくとも、会社は会社として独立して存在する。所有ではなく“関与”という視点を持つことが重要だ。
会社を所有物と誤認すると起こる3つの経営リスク
- 社員が“使用人”に成り下がる
- 経営判断が独裁化し、反対意見が出なくなる
- 承継やM&Aの妨げになる
会社を「自分のもの」と思い込むことで、社員との対話が減り、組織は“トップの命令待ち”になる。これでは優秀な人材は定着せず、組織の継続性にも悪影響が出る。
「俺の会社」思考が生む組織の歪み
所有感が暴走すると、経営のスピードは上がるかもしれないが、組織としての成長は止まる。なぜなら、“社長の器”が組織の限界になるからだ。
社長の“器”以上に会社が大きくならない理由
「俺が決める」「俺がやった方が早い」——このような思考では、いくら売上を伸ばしても組織の器は広がらない。会社の成長は、社長の器を超える人材の活躍に支えられてこそ実現する。だが、「社長=会社」という誤認識がある限り、その器は広がることはない。
社員が自発的に動かなくなる構造
命令がすべてになると、社員は指示待ち人間になる。自分で考え、提案し、実行する力が育たない。これは「指示されたことはやるが、それ以上はやらない」という文化を生み、結果として組織の停滞を招く。
優秀な人材ほど静かに離れていく現象
成長意欲が高く、視座の高い人材ほど、トップの独善に耐えられない。議論ができず、意思決定に関与できない会社に未来を感じることはないからだ。離職の理由は語られなくとも、「社風が合わない」「成長機会がない」といった言葉で、優秀な人材は静かに去っていく。
「所有の論理」から「経営の論理」へ——成熟した社長はここが違う
会社を“自分の器”と捉える限り、組織は限界を迎える。法人を“社会の器”と捉え直すことで、経営は新たなステージへ進む。
会社は“みんなの器”という発想に変える
会社は社員、顧客、地域社会、取引先など、さまざまな関係者によって成立している。“みんなの器”として捉えることで、意思決定も、組織運営も、より調和的かつ合理的になる。これは中小企業こそ必要な視点だ。
社長は“オーナー”ではなく“器の拡張者”
会社を大きくするとは、単に売上を伸ばすことではなく、“この器をどれだけ多くの人が使いやすい状態に整えるか”である。器の壁を壊し、広げていくのが社長の仕事であり、それができる人こそが次のステージに進める経営者である。
法人を人格として扱える社長ほど社員に信頼される
会社を一人の人格として扱う——この考えを持てる社長は、社員に対してもフェアでいられる。自分の感情や好き嫌いで判断せず、“会社の人格ならどうするか”という視点が信頼を生み出す。
会社を“自分以外の存在”として認識できる人が組織を伸ばす
会社を自分と切り離して認識することができた時、初めて「自分以外の視点」で経営ができるようになる。これが、組織が自律的に動き出す第一歩であり、社長が“手放す勇気”を持てるかどうかがカギとなる。
明日からできる「俺の会社」から脱却する実践ステップ
行動は小さくても、視点が変われば会社は確実に変わる。ここでは、経営者がすぐにでも実践できるステップを紹介する。
「俺」ではなく「私たち」に言い換える習慣
まずは言葉から。「俺の会社」ではなく「私たちの会社」「うちの会社」という表現を使うことで、自然と視点が広がる。小さな言い換えが、社内文化の変化を生むきっかけになる。
会社の意思決定に“第三者視点”を入れる
経営判断を行う際には、「顧問税理士」「社外取締役」「IT顧問」など外部の第三者視点を入れることで、“俺だけの判断”から脱却できる。特に「IT顧問のススメ」にあるように、専門家のアドバイスが経営判断を支えるケースは多い。
会社の目的と価値観を“法人の価値”として明文化する
会社の存在意義、価値観、目指す未来像を言語化することで、法人としての「人格」が明確になる。「中小企業に必要なリーダーシップの土壌」でも指摘されているように、価値観の共有は組織文化を形成する要である。
社員との対話で“会社は誰のものか”を再定義する
「会社は誰のものか?」を問いかけるワークショップや対話の場を持つ。答えは一つではなくても、この問いを持つことで社員との距離感が変わる。対話が会社の輪郭をつくるのだ。
外部の専門家・幹部の意見を取り入れる制度を作る
定例の経営会議に幹部や外部パートナーを参加させ、意思決定を共有化する仕組みを構築する。これにより、社長一人の「感覚経営」から脱却し、組織としての判断力が養われる。
まとめ——会社を“所有物”から“共に育てる存在”へ
組織を育てる視点が、経営の質を変える
会社を「俺のもの」と考えている限り、組織は社長の限界以上に成長しない。それはガラスの天井であり、見えない制限である。
法人格への理解と尊重が、成熟した経営のスタートライン
会社を“人格”として扱うことで、社長の意思決定が洗練され、社員との関係もフラットになる。法人格の尊重こそ、真の経営者への第一歩だ。
会社は“あなたの作品”ではなく“社会に属する器”である
会社は社長の情熱から生まれたかもしれないが、成長していく中で、多くの人に支えられ、社会と接続されていく。だからこそ、「俺の会社」ではなく「社会の器」として、共に育てていく存在でなければならない。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。