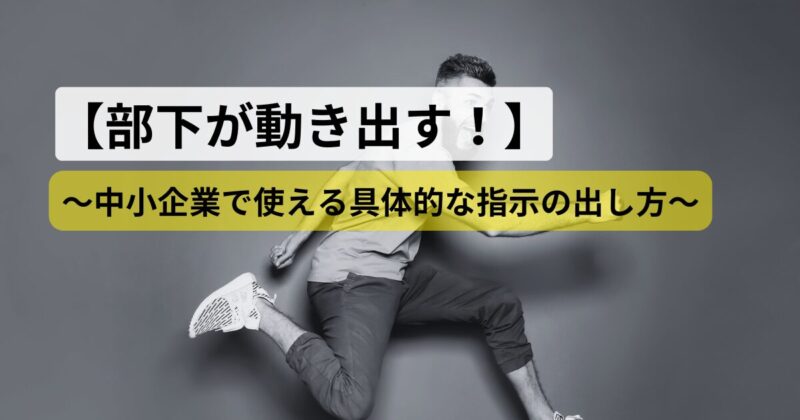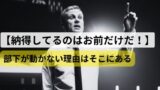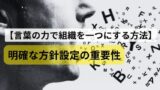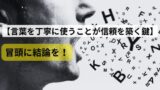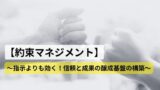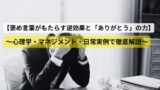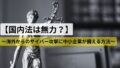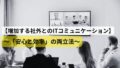「ちゃんと伝えたはずなのに、なぜ動いてくれないのか?」中小企業の経営者や管理職がよく抱えるこの悩み。その背景には“指示の出し方”に潜むズレがある。前回の記事「上手な指示 指示の正しい認識」では、スタンスや責任の持ち方といった基本的なマインドを解説したが、今回はより実践的なテクニックに踏み込む。明日から現場で使える「指示の型」「心理的配慮」「NGワード」「組織に定着させるための工夫」を事例とともに詳しく紹介していく。
なぜ「ちゃんと伝えた指示」が伝わらないのか?
どれだけ丁寧に伝えたつもりでも、相手が意図通りに動いてくれない──。この問題は、指示する側の「伝えたつもり」と、受け取る側の「わかったつもり」の間に横たわる“認識のギャップ”が原因である。そしてこのギャップの正体を突き止めなければ、いくら指示の出し方を工夫しても、成果にはつながらない。

本章では、伝わらない指示の根本原因を3つの視点から深掘りし、どうしてそのズレが起きるのか、心理・構造・現場実態から徹底的に解説する。
言葉の抽象度がズレる瞬間
─ 同じ日本語でも「意味」がズレて伝わるのはなぜか?
経営者や上司は「今週中に資料をまとめておいて」と言う。
この指示を受けた部下は「金曜の午後までに、概要をざっくり固めておこう」と考える。
ここでのズレは、「抽象度」の差によって起きている。指示する側は、背景や意図をすでに把握しているから、「資料をまとめる」と言えば、どんな体裁で・どこまで完成度が必要かを自分の中で明確にイメージできている。しかし、受ける側はその前提がない。ゆえに、自分なりの常識・感覚で解釈するしかないのだ。
たとえば、「丁寧にやってね」と言えば、「ミスしないように気をつけること」と捉える人もいれば、「時間をかけてゆっくり取り組むこと」と理解する人もいる。「急ぎで」と言えば、「今日中」だと解釈する人もいれば、「なる早で動き出せばOK」と考える人もいる。
つまり、言葉自体が問題なのではなく、その言葉が指す“意味の幅”が広すぎることが問題であり、その幅を埋める努力なしに「ちゃんと伝えた」は成立しない。
なぜこのズレが生まれるか?それは、「自分と同じ知識・経験・前提を持っているはず」という思い込みにある。言い換えれば、「相手も自分と同じ理解をするだろう」と思ってしまう、無意識の過信こそが指示をズラす最大の原因だ。
伝えた側と受けた側の「前提条件」の違い
指示をした瞬間に“見えてる景色”が違っている
「とりあえずやってみて」「まず動いてみて」──これらの言葉が危険なのは、言葉の抽象性だけでなく、その背景にある前提の食い違いにある。
たとえば、「業務改善を目的とした提案書を作って」と指示したとしよう。
上司は、「現場の無駄を洗い出して、改善案を提案するもの」という前提で話している。
一方、受け手は「今やっている作業をもっと早く終わらせる方法を考えればいいのか」と捉える。
結果、部下は「現状を効率化するだけの提案」を仕上げてくるが、上司は「抜本的な改善案がない」として突き返す。部下は「言われた通りやったのに」と落胆し、指示者は「話が伝わってない」と嘆く。このすれ違いは、どちらが悪いのでもない。
“伝える前に共有すべき背景”を省略したことが、ズレを生むのだ。
なぜこのような前提のズレが起きるのか?その根本原因は、「上司は背景を知りすぎていて、説明が不要だと錯覚してしまう」ことにある。要は、知っている人ほど説明を端折るのである。これは“知識の呪い”とも呼ばれ、経験豊富な上司ほど陥りやすい落とし穴だ。
だからこそ、指示を出す前には一言、「なぜこれが必要なのか」「この仕事は何のためにやるのか」といった背景を共有することが、指示を成立させる“接続詞”になる。
「報告しろ!」では動かない部下の心理
─ なぜ指示をしても部下は報告してこないのか?
「ちゃんと報告しろって言ってるだろ!」──この言葉は、現場でよく聞かれる叱責だ。しかしこの叱責の裏には、部下の“心理的ブレーキ”があることを忘れてはならない。
部下はなぜ報告を避けるのか?
多くの人が抱えているのは、「今の状態で報告したら怒られるかもしれない」「まだ完成していないのに言うのは迷惑かもしれない」という“評価への恐怖”である。

とくに中小企業の現場では、「報告=結果報告」と思い込んでいる若手も多い。
「中間報告していい空気」が作られていなければ、彼らは“完成していない=報告しちゃダメ”という思考になってしまうのだ。
また、上司の反応が一貫していない場合も、部下は報告をためらう。「前回は“早く教えてくれ”って言ってたのに、今回は“そんな中途半端で何を言ってるんだ”と怒られた…」という経験があると、「結局、どうすればいいのか分からない」→「なら黙っておこう」という心理が生まれる。
報告が来ない原因を「部下のやる気の問題」にすり替えてはいけない。
むしろ、「報告しやすい雰囲気をつくってこなかった指示者側の責任」として捉えるべきだ。
「うまくいってなくても、状況を知りたいだけだから安心して話してね」というスタンスが伝われば、報告は自然と上がってくる。
報告は命令するものではなく、「安心して情報を共有できる関係性を築くもの」である。
これを忘れると、「報告しろ!」は、逆効果の圧力にしかならない。
この3つのズレ──
- 言葉の抽象度の違い
- 前提知識の違い
- 心理的ハードルの違い
これらが組み合わさると、「伝えたつもりが伝わらない」という典型的なすれ違いが生まれる。
「伝える」ことは、「声に出す」ことではない。「同じ景色を見せる」ことこそが、指示の本質なのである。
上手な指示の“型”を持てば現場は動く
上手に動かす指示とは、感覚で出すものではなく、再現可能な“型”がある。ここでは3つの方法を紹介する。
「5W2H」を現場にフィットさせるには?
Who(誰が)、What(何を)、When(いつ)、Where(どこで)、Why(なぜ)、How(どうやって)、How much(どのくらい)….。この7項目を意識するだけで、指示は圧倒的に明確になる。
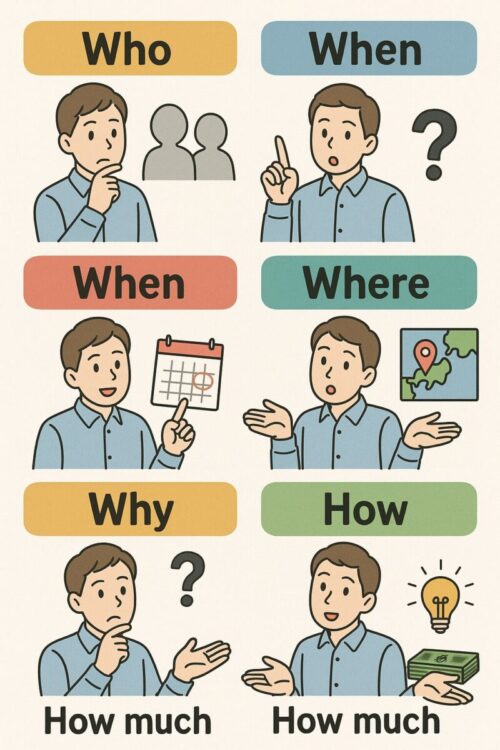
例:「金曜日18時までに(When)営業の田中さんが(Who)B社向けの提案資料を(What)メールで(Where/How)送る。その目的は、週明けの商談で活用するため(Why)」。このように情報を整理すると、認識ズレは激減する。
単純で馬鹿げているようで…今更こんなん言われんでも…ということかもしれないが、現実的に具体的かつ明確に指示をしていることは極めて少ないのだ…面倒…手間…と、思えるかもしれない。ちょっとした気遣い?…これも違う、顧客のために質の高いアウトプットをするためのことだ。ここに好き嫌いも感情も面倒もない。
抽象語を避けて「行動に変換できる言葉」で伝える
「ちゃんとやって」「もう少し丁寧に」「臨機応変に対応して」…これらは曖昧さの代表格。受け手が「何をどうすればいいのか」が分からなければ、行動にはつながらない。代わりに「チェックリストの2番までを10分以内に確認」「名刺交換したら30分以内にメールを送る」など、動作と条件をセットにする言葉が効果的だ。
確認の習慣 ― 受け手に“復唱”させるテクニック
指示が伝わったか不安なら、復唱が最も確実な確認方法である。たとえば「じゃあ、今の内容を30秒でまとめてみて」と言えば、相手がどこまで理解しているかが明確になる。この復唱は、「あなたを信頼しているからこそ確認している」という姿勢で行うのがポイントである。
人を動かす指示の心理テクニック
心理的な納得感を生むことで、指示の実行率は格段に高まる。次に挙げるのは、そのための具体的な方法である。
「やらされ感」を消す問いかけ型の指示
「〜してくれると助かるんだけど、どう思う?」という問いかけ形式にするだけで、受け手の心理は能動に切り替わる。「言われたからやる」から「自分が納得してやる」に変わるこの形式は、特に若手社員に有効だ。
期限は“数字”で伝え、安心感は“言葉”で補う
「できるだけ早く」ではなく「●日(金)18時までに」と明示し、その上で「急ぎだけど、無理そうなら早めに教えて」と補足する。この一言で「プレッシャー」から「信頼」へと印象が変わる。期限を明示することが信頼感を生む。
小さな約束を積み重ねて信頼を育てる
日常の小さな指示こそ、指導力を育てるチャンスである。たとえば「来週の会議で5分だけ報告してくれる?」という軽い依頼から始め、それを守ってくれたら「ありがとう。助かった」とフィードバックする。これを繰り返すことで、信頼関係が構築され、次第に大きな仕事を任せられるようになる。
経営者・管理職が避けるべきNG指示集
意図していなくても、部下を混乱・萎縮させる指示がある。以下は特に避けたい表現だ。
「とりあえず」「いい感じで」などの抽象表現
「とりあえず始めておいて」「いい感じでまとめておいて」…これらは指示ではなく、混乱のもとである。具体性がなければ、判断が属人化し、成果物もバラバラになる。「まずは3件の事例を調べて」「A社とC社の見積書を比較して」など、明確なスタート地点を提示すべきだ。
報告の丸投げ「ちゃんと見ておいて」
「報告しといて」や「後で教えて」は、責任の所在が不明確になる典型例である。報告のフォーマット、期限、形式(口頭/メール/資料)を指示せずに「報告しろ」と言っても、伝わるわけがない。
【文章化できない病が組織を蝕む】でも示したた通り、「口頭だけでは情報の正確性が保てない」ため、書面での明確な指示が不可欠である。
責任の転嫁「結果はお前に任せた」
「任せたぞ」の裏に、「失敗したら自己責任」という空気が漂うと、部下は萎縮する。「やってみて。結果は一緒に検証しよう」という伝え方に変えるだけで、責任の押し付けではなく支援の意思が伝わる。
組織に定着させる“伝え方改革”のすすめ
指示の質は、個人スキルではなく組織文化として育てていくべきだ。ここではそのための仕組みづくりを紹介する。
共通の「指示フォーマット」を作る
指示を受けた際に「誰が、何を、いつまでに、どうやって」を記録するテンプレートを用意し、SlackやLINEなどで簡単に共有できる形にする。これにより、「聞いた・聞いていない」問題はほぼ解消される。定型フォーマットは、一見…面倒で柔軟性を欠くと思われるかもしれないが、思考を定型化させることについては有効であり、組織の業務として定着しやすくなる。指示や報告が主観的であっては、それはもはや情報共有とは言えないだろう。
ミーティングで「指示の理解度チェック」を習慣化する
会議の最後に「今日のタスクを1人ずつ口頭で確認する」だけで、理解のズレはかなり防げる。これは【任せる勇気が経営を変える】で提案した「確認ではなく対話で信頼を構築する」と共鳴する実践策である。
経営者が率先して「伝え方を改善する姿勢」を見せる
「部下が動かない」と嘆く前に、自らの指示の出し方を点検しよう。日々の業務の中で「今の指示、分かりづらかったら遠慮なく言って」と伝えるだけで、チームの空気はガラリと変わる。トップが変われば、現場も変わる。
まとめ:指示は「伝え方」で未来を変える
「言ったはず」が通用しないのが組織のリアル。だからこそ、伝え方にこだわるべきだ。今回紹介した指示の型、心理的テクニック、NGワードの回避、定着の工夫…これらはすべて、組織を動かすための“伝え方の武器”である。
中小企業における人材育成や業務効率化は、突き詰めれば「伝え方」に帰着する。適切な指示を通じて、個人の能力を引き出し、組織全体の力に変えていく。そのためには、経営者自身が最初に変わる覚悟が必要である。
明日から始めよう。変化は小さな一言から起こせる。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。