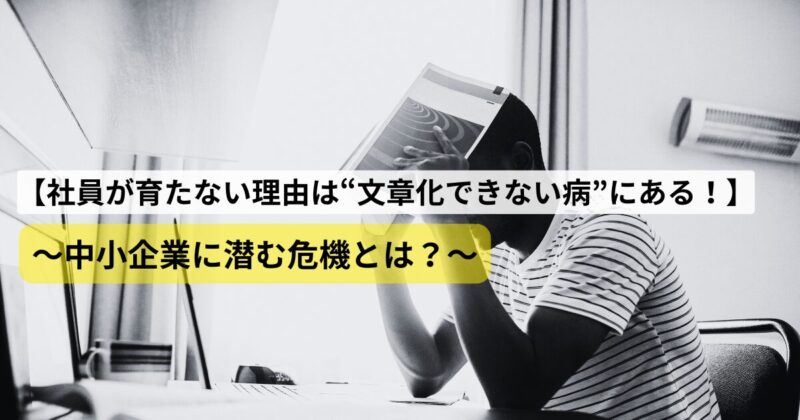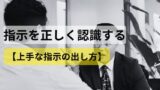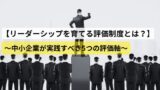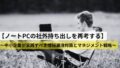中小企業の経営者が抱える悩みとして、「社員が育たない」「指示が通じない」「報告が曖昧」といった課題は定番である。しかし、その原因を「やる気」や「能力不足」と片付けてはいないだろうか。実は、こうした問題の根本には“文章化できない病”という、言語化能力の欠如が潜んでいる。
報告書、議事録、提案書、ToDoの整理すら満足に書けない人材が増えており、それが組織の停滞を生んでいる。本稿では、「社員がなぜ育たないのか?」を文章化スキルの観点から掘り下げ、中小企業が直面する見えざる経営リスクを明らかにする。
社員が育たない原因は「文章化できない病」にある
文章化能力が低い社員が組織に与える影響は小さくない。特に中小企業では一人ひとりの生産性が売上に直結するため、文章力=業績に直結する構造になっている。
文章にできない=理解できていない
指示を受けた社員が「はい、わかりました」と返事をする。しかしその仕事の締切を問うと答えられない。やるべき作業の優先順位を説明させても曖昧。このようなケースは、「実は理解していない」か「理解したつもりになっている」状態が多い。これは文章化能力が低いために、頭の中で情報を整理・構造化できていないから起きる現象だ。理解力と思考力の弱さが、そのまま文章化できないという形で表面化している。

また、近年の若者世代においては、活字に触れる時間が極端に減っていることも深刻な要因である。例えば、LINEやSNSでのスタンプ文化の普及により、感情や意図を「絵」で済ませる習慣が定着しつつある。「了解」を「り」などと省略するやり取りも一般化し、文章としての“構築”を経ずに意思疎通を行う風潮が強まっている。加えて、ニュースも新聞や記事よりも、LINEニュースの見出しや、YouTubeの解説動画で得るスタイルが主流化し、言語を読み、考え、再構築する機会そのものが失われつつある。これらの言語環境の変化が、“文章化できない病”を無意識に助長しているのは間違いない。

報連相が曖昧な社員はリスクとなる…
報告・連絡・相談が苦手な社員には共通して、状況説明を文章にできないという傾向がある。「とりあえずやってみました」「あの件は進めてます」といった表現では、具体的な進捗や課題は一切見えてこない。こうした報告の質の低さは、経営判断を誤らせるリスク要因となる。社員が状況を正確に文章で伝える力を持っていなければ、マネジメントは常に「感覚と勘」に頼ることになる。
文章化できないと育成ができない構造
新人や若手社員に「業務の目的」や「改善提案」を文章でアウトプットさせると、その内容で彼らの理解度や成長度が可視化される。だが、文章化を避ける社員は、考えることから逃げている場合が多く、育成のステップすら踏めない。「何を考えているかわからない人材」は、指導のしようがなく、育たないのは当然なのである。
組織に蔓延する“口頭依存”の風土とその弊害
中小企業にありがちな「直接話したほうが早い」というカルチャーが、文章化能力の育成を阻んでいる。これは業務の属人化や情報の断絶を招き、組織のボトルネックとなる。
経営者も文章化から逃げている
「言わなくてもわかるだろう」「前に説明したはずだ」――これは経営者がよく使う言葉だが、社員にとっては迷惑極まりない。伝えたつもりでも、相手は受け取っていない。文章で残さない指示や理念は、あっという間に忘れられる。経営者自身が率先して文章化する姿勢を示さなければ、社員にそれを求めても効果はない。
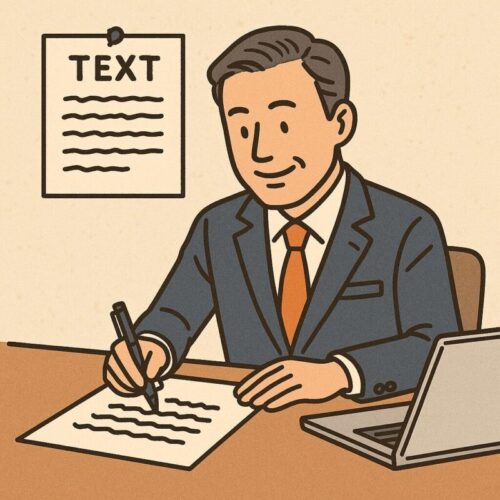
会議で話した内容が「なかったこと」になる
議事録を残さない、残しても誰も読まない、読んでもアクションに反映されない――このような会議は「時間の浪費」でしかない。文章にしない情報は、共有されないし、責任の所在も曖昧になる。言った言わないのトラブルも発生し、社内に不信感を生む。

属人化を助長し、ミスの再発を招く
口頭で伝達された業務は、誰かが不在になるだけで再現性が失われる。「あの人しか知らない」「この仕事は○○さんに聞かないとわからない」といった状態は、文章化による情報共有がされていない証拠だ。これは人に依存した脆弱な組織であり、業務効率の大きな阻害要因である。
中小企業が取り組むべき文章化能力の底上げ施策
文章化できる組織は、情報の精度・判断の速さ・属人性の排除という観点から圧倒的に強い。では、どうやってその文化を社内に浸透させるべきか。
文章化を「義務」ではなく「習慣」にする
報告書・議事録・提案書など、日常的なアウトプットに文章化を組み込む。これを「ルール」ではなく「文化」にまで昇華させるためには、上司や経営者自らが率先して文書で残すことが重要である。「○○さんの報告は読みやすくて助かる」と評価するだけでも、社内の文章力は確実に底上げされていく。
書き方のテンプレートと教育制度を整備
「文章が苦手」という社員の多くは、「書き方がわからない」だけである。提案書や報告書のテンプレートを整備し、全社で共通化することで「何を書くべきか」を明確にできる。また、社内研修でメールの書き方、箇条書きの整理術、PREP法などの基本的な文書作成スキルを習得させることも有効だ。

必要な要素を入力することで、文章化はAIが担うという仕組みの導入も効果的だろう。本人の文章作成スキルの向上は願ってもないことだが…文章で共有する仕組みを根付かせ、それを機能させることで効果を実感してもらうことが第一歩だろう。
言語化力のある人材を評価対象に含める
成果主義が強すぎると、「書く力」や「伝える力」は軽視されがちになる。だが、情報共有やマネジメントにおいてこの能力は極めて重要であり、組織全体のパフォーマンスに影響する。社内で言語化力に優れた人材を「可視化」し、その価値を評価する制度設計が必要である。
まとめ:文章化は中小企業にとって“見えない競争力”である
社員が育たない理由を「能力不足」や「やる気のなさ」として切り捨てる前に、文章化能力という観点から組織を見直すべきだ。文章にできないというのは、思考が未成熟である証拠であり、それは育成の初期段階を超えられていないことを意味する。
中小企業が強い組織を作るには、まず「書ける人材」を育て、「残す文化」を作ることである。それこそが、指示が通る組織、育つ社員、強い経営体質を育む土台となる。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。