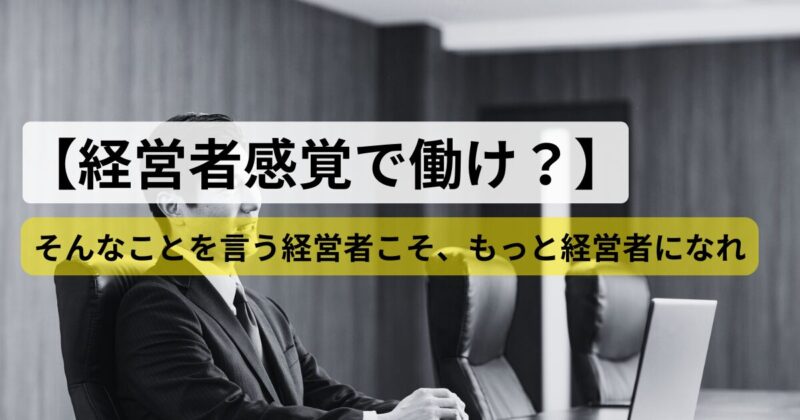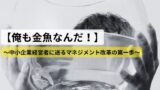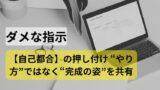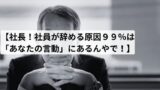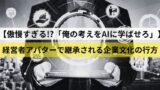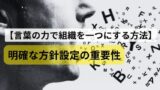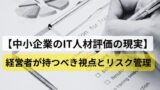中小企業の経営者が口にしがちなフレーズに「もっと経営者感覚をもって仕事をしてくれ」といったものがある。この言葉には一見「経営視点をもって主体的に判断して欲しい」という意図が込められているようだが、実はこの発言そのものが経営者の未成熟さを露呈しているケースが少なくない。
「経営者感覚を持て」と部下や社員に言う前に、まずは自らが本当の意味で“経営”に向き合っているかを問うべきだ。本稿では、経営者感覚という曖昧な表現がいかに現場を混乱させ、本来果たすべき経営者の責任から逃避するための口実になっていないかを掘り下げていく。「経営者感覚」という言葉の誤用・誤解が引き起こす問題を明らかにし、真に求められる経営視点とは何かを論理的に整理する。
経営者感覚の押し付けが招く組織の混乱
「経営者感覚で仕事をしろ」と言うことの本質と問題点

「経営者の立場で考えて」は、責任の放棄にすぎない
経営者が社員に向かって「もっと経営者感覚をもってくれ」と言う場合、その真意はどこにあるのか?多くは「利益を意識して行動しろ」「ムダなコストをかけるな」「原価を抑える工夫をしてくれ」といった要求だ。

しかし、これは一見、合理的な指示のようでいて、実は責任の押し付けになっているのでは…疑問を禁じ得ない。経営者でない社員に「経営者のように考えろ」と言うのは、経営者が自らの責任や判断を曖昧にし、あたかも社員が未成熟だから成果が出ないかのようにすり替えているだけだ。社員は自分の権限の範囲内で最善を尽くすべきであり、経営者と同等の判断を期待するのは筋違いである。
現場は顧客に近く、経営者は現場から遠い
「経営者感覚」として語られるものは、実際には現場と顧客から離れた経営層の視点に過ぎない。一方、現場の社員こそが顧客の本当の声を聞き、日々の対応を通じてサービスを磨き上げている。
ならば「お客様の立場になって考えろ」と伝えるほうが、よほど的を射た助言である。顧客満足を徹底して追求する現場社員を支え、その障害を取り除くのが経営者の務めであり、逆に「経営者の立場で考えろ」とは、現場を理解しない経営者の無責任な発言でしかない。
経営者感覚とは「俺の苦労をわかってくれ」という甘え
「経営者感覚を持ってほしい」という言葉の裏には、「俺の苦労を理解してくれ」という感情が透けて見える。要するに、自分がどれだけ苦労して判断しているかを理解して欲しいという自己中心的な願望だ。
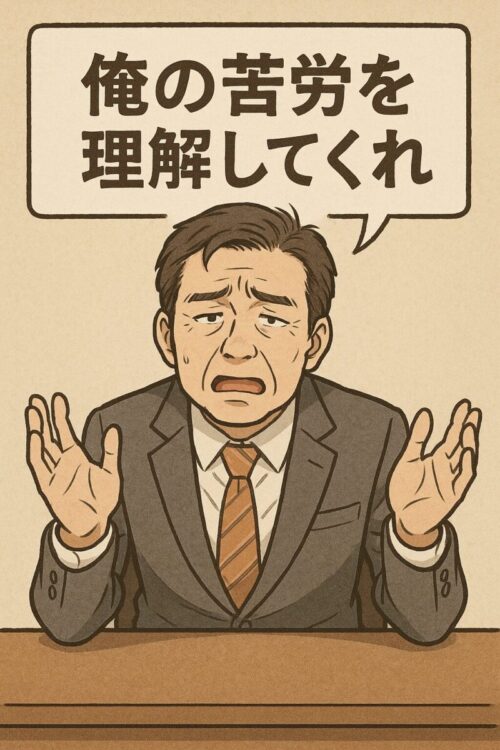
しかもそれを、あたかも高尚なビジネス的発言かのように「経営者感覚」という言葉で包み込む。このような発言は、経営者が自らの感情を言語化できず、無意識のうちに責任転嫁している証拠だ。経営とは感情ではなく、ロジックと意思決定の連続であり、「感覚」でやるものではない。

経営者とは何か?本来の責務とその重み
経営者感覚ではなく、経営者の仕事を果たしているかを自問せよ
権限の範囲で判断し、責任を持たせることが信頼
現場の社員に必要なのは「経営者のように振る舞う」ことではなく、自らの役割と権限の範囲で最善の判断をすることだ。
逆に、経営者がすべきなのは、社員が判断に迷わないようルールと責任の所在を明確にすること。権限の範囲を超える場合は報告・決裁の仕組みが機能すれば、ミスも統制も取れる。経営とは、適切なガバナンスを構築することであり、経営者感覚でなんとなく任せてはいけない。
判断の重みは「責任を負う覚悟」にある
経営者の立場とは、単なる判断者ではなく、結果に対して全面的な責任を負う者のことだ。「経営者感覚」としてあれこれ考えるのと、実際に経営責任を背負うのでは天と地ほどの差がある。
原価を削減した判断が顧客満足を損ねるかもしれない。納期優先の仕入れが結果的にコスト増につながるかもしれない。そのすべてに責任を負うのが経営者である。社員に同じ感覚を求めるなら、極論ではあるが、同じ責任と報酬も与えなければ不公平だ…という心情にならないか…熟考がが必要だ。
経営者の使命は社員の挑戦を支援すること
社員が工夫し、コスト削減や業務改善を目指すとき、それを「経営者感覚があって素晴らしい」と評価するのは良い。しかし、それをやらなかった社員に対して「経営者感覚がない」と責めるのは間違いだ。
情報が足りない、判断基準が曖昧、あるいは動機が不明確であることが原因であれば、それを整えるのが経営者の役割である。経営者の仕事とは、社員が正しく判断できるよう、材料と環境を整えることに他ならない。
社員に求めるべきは「経営者感覚」ではなく「顧客志向」
現場からの価値創出こそが企業の競争力を生む
顧客の視点で考える力を育てよ
企業の存在意義は「顧客の課題を解決すること」にある。現場社員こそが最前線で顧客と接し、彼らのニーズや課題を直接感じている。
だからこそ、経営者が社員に求めるべきは「お客様の立場で考える力」だ。この力を持った社員が多ければ、商品・サービスの質が上がり、結果的に収益力も向上する。「経営者感覚」などという曖昧な概念より、よほど具体的で実践的な行動につながる。
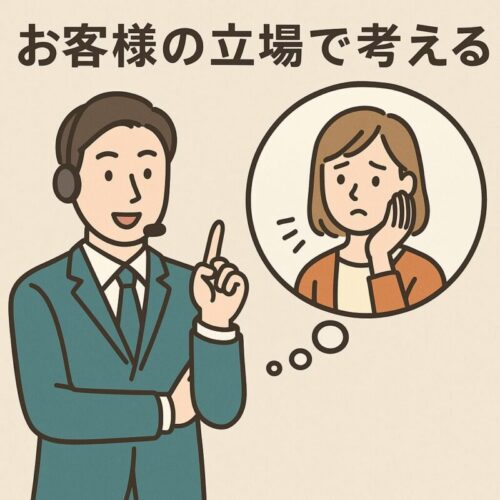
経営者は「現場の声の翻訳者」であるべき
現場の声をどう拾い上げ、どう意思決定に反映するかが、経営者の力量だ。社員からの意見や提案に耳を傾け、それを戦略的に活かすことで、企業は持続的に成長できる。経営者感覚という“主観”ではなく、現場の“事実”を重視する姿勢が信頼を生み、組織の方向性を整えることになる。
報酬と責任のバランスが行動を決める
社員がどれだけ「経営者感覚」で行動しても、それが自らの報酬や評価に反映されなければ意味がない…そう捉えられても仕方がないだろう。むしろ、徒労感を与える結果となる。
社員の行動に対しては、適切な報酬設計やキャリア設計をセットで考えなければ、本気の行動を促すことにはならない。インセンティブ設計は経営者の仕事であり、それができていないのに「経営者感覚が足りない」と言うのは、完全に責任転嫁である。
まとめ:経営者感覚を語る前に、まず経営者の責任を果たせ
経営者感覚という言葉は、時として経営者の未熟さと逃避の象徴になっている。本来、経営とは感覚で行うものではなく、責任ある意思決定と環境整備、そして組織を成長させるためのマネジメントである。
社員に「経営者感覚を持て」と言いたくなったときは、自分がどれだけ経営者としての責務を果たしているかをまず確認すべきだ。社員に求める前に、経営者自身が経営者として真摯に在ること。それこそが、組織を動かし、成果を生み出す本質なのである。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。