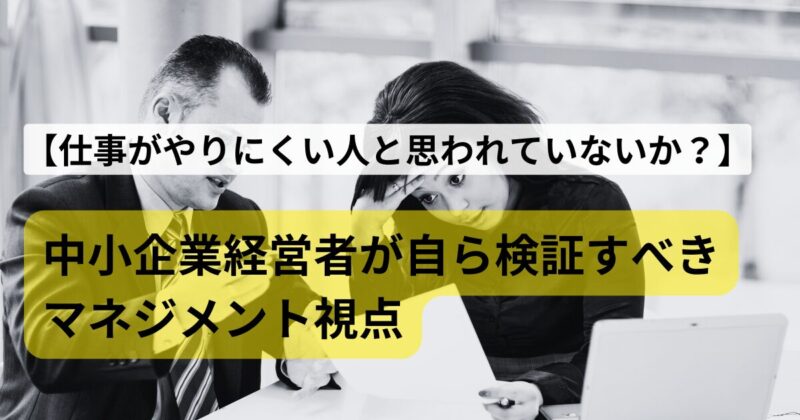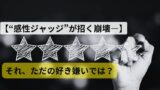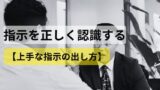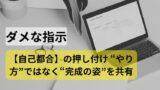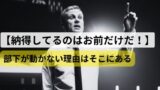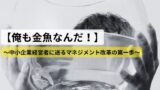中小企業の経営者向けに「自分自身が周囲から“仕事のやりにくい人”になっていないか」を検証する視点を提供する。経営者はマネジメントと業務推進の先頭に立つ存在であるが、完璧主義や厳格さが時にプレッシャーとなり、文字どおり“やりにくい”メンバーを生み出してしまうことがある。
一方で、自らの徹底した姿勢が“信頼されるプロフェッショナル”として評価される場合もある。本項では、仕事がやりにくい人のパターンを「良い意味」「文字どおり」「あるべき姿を追求する姿勢」の3つの観点で整理し、経営者が自らのコミュニケーションや意思決定を振り返るための具体的なヒントを示す。
プロフェッショナルとして「良い意味」でやりにくい人
仕事をともに進めるうえで堅実かつ厳格な姿勢は、成果の質を高め、信頼を醸成する原動力となる。しかし、その完璧志向は周囲にプレッシャーを与え、「やりにくい」と感じさせることもある。経営者として自身がこうした人物像になっていないか、ポジティブ/ネガティブ両面を俯瞰することが重要である。
妥協を許さない完璧志向
完璧を追求し、成果物の仕様や品質に一切の妥協を許さない姿勢は、品質担保の観点では最上級である。しかし、細部まで厳しく検証されることで、メンバーは「どこまで許容されるのか」「いつ評価が成立するのか」がつかみにくくなり、心理的な負荷を感じやすい。経営者自身、自らの基準や期待値を言語化し、適宜「ここまではOK」という明示的なガイドラインを示すことが求められる。
約束・期日を厳守する信頼感
経営者は期日・ルールを徹底し、合意どおりの行動を求めることで組織に秩序をもたらす。これは組織運営の基本であり、信頼を担保する要素でもある。しかし、抜けやミスを一切許さない空気が強くなると、メンバーは「失敗を恐れて動けない」「小さな判断も相談しないと先に進めない」と感じる。重要なのは「なぜそのルールがあるのか」を常に併記し、守るべき理由と例外判断のプロセスを共有することである。
明確な意思表示と迅速な決断
経営者の迅速で明快な意思決定は、組織に推進力と安心感をもたらす。ただし、配慮に欠けるストレートな表現や、社交辞令を忌避する姿勢は、「言葉がきつい」「配慮が足りない」と受け止められることがある。経営者としては、結論をはっきり伝えつつも、相手の立場や感情を意識した前置きやフォローを添えることで、効率と人間関係の両立を図るべきである。
文字どおり「やりにくい」人―本質を欠くコミュニケーション
一見正しく見えても、本質的な意味や目的を理解せず「手順だけを追う」「結論を示さない」コミュニケーションは、時間と労力の浪費を招き、結果として業務を停滞させる。本当に“やりにくい”のは、当事者間で共通認識が形成されず、何をすべきかがつかめない状況である。
結論や目的を示さない長話
会議や説明の冒頭で前置きが長く、本題に入るまで時間を要するケースが多い。たとえば製品やサービスの紹介で会社案内に15分を費やし、肝心の説明時間が不足するようでは本末転倒である。経営者自身、発言の前に「結論」「目的」「期待するアウトプット」を冒頭で示し、その後に背景を説明する「ピラミッド構造」のコミュニケーションを実践するとよい。
相手視点を欠く一方的な要求
必要書類の提出や手続きの指示を、相手の状況や背景を無視して行うと、「なぜ今それが必要なのか」「どのタイミングで出せばいいのか」が共有されず、混乱が生じる。経営者は指示の際に「この根拠」「相手が困りそうなポイント」「支援できるリソース」をセットで伝え、相手が適切に判断できる環境を整える必要がある。
理解不足のまま手順だけを追う
見積書・請求書などの事務処理は、形式よりも「なぜ」「いつ」「誰に」という本質的な意味を理解したうえで実行されるべきである。経営者は、ただ書類を通せばOKとするのではなく、それぞれの手順の意義を確認し、「何のために」「どのタイミングで」「どんな影響をもたらすのか」をメンバーに問いかける習慣を推奨すべきである。
「何のために?」を問い続ける習慣が信頼を生む
逆説的だが、「やりにくい」とネガティブに思われがちな人物像こそ、組織を強化し、信頼を醸成する可能性を秘める。本質を問うことで業務の抜本的な改善が進み、メンバーは共通の目的意識を持って動けるようになる。
本質的な問いかけで課題を見極める
経営者自身が常に「この施策は何を解決するのか?」「本当に必要なステップか?」と自問し、その思考プロセスをチームと共有することで、同じ視点で課題を捉えられるようになる。問いかけは業務の要・不要を判断する最高のフィルターである。
意味と目的を共有する意思決定
プロジェクトや新規施策の決裁時に、目的、期待効果、成功要件をキチンと文書化・口頭共有することで、メンバーは自律的に動きやすくなる。経営者の“やりにくいほど厳格な管理”は、実はメンバーにとって「何をすべきか迷わない安心感」を生む。
継続的な学びで信頼を築く
自分が知らないことを自覚し、積極的に学びを深める姿勢は、「この人は常に成長している」という信頼感を醸成する。経営者は決算書の利益構造や事務処理の本質を再確認し、メンバーとともに学ぶことを通じて、組織全体の理解度と信頼度を高めるべきである。
まとめ
「仕事がやりにくい人」という評価は、一見ネガティブに思えるが、内容を紐解けば「信頼される人」「学びを促す人」「成長を支える人」と同義である場合が多い。中小企業の経営者として目指すべきは、人に好かれることではなく、組織にとって必要不可欠な存在と認められることである。
そのためには、自らのコミュニケーションや意思決定スタイルを定期的に振り返り、「完璧志向」「厳格なルール運用」「本質への問いかけ」の三つの観点でバランスを調整することが重要である。ネガティブに思われる要素を「成長のきっかけ」と捉え直し、メンバーとともに学び続けることで、真の信頼と成果を手に入れられる組織を築いてほしい。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。