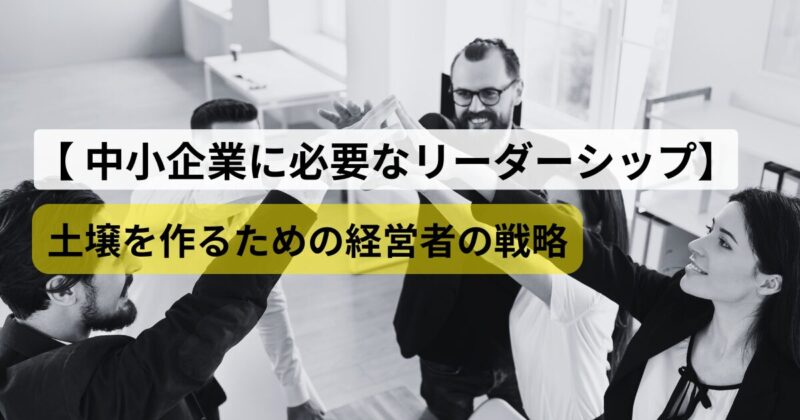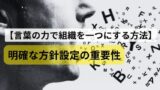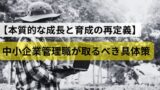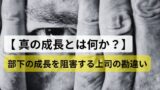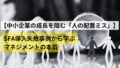中小企業が成長し、売上を拡大し、新規事業を成功させるためには、俗っぽく表現すると「社員全員が同じ目標に向かって一丸となって取り組む」ということになるだろう。ただ現実的には、経営方針やビジョンが示されても、社員がそれを自分ごととして捉え、主体的に行動するとは限らない。日々の業務に追われ、新しい取り組みに対して「忙しいから」「他の人がやるだろう」と後回しにしたり消極的な無関心となってしまうこともある。結果として、企業の成長が停滞し、現状維持のまま市場競争に取り残されるリスクが生じる。
だが、こうした状況の中でも、一人の社員のリーダーシップが組織全体に大きな影響を与え、企業文化を変革し、成功へと導くことは十分に可能である。リーダーシップは、特定の役職や肩書きを持つ者だけが発揮するものではなく、全社員が主体的に行動できる環境を作ることが重要だ。
そこで、本稿では、中小企業の経営者が「リーダーシップを発揮できる企業文化をどのように作るか?」というテーマについて、具体的な施策を解説する。社員が自発的にリーダーシップを発揮する土壌を作るために、経営者が取るべき行動や判断、実行施策を具体的に提示し、それがなぜ必要なのか、どう構築すればよいのかを考察する。
リーダーシップを発揮する企業文化をどう作るか
中小企業においてリーダーシップは、経営者や管理職の専売特許ではなく、社員一人ひとりが発揮すべき(発揮してもよい・発揮できる)能力である。しかし、現実には、リーダーシップを発揮する人材がなかなか育たない(発揮できない)ケースが多い。その原因は、組織の文化や仕組みにある。社員が主体的に行動し、リーダーシップを発揮できる環境を作ることが、中小企業の成長には欠かせない。
経営者の価値観を明確にし、浸透させる
企業の成長には、経営者の価値観やビジョンが社員にしっかりと浸透していることが不可欠である。これが曖昧だと、社員が何を基準に行動すればよいのか分からず、結果的に受け身の姿勢が定着してしまう。

企業理念…ビジョン…社是…パーパス…ミッション… いろいろ表現や企業によって何を定めているかは様々だと思うが、明確になっている企業は少ないように感じる。社是が書いてある額縁を壁に掲げている企業もあるが、その本質的意味や意義を自分の中に落とし込んで業務に励んでいる従業員はほとんど存在しないのではないか…
そういう状況だと“灯台の光”のようなリーダーが必要となる。中小企業でも伸びているなぁ…と、感じる(実際に伸びている)企業はしっかりとしたビジョンを構築している。ビジョンが売上を伸ばすか?と、言われると直接的には関係ないが、売上を確保・拡大するために尽力する従業員の「言動」には直接的に関係ある(動き方に大きな変化を及ぼす)ことは、筆者の経験からも間違っていない視点だと思う。
企業の目的と価値観を明確化する
社員が会社の方向性を理解し、自分の役割を認識できるように、企業の目的やビジョンを明確に定めることが重要だ。例えば、以下のような要素を言語化し、社内で共有することが効果的である。

長々とした文章は受け入れられない。抽象的でそれぞれの主観で解釈が変わってしまうようなものも意味がない。具体的なものが望ましい。シンプルで、普遍的かつ不変的なものだと、抵抗なく受け入れられるだろう。
日常的な対話を重視する
ビジョンや価値観を単なるスローガンに終わらせず、日々の業務や会議の場で繰り返し伝えることが重要だ。トップダウンでの一方的な発信ではなく、社員と対話しながら浸透させていく必要がある。
例えば、経営者が定期的に全社員とのミーティングを実施し、企業のビジョンや方向性について説明するとともに、社員の意見を聞く機会を設けるとよい。こうした対話を重ねることで、社員の理解が深まり、共通の目的に向かって行動する文化が醸成される。

当たり前とするために日常的な対話の中でビジョンを語ることは重要だと思う。それだけでなく、何か判断する時に「これはビジョンに則っているか?」こう自問自答できるような環境が構築できた時は「全社一丸となって…」が実現できているのではないか。
社員がリーダーシップを発揮できる環境づくり
リーダーシップを発揮する文化を作るためには、社員が自主的に考え、行動できる環境を整えることが不可欠である。「これは俺の役割・仕事の範囲ではない」「どうせ言っても、聞いてくれない…」「まっ、いいか…」このような心理(思わずつぶやく…)にさせないような社風が自主性を発揮させることになる。
主体性を引き出す業務設計
社員がリーダーシップを発揮するためには、仕事の進め方にも工夫が必要だ。指示待ちの状態では、主体的に動くことができず、リーダーシップは育まれない。
裁量を持たせた業務設計
指示を待つのではなく、社員が自ら考えて行動できるような業務設計を行うことが重要だ。例えば、以下のような方法が考えられる。

任せると言っておきながら、細かく口出しをする上司がいる。失敗しないようにアドバイスしているつもりなのだろうが、結果として自分のやり方を押し付けて自分が納得したいだけのように思えるのだ。これは自主性を潰してしまう、最悪の行動であることは上司であれば認識すべきだろう。任せると言ったからには、じっと我慢して結果責任を引き受けるという覚悟が要る。
チャレンジを奨励する環境
失敗を許容し、挑戦すること自体を評価する文化を作ることも大切だ。社員が安心して新しいことに挑戦できる環境を整えなければ、リーダーシップは発揮されにくい。
例えば、新しい取り組みを行った社員に対して、失敗したとしてもそのプロセスを評価する制度を設けるとよい。これにより、社員は「やってみよう」と思うようになり、主体的に動く文化が醸成される。ただ、あくまでも評価は結果に対して重きを置かなければ、「やることはやった。結果は結果で仕方がない…」制度がそのような認識・風潮で運用されると本末転倒である。ここは経営者・管理職がバランス良く手腕を発揮しなければならない。
評価制度の見直し
社員がリーダーシップを発揮するためには、その行動が正当に評価される仕組みが必要である。
このような評価制度を整えることで、社員は自発的にリーダーシップを発揮するようになり、組織全体の成長につながると考える。ただ、評価は「定量・定性」のバランスをとることが難しい。自社内で知識・知見・ノウハウがないのならば、外部の専門家に依頼することも必要となるだろう。(筆者も評価基準をバランス良く設定することには苦労を重ねてきた…多くの失敗の積み重ねによって、気がつけば助言する立場でそれを生業とするようになっていた)
まとめ
中小企業の成長には、社員が自らリーダーシップを発揮する文化を作ることが不可欠である。そのためには、経営者がビジョンを明確にし、裁量を与え、挑戦を奨励する環境を整えることが必要だ。また、継続的なフィードバックや評価制度の見直しを通じて、リーダーシップを発揮した社員を正当に評価することが組織の成長につながる。これは一般的によく言われていることだろう。別の表現をするならば、経営者の思い切った決断に依存する部分が大きい。自分の判断以外は信用・信頼していない…それが本音。と、言わんばかりの運営をしていると、社員がリーダーシップを発揮することはない。

自ら考えて動く社員が少ないんですよね…なかなか成長しないんです…という相談を受けることがよくあるのだが、社員を変えようとする視点が強すぎて、自らの意識改革・行動変容が社員の意識や動きが変わるとの認識が希薄と感じる。面と向かっては言い難いので、遠回しに相手よりも自分が変わることが第一歩じゃないでしょうか…程度しか言及しないが「自分の問題」として認識してない上司の下で働く社員には同情を禁じ得ない…
リーダーシップは、特定の役職にある人だけが発揮するものではなく、全社員が主体的に行動できる環境を作ることで初めて根付くものである。これを実現するために、経営者は戦略的に組織文化を変革し、社員が成長を実感できる制度設計と運営が求められる。
最後までお付き合いくださいありがとうございました。
また、お会いしましょ。