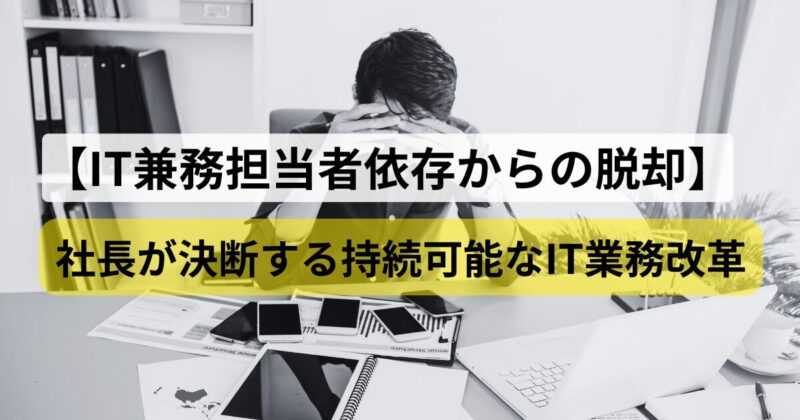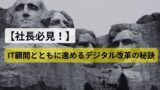中小企業が持続可能なIT業務体制を構築するには、単に製品を導入するだけではなく、運用体制の整備や人依存からの脱却が不可欠である。そのためには現状の課題を把握し、業務の整理と可視化を進めるとともに、外部専門家や経営者のリーダーシップを活用した包括的なアプローチが必要である。本稿では、IT顧問として活動をしている筆者の体験などを交えて、その具体的なステップを詳細に解説する。
現状把握と課題分析
持続可能なIT業務体制を作るための出発点は、現状の課題を正確に把握することにある。自社のIT環境を正確に理解し、どのような問題があるのかを明確にすることが重要である。「今がどうなっているのか?」これが現状把握ということなのだが、IT業務のみならず、何をするにも今、どうなっているのかからスタートすることは至極当然であり、言うまでもないだろう。IT業務体制という意味において現状把握するために必要な要件は以下が考えられる。
IT資産と運用状況の棚卸し
多くの中小企業では、IT資産の全容が正確に把握されていない。これには、所有するハードウェア、ソフトウェア、クラウドサービス、ネットワーク機器などが含まれる。それぞれの資産について以下のような項目を調査し、一覧表にまとめることが有効だ。
特に、運用がされていない「放置資産」や、更新が必要なまま放置されているソフトウェアは、セキュリティリスクの原因になるため、優先的に対応する必要がある。資産管理を導入している中小企業は決して少なくない。しかし、運用されずに放置されていることもまた少なくないのだ。これでは、宝の持ち腐れとなってしまう。資産管理ツールは現状把握には非常に有効だ。所有されているなら活用いただきたいし、PCが数十台規模で運用しているなら、導入することをお勧めする。
課題の優先順位付け
棚卸しが完了したら、見つかった課題をリスクとコストの観点から優先順位付けする。例えば、次のような基準が考えられる。
これにより、すべての問題を一度に解決しようとせず、重要な課題から着手する計画を立てることができる。筆者はIT顧問サービスの中でこれを【IT投資分析】として、独自のテンプレートを作成しそれを顧客に提供している。何に、どれくらい費用がかかっているのか?どういう目的・要因によって導入されているものなのか?…等々…筆者のIT関連事業の従事経験から導いた視点で分析をしている。
これと並行するカタチで【IT投資計画】というテンプレートも用意しており、これはIT投資の「重要度」と「緊急度」を点数化することで投資の「優先度」をか可視化するものであり、3ヶ月に1度くらいの頻度で更新して計画を実効性の高いものにしている。
IT業務の整理と可視化
現状把握と課題分析の次に重要なのが、IT業務を整理し、可視化することである。これにより、担当者が変わっても業務がスムーズに引き継がれ、人に依存しない体制を実現できる。
フローチャートやテンプレートの活用
IT業務の流れをフローチャートとして視覚化することは、誰が見ても理解できるように業務を整理するための基本的な方法である。例えば、次のような業務についてフローチャートを作成する。
- 問題発生の確認
- 問題の切り分け(ハードウェアかソフトウェアか)
- 外部ベンダーへの連絡手順
これに加え、業務で使用する定型文書やテンプレートを用意することで、情報が一元化され、担当者間の情報共有が円滑になる。これは結果として業務マニュアル的な位置付けにもなる。IT業務が煩雑になり人手が欲しい時など、一時的に派遣社員を依頼するとなった場合、このマニュアルに従って業務を遂行してもらえば良い。何もなければ、誰かが教えないと何も進まないということになり無駄になる。
IT業務ではないが、経理業務など繁忙期に派遣社員に頼んで来てもらったが、そもそも経理業務が属人的で整理されておらず簡潔に説明できる状態ではないので、派遣社員はその会社の経理業務プロセスを理解することなく1日が終わり無駄となってしまったという事例を見たことがある。経理の人手不足を現場の声として聞いた社長は派遣社員により、賄おうとして動いたのだが、経理業務の実態を把握していなかったため、依頼した派遣社員が結果として1日遊んでしまうことになると想像もしてなかったようだ。
現場の社員は「派遣の人に来てもらっても…」という思いはあったのだろうと想像するが、社長が現場の声を聞いて講じた派遣社員という対策が、無駄になります。とは言えなかったのだろう…現場と経営層の認識ギャップが対策のミスマッチを引き起こすことになったのだ。業務分析と整理と可視化というのは、何かあった時に必要になることではなく日常的にやっておくべきことで、リスクヘッジの強力なツールになることを証明している事例だといえる。
業務の分類と分担
業務分類はいろいろな視点が考えられるが、シンプルに以下のように分類し、それぞれに適切な担当者を割り振る。
こうした分類は、IT業務を定型化し、誰でも対応可能な部分と専門知識が必要な部分を明確に分けるのに役立つ。さらに、業務量に応じて、外部専門家やサービスプロバイダーに委託する範囲を明確化する。具体的な分類をするには、表面的なことや今やっていることだけではなく、本来必要なことや、もう少し突っ込んで考えないと…ということも存在するはずだ。
それを考慮すると、以下に述べる「IT顧問」を利用するという思考は成功の鍵を握ることになるだろう。
IT顧問の導入と業務分担の明確化
IT顧問などの外部専門家の活用は、中小企業の限られたリソースを有効活用し、効率的なIT業務を実現するための鍵となる。
IT顧問の役割と価値
- 現状分析と課題特定:第三者の視点で自社のIT環境を評価し、見過ごされていた課題を発見する。
- 運用改善提案:業務フローや運用プロセスの最適化を支援する。
- 新規技術の導入支援:企業に適した新しいツールやシステムの選定をサポートする。
さらに、IT顧問は製品の販売をするという目的がないので、中立的な立場からアドバイスを提供することになる。ベンダーの提案に左右されず、より適切な判断を与えてくれる安心・安全な存在になってくれるであろう。
外部サービス事業者との連携
特定の業務を専門事業者に委託することで、内部のリソースをより効率的に活用できる。例えば、クラウドサービスの管理やセキュリティ監視などの業務は、外部事業者が提供するサービスを活用することで負担を大幅に軽減できる。これにより、IT担当者は本来の業務に集中できるようになる。
とくにセキュリティ対策…維持・運用は兼務体制では現実的には難しいかと思われる(筆者の経験から)。監視ツールの導入しても、発報されるアラートにどう対処・対応するかが判断できず放置しているケースが散見される。だとしたら、最初から監視サービスを提供する事業者に委託した方が本来の目的を満たしてくれることになるだろう。サービスや事業者の選定についてもIT顧問なら適切な助言を提供してくれる。結果、無駄なIT投資が回避できる。
社長の決断と組織全体での取り組み
最後に、IT業務の改革を進めるためには、経営者の強い意思決定が不可欠である。IT改革の成否は、社長を中心とした組織全体の取り組みにかかっている。
経営者のリーダーシップ
経営者は、IT業務の課題を全社的な問題として認識し、解決に向けた方向性を示す必要がある。具体的には以下のような行動が求められる。経営者が具体的にどのような認識を持っているのか。何をしようとしているのか。そして、行動をしなければ、IT業務を兼務で担当している人材は、文句を言いながらでも「頼られている喜び」から脱却しようとは思わない可能性もあるのだ。
「大変だろうけど、人がいないのでなんとか頼む…」「わかりました。やります…」このような暗黙の了解はリスクを放置していることに他ならない。これを打破できるのは経営者の意思・意識・行動しかない。
改革のロードマップ作成
IT業務体制を持続可能にするためのロードマップを作成し、以下のようなステップを段階的に進める。
このような計画的なアプローチにより、確実に持続可能なIT体制の構築へと繋がっていく。
まとめ
持続可能なIT業務体制を構築するためには、現状把握、業務整理、外部専門家の活用、そして経営者のリーダーシップが不可欠である。これらのステップを踏むことで、IT業務の効率化とリスク管理が進み、中小企業でも高度なIT統制を実現できる。この取り組みは、経営資源を最適に活用し、企業の成長を支える重要な基盤となる。経営者は決断を先送りせず、今こそ行動を起こすべきである。
最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。
また、お会いしましょ。