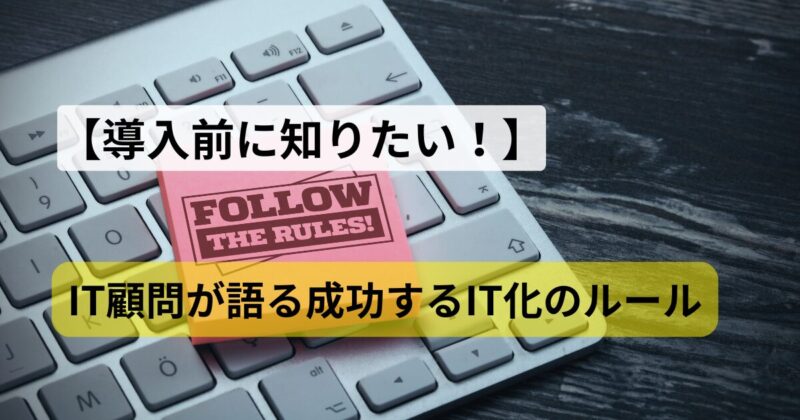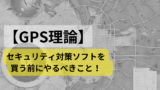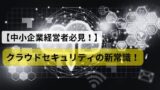IT化を成功させるためには、単にシステムを導入するだけではなく、現場での実践的な運用を見据えた計画が不可欠となる。特に中小企業においては、限られた予算や人材の中で、導入後の運用負荷やコストを最小限に抑えながら最大の効果を引き出すことが重要だ。IT化の失敗事例としてよく挙げられるのが、「ベンダーに言われるまま導入したが使いこなせず放置された」「現場のニーズと乖離していて効果が感じられない」といったケースである。本稿では、こうした失敗を防ぎ、IT化を成功させるための具体的な方法と視点を詳しく解説する。IT顧問としての長年の経験をもとに、中小企業が現実的かつ効果的にIT化を進めるためのルールを提案する。
IT化を成功させるための3つの基礎
IT化を成功させるための最初のステップは、「現状を正確に把握する」「目的を明確にする」「適切なツールを選択する」という3つの基礎を固めることである。この章では、それぞれについて詳しく解説する。
① 現状の把握
IT化プロジェクトの出発点は、現状を正確に把握することから始まる。このステップを軽視すると、導入するシステムが現実の業務に合わない無駄な投資になりかねない。
目的と課題の明確化
現状を把握するためには、まず「なぜIT化を行うのか」「どの課題を解決するのか」を明確にする必要がある。例えば、「業務効率を向上させたい」「人的ミスを削減したい」「在庫管理を簡素化したい」といった具体的な目的を設定する。これにより、IT化が解決すべき課題が絞り込まれる。課題が明確でない場合、IT化の方向性がぼやけ、結果的に効果が薄い投資となるリスクが高まる。
別の言い方をすればITシステムを導入すること自体が目的と化してしまうことになる。ITは万能ではない。ITが何かを変えてくれるものでもない。人がITを使って現状を変えることになる。ITの導入は確かに何かが変わることになる…ただ、目的が不明確であれば運用ルールも決めることもできず、なんか知らんけど前よりは便利になったね…。この程度では投資対効果があったとは言えないだろう。
既存環境の分析
現在使用しているツールやシステム、業務プロセスがどのように機能しているかを詳細に調査・把握することも重要だ。このプロセスでは、以下の項目を確認する。
特に中小企業においては、導入済みのシステムの詳細機能を把握してないことが多い(ITに詳しい担当者が不在であることが多い)。そのために、新たに提案されたものが既存の機器と機能が重複していても気が付かず導入してしまうことがあるのだ。このような無駄は、ちょっとした事前の確認や調査で避けることができるので必須事項として実施していただきたい。
課題に優先順位をつける
多くの課題に取り組むことは魅力的だが、すべてを一度に解決することは現実的ではない。例えば、「在庫管理の効率化」が最優先事項である場合、まずはその課題を中心に据えてシステムを導入し、運用を定着させる。その後、次の課題に取り組むことで、効果的にIT化を進めることができる。何が優先なのかを明確にするために、【緊急度】と【重要度】という2つの視点で思考し、それぞれに点数を付与し合計が高いものが優先度が高いと認識してみたらどうだろうか。筆者が提供するサービス【PIT-Sec】のIT投資マップはこれを可視化(図示)することで経営者が適切な判断ができるようにしている。
期日が迫っているため緊急度は高いが、事案としてはそれほど重要ではない場合は、機能的な問題よりも早期に実現させることが優先されることになる。いつまでにやるべきという具体的な日程や期限が決められているわけではないが、これをやっておかないと無駄なコストが積み上がる。という事案は緊急度は低いが重要度は高いものとなる。
② 明確なゴール設定
IT化のプロジェクトでは、目標が明確であればあるほど、成功する可能性が高まる。曖昧なゴールでは、途中で方針がぶれたり、効果測定ができなくなったりするため、定量的かつ測定可能な目標を設定することが重要である。
具体的な成果指標の設定
例えば、「月次の業務処理時間を30%削減する」「売上管理の正確性を99%に向上させる」といった、具体的かつ測定可能な指標を設定する。これにより、導入後にIT化が成功しているかどうかを判断できる。
30%や99%など定量化することは重要だが、この算出方法もよく検討しなければならない。感覚的なものや、本来の目標に対して焦点がズレているものを算出データにしてしまうとまったく意味のないものになる。
現実的な期待値の設定
IT化は万能ではない。システムを導入しただけで売上が劇的に伸びるわけではないため、実現可能な範囲での効果を見込むことが重要だ。「まずは手作業の削減により年間100時間の工数を節約する」など、小さな成功を積み重ねることが、最終的な目標達成への近道となる。やってみないとわからないということも多々あるため、目指すべき指標は状況に応じて変更や工夫してIT化の効果が後退しないよう運用することが大事なポイントとなる。
③ ツール選定の基本
中小企業が限られたリソースの中で最適なツールを選定するためには、いくつかの基本的な指針を押さえておくべきだ。
必要な機能を絞り込む
必要以上に多機能なツールを選ぶと、導入コストが増大し、運用も複雑化する。業務に必要な最低限の機能を明確にし、それを満たすツールを選ぶことが基本である。
拡張性を確認する
業務が拡大した際や新しいニーズが生まれた際に、追加機能を導入できるかどうかを確認しておくことも重要だ。特に、クラウドベースのツールでは拡張性が高いものが多いため、中小企業には最適な選択肢となる。
コストパフォーマンスの比較
初期費用だけでなく、月額料金や保守費用など、トータルでのコストを考慮すること。多くの中小企業では、初期投資が低いクラウド型サービスを選ぶ傾向があるが、長期的なコストを見積もることも忘れてはならない。
運用の成功を左右する3つのポイント
IT化を導入するだけで満足してはいけない。本当に効果を発揮するためには、運用のフェーズが極めて重要である。この章では、運用を軌道に乗せるための具体的なアプローチを解説する。
チーム体制の構築
IT化のプロジェクトが失敗する原因の多くは、プロジェクトを進める体制が整っていないことにある。
❶ プロジェクト責任者の任命
プロジェクトマネージャーを任命し、プロジェクト全体の進捗管理や調整を担当させる。この役割は、経営層が担うことも多いが、ITに詳しい社員がいればその人材を活用することが望ましい。
❷ 教育とトレーニング
システムを導入した後、従業員がそれを正しく利用できるようにするための教育が必要である。短期間で習得できるように簡潔なマニュアルを作成し、導入後すぐにトレーニングを実施することを推奨する。
❸ 外部専門家の活用
自社に十分なリソースや専門知識がない場合は、外部のIT顧問やベンダーを活用する。特に、運用中に発生するトラブルや疑問に迅速に対応できる体制を構築しておくことが重要だ。
効果測定とフィードバック
IT化の成果を測定することで、プロジェクトの進捗や改善点を把握しやすくなる。ここまでやっている企業はほとんどないかもしれないが、ゴールを決めて導入したのであれば、効果測定をしないと次のIT投資へと繋がっていかない。事業を継続・拡大する上でITは必要不可欠な存在になっているので、人事同様の位置付けで運営をしていく必要があるのではなかろうか。
KPIの設定
具体的な成果指標(KPI)を設定し、定期的にレビューを行う。例えば、「月次のエラー件数を20件以下に減らす」といった目標を設定することで、効果を測定しやすくなる。当初は現実と乖離することもあるかもしれない。だが、継続することでKPIも現実的になり精度も高くなってくるだろう。
フィードバックループの構築
現場の従業員からのフィードバックを収集し、それをもとにシステムを改善する。これにより、従業員の満足度とシステムの効果を両立させることができる。第三者的に眺めているだけでは正確な効果を知ることはできない。使っている人からの情報は、心理面に与える満足度など表面化しない部分でも導入効果を測ることができる。IT化により働く環境が整備・向上したのか…ここは効果測定の項目としては重要である。
継続的な改善
IT化は導入して終わりではなく、継続的な改善が必要であることは言うまでもない。
技術のアップデートへの対応
新しい技術やトレンドに適応するために、定期的なリサーチや導入検討を行う。例えば、セキュリティ対策の強化や新機能の活用など、最新技術動向を知っておかなければ意味のない対策を施していることになりかねない。自社でやるのか…自分でやるのか…誰がやるのかは要検討だが、重要なことである。繰り返し、かつ重複だが最新の技術情報が自社に必要かどうか評価して提供してくれることを考慮すると、IT顧問に任せてしまえば内部要員の負担は軽減されることになるだろう。
運用フローの見直し
業務プロセスの変更や組織の拡大に応じて、運用ルールやシステム設定を見直すことで、IT化の効果を最大限に引き出すことができる。ただ、ITだけの問題ではなく、結果としてITによって解決が可能…こうなるのがITの役割である。管理職の定例会議等で、現状の実務をITに置き換え期待する効果は…というような視点で議論をすることが見直しを促すことになる。
まとめ
IT化を成功させるためには、明確な目標設定、適切なツール選び、そして運用体制の構築が重要である。また、これらのプロセスを支えるためには、専門家の意見を取り入れ、継続的に改善していく視点と姿勢が必要だと考える。中小企業がIT化を成功させるには、これらの基本を確実に押さえ、長期的な視野で計画を進めることが不可欠である。
ただ、現実的にはIT化に多くの人材と時間を費やすことは中小企業では困難である。IT業務は、法務、経理などと同様に専門家を必要とする業務なので自社で全て完結するものではないと捉えていただければ、IT顧問に依頼するというハードルは下がるのではないか。ITの進化は見た目や、操作性という意味では簡単で誰でも使えるものとなっていくであろうが、その反面それを企業でどうやって有効に利活用するか、どう運用するかという意味においては、より専門知識と経験を必要とされることになる。ちょっと勉強して…という位置付けのものではなくなってきていることを最後にお伝えして本稿を締めくくる。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
また、お会いしましょ。