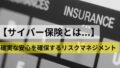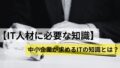成長って言葉はよく使われているが、その意味するところはなんなのだろうか?前向きだし、努力しているということにもなるし、良い意味で捉えられる都合の良い言葉(マイナスイメージがない)なので、つい口から出てしまうのだろうか?私も様々な場面で聞くのだが「それってどういう意味で言ってますか?あなたにとって成長するってどういうこと?」って聞きたくなるようなこともあります。辞書で調べたら言葉の意味はわかるが、ここでは私の経験から組織において、しっくりとくる“成長する”の定義を含め以下の3つのポイントで解説させていただきます。
✅ “成長する”をよく耳にする場面
✅【成長する】の定義
✅ 成長を促すマネジメント
“成長する”をよく耳にする場面
「成長する」「成長したい」という言葉を耳にする機会はよくあると思っているのだが、実際にどういうところでよく聞くのだろうか?私の記憶の中で、この場面ではよく聞いたなぁ…ということを思い出しながら、どのような使われているか検証してみる。
その❶:採用面接
新卒、中途、派遣登録…等々…2000人以上の人と面接で向き合ったことがあるが(プロフィールを参照くだだい)、中でも新卒の方に「成長」という言葉を使っている人が多かった。
志望動機やこの会社で何をやりたいの?などの質問に“成長”というワードを入れてくる学生が多くいた。学校側の指導で、“成長”って言葉を入れて回答したら、評価されるぞ。とでも、アドバイスされているのだろうか?なんとなく、こういうことを言いなさい、こんな感じで答えなさい。と、言われたか、何か「面接の極意」のような本で読んだのか、あ…そういうことだろうなぁ…と、感じたことはあるが、成長については単純によく聞くなぁ…程度の印象であった。
「君にとって成長するとはどういうことですか。」という質問をするようにしてみた。そうすると、ほとんどの学生が「えっ?…」という反応をするのだ。「なんだその質問は…成長は成長ですよね…」とでも言いたげな雰囲気を出すのだ。「成長したいって、身長を伸ばしたいとかそんなことじゃないでしょ。どういう意味で言ってるのかが知りたいと思って聞いたんですよ。」と、質問の意図を問うても、明確な回答を得られたことがない。(どんな回答が多いかは後述)
その❷:アスリートのインタビュー
何かの大会での優勝インビューのシーンで…

優勝おめでとうございます。

ありがとうございます。
〜 中略 〜

今後の目標などありましたらお願いします。

もっともっと練習をして自分を成長させて、次の**大会でも優勝できるように頑張ります
など、成長させて優勝…優勝することが成長?優勝の前に成長した自分がいるから優勝できる?だとすると、成長するというのはどういう状態のことなのだろうか?決しておかしな会話でも、回答でもないのだが、どうも成長という部分に関しては、何を意味しているのかがいまいちピンと来ないと感じてしまうのだ
その❸:部下と上司
営業部門の上司と部下の会話で、部下が売上目標を達成したという時に

おー!やったな目標達成したじゃないか。おめでとう!
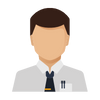
はい。
ありがとうございます。嬉しいです。

だろうな。
いや…お前も目標達成できるようになって、成長したな!
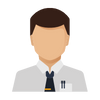
はい。
これからも、もっともっと成長できるよう頑張ります。
シンプルな会話例なのですが、このような場面でも成長という言葉を聞くことがある。上司も部下もお互いに成長という言葉を使っている。同じ意味で言ってるのだろうか…?これもどうにもピンと来ないのである。
【成長する】の定義
どういう意味で成長という言葉を使うとピンとくるのだろうか?その前に、前述のよく耳にする場面での成長とはどういう意味で使われているか考えてみる。
使われている成長の意味を分析してみると…
✔️ 早く仕事を覚えること。(仕事ができるようになること)
✔️ できる仕事の量と質が増えること
✔️ 今までできなかったことができるようになること
✔️ 今までの記録を更新すること
✔️ 練習量を増やすこと
✔️ 新たな技術を身につけること
✔️ 成功率が上がる
✔️ できなかったことができるようになる
✔️ 継続して成果を出せるようになる
✔️ 期待に応えることができる
このような感じだろうか。共通していることは何かと見ると…
今までできていない(できなかった)ことができるようになる。
こういうことになるのではないか。確かに、今まで150cmだった身長が160cmになると成長したと言える。今までは到達していなかったのだから…できなかったことができると成長した…?ホントにそれが適切なのだろうか?アスリートの場合はそれでピンとくると思うのだが、組織において、できなかったことができるようになることは成長なのだろうか?
仕事を覚えるとか、別の仕事がこなせるようになったというのは、成長なのだろうか?今まで解けなかった数学の問題が解けるようになったら、それは成長なのだろうか?学力がアップしたということなのではないか。「学力向上=成長」ということなのだろうか?
営業マンがA商品しか説明できなかったが、B商品も説明できるようになった。これも成長としていいのだろうか?
組織で最も成長した人は誰か?
組織内で、一番成長している人は誰だろうか?多分、社長ということになるだろう。社長は会社を成長させたいとは言うが、自分を成長させたいとは言わない(ほとんど聞いたことがない)。新入社員は自分を成長させたいと言う。この違いはなんなのだろうか?
経験値が多いから、社長の方が仕事ができるのだろうが、仕事が多岐に渡ると社長と言えども全てに精通しやり遂げる能力があるかと言えばそうではないだろう。仕事によっては、社員の方が社長よりもできることがあるはずだ。そうなると、単純に仕事ができるようになったから成長したということにはならないのではないか。
ここで、社長と新入社員の違いを何かを考えてみる。
成長の定義
社長が持っていて、新入社員が持っていないものは何か?普通に考えると多々あるのだが、ここでは組織内ということで考えると“決裁権”ということになるのではないか。決裁権とは自分で判断して決めることのできる、権限と範囲のことである。重要な視点は「自分で判断して決めることのできる…」この部分である。
今まで、できなかったことができるようになれば、その仕事については、都度、確認したり上司に聞いたりしなくても、自分で判断して決めて動くことができるようになる。これが成長したということなのではないか。今までは、訪問先も、行くタイミングも上司や先輩に確認していたが、行動予定については自分で全て決めることができるようになった。これが成長した。ということだろう。新入社員の時は、業務中にトイレに行っていいのかもわからずに…ということがあったのではないか。
ここで、成長の定義が明確になったのではないか。
「自分で判断して決めることができる範囲が広がっていく(増えて)こと」
課長より部長の方が決裁権は広い。役職が上位だから成長したのではなく、自分の判断で決められることが多くなったから成長したと言えるのだ。社長は最高決裁者なので、自分の判断で決められないことはない。(現実には独断でなんでも決めてやるということはないと思うが)それ故、自分を成長させるとは言わないのではないか。それ以上がないのだから…
このように定義して、意味を当てはめると面接の学生の言ってることもつじつまが合う。上司と部下の会話もそうだろう。アスリートに関しては組織という概念で活動をしていないため、少し違ってくるのだが。学力向上についても、それ自体が成長ということではなく、自分で決めて勉強方法を工夫した。親に勧められたのではなく、評判の良い塾を見つけてきて、そこに行きたいと志願したなど。自分の判断で決めて行動するということが、親からすると子供の成長を感じる部分であり、学力そのものは成長とは別の話であろう。
成長を促すマネジメント
成長の定義が明確になれば、社員(部下)をどのように育成したらいいかも見えてくるのではないか。成長を促すマネジメントについて考えてみよう。
指導は直接的に成長に寄与しない
こうしたらいい。こうやらないとダメ。…等々….指導することはNGではないが、できなかったことができるようになることと成長することは別問題なので、成長促進とはならない。口を出すよりも、部下自身が多くの経験から何かを掴み取るようにしてあげる方が成長には繋がって行く。
環境を与える
指導が直接的に成長を促さないのであれば、上司は何をしたらいいのか。それは、仕事の範囲を増やして経験させることである。つまり、環境を与えることである。やらせてみないことには、自分で何を判断するべきかもわからない。これを経験し、失敗と成功の中から、どう捉え、考えるべきかを学習していく。それが成長に繋がる。未知のことを自分自身で考えて判断するようになれば、それは既に成長していると言える。ただし、自分で考えてやらせることはいいのだが、決裁権まで与えるのは時期尚早ということもあるので、部下が勘違いしないような指導は必要である。
信頼が成長を促す
環境を与え、経験を積ませるよう何らかの指示を出したら、あとは部下を信頼し口を出さないことが重要だ。事細かに報告することを求めたり、やり方に口を出すと、部下は自分の仕事として捉えられなくなる。上司の代わりにやっている仕事と認識するだろう。それは、成長のための経験ではなくなってしまう。
失敗するかもしれないと見えても、部下を信頼して任せるという度量もマネジメントでは重要である。失敗しないように…失敗しないように…と、口と手が出てしまうと、仕事は成功するかもしれないが、部下の成長は停滞することになるだろうし、失敗したくないのであれば自分(上司)でやった方がいい。任せることができないのは、自己保身が強いからで、そのような接し方では部下は自発的に考えて…ということはしなくなってしまう。言われたことをやればいい。という感覚になるのだ。これで成長は止まる。
中小企業の経営者は、なかなか部下が育たないので将来を考えると厳しいんですよね…との声は多く聞くのだが、私の見聞きした経験からすると、その経営者のほとんどが部下を信頼していないのだ。やらせてはいるが、俺(経営者)の言った通り、俺の好むやり方でやりなさい。という運営していることが多いのだ。これでは、人は成長しない。
部下を信頼できない上司…その理由と改善などについては、また別の記事で詳しく解説させていただきます。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。