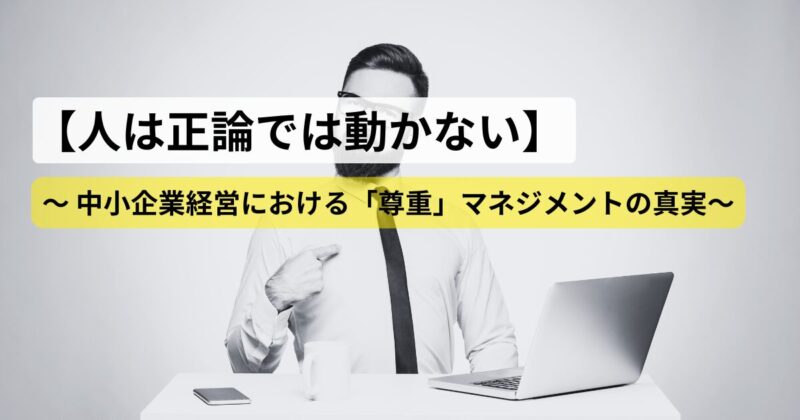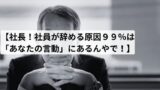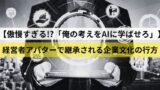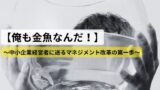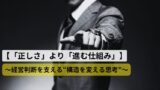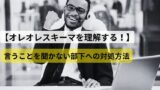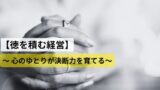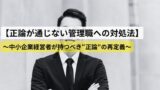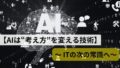中小企業の経営やマネジメントにおいて、「正しいことを言っていれば人は動く」と信じているリーダーは少なくない。だが、現場で人を動かすのに必要なのは正論ではなく「尊重」である。筆者自身が経験した“全社員退職”という地獄のような失敗から、やっとのことで掴んだ「人を動かす本質」──それは「降りていく勇気」と「支配しない覚悟」だった。本稿では、中小企業の経営者や管理職に向けて、感情と信頼をベースにしたマネジメントのリアルを、実話と共に伝える。
若き日の失敗 ― 正論マネジメントの限界
「正しいことを言ってるのに、なぜ誰も動かない?」──これは、私がマネジメントの入口で何度も叫び、つまずき、そして打ちひしがれた問いである。答えはシンプルだった。人は正論では動かない。むしろ、正論ほど人の心を閉ざすものはない。そう気づいた時には、すでに遅かった。
「正しいことを言えば伝わる」と信じていた日々
20代後半でマネージャーになった。ありがちな話だが、現場のエースとして結果を出していた私は、「その延長線上に管理職がある」と思っていた。数字に強く、論理的に説明できて、段取りもうまい。だから、自分のように“ちゃんと”やれば、みんなできるはずだと本気で信じていた。
「なぜ締切を守らない?」「なんで報告がない?」「そんなの当たり前だろ!」──そうやって部下を詰めていた。もちろん私は悪気などなかった。会社のため、本人の成長のため、「正しいことを言っている」という自負があった。
でも気づけば、報告は減り、会話は減り、職場の空気は静まり返っていた。そしてある日、社員が一人、また一人と辞めていった。気づけば社長と私の二人だけ。まさに“地獄のようなオフィス”で、私は呆然と立ち尽くしていた。
正論で人の心は閉ざされる
今になって思う。「言われた側はどう感じていたのか?」と。
私の「正論」は、きっとこう聞こえていたのだろう。
「お前のやり方は間違ってる」
「お前はダメだ、俺の言う通りにやれ」
「お前には判断力がない、だから俺が決める」
言ってるつもりはなくても、伝わるのはそこだった。実際に面と向かって「言い方がキツい」と言われたこともある。だがそのときの私は、「甘えるな」「こっちは真剣だ」と返していた。完全に独りよがりだった。
そうなると、部下は報告を控えるようになる。話しかけづらい上司には誰も近づかない。結果的に、上には良い情報しか上がってこなくなる。問題が発覚するのはいつも“手遅れ”になってから。これはまさに、会社という組織の「死にかけサイン」である。
正論は、実は“自分都合の押しつけ”
当時の私は、「正論=普遍的な正しさ」だと勘違いしていた。けれど本当のところ、「自分の物差し」で相手を測っていただけだった。
・自分はやれているのに、なぜ君はできない?
・こうやれば早いのに、なぜその方法を選ぶ?
・何度も言ってるのに、なぜ改善されない?
今にして思えば、これらは全部、「自分の常識」を押し付けているだけだった。相手には相手の事情、経験、苦手意識やプライドがある。にもかかわらず、私はそれを無視して「俺ならこうする」を基準に人を評価していた。
「正しいことを言ってるのに通じない」というのは、言っている内容ではなく、受け手の“心の状態”に寄り添えていない証拠だと、あとから痛感した。
「降りていく」ことで人は動き出す
指示を出すのではなく、寄り添う。これだけで空気は劇的に変わる。
「報告しろ!」をやめて「どう?」と聞いた
報告がないことにイライラし、「なんで言わないんだ!」と怒鳴ったこともある。だがある日、「そうだ、こっちから聞けばいいだけじゃないか」と思った。そこで、業務の合間に「どう? 順調?」と軽く声をかけるようにした。それだけで、驚くほど話してくれるようになった。
会話でつなぐ、共感で動かす
「指示」より「対話」。これが全ての原点だった。話し方も意識的に変えた。飲みに行った時のようなトーンで話すようにした。「これ、どう思う?」と相談し、「任せていい?」と頼んだ。そうすると部下たちは「はい、やってみます」と自然に動くようになった。
売上と人間関係はリンクしている
人間関係が変わると、数字も変わる。売上が自然と伸び始め、離職も止まり、職場の空気が明るくなった。「ああ、マネジメントって、人の心の動きそのものなんだ」と、この時やっと腑に落ちた。
上司・部下の関係を超えて ― 社外の人をどう動かすか
会社という“肩書き”を脱ぎ捨てたとき、マネジメントの本質が突きつけられる。独立後、私が最初に直面したのは「指示が通じない相手との協働」だった。部下でもなければ社内でもない。だが、一緒に成果を出さなければならない。そんな「距離があって、責任が重い」関係性の中で、私はまた、痛烈な“正論の罠”に落ちていった。
指示が通じない相手に、どう働きかけるか?
独立して最初に組んだのは、フリーランスのデザイナーとエンジニアだった。彼らは腕が立つが、納期にはルーズ、返信も遅く、時に勝手な判断で進めてしまう。こっちはクライアントに対して責任を負っている。どうしても口調が強くなり、「それはおかしい」「ちゃんと報告してくれ」と言いたくなる。
だが、ここで一つ厄介なのが、「言っても響かない」という現実だ。
なぜか?それは、こちらには“命令権”がないからだ。会社の中なら、「上司の指示」で押し通せる。だが社外ではそうはいかない。フリーランスも外部事業者も、自分の裁量と価値観で動いている。
「正論」で詰めれば、関係は壊れる。かといって「放置」すればプロジェクトは崩壊する。この“板挟み”に、ずっとモヤモヤが蓄積されていった。
正論で切って、孤立した経験
あるプロジェクトで、外部パートナーの対応のまずさが続き、ついに私は我慢の限界を超えてしまった。ミーティングで強めに、「これでは困る」と伝えた。相手は静かにうなずいたが、翌週から明らかに熱量が下がった。そして、次の案件の打診には返事が来なかった。
あとで聞いた話では、「一緒にやってて疲れる」と言われていたそうだ。
正しいことを言ったはずだった。だが、彼の中で「関わりたくない人」リストに私が入ってしまった。それは、“正論で関係を切った”ということだった。
この時、やっと気づいた。「社外の人ほど、感情で動いている」という当たり前の事実に。
「得よりも、徳を積む」──信頼は“人としての評価”で動く
それ以来、私は少しずつ関わり方を変えていった。
不満があっても、一呼吸置く。言いたいことがあっても、「今言うべきか?相手はどう受け取るか?」と考える。結果、「言わない」選択をすることも増えた。
これは「我慢」ではない。「徳を積む」ための投資だ。相手のプライドを守り、信頼関係を壊さないように意識する。「この人と仕事をすると気持ちがいい」と思われること。社外では、そこが最重要になる。
一度だけ、相手の納品が遅れた時に、こう言ったことがある。
「今回は納期がタイトで大変だったよね。でも、君がこのクオリティを仕上げてくれたおかげで助かった。本当にありがとう」
内心では、「もっと早く出してくれよ…」と思っていた。だが、それを飲み込んで“ありがとう”を先に言った。その後、彼は明らかに態度を変え、次の案件では納期前日に仕上げてきた。
信頼とは、相手を変えようとする前に、まず「信じて接する」ことで生まれるものだと知った瞬間だった。
感情の摩擦も、信頼のチャンスに変えられる
社外の人と仕事をしていると、こちらの常識が通じないことが頻繁に起きる。例えば「連絡を1日返さないのは失礼だ」という感覚も、相手にはなかったりする。それに腹を立ててしまうと、「感情の衝突」になる。
だが、ここでも学んだことがある。
「そういう考え方もあるんだね。ちょっと驚いたけど、なるほどと思った」
この一言で、空気が変わる。相手が「攻撃された」と感じなければ、防御しない。人間関係において、正しさよりも「理解されている感覚」が大事なのだ。
“論破されて納得する”のではない。“共感されたから動きたくなる”。
これは社内でも社外でも同じだが、とくに社外では、「正論」は関係を切る刃物になりうる。
尊重・信頼・尊敬 ― 似て非なる3つの軸
リーダーが持つべき“人との距離感”には、3つの段階がある。
尊重:存在を認め、居場所を与えること
まずは「あなたがここにいることを嬉しく思っている」というメッセージを伝えること。これは「おはよう」「ありがとう」「頼りにしてる」といった、ちょっとした言葉に込められる。
信頼:能力を認め、任せること
次の段階は「あなたに任せたい」と伝えること。任せるということは、口を出さずに待つこと。部下が自信を持てるよう、結果が出る前に応援する姿勢が必要だ。
尊敬:積み重ねた結果として自然に生まれる
尊敬は与えるものではない。得るものだ。そして、尊重と信頼を地道に重ねていけば、相手から自然に湧き上がってくる。だからこそ、焦らず、諦めず、続けることが大切だ。
まとめ ― 人を動かす前に、自分が“降りる”勇気を持て
経営もマネジメントも、結局は「人間同士」の関係で成り立っている。そこには正論よりも、共感が必要だ。理屈ではなく、感情に届く言葉を。上から押しつけるのではなく、隣に寄り添う姿勢を。
「降りること」は、弱さではない。むしろ、最も強いリーダーができる選択だ。尊重が信頼を生み、信頼が成果を生む。その循環を作ることこそが、中小企業の成長を支えるマネジメントの核心である。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。