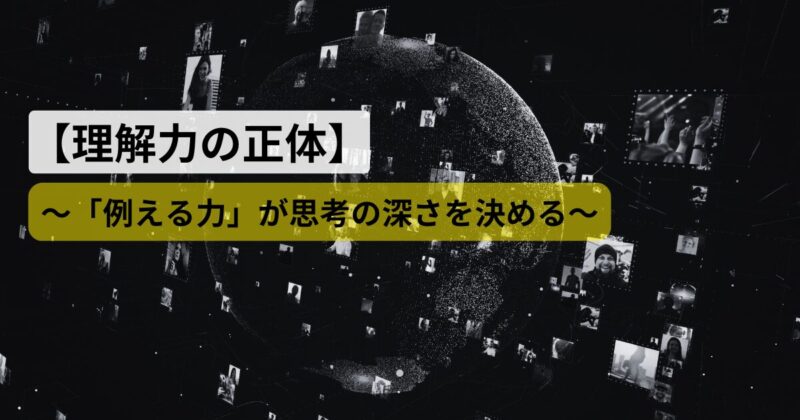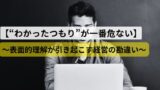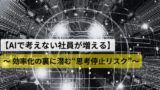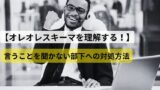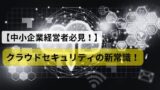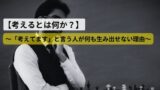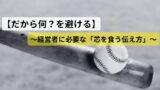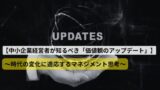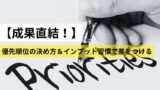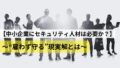「理解したつもり」が招く誤解や伝達ミスは、中小企業の経営現場における大きな課題である。部下との認識のズレ、会議の空回り、施策の形骸化…。これらの根本にあるのは「本質を掴む理解力の欠如」である。理解とは単なる情報処理ではない。構造を捉え、置き換え、他者と共有できる力こそが真の理解力だ。本項では、経営者や管理職が身につけるべき「例える力」を通じて、組織内の理解精度を高め、論理と直感を両立させた思考の習慣化について提案する。
なぜ理解できない人が増えているのか
情報があふれる現代において、「理解したつもり」がもたらす齟齬や誤解が、経営のあらゆる現場で顕在化している。これは単なる知識不足ではない。もっと根深い、「思考の構造」にまつわる問題である。
「わかっていない」ということを、わかっていない
本当に危ういのは、「理解していないこと」に無自覚な状態だ。人は、自分の頭の中で“意味がつながった気がする”と、それだけで理解したと錯覚する。しかし、その理解が本物かどうかは、説明を求められた時に露呈する。
たとえば、ある施策の目的を「わかっている?」と尋ねられ、「大丈夫です。理解しています」と答えた部下が、その根拠や背景、期待する結果をうまく言語化できない。これは決して珍しい場面ではない。だが、この時点で「わかっている」のではなく、「わかった気になっている」に過ぎない。言葉にできない理解は、理解とは言えない。構造を掴めていないから説明ができず、例えることもできないのだ。
表面的な「知識の受け渡し」が理解力を鈍らせる
Google検索、AIチャット、要約アプリ。現代は情報取得が容易であるがゆえに、自分で考えずに「コピペの理解」に頼ってしまう傾向がある。つまり、自分の思考を通さず、外部の表現をそのまま借りる。こうして語彙だけが増え、意味が自分の中で咀嚼されないまま使われる。
結果として、会議の中では「もっとPDCAを回さなきゃ」とか「このKPIはUXに関わってくる」といった“通っぽい言葉”が並ぶが、それぞれの文脈や因果関係を尋ねると、言葉が止まる。これはまさに、“言えている”のに“わかっていない”状態である。
理解とは、「再構築できる」こと
理解とは、ただ情報を受け取ることではない。受け取った情報を、自分の文脈に置き換え、構造を再構築し、それを他者と共有できて初めて“わかっている”といえる。その意味で、理解とは能動的な作業であり、受け身のインプットとはまったく別の営みである。
たとえば、「クラウドセキュリティが重要だ」と言われた時に、「なぜ重要なのか」「従来の仕組みと何が違うのか」「うちの会社にとって何がリスクで、何が守られるのか」を自分の言葉で整理できていなければ、それは単なる知識であって、理解ではない。
思考の“構造のズレ”が会話を迷走させる
「この人とはなんとなく話が噛み合わない」と感じる相手がいるとすれば、それは言葉の選び方の問題ではなく、思考の構造がズレているからである。たとえば「任せる」という言葉ひとつ取っても、それを「信頼の証」と捉える人もいれば、「丸投げ」と感じる人もいる。
共通の土台がなければ、言葉だけがすれ違い、同じ会議にいながら別々の議題を議論しているような状況に陥る。それが、現場でしばしば起きる“議論の空転”の正体である。
「理解力=例える力」という視点
「理解力とは何か?」という問いに対して、多くの人は「物事を正しく知ること」「相手の話をきちんと把握すること」と答える。しかし、ここにひとつの重要な視点が抜けている。それは、「理解したことを他者と共有できる形で再構築する」力である。
そして、この“再構築”の最も純度の高い表現方法が「例える力」である。
なぜ“例え”が理解の証明になるのか
例え話ができるということは、単に知識を持っているだけではなく、それを自分の中で“構造化”し、別の文脈へと「変換」できる力を持っているということだ。
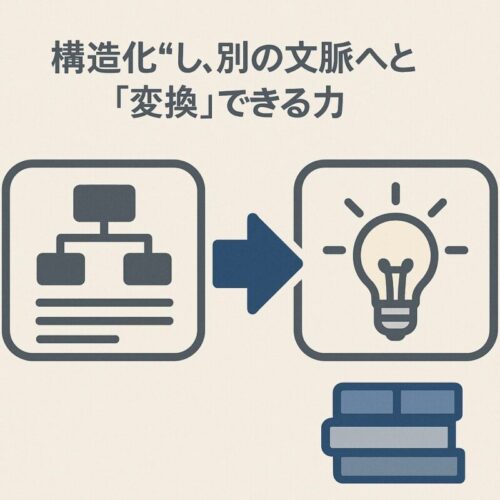
これはつまり、情報をコピーするだけではなく、自分の思考で“組み替える”能力があるということであり、そこには「理解の本質」が宿る。
たとえば、「会社のチーム運営はオーケストラと同じだ」と例える人がいたとする。その人は、演奏するメンバーの役割の違い、指揮者の統率力、各パートが奏でる音の調和といった“構造的な類似性”を抽出し、別の概念に“橋を架けて”いるのである。ここには単なる知識ではなく、明確な“認識の再設計”がある。
これはもはや、ただの表現技術ではない。構造的に捉え、他者に渡せる形で整理し直す「知的な作業」そのものだ。
「例えられない人」は、構造を掴んでいない
逆に言えば、例えが出てこないというのは、それが単なる“断片的な記憶”として存在している証拠だ。専門用語や横文字ばかりを並べ、説明になっていない説明が横行するのはそのせいである。
たとえば「VPNが必要です」と言われても、ITに明るくない経営者はピンとこない。「外部と安全に繋がる仕組み」と言われても、まだ抽象的だ。しかし、「公共のカフェで話すのは危ないから、個室を借りて会話するようなものですよ」と例えられた瞬間、意味が“腹に落ちる”。
この“腹落ち”こそが理解であり、そのための技法が「例える力」なのである。
「例える力」とは、抽象化と具体化を往復できる能力
本質を理解するとは、言い換えれば“構造の抽象化”である。複雑な事象から無駄をそぎ落とし、中心的な構造を浮かび上がらせる。そして、それを他の文脈や日常の具体例に“翻訳”できることが「例える力」の正体だ。
この“抽象⇔具体”の行き来ができる人は、ビジネスのあらゆる場面で応用が利く。なぜなら、問題の根っこを掴んでいるからだ。表層的な違いに惑わされず、課題の“構造的な本質”を見抜くことができる。
この力こそが、経営において最も重要な「判断力」の源泉である。
理解とは、「再現できること」
もう一歩踏み込めば、理解とは「他者に伝えることができる」「別の領域に応用できる」「言い換えても崩れない」状態のことだ。これができて初めて、本当に理解していると言える。
つまり、例えることができないというのは、それを再現できない、つまり「使えない知識」にすぎないということだ。理解が単なる記憶にとどまっていて、自分の文脈に落とし込めていない証拠である。
このように整理すると、「理解力=例える力」という等式は、単なる便利なキャッチコピーではない。構造的に考えれば、他に選択肢がないほど“必然の公式”である。
だからこそ、経営者やリーダーこそ、例える力を磨くべきなのだ。
それは「説明のため」ではなく、「本当に理解するため」に。
経営者は「構造の翻訳者」であれ
― 経営における“例える力”の本質的役割
経営者の仕事とは、組織を動かすことである。だが、組織を動かすとは、決して「命令を下すこと」ではない。本質は、“理解の座標軸”を揃えることにある。
施策の意図、目標の背景、戦略の意味。それらは言葉だけで伝わることはない。なぜなら、言葉は常に“解釈の余地”を孕んでいるからだ。だからこそ、経営者には「構造を翻訳する力」、つまり例える力が必要とされる。
たとえば、「マーケティングを強化する」と言った時、それを「広告費を増やすこと」と解釈する人もいれば、「SNSで発信すること」と捉える人もいる。これは言葉の問題ではなく、構造の認識がズレているということだ。表現ではなく「意味」が揃っていない。このままでは会議は空回りするだけだ。
ここで例えが効力を発揮する。
「マーケティングとは筋肉づくりだ。すぐに成果は出ないが、継続と負荷の設計が成果を生む。広告はプロテイン。SNSはストレッチ。どれも一部に過ぎず、本質は“筋肉を動かすこと”にある」と説明すれば、組織内の共通理解が一気に立ち上がる。
このように、例えとは、言葉の精度を高めるのではなく、構造の座標を合わせるための“翻訳”である。
「例え」は判断力を支える構造理解ツール
例えを使える経営者は、構造を理解している経営者だ。逆に例えを使えない人は、構造ではなく“見た目”で判断している可能性が高い。IT投資の場面を見れば、それは明らかだ。
「AIが話題だから」「今のうちにDXを」と言って、新しいツールを導入する経営者は少なくない。しかし、それは「テレビで見た薬が良さそうだからと買って飲む」のと同じである。本来ならば「診断→処方→投与→経過観察」という順番があるべきで、企業の“体質”に合わない薬は逆効果にもなる。
これは単なる比喩ではない。例え話を使うことで、「自社にとっての最適なIT投資とは何か?」を、構造的に理解し、判断できるようになる。
同様に、人材育成においても、「任せるのが怖い」と感じる経営者は多い。だがそれは、筋トレで「負荷をかけずに筋力をつけよう」としているのと同じ。筋肉は適切な負荷と回復によって成長する。人も同じだ。これは感覚ではなく、構造的な話である。
このように、例えは単なる説明技法ではなく、「判断の質」を高めるためのツールなのだ。
経営者が例える力を持つべき理由
経営における意思決定とは、常に「複雑な構造を、他人に理解可能な形で伝えること」を伴う。人を動かす、予算を配分する、戦略を実行に移す。そのすべてが、理解の精度に依存している。
だからこそ、例える力は経営者にとっての“翻訳装置”であり、“調律器”である。音の合わないオーケストラを、ひとつの旋律に合わせるのが指揮者の役割であるように、例え話は組織の理解を“調律”する手段である。
そしてこの調律が揃えば、組織は自律的に動き始める。逆に言えば、「例える力のない経営者」は、毎回自分の手でハンドルを握り続けなければならない。指示、確認、修正、説得…。永遠の手間を抱え込むことになる。
「例える力」は、経営の質を底上げする“可視化スキル”
さらに言えば、例える力は「無形のものを可視化する力」でもある。
たとえば、セキュリティ対策を「毎日の歯磨き」と例えた瞬間、ITが苦手な経営層にも「継続の重要性」「習慣化の価値」「過剰対応のナンセンスさ」などが一気に伝わる。ここには、単なる例え以上の効果がある。「可視化されたこと」によって、人はそれを“信じられるようになる”からだ。
経営判断とは、見えないものを決断する行為である。売上、組織、人材、リスク、未来。そのすべてが、例えによって“触れられる形”に変換された時、はじめて合意が生まれ、実行が可能になる。
まとめ:例える力とは「構造の翻訳力」である
例える力は、話を面白くするためのテクニックではない。それは、複雑な経営構造を理解し、他者に伝わる形に翻訳し、判断を支えるための“構造的能力”である。
だからこそ、経営者は「わかりやすく話す」のではなく、「構造を伝える」ために例えなければならない。そしてそれは、信頼をつくり、意思決定の質を高め、組織の共通理解を生み出す根幹となる力である。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。