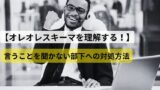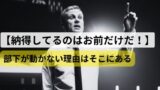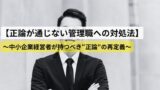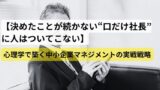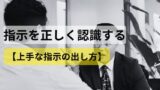中小企業の経営を成功させるには、「伝える力」が不可欠だ。しかし多くの経営者が誤解している。伝える力とは「話し上手になること」ではない。ましてや「論理的にわかりやすく説明すること」でもない。本当に大切なのは、相手の見ている世界を理解し、その地図に合わせて言葉を届ける“相手理解力”だ。本稿では、現場でよく起こる「伝わらない経営者の言葉」のズレを具体例を交えながらひも解き、中小企業における実践的な“伝える力”の本質を明らかにしていく。
「伝える力」は“相手理解力”である
伝えるとは、自分の言葉を磨くことではない。相手の理解構造を知り、そこにフィットする形で言葉を届けることが本質である。
相手が見ている世界は、自分とは違う
経営者は「全社の状況」や「中長期の戦略」「業績数値」など、広い視野から物事を見ている。一方、現場の社員は「今日のタスク」「お客様対応」「業務のやりやすさ」など、ごく身近で具体的な課題に意識が集中している。これは、役割と責任の違いによって当然起こる「視点のギャップ」だ。
このギャップがある状態で、経営者が「今期は利益率を重視しよう」と話しても、社員は「なんのこと?それより出荷のトラブルが…」という受け止め方をしてしまう。このズレに気づかずに「なんで伝わらないんだ」と苛立ってしまうのは、実は経営者側の“想像力不足”でもある。
相手がどんな世界観で日々の仕事を捉えているか。どこに関心があり、どこに不安を抱えているのか。それを想像しないまま言葉を投げても、届かないのは当然のことだ。
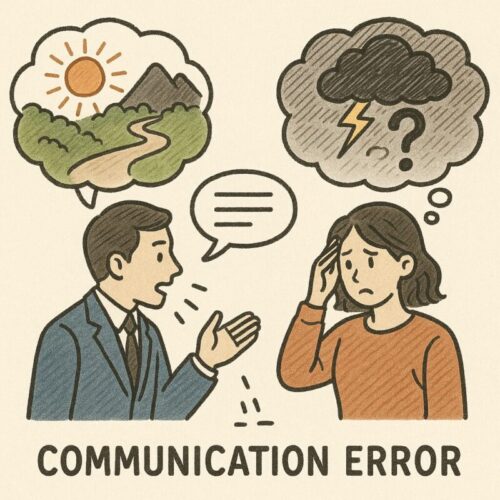
言葉は「相手の地図」の上でしか意味を持たない
人は、自分の「経験」や「知識」「関心」の中でしか、言葉を理解できない。「数字で考えろ」という言葉も、経営者にとってはPLやKPIを意識した行動を意味するが、社員にとっては「計算が必要なのか」「表を作ること?」と解釈されてしまうことがある。
つまり、言葉が通じないのではない。“同じ言葉”を使っても、それぞれが違う意味で受け取っているだけなのだ。この「意味の解釈のズレ」がある限り、どんなに丁寧に話しても、伝達は成立しない。
ではどうすればいいか?まずは、相手がその言葉をどのように受け取っているかを知ることだ。「数字で考えろ」と伝えたあとに、「たとえば、どんな場面で使えると思う?」と尋ねてみる。そこで返ってくる答えが、相手の“理解の地図”を映し出すヒントになる。
💡伝えたつもりでも、伝わっていない
たとえば「もっと主体的に動いてほしい」と経営者が願っているとする。ところが社員にとっては「どう動けばいいか、具体的に指示されないとわからない」と感じている。経営者は「自分で考えて動け」という思いで話しているが、社員は「放任された」と誤解する。
このように「主体性」という言葉一つとっても、受け取る側の経験や理解度によって、まったく別の意味になる。だからこそ、伝える前に「相手の地図」を知ることが何よりも大切なのだ。
“わかりやすく”伝えることが、必ずしも“伝わる”とは限らない
どれだけ整理された説明でも、相手の理解スタイルと合っていなければ伝わらない。大切なのは「わかりやすさ」ではなく、「合っているか」である。
「論理的に話せば伝わる」という思い込み
「何が悪かったんだろう?」「説明が下手だったか?」と反省する経営者は多い。しかし、実際には説明の問題ではなく「相手の理解の出発点が違った」ということが多い。
人はそれぞれ、話を聞く「入り口」が違う。論理より感情で動く人もいれば、イメージで理解する人もいる。つまり、“説明の質”ではなく、“受け手の理解スタイル”の違いが、伝わらない原因となっていることが少なくない。
「言語型」と「ビジュアル型」 ― 理解のスタイルが違う
ある社員は「理屈」が好きで、フローチャートや手順書で理解が進む。一方、別の社員は「とにかく見せてもらえればわかる」というタイプで、手順書より実演が効果的。このように、同じ話をしても、受け取り方が全然違うのは「理解のチャンネル」が違うからだ。

重要なのは、どちらが優れているという話ではない。どちらも“正しい理解方法”である。だからこそ、経営者には「伝え方の引き出し」を複数持っておくことが求められる。
💡図を描いたら一発で理解された
ある会議で、プロジェクトの全体像を紙で配ったが、誰もピンとこなかった。ところが、経営者がホワイトボードに図を描いて説明し始めた瞬間、空気が変わった。「ああ、なるほど」「そういう流れか」と一気に理解が進んだ。これは、言葉ではなく「絵」で伝わった好例である。
「伝える力」は“言葉の外側”にもある
言葉だけで伝えようとするのは、情報伝達のほんの一部にすぎない。言葉が届かないとき、真に伝わるものは「空気」や「態度」、そして「共にいる時間」から生まれている。経営者として大切なのは、“話し方”だけでなく、“在り方”で語ることなのだ。
言葉以外のチャンネルも“伝達”である
たとえば、朝の「おはようございます」。これひとつ取っても、無表情でつぶやくように言うのか、笑顔で目を見て言うのかで、受け取る側の気持ちは天と地ほど違う。
言葉の中身は同じなのに、「感じ方」がまるで違うのだ。
これは“非言語コミュニケーション(ノンバーバル)”と呼ばれる分野でも証明されている。人間が受け取る情報のうち、実に9割近くは“言葉以外”の要素から影響を受けているという研究もある。
- 声のトーン
- 話すスピード
- 呼吸のリズム
- 視線の合わせ方
- 頷きや身振り
- 沈黙の取り方
- その場の空気感
これらはすべて、言葉以上に「何を伝えたいか」を表している。
💡あるある:空気で「察してしまう」現場
たとえば、会議の冒頭に「何でも自由に意見を言ってください」と言いながら、経営者の表情が険しかったり、腕を組んでいたら、社員はどう感じるか?
言葉では“自由”と言っているが、空気は“緊張”を放っている。
このような場では、社員の発言は途端に減る。そして、「何も意見が出なかったな、やる気がないのか」と感じてしまう。しかしそれは誤解であり、“言葉の外側”から放たれていた空気の影響なのだ。
同じ言葉でも、「どういう状態のあなたが言ったか」で伝達の結果は180度変わる。これが“言葉の外側”が持つ影響力である。
「見せる」「体験させる」「一緒にやる」
言葉より強い伝達手段――それが“見せること”だ。
「こうやってやるんだよ」と言っても伝わらないことは多いが、「こうやってみせるよ」と実際にやって見せれば、言葉は最小限でも伝わる。
これは決して“手取り足取りやるべき”という意味ではない。
「伝えようとしている姿勢」そのものが信頼を生み、理解を深める鍵になるということだ。
特に、以下のような場面では“見せる”ことが抜群の効果を発揮する。
✅ ルーチン業務の改善
「そのやり方、もっと効率的になるよ」と説明しても伝わらない。
→ 実際に隣に座って一緒にやってみせると、「あっ、そんな簡単な方法あったんですね!」と気づく。
✅ 現場の動線や配置の見直し
「もう少し整理して並べたほうがいい」と口頭で言ってもピンとこない。
→ 自ら手を動かしてレイアウトを変えてみせると、「なるほど、こういうことか」と腹落ちする。
✅ お客様への応対方法の共有
「丁寧に対応して」とだけ言っても、具体的にどう丁寧なのかわからない。
→ 実際に模擬応対して見せると、ニュアンスまで伝わる。
💡一緒にやったら伝わった
ある中小の製造業で、出荷指示のミスが頻発していた。
社長は「なぜこんな簡単なことができないんだ」と思いながら、毎朝の朝礼で「確認を徹底しよう」と声を上げていたが、改善は見られなかった。
ある日、社長は現場に降りて、出荷準備の工程に最初から最後まで立ち会った。
そして、社員と一緒に作業をしながら、指示書の見方、伝票の確認、ラベルの貼り方などをその場で共有した。
するとその翌週から、出荷ミスは激減した。
社員が「こういう意味だったんですね」「だから重要だったんだ」と初めて“体感”したことで、言葉では伝わらなかった背景まで理解したのだった。
このとき社長は、「何度も言ったはずなのに」ではなく、「一度“見せた”だけで伝わった」ことの威力を知ったという。
💡あるある:「スマホを見ながら話す」経営者
「よし、頑張っていこう」と社員に言いながら、スマホに目を落としたまま話す経営者。これ、現場でよく見られる光景だ。
本人は何も悪気はないのだが、受け手は「関心がない」「真剣じゃない」と感じてしまう。「言葉の内容」よりも、「どう言っているか」が印象に残ってしまうのだ。
社員は言葉の裏にある“温度”や“関心度”を無意識に読み取っている。だからこそ、伝えるとは「一緒にいる時間の質」であり、「どんな姿勢でその言葉を発しているか」なのだ。
言葉だけでは「心」は届かない
“言葉を尽くしても伝わらない”と感じたとき、それはあなたの「説明力」の問題ではない。
それは、“言葉の外側”が欠けていたというシンプルな話だ。
- 笑顔で話しているか
- 相手と目を合わせているか
- 自分も相手と同じ場に立っているか
- 一緒にやろうとしているか
こうした要素こそが、本当の意味での「伝える力」を支えている。
「伝える力」は“相手を信頼する力”でもある
信頼のないところに、伝達は成立しない。「わかってくれるはず」という前提があるから、言葉は届く。
「どうせわかってもらえない」という前提が、伝達を曇らせる
「またどうせ伝わらないだろう」と思いながら話すと、その“疑念”は相手にも伝わってしまう。すると、言葉の選び方や声のトーンがどこかよそよそしくなり、結果的に「本気じゃないな」と受け止められてしまう。
伝えるという行為は、「相手を信じる」ことから始まる。信頼があるとき、多少言葉足らずでも伝わる。逆に、信頼がなければ、どんなに丁寧でも届かない。
「共に考える」姿勢が信頼を生む
「教える」ではなく「一緒に考える」。これは中小企業におけるコミュニケーションで特に大切だ。トップダウンではなく、「これってどう思う?」「どうしたらいいかな?」と問いかけることで、社員は“当事者意識”を持つようになる。
その関係性があるからこそ、「言われたからやる」のではなく、「自分もやりたい」と思える。伝えるとは、相手を巻き込むことであり、信頼をかける行為でもある。
💡「できるよ、お前なら」の力
ある営業社員が、大口顧客への提案に不安を感じていたとき、上司がそっと「できるよ、お前なら」と声をかけた。その一言で、彼の表情が変わり、自信を取り戻した。信頼は言葉以上の力を持つ。関係性の質が、伝達の深度を決めるのだ。
まとめ :「伝える力」は“理解される力”ではなく“理解しようとする力”
伝える力を磨くとは、「わかりやすく話せるようになること」ではない。もっとも重要なのは、相手がどこにいるのか、何を見ているのかを“見に行く”力である。
伝わらない原因の9割は「前提のズレ」
言葉の壁ではなく、「見えているものが違う」というズレ。これを前提として認識しない限り、何をどう話しても届かない。だからこそ、まずは「ズレている前提」で会話に臨む必要がある。
わかりやすさよりも「相手の世界を見に行く」
伝えるとは、自分の表現を磨くことではなく、相手の“今の理解状態”に合わせて言葉を選ぶことだ。「話す」のではなく、「届ける」こと。これは、経営者にとっての大事な能力の一つである。
経営者が「伝える力」を磨くということ
経営者の使命は、理念を語ることではない。それを“社員の言語”に変換し、“現場の文脈”で再構築して届けることだ。伝える力とは、社員一人ひとりの“世界観”にチューニングする力。その力を持つ経営者は、言葉で組織を動かす。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。