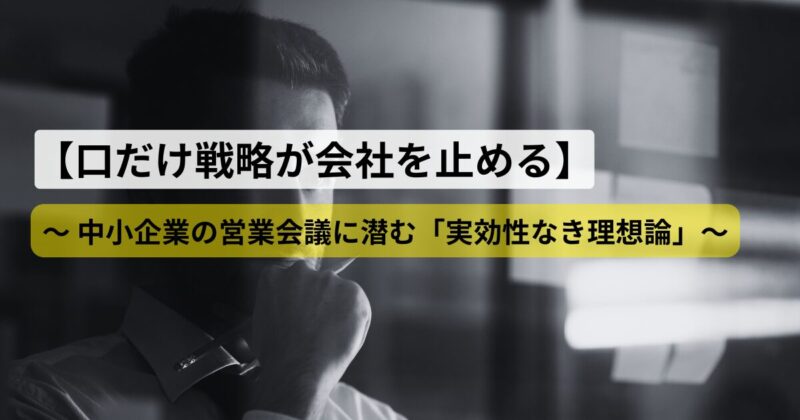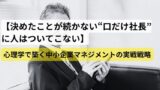中小企業で、例えば…情報セキュリティ対策製品を開発し、その販売戦略を練る会議で「国のガイドラインに登録すれば広がる」「補助金制度を活用すれば自治体経由で採用される」といった“理想的な成功モデル”が語られる光景は珍しくない。だが実際に成果が出ることは少ない。それはなぜか?…答えは明白だ。それは“口だけ戦略”だからである。実行計画が曖昧なまま、立派な戦略だけが会議室を舞う。本稿では、中小企業が陥りやすい理想論の罠と、それを打破する具体策を提示する。ターゲットは中小企業の経営者および管理職。現場を動かすリーダーこそ、抽象から具体へと戦略を落とし込む責任がある。
なぜ会議は“きれいな理想論”に流れるのか
営業戦略会議ではしばしば「もっともらしい話」ばかりが並び、現場のリアリティが欠落する。なぜこのような“理想論先行”の思考回路が蔓延するのか、その構造を分解する。
誰も否定できない「もっともらしい話」の罠
会議で語られる理想論は、抽象度が高く、聞こえは良い。誰もが賛同できる分、反論が起きにくい。例えば「国の制度に載せよう」「社会課題と紐づけよう」といった発言は、言葉として正しいように聞こえるが、実行の道筋が語られない。こうした提案は、責任の所在が曖昧なまま、発言者が「考えている感」だけを獲得できる構造になっている。そして多くの場合、語りの巧さが評価そのものを代替してしまう。
「上から攻めよう」は魅力的に聞こえるが動かない
「自治体や官公庁に提案すれば広がる」「○○省にアプローチしよう」といった“上流”アプローチもよく見かける。だがこれは、権威に寄りかかる錯覚であり、現場での積み上げを省略する発想だ。成果が出れば「私の戦略が的中した」と言えるが、失敗したときには「先方の事情だった」で済まされる。つまり、成果を外部要因に依存する構造をつくってしまっている。
周囲が同調してしまう心理(空気に飲まれる・無知による沈黙)
反論が起きないもう一つの理由は、“空気の支配”である。説明コストが高くなると、面倒だから黙る。専門外の分野になると、自信がなくて沈黙する。こうして「多元的無知」の状態が発生する。つまり、みんな内心では「おかしい」と思っていても、誰も声を上げないため、あたかも合意しているように見える。結果、“何も動かない理想論”だけが残る。
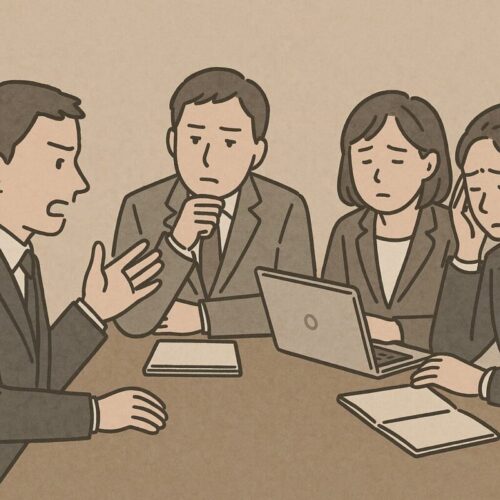
実効性のない戦略が生まれる背景
単なる理想論ではなく、なぜ「実行されない戦略」が堂々と会議で語られるのか。その背後には人間心理と組織構造の罠がある。
現場を知らない人ほど「口でまとめる」傾向…ではなく“半経験者の罠”
現場未経験者ではなく、“少しだけ知っている人”が最も危険だ。過去にプロジェクトに関わったことがある人ほど、チーム全体の成果を「自分の手柄」として記憶する。こうした自己奉仕的バイアスは、「自分はやったつもり」で語るが、実際の行動には乏しい。そして説明できること=実行できること、という錯覚に陥る。結果として、「皆でやった」と言いながら、自分の行動は言語化できない状態に陥る。
責任の所在を曖昧にすることで“自分は有能”を演出
「プロジェクトを動かしました」「関係構築ができました」といった“測定不能ワード”を使い、成果を語る人は要注意だ。実行計画の明文化やKPI設定がないまま、「やっている感」だけが広がる。これは会議文化に依存した“発言での自己評価”が成立してしまっているからだ。中小企業においては、こうした“見えない成果”が放置されがちだ。
中小企業では「人脈や制度の活用」が現実的に難しいのに夢を語ってしまう
「中小企業こそ国の制度を活用すべき」「自治体ルートを使えば販路が広がる」…こうした提案は、いかにも戦略的で賢そうに聞こえる。しかし実際の現場では、それが実行に移されることはほとんどない。なぜか?その理由は、“語っているだけで何も決まっていない”からだ。
具体的に問えばすぐにボロが出る。「どの自治体にアプローチするのか?」「担当者の名前は?」「どんな関係性が築けているのか?」こうした問いに対して返ってくる答えは、
- 「まぁ、そこはこれから詰めます」
- 「動きながら探るしかない」
- 「会ってみないとわからない」
……という“考えてないことを、思考中だと誤魔化すテンプレート”ばかりだ。
さらに突っ込めば、「それって机上の空論じゃない?」と指摘されると、「まあ、意見の違いだね」と話の焦点をずらし始める。「反対するのか」「否定から入るのは良くない」と“会話の地ならし”で正面からの対話を避ける。
このような人物に共通するのは、自己評価が高く、「自分は分かっている」と信じて疑わないことだ。中身が伴っていなくても、言葉だけは一丁前で、自分なりの“語り”で場を支配する。だがその語りには、対象者の顔がなく、行動の導線もない。
つまり….
「誰に」「何を」「どうやって」伝えるのかが決まっていない戦略は、戦略ではなく“念仏”である。
「IT顧問のススメ」でも繰り返し語っているが、制度や外部リソースの活用は、自社の体制と照らし合わせて初めて意味を持つ。ただ語るだけでは、何も生まれないどころか、チームの時間と集中力を奪う“戦略ごっこ”に過ぎない。
経営者が見抜くべき“口だけ戦略”のサインと打開策
抽象的な理想論を具体的行動に落とし込めるかどうか。ここが経営者の真価が問われる部分だ。
口だけ戦略のチェックリスト
以下の特徴が見られる戦略は要注意である。
- 「誰に届けるのか?」と尋ねても、具体的な名前が出てこない
- 成果指標を「登録完了」「認知度向上」など、プロセスで語る
- 「皆でやった」というが、自分の役割を説明できない
これらの特徴は、「【文章化できない病】が組織を蝕む」で指摘したに、発言が行動や責任と結びついていない状態である。
実効性を持たせるための3つの視点
- 担当・期限・成果物をセットで定義する
→「誰が」「いつまでに」「何をするか」がない発言は戦略ではなく願望である。 - 小さく検証可能な一歩に分解する
→「とりあえず3社に提案し、反応を確認する」など、すぐに実行できる行動に落とし込む。 - 発言に責任を宿す仕組みを導入する
→「発言メモを共有」「担当者が進捗を週報に記録」といった仕組みで、責任の“見える化”を図る。
理想を現実に落とすリーダーの役割
リーダーの最大の役割は、理想論を“次の10日間で動かせること”に翻訳する(初動10日!)ことである。抽象的な提案をそのままにせず、「誰が、いつ、どこで動くか」に変換して初めて意味を持つ。
これは「任せる勇気が経営を変える」で述べたが、部下に任せ、責任を持ちつつ結果を引き受けるリーダーの構造と一致する。
経営者は「抽象は安全、具体は責任」という構造を理解した上で、あえて具体化に踏み込まなければならない。
まとめ ― 理想を語る前に、動ける一歩を設計せよ
中小企業の営業会議に蔓延する“実効性なき理想論”は、確かに耳障りが良く、参加者の気分を良くする。だが、それが行動に結びつかなければ何の意味もない。経営者はこうした“口だけ戦略”を見抜き、抽象的な言葉を「具体的な行動」に翻訳する力を持たねばならない。
理想と現実の間に橋を架けるのは、システムでも制度でもない。日々の言葉と行動である。抽象から具体へ…この変換こそが、成果を生む唯一の方法だ。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
また、お会いしましょ。